『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第三章 弟子たちとの交わり(その2) — 2 大いなる弟子たち — 顔回 「賢なる哉」、最愛の弟子
今日のところは、「第三章 弟子たちのとの交わり」(その2)である。ここから 2節 「大いなる弟子」に入り、孔子の高弟の話となる。
孔子には七十七人の高弟がいたとされる。先進第十一に
「徳行には、顔淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓。言語には、宰我、子貢。政事には、冉有、季路。文学には、子游、子夏」(抜粋)
とあり、徳行、言語(弁論)、政事(政治)、文学の「孔門四科」において、優れた高弟十名の名を列挙している。
ここでは、「顔回」「子貢」「子路」の三人の高弟が取り上げられている。今日のところは、「顔回」である。それでは読み始めよう。
顔回 — 「賢なる哉」、最愛の弟子
No.75
子曰く、吾れ回と言うこと終日。違わざること愚なるが如し。退きて其の私を省りみれば、亦た以て発するに足れり。回や愚ならず。(為政第二)(抜粋)
先生は言われた。「顔回と朝から晩まで話をしていると、はいはいと逆らわないさまはバカのようだ。しかし、私の前からしりぞいた後の私生活を見ると、やはり人をハッとさせるものがある。顔回は、バカじゃない。(抜粋)
顔回は孔子の最愛の弟子で、『論語』でしばしば言及されているが、ほとんど絶賛である。顔回は、秀才型ではないが、北宋の蘇東坡のいう「大智は愚の如し(大いなる知者は愚か者のようだ)」そのものだった。
No.76
子曰く、賢なる哉 回や。一簞の食、一瓢の飲、陋巷に在り。人は其の憂いに堪えず。回や其の楽しみを改めず。賢なる哉 回や。(雍也第六)(抜粋)
先生は言われた。「えらい男だな、顔回は、弁当箱に一杯のごはん、ひさごのお椀に一杯の飲み物だけで、狭い路地裏に住んでいる。ふつうの人間ならうんざりして耐えられないが、顔回はその暮らしの楽しさを改めようとしない。えらい男だよ。顔回は。」(抜粋)
この顔回への称賛は大変有名である。顔回は質素な暮らし意に介さず、自分の思い通りに学問して生きることを楽しんでいる。そのような顔回の姿を孔子は絶賛している。しかし、孔子は日常の暮らしにおいて繊細な美学を発揮した人であり、顔回のような生活を送った人ではない。ただし、
「疏食を飯らい水を飲み、肱を曲げて之れを枕とす。楽しみ亦た其の中に在り。不義にして富み且つ貴きは、我れに於いて浮雲の如し」(抜粋)
と述べていて、不正な手段で得た富で豊かな暮らしをするよりは、質素な暮らしでいた方が楽しいという信念があった。
No.77
子 顔淵に謂いて曰く、之れを用うれば則ち行い。之れを舎つれば則ち蔵る。惟だ我れと爾とのみ是れ有るかな。子路曰く、子 三軍を行わば、則ち誰と与にせん。子曰く、暴虎馮河、死して悔い無き者は、吾れ与にせざる也。必ずや事に臨んで懼れ、謀を好んで成る者也。(述而第七)(抜粋)
先生は顔淵(顔回)に言われた。「自分を認めて任用する者がいれば、世に出て活動する。見捨てられれば、隠遁する。そんなふうにできるのは、私とおまえだけだね」。子路[しろ]が言った。「もし先生が三軍(諸侯の軍隊)を指揮されるなら、誰といっしょになさいますか」。先生は言われた。「虎と素手で闘い、大河を徒歩わたりして、死んでもかまわないという者とは、私はいっしょに行動しない。必ずや事にあたって慎重にかまえ、計画性があって成功するような者でなければならないのだ」。(抜粋)
孔子が顔回を褒めたときに、子路が口をはさみ、孔子にたしなめられたという話である。孔子は、優秀な顔回に過剰とも思える期待をかけた。そして、純情な熱血漢の子路の長所も十分に理解して、愛情を注いだ。
No.78
子曰く、之れに語げて情らざる者は、其れ回なるか。(子罕第九)(抜粋)
先生は言われた。「講義をしているとき、退屈そうにしない者は顔回だけだな」。(抜粋)
顔回が退屈しなかったのは、孔子の話がすべてわかったからだとしている。これとNo.75の条を合わせて考えると、顔回は、才気走しった反論をしないが、かといって退屈することもなく、黙々と孔子の言葉に耳を傾けていたことになる。
No.79
子 匡に畏す。顔淵後る。子曰く、吾れ汝を以て死せりと為す。曰く、子在す。回 何ぞ敢えて死ん。(先進第十一)(抜粋)
先生が匡で襲撃を受けられたとき、顔淵(顔回)がおくれて追いついてきた。先生は言われた。「私はおまえが死んでしまったものと思っていた」。顔淵は言った。「先生が生きていらっしゃるかぎり、私は死にません」。(抜粋)
孔子一向が、匡で襲撃を受けた時の逸話である。このとき孔子一向は、子路をはじめとした腕におぼえのある弟子が先頭に立って血路を開いて逃げた。そして遅れて顔回が追いついた時の会話である。
No.80
哀公問う、弟子 孰が学を好むと為す。孔子対えて曰く。顔回なる者有り、学を好む。怒りを遷さず。過ちを弐びせず。不幸 短命にして死せり。今や則ち亡し。未だ学を好む者を聞かざある也。(雍也第六)(抜粋)
哀公が聞かれた。「お弟子さんのうち、誰が学問好きと思いますか」。孔子は答えて言った。「顔回という者がおりました。学問好きで、怒りに駆られず、同じ過ちを繰り返すことはありませんでしたが、不幸にも短命で死にました。今はもうこの世にいません。(彼の死後)学問好きの者がいるとは聞いたことがありません」。(抜粋)
顔回は、孔子に先立つこと二年、四十一歳で亡くなった。この言葉は、最愛の弟子を失ったことが、晩年の孔子に深刻な打撃を与えたことを示している。孔子は、顔回がなくなったとき「噫、天 予れを喪ぼせり。天 予れを喪ぼせり」といって悲観にくれた。
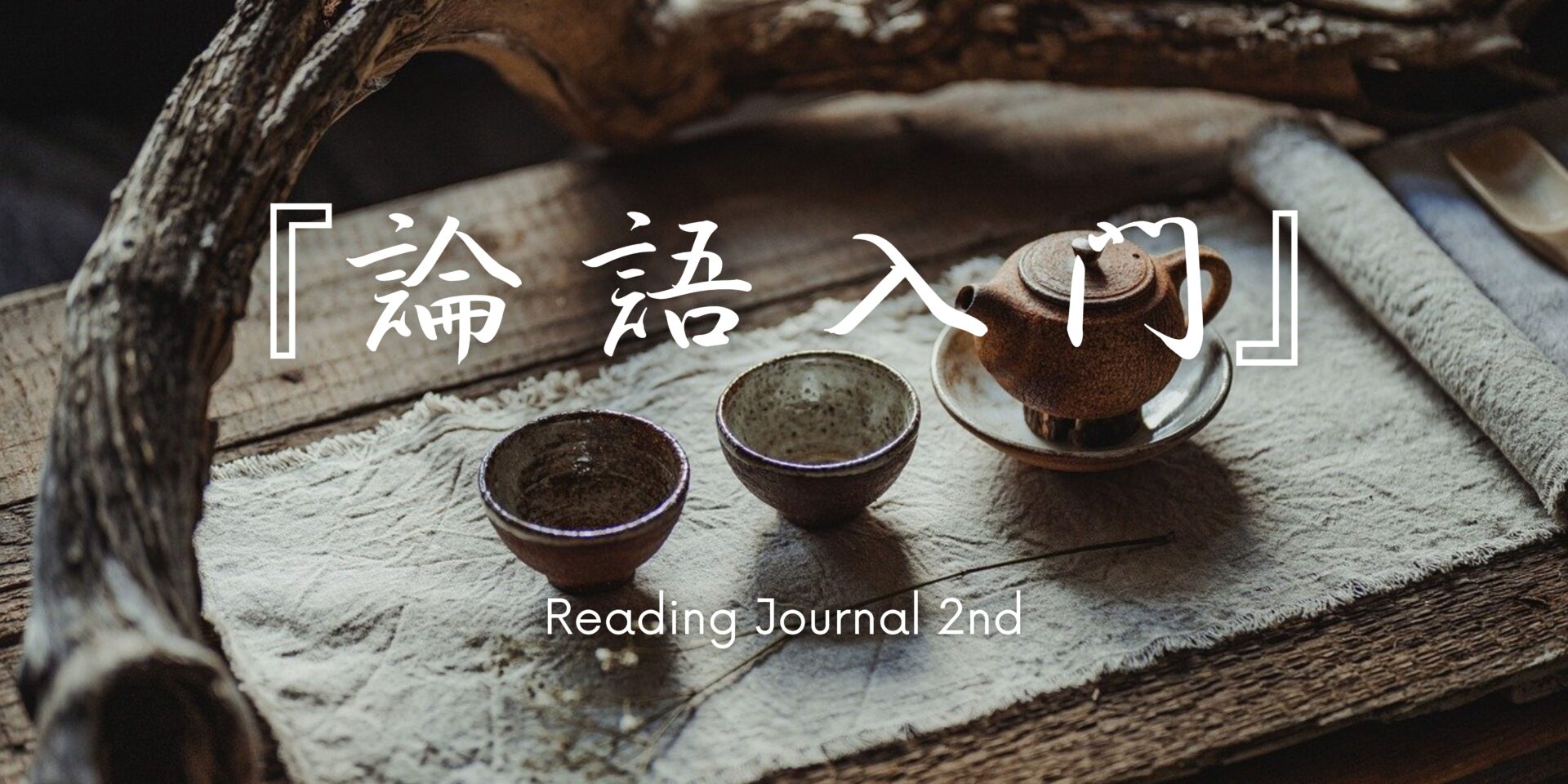
-120x68.jpg)

コメント