『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二章 考え方の原点(その5) — 1 核となるキーワード — 「鬼神」 不可知なものとの距離、「狂」 過剰なる者への好意
今日のところは、「第二章 考え方の原点」の“その5”である。ここでは、『論語』の核となるキーワードのうち「鬼神」と「狂」を取り扱う。それでは読み始めよう。
「鬼神」 — 不可知なものとの距離
No.58
子は怪・力・乱・神を語らず。(述而第七)(抜粋)
先生は怪(怪異)、力(超人的な力)、乱(混乱、無秩序)、神(鬼神)について語られなかった。(抜粋)
孔子は、怪奇現象や超人的な力、人力では収集困難な大混乱、鬼神などの不可知時には、真っ向から否定しないが、距離を置いていた。
No.59
樊遅 知を問う。子曰く、民の義を務め、鬼神を敬して之れを遠ざく。知と謂う可し。仁を問う。曰く。仁者は先ず難んで後に獲。仁と謂う可し。(雍也第六)(抜粋)
樊遅が知について質問した。先生は言われた。「人として道理を得るようにつとめ、鬼神には敬意を表するが距離を置く。これが知だ」。さらに仁について質問すると、先生は言われた。「仁徳をそなえた人はまずいろいろ苦労をしたあげく、目的に達する。これが仁だ」。(抜粋)
樊遅が、「知とはなにか」と質問したときに、孔子は前条と同じように、鬼神と距離を置くと答えた。
論語には、樊遅が、孔子に「仁」と「知」について質問した話がある。
「樊遅 仁を問う。子曰く、人を愛す、知を問う。子曰く、人を知る(以下略)」(抜粋)
ここ(No.96)では、この条とは異なる視点から説明がなされている。
No.60
季路 鬼神に事えんことを問う。子曰く、未だ人に事うる能わず、焉んぞ能く鬼に事えん。敢えて死を問う。曰く、未だ生を知らず、焉んぞ死を知らん(先進第十二)(抜粋)
季路(子路)が鬼神へのつかえかたを質問した。先生は言われた。「生きている人間につかえることもできないのに、どうして鬼(死んだ人の霊魂)につかえることができようか」。(子路がさらに)果敢にも死について質問した。(先生は)言われた。「生きている間のこともわからないのに、どうして死んだあとのことがわかるか」。(抜粋)
ここでは、弟子の子路が、鬼神への仕え方を尋ねたとき、孔子は、不可知な世界に踏み込まないことをきっぱりと伝えている。
このように孔子は、不可知な世界には、決して踏み込まず、厳然と距離をおくリアリストであった。この態度が、その後、宋代儒学における無神論の論拠となった。
No.61
子の疾病なり。子路 禱らんことを謂う。子曰く、諸有りや。子路対えて曰く。之れ有り。誄に曰く。爾を上下の神祇に禱ると。子曰く、丘の禱ること久し。(述而第七)(抜粋)
先生が病気で重態になられたので、子路は祈禱させてほしいと頼んだ。先生は言われた。「そんな例があるのか」。子路は答えて言った。「あります。誄に「爾を天地の神々に禱る」とあります」。先生は言われた。「私(丘は孔子の本名)はずっと前から祈っているよ」。(抜粋)
孔子が重病となったときに、子路が祈禱させてほしいと頼んだ場面である。子路の言葉を聞いた孔子は、「私(丘は孔子の本名)はずっと前から祈っているよ」と祈禱の申し出を断固はねつけた。この言葉について、著者は
現実主義者の孔子は神秘的な祈禱の類は否定したが、仁を核とする節度ある社会の到来を祈願し、尽力しつづけた。その意味において「丘の禱ること久し」の生涯にほかならなかった。孔子の生涯が凝縮された美しい言葉である。(抜粋)
と言っている。
「狂」 — 過剰なる者への好意
No.62
子曰く、狂にして直ならず、侗にして愿ならず、悾悾にして信ならず。吾れ之れを知らず。(泰伯第八)(抜粋)
先生は言われた。「情熱的なのに真正直でない者、子どもっぽいのにまじめでない者、ばか正直なのに誠実でない者を、私は見たことがない」。(抜粋)
孔子は、不可知な世界には距離をおくが、現実世界における過剰性を帯びた人々には好意的だった。ここで
- 狂:狂おしいほど情熱的な人
- 侗:愚かしいほど子供っぽいこと
- 悾悾:ばか正直であること
である。孔子はこのようなバランスを欠いた人にも美点を見出していた。
No.63
子曰く、中行を得て之れと与にせずんば、必や狂狷。狂者は進み取る。狷者は為さざる所有る也。(子路第十三)(抜粋)
先生は言われた。「バランスのとれた中庸な人物をみつけ、ともに行動することができないときは、狂なる者(過剰に情熱的な人間)か狷[けん]なる者(片意地で偏屈な人間)と行動をともにするしかないだろう。狂者は積極的に行動し、狷者は断固として妥協しない。(抜粋)
この条も、常識から外れた狂者と狷者を価値ある存在として捉えた発言である。孔子は、中庸な人物がいない場合は、条件付きではあるが、このような真情にあふれる過剰さや、主体性過剰の奇矯を帯びた人々に親近感を持っていた。
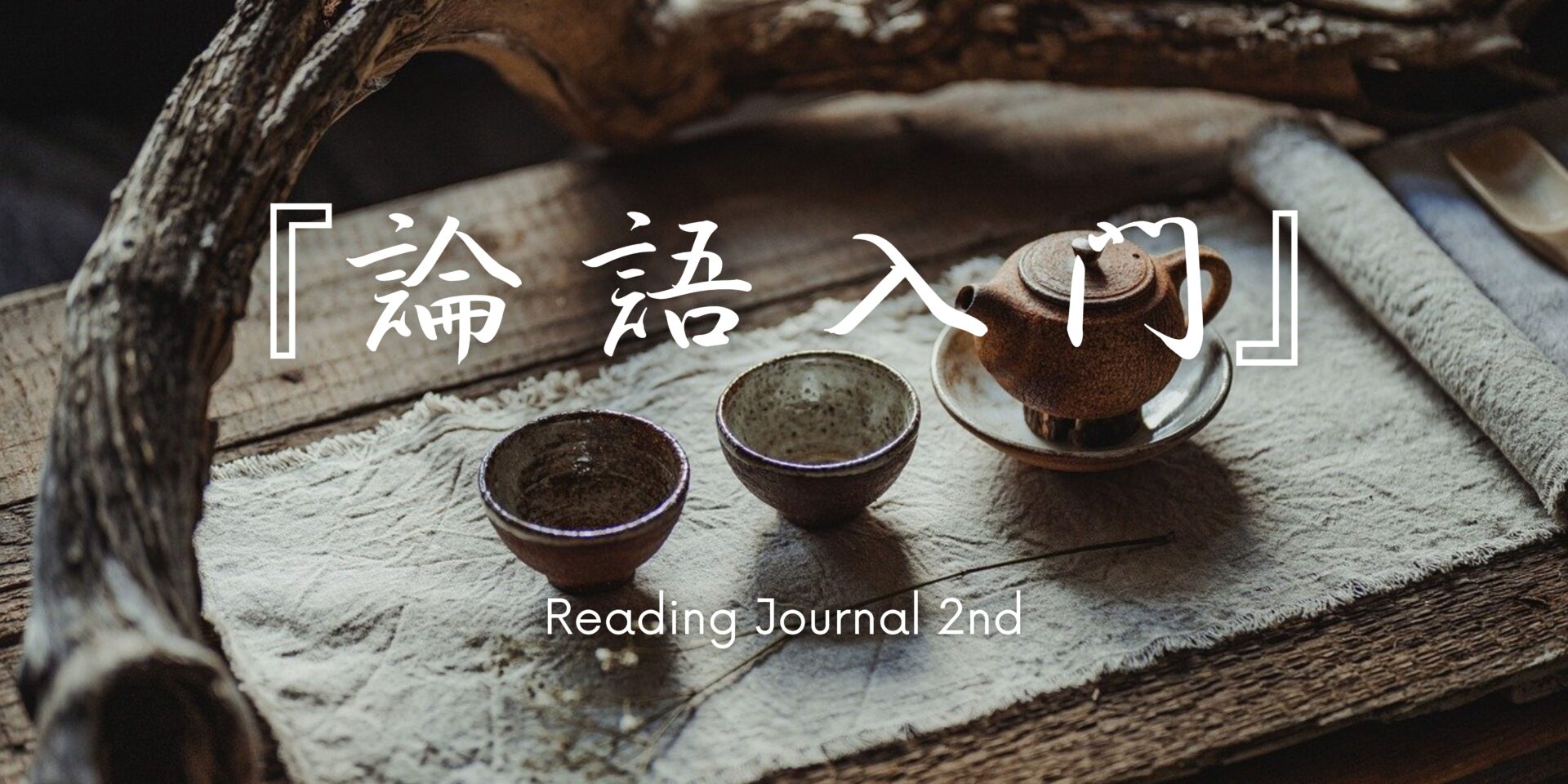
-120x68.jpg)

コメント