『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二章 考え方の原点(その4) — 1核となるキーワード — 「道」 理想社会の希求、「文」 文化のとらえかた
今日のところは、「第二章 考え方の原点」の“その4”である。ここでは、『論語』の核となるキーワードのうち「道」と「文」を取り扱う。それでは読み始めよう。
「道」 — 理想社会の希求
No.49
子曰く、朝に道を聞かば、夕に死すとも可なり。(里仁第四)(抜粋)
先生は言われた。「朝、おだやかな節度と調和にあふれる理想社会が到来したと聞いたら、その日の夜に、死んでもかまわない。(抜粋)
これは大変有名な言葉である。ここでは、伝統的な古注(ココ参照)に基づいて訳している。朱子の新注では、「道」を倫理的・道徳的な真理ととらえ、そうした「道」について聞いたならば、すぐ死んでもかまわない、の意とした。著者は、孔子はそのような性急で無謀な人ではなく、この「道」は、伝統的な解釈、つまり思いやりを基本とし、おだやかな節度と調和にあふれた理想社会の実現、もしくは到来の意とするのがふさわしいとしている。
さらに、桑原武夫が『論語』(ちくま文庫)で、この「死すとも可なり」に言及した
「立派な美しい言葉だが、孔子の時代を考えれば、ここはやはり、どこか個人の自覚といった色彩のある新注よりも、共同体的雰囲気の感じられる古注に従うほうが適切であろう。礼楽を中心とする先生の道が光被する世界へのノスタルジア、しかし、それはただ夢のような憧れではなく、あの人にひと目会えたらすぐ死んでもいい、などというときのような切実さをもっての希求なのである」。(抜粋)
いう言葉を引用している
No.50
子曰く、邦に道有れば、言を危くし行いを危くす。邦に道無ければ、行いを危くし言は孫る。(憲問第十四)(抜粋)
先生は言われた。「国家がまっとうな状態にあるときは、高い見地に立って率直に発言し、高い見地に立って率直な行動をする。国家がまっとうな状態にないときには、高い見地に立って率直に行動し、発言はひかえめにする」。(抜粋)
この条の道は、前条(No.49)よりも現実的な意味で、国家が秩序や節度を保ち、まっとうに機能している状態を言っている。そして「危」については、いろいろな解釈があるが、要は他に迎合しない、きっぱりした態度である。
ここでは、国家に「道」があるときと無いときを対比させ、道が無いときは、発言は控えめにしたほうが良いとしている。孔子は、状況を見極めることなく、賭突猛進する無謀嗟を否定し、辛抱強く理想の実現の道を探索していた。
No.51
子曰く、士 道に志して、而も悪衣悪食を恥ずる者は、未だ与に議るに足らざる也。(里仁第四)(抜粋)
先生は言われた。「道に志ながら、粗末な衣類や食物を恥ずかしがる者は、まったく問題にならない」。(抜粋)
この条は、道に志したものは、粗末な衣類や食物を恥ずかしがっては何らないと言っている。しかし、孔子は必ずしも悪衣悪食でなければならないと言っているわけではないと著者は注意している。孔子は生活美学を重んじ、食生活においても繊細な美意識を発揮していた。
No.52
子曰く、君子は道を謀って食を謀らず、耕して飢え其の中に在り。学びて禄其の中に在り。君子は道を憂えて貧しきを憂えず。(衛霊公第十五)(抜粋)
先生は言われた。「君子は道について考えるが、食について考えない。耕作をしてもそのなかで(飢饉のため)飢えることもある。学問をしていても俸禄がそのなかから生じることもある。君子は道を心にかけるが、貧しさは気にかけない」。(抜粋)
解説ここで孔子は、君子は節度のある理想社会の実現について考えるが、食について考えないといい、そして、なぜそうなのかという例を二つ上げている。
- 食に結び付く農耕をしても、飢饉のときには飢える場合がある。
- 食と結び付かない学問をしても、抜擢されて士官し食の糧を得ることもある
このように、いかに食を得るかあれこれかが得ても仕方ないと、言っている。
No.53
子曰く、参よ、吾が道は一以て之れを貫く。曾子曰く、唯。子出づ。門人問いて曰く、何の謂ぞや。曾子曰く、夫子の道は、忠恕のみ。(里仁第四)(抜粋)
先生は言われた。「参よ、私の道はただ一つのもので貫かれている」。曾子は答えた。「はい」。先生が出ていかれた後、他の弟子がたずねて言った。「どういう意味ですか」。曾子は言った。「先生の道は忠恕[自分に対する誠実さ、他人に対する思いやり]」で貫かれている、ということだよ」。(抜粋)
ここでいう「道」は、広く行動、態度、生き方を指す。ここで「忠」は、自分に対する誠実さ、忠実さ、であり「恕」は、「忠」を他者に及ぼしたものである。そしてこの「忠恕」の感情を統合すると「仁」となると思われる。
No.54
厩焚けたり。子 朝より退きて曰く、人を傷なえりやと。馬を問わず。(郷党第十)(抜粋)
(孔子が自宅の)馬屋が火事になって焼けた。先生は朝廷から退出し帰宅されて言われた。「誰かケガをしなかったか」。馬のことは聞かれなかった。(抜粋)
解説これは前条(No.53)の「夫子の道は、忠恕のみ」の実践版である。厩の火事の際、孔子がまず人の身を案じたというこの話は、中国でも日本でも人口に膾炙する。
「文」 — 文化のとらえかた
No.55
子張問う、十世知る可きや。子曰く、殷の夏の礼に因る。損益する所、知る可き也。周は殷の礼に因る。損益する所、知る可き也。其の或いは周を継ぐ者は、百世と雖も知る可き也。(為政第二)(抜粋)
子張が質問した。「十代さきの王朝のことを予知できるでしょうか」。先生は言われた。「殷王朝は夏王朝の礼法制度をうけついだ。増したり減らしたりして変更を加えたところは、察知できるはずだ。周王朝は殷王朝の礼法制度をうけついだ。増したり減らしたりして変更を加えたところは、察知できるはずだ。だから、周王朝を継ぐ王朝の礼法制度は、百代さきであっても察知できるはずだ。(抜粋)
ここで孔子は、過去の夏、殷、周王朝を取り上げ、それらは先代の王朝の礼法制度に変更や修正を加えたものだから、そのありかたは察知でき、さらに後世の王朝も、同じように十代はおろか百代だって察知できるはずと言っている。
すでに多くの論者が指摘するように、この発言は、孔子には、部分的な変更や修正をともないつつ、歴史は無限に連続し発展するものだという、核心に満ちた歴史観があったことを示している。(抜粋)
なお、ここにでてくる夏王朝、殷王朝、周王朝などは、同著者の『故事成句でたどる楽しい中国史』に詳しいよ(つくジー)。
No.56
子曰く、周は二代に監む。郁郁乎として文なる哉。吾れは周に従わん。(八佾第三)(抜粋)
先生は言われた。「周王朝は二代(夏王朝と殷王朝)を参考にしてつくられ、かぐわしくもうるわしい。私は周の文化に従いたい」。(抜粋)
孔子は、周の礼法や制度を定めた周公旦を、終生敬愛した。周公旦が基礎を築いた周の文化こそ孔子の理想であった。
ここでは、その文化を「郁郁乎として文なる哉」と例えている。
No.57
子曰く、質 文に勝てば則ち野。文 質に勝てば則ち史。文質彬彬として、然る後に君子(雍也第六)(抜粋)
先生は言われた。「素朴さが文化的要素をしのぐと野蛮になり、文化的要素が素朴さをしのぐと自然さがなくなる。素朴さと文化的要素の均衡がとれてこそ君子だ」。(抜粋)
ここで「彬彬」は、均衡の取れたさまを表す。孔子は「文」と「質」のバランスが取れた人が君子であるとしている。文化的素養を身につけながら、人間としての自然な素朴さを失わないことが理想である。
関連図書:
桑原武夫(著)『論語』 、筑摩書房(ちくま文庫)、1985年
井波律子(著)『故事成句でたどる楽しい中国史』 、岩波書店(岩波ジュニア新書)、2004年
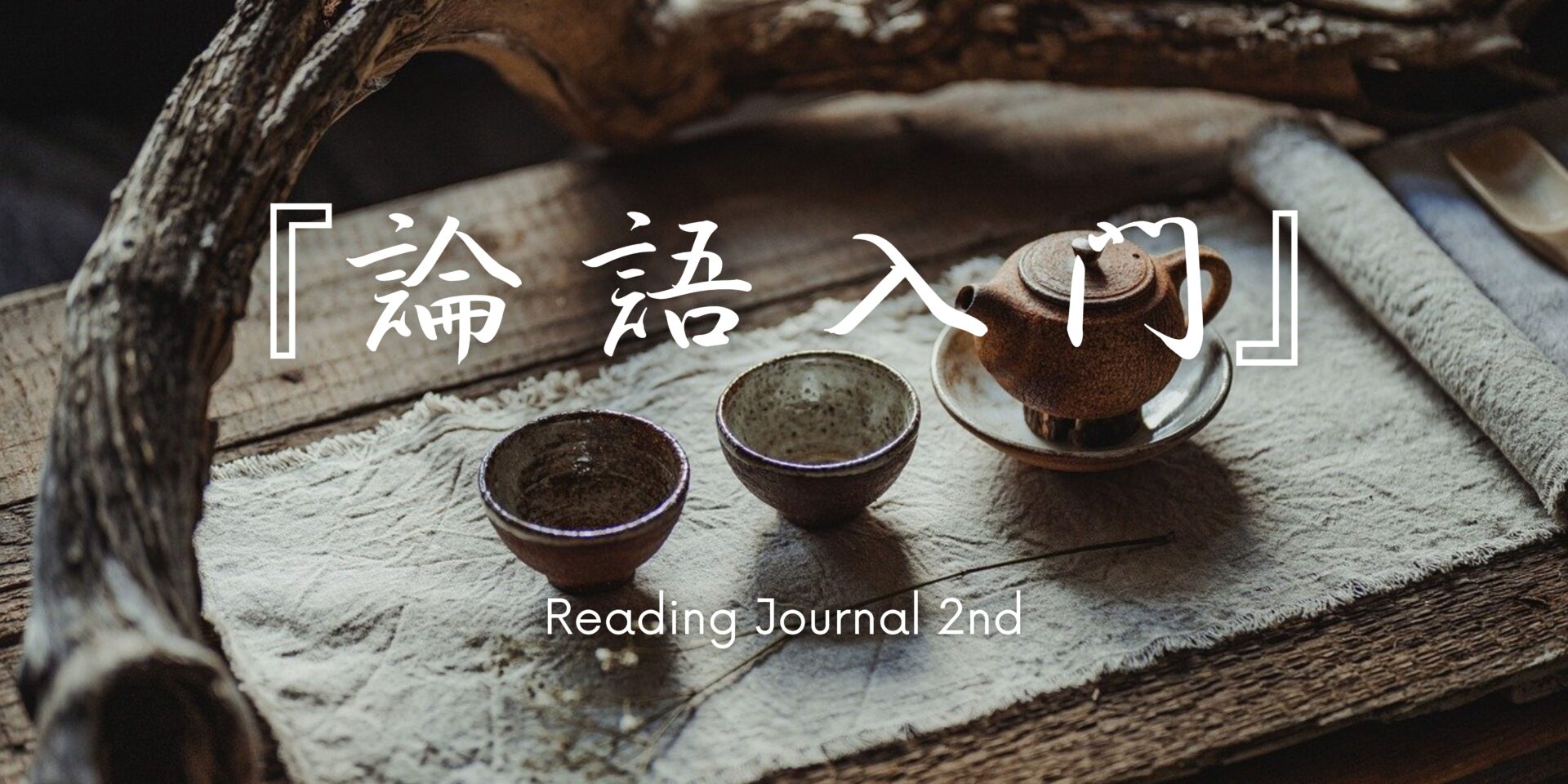


コメント