『本を読む本』 M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
日本人の読書 – 訳者あとがきにかえて 外山 滋比古
最後に「あとがき」として、訳者の外山滋比古の「日本人の読書」という小文がある。文化は民族、時代によって変化する。そして本を読むという行為はその文化で重要な役割を果たすため、同じように民族、時代によってさまざまである。そこで外山は日本人の読書の特徴について概観するとしている。それでは読み始めよう。
若年読書
どこの国でも基礎教育の中心は読解に置かれる。子供は学校で読むことを覚え、読んでいるうちに喜びを感じ、そしてさらに本を読む。このようにして読書好きが生れる。しかし、社会に出て仕事が忙しくなると、読書から遠ざかり中年になるまで読書の習慣を維持している人は例外的である。
若者の読書は、自己を改造しようという気持ちや、周囲から離脱したいという気持ちがある。このような読書は精神的な要素を漂わせ、さらには、宗教的となる。モラリスティックであり、人間はいかに生きるべきかというテーマを持っていた。そのため、技術的、実用的読書は軽んじられた。
しかし、このような情熱的な読書はどんどん成長する精神に追いつかずいしか燃え尽きてしまう。若者の読書は通過儀礼のようなものである。
ところが近年になって、新しい中年読者層が形成されようとしている。日本人の読者も大きく変化することが予想される。(抜粋)
短編読書
日本文化の特色の一つに、小粒ということがある。(抜粋)
そのため、文芸では、俳句、短歌などの短詩型文学が主流となり、短編文学の水準も高い。これは読書にも影響し、読みはセンテンス(文)単位で読み進み、その上のパラグラフ(段落)をあまり気にしない。そして、センテンスごとの読みかたでは、どうしても主情的になり、形式的論理の筋はあいまいになりやすい。そのため叙情的読書に傾倒し、抽象的思考による探求は苦手となる。そして思想書や宗教書も小説的な読みn
近年、高等教育がいちじるしく普及したのにつれて、こういう読書態度にも変化がみられるようになった。フィクションしかおもしろいものはないように考えていた若年読者に対して、ノンフィクションのおもしろさを発見した読者があらわれてきたのである。(抜粋)
難解信仰
日本では、文章が難解な本の方が価値があるとする「難解信仰」がある。これは明治以降に欧米の新しい文化が翻訳を通じて入ってきたことによっている。欧米からの翻訳ではどうしても悪文になるが、それをすぐれた本は難解であるべきで悪文でもよいという錯覚が一般化した。そのため本は早く読んだり、ざっくりと読んだりするのではなく精読が正しいとされた。また、一度読みはじめたら、わかってもわからなくても最後まで読むのが良いとされた。
返り点読み
日本人には、同じところを往復して読む癖がある。これは、漢文を読むときに返り点で読むことが影響している。近年は漢文を読まなくなったが、外国語の解釈の型により返り点読みとなってしまう。
こみいった内容の文章を読む場合、知らず知らずにもとにもどって返り点読みとなってしまう。しかしこのような読みかたは、流れの無い読書になりやすい。
変化
日本人の読書は求道的、人生的、ときに宗教的であったが、近年の教育の普及により、実際的で知的な情報処理としての読書が注目されるようになった。これまでの求道的読書では、読書の技術は顧みられなかったが、新しい知的読書には、ざっと目を通すだけでよい本とじっくりと精読する本を有効に読み分けるような読書の技術が必要である。
こういうわけで、日本人の読書はいま激減しようとしている。新しい知的読書へ向かうにも本書のような技法はきわめて有益であろう。新しいタイプのすぐれた読書家が生れることを期待する。(抜粋)
[完了] 全20回
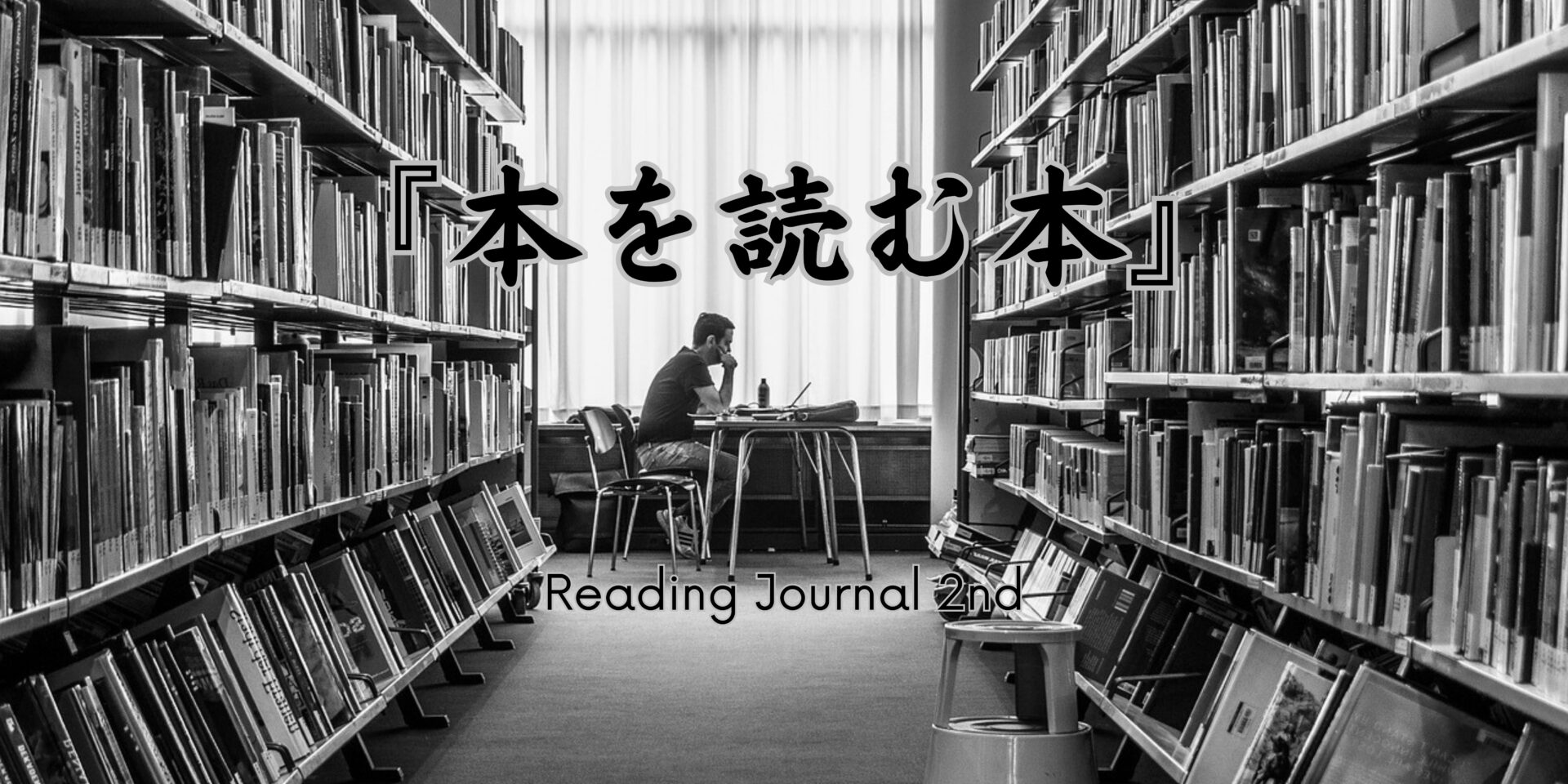
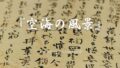

コメント