『アメリカ革命』 上村 剛 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2章 独立 ― 一七六三~一七八七年 (その1)
今日から「第2章 独立」である。前章「第1章 植民地時代」では、アメリカの植民地時代を現代的な歴史の観点から概観した。第2章では、イギリスと植民地の対立から独立に至る過程を、詳細に検討する。
「第2章 独立」は、4回に分けてまとめるとする。今日のところ“その1”では、イギリスとの争いの原因を本国側と植民地側の論理の違いから読み解いていく。それでは読み始めよう。
私たちは、アメリカの独立戦争というと、ついイギリス本国と一三の植民地の対決として捉えてしまう。しかし、その戦争に参加し、あるいは否応なく巻き込まれた人々はもっと多様であり、そこには多くの絡み合った複雑な人間関係、国際関係が存在したのである。本章はその過程を描く。(抜粋)
著者はまず冒頭でこのように言って、本章を始めている。
「代表なくして課税なし」
イギリスはフランスとの戦争を制し、一七六三年のパリ条約により帝国としての地位をあげた。しかしこの戦争がアメリカを手放す原因となった。
イギリスは、植民地に対して課税を課したそれに対して植民地の反発は激化した。本国側は、植民地に軍隊を駐屯させ、植民地側はそれを脅威に感じた。このような本国側の政策に対する植民地側の反発が「代表無くして課税なし」である。
一般に、アメリカの独立に対しては、イングランド本国が悪で、アメリカが善という単純な図式で語られるが、しかしこれはアメリカ側に偏っている。なぜならば本国側にも本国なりの論拠があるからである。
経済学の勃興
本国側の課税政策の導入は、当時勃興しつつあった経済学の重要問題だった。フランスとの戦争のための国家収入をどのように増やす必要があったため、それを課税により増やすか、反対に税を押さえて消費活動を促進すべきか、という問題に関わっていた。
議会主権との関係
また代表なくして課税なしと言った際に私たちは、それが当時の自明の常識であり、英本国が破ってしまったという印象をつい受けてしまうが、それは国民の参政権が保証されている今日の価値観に引きずられすぎである。英本国は彼らの原理を持っていた。(抜粋)
その論理が「議会主権」であり、イギリスでは、今日でも国民主権でなく議会に主権が置かれている。
議会に主権があるということは、議会の構成要素である国王、貴族院、庶民院の三つが対等な関係とされ、その三つが合わさって権力を持つ、という考え方である。その背景には「混合政体」(ココ参照)という考え方があった。
このように議会に主権があるということは、いったん立法されれば、いかなるものも反論できないということである。そのため植民地が課税に待ったをかけるのを認めるわけにはいかなかった。
そしてそのいような王権論のもとで、トマス・ウェイトリーといった本国の政治家は、植民地人の言う「代表なくして課税なし」を否定した。(抜粋)
さらに著者は、当時の参政権について言及している。当時イギリスの庶民院の有権者は全人口の数%であり、九割以上の人びとは、自分が選んでいない議員によって法律を定められていた。そのため、本国の議員からすれば、本国の状況が植民地にあてはまらないことは、よくわからないことだった。もっとも本国でも、大ビッドなどは、課税の場合は通常の法律と異なって人々の同意が必要である、という反論をする人もいたが、少数派だった。
しかし、植民地側からは、本国議会に植民地に対する立法権はないとする「ドミニオン・セオリー」と呼ばれる議論が浮上した。
植民地と本国の法的つながり
この「ドミニオン・セオリー」は、議会の権限は領域内にとどまり、植民地は領域の外にあるので、議会の立法権は及ばないという理屈である。
しかし、この議論は、本国と植民地の複雑な歴史的関係を考えることが必要であるため議論は錯綜した。
仮に植民地が完全に本国から切り離された存在であるならば、イギリスが共和制になった際には、その支配は及ばないはずであった。しかし、実際には共和政府に反旗を翻したところあったが、それは一部であった。そのため、本国からすると、歴史的にも議会の支配が行われたことがあるのだから、どうして今またそれが否定されるのか理解できないということになった。
陰謀論
このように双方の議論がかみ合わない状態であるため、植民地側、本国側ともに陰謀論まで現れた。
アメリカ側では、これは一部の腐敗した政治家が自分の利益を追求しているからだと考えた。一方、イギリス側では、アメリカの防衛のために戦い、和平のために軍隊まで送り込んでいるのに、植民地側が反発してくる、これは悪い輩がいるからという発想で考える人も出てきた。
ここで著者は、植民地でのジョージ三世の信頼はそれでも揺らがず、悪いのはあくまでもその腹心であると考えていたと指摘している。
群衆の抵抗運動
反英抗争は、このような論争レベルにとどまっているわけではなく、民衆レベルでは、しばしば暴動となった。
アメリカでは反英抗争が激化するまでは、あまり暴動は無かったが、印紙法の報せが届くと暴動は激化し、一七六五年には、トマス・ハンチソン副総督の邸宅の襲撃も起こった。
これに対して、危険な暴動運動をおさえるために「自由の息子たち」という組織がつくられた。これにより抗争は過激化することなく、本国製品の不買運動などを通じて行われた。この抵抗は、政治家サミュエル・アダムズを中心として組織され、一三植民地へのネットワークに広がった。そして、さらに抵抗運動は、本国にまでわたり、そのころ本国jで起こっていた政府への反対運動にパンフレットを贈るなどしていた。
ここで著者は、この群衆運動は、単に反英の行動というだけでなく、支配階級へのヨーマン(独立自営農民)の抵抗運動という側面もあると指摘している。そしてこの国内での階級対立を、アメリカ革命の勃発の主要因であるという、考え方は一〇〇年前からあったが、今でも刷新を続け有力である。
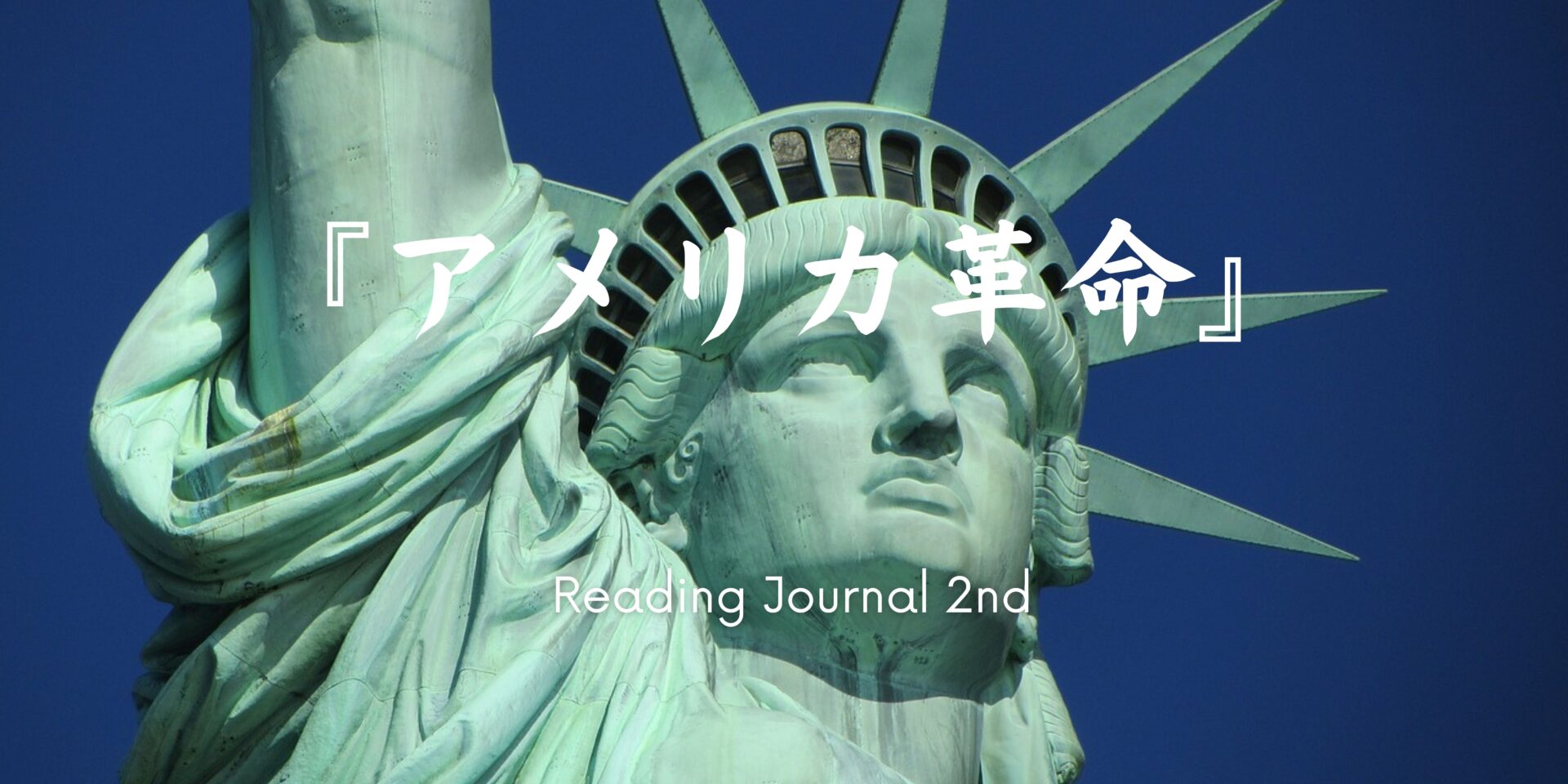


コメント