『本を読む本』 M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第四部 読書の最終目標 14 シントピカル読書 — 読書の四レベル(前半)
今日からいよいよ「第四部 読書の最終目標」「14 シントピカル読書」に入る。シントピカル読書とは、「一冊だけでなく一つの主題について何冊もの本を相互に関連づけて読むこと」である。
「シントピカル読書」は、“前半”と“後半”の二つに分け“前半”では、シントピカル読書における点検読書の役割とシントピカル読書の五つの段階についてまとめることにする。それでは読み始めよう。
シントピカル読書における主題
シントピカル読書は、同一主題についての本を二冊以上読むことを言う。一つの問題について、いくつかの関連書があるが、同一主題についての二冊以上の本を選び出す作業は非常に困難である。
ある主題に関係する本の範囲は、非常に広く、読者はまず研究しようとする主題を定めなければならない。しかし、その主題を定める作業をするためには多くの本を読む必要がある。
どんな主題でシントピカル読書をするにせよ、読者は、奇妙な矛盾におちいる。同一主題について二冊以上の本を読むからには、はじめに、主題そのものがはっきりしなければならない。ところが、まず読んでみなければ、主題がはっきりしないというのも、ある意味正しい。(抜粋)
シントピカル読書における点検読書
読書のレベルは、次々と積み重なっていくものであるので、点検読書(ココ参照)も分析読書もシントピカル読書の準備段階と言える。そして、点検読書は、ここにいたり読者の大切な道具として本領を発揮する。
読者が研究しようとしている主題に対する本は数多くある。これをすべて分析読書するのは、大変に時間のかかる作業とある。そのとき、読者が点検読書に熟達している場合は、その近道となる。
まず、分析読書をする前に、集めた文献リストの書物を全部点検することである。それには、二つの効力がある。
- 主題がはっきりつかめるので、その後の分析読書の成果が大きくなる。
- 膨大な文献を、扱いよい量に整理することができる
点検読書に熟達すれば、その本が自分の追及している主題に関して重要なことを射ているかが見極められ、再読の必要があるかがわかる。
そのようにして主題に関連した書物が何冊か決まったら、いよいよ「シントピカルな方法で」読む段階となる。ここで「分析的に」ではないことに注意が必要である。
シントピカル読書の五つの段階
「シントピカル読書」には五つの段階がある。
第一段階 関連個所を見つける
シントピカル読書の第一段階は、関連個所をみつけること、である。
個々の関連書を分析的に読むのでは、個々の書物に重点がおかれ、主題は二の次になってしまう。シントピカル読書では、読む本でなく読者の関心時が優先されるため、関連図書を確認し「読者の要求に密接なかかわりのある箇所を見つける」ことが必要である。このとき、その本をくまなく読むのではなく、その本が自分にとって役に立つかという視点で見極めることが大切である。ここでは、本の著者の意図と外れた箇所が役に立つ場合でも差し支えない。
第二段階 著者に折り合いをつけさせる
分析読書では、著者と折り合いをつけるため、キー・ワードを探し、その使い方をつかむ必要があった。しかし、シントピカル読書では、複数の著者を相手にする。そのため、多数の著者が同じ言葉を同じ意味で使っていることは考えられず、読者の方が用語をしっかりきめ、言葉の使い方について著者に折り合いをつけさせなくてはならない。これがシントピカル読書で一番難しいところである。
第三段階 質問を明確にすること
分析読書では、命題を理解する必要があったが、これはシントピカル読書でも同じである。読者が用語の意味を決める必要があるのと同じように読者が命題を立てる必要がある。
この作業に一番良い方法は、問題の解決を与えてくれそうな一連の質問を作り、それぞれの著者から答えをもらうことである。質問は、問題解決を助けるような方法と、順序で述べられなければならず、また大部分の著者から回答があるように作らなければならない。
最初の質問は、研究しようとする現象が存在するか、またある思想には、どんな特徴があるかということに関するものである。これらの質問に、著者が答えていれば、次に、その現象があるとどうしてわかるか、その思想はどういう形をとってあらわれているかを、問うことができよう。そして最後に、前の質問に対する著者のさまざまな答えから得られる結論に関する一連の質問をすることになるだろう。(抜粋)
第四段階 論点を定める
ここで、質問が明確であり、それに対する著者の答えが対立していることがはっきりした場合は、論点が生じたことになる。このあい対立する意見が二つの場合は、比較的単純だが、三つ以上の場合は、対立する意見を整理し、著者をそれぞれの意見によって分類する必要がある。
このとき意見の相違が、主題に対する意見の相違でなく、単に質問についての解釈の相違であることが多いので注意が必要である。真の論争は、質問の意味を双方が取り違えていないのにかかわらず、著者の意見が対立する場合である。
この主題に関する論考は、多くの論点を含むため、これらを分類する必要があり、一連の質問から生まれる多数の論点の集まりは、「論争」と呼ぶことが出来る。
シントピカル読書では、これらをはっきりと分類し、きちんと配列できなければならない。
第五段階 主題についての論考を分析する
ここまでの段階は、分析読書の第一、第二段階に相当する。ここまでくれば「それは何を言っているか」「どのように言っているか」という二つの質問に答えられるはずである。
シントピカル読書の第五段階では、上の質問に加えて「それは真実か」「それにはどんな意味があるか」の二つの質問に答えねばならない。
読者が取り上げた主題に真実があるとすれば、それは命題や主張の中にあるのではなく、秩序だった論考のなかにある。真実をつかみそれを他に人に示すには、ただ質問しただけでは十分でない。質問の順序意味や各著者の答えが違っている理由などを述べる必要がある。さらに出展を明らかにする必要もある。これらの作業を終えて、論考を分析したと言える。
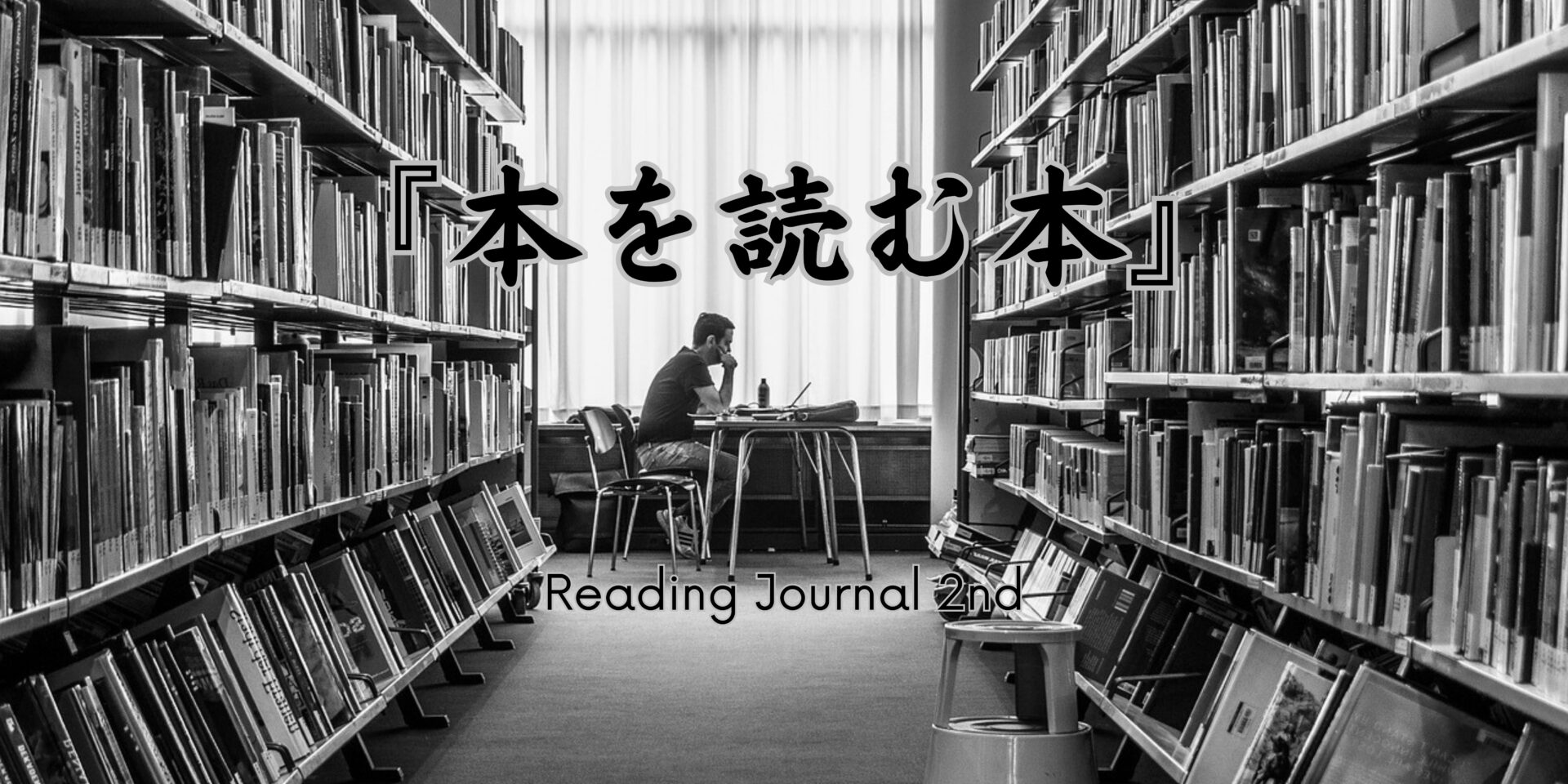


コメント