『本を読む本』 M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第三部 文学書の読みかた 13 小説、戯曲、詩の読みかた (前半)
「第二部 分析読書」が終わって、今日から「第三部 文学書の読みかた」「13 小説、戯曲、詩の読みかた」に入る。この本のメインテーマは、分析読書なのだが、最後に究極の読書法として「シントピカル読書」についての解説がある。分析読書とシントピカル読書の間に本章が挟んであって、一息入れよういうことだと思う。
「文学書の読みかた」は、“前半”と“後半”に二つに分けて、”前半“では、「文学書を読むときにすべきでないこと」と「ノンフィクションの読書法からの類推したフィクションの読みかた」をまとめ、”後半“では、小説、戯曲、詩といったジャンル別のところをまとめることにする。
本書で取り扱っていた読書法は、主としてノンフィクションのそれもかたい方に属するものばかりであった。これまで小説などのフィクションの読み方を扱わなかったのは、ノンフィクションの本と一緒に論じたのでは、混乱を招くからである。
小説などのフィクションについては、その読みかたを心得ている人も多いが、実際には、「なぜ面白かったか」「小説のどこが好きか」などの質問に答えられる人は少ない。
この「なぜ」に明確に答えるには、審美的な能力を広汎に分析する必要がある。(抜粋)
しかし、ここでは、いくつかの助言を与えることだけに留める。
文学書を読むとき、してはならないこと
「文学の影響力に抵抗してはならない」
文学書を読むときにしてはならないことの一つ目は、「文学の影響力に抵抗してはならない」である。
まず、教養書と文学書の根本的違いは、前者が経験によって得られた「知識」を伝えるが、後者は、「経験そのもの」を伝えるという点にある。何かを「知る」には、知性(判断力、推理力)が必要であるが、何かを「経験する」には、感覚と想像力が必要である。そのため文学は主として想像力に訴える。
また、教養書を読む態度と文学を読む態度にも違いがあり、文学を読むときは「積極的な受け身」のような姿勢が必要である。つまり無防備で作品に向かうのである。
文学を読むときには深みのある経験を目標にすべきであり、そのため感動を妨げる者は取り除く必要がある。
「文学の中に名辞、命題、論証を求めてはならない」
文学を読むときにしてはならないことの二つ目は「文学の中に名辞、命題、論証を求めてはならない」である。
「教養書」と文学では、目的が異なるため、言葉の使い方が違ってくる。文学では言語の曖昧さを最大限に使用する。その曖昧さにより独特の豊かさと力強さが得られる。教養書では論理を大切にするため、あいまいさのない明確さを理相とするが、文学でははっきり述べることと同じくらい言外の意味がものをいう。そのため、文学には名辞、命題、論証などを求めてはならないことになる。
教養書と同じように詩や小説、戯曲などからも学ぶことはできる。しかしそれは、フィクションの中の代行経験から学ぶのである。
「知識の伝達の真実性や一貫性をはかる尺度によって文学を批判してはならない」
文学を読むときにしてはならないことの最後は「知識の伝達の真実性や一貫性をはかる尺度によって文学を批判してはならない」である。
良い小説の「真実」は、迫真性であり、人生や社会の事実を描く必要はない。小説では、作家が創造した世界の中で、真実の物語があればよい。
文学を読むための一般法則
次に著者は、「教養書」の読みかたの規則から類推して文学の読みかたを考察しt下いる。
教養書の読みかたの規則は、
- 第一段階(構造的):本の構造を調べ、統一と部分の成り立ちを発見する
- 第二段階(解釈的):名辞、命題、論証をつきとめる
- 第三段階(批判的):著者の主張に賛成するか反対するか
に分かれていた。
これを、詩や小説、戯曲を読む場合に応用する。
構造的規則の文学への応用
- 文学作品の種類を知ること。詩や小説、そして戯曲など文学の種類が違えば、創作の方法も異なる。そのため読者のほうも読み方を変えなければならない。
- 作品全体の統一を把握する。それが出来たかどうかは、その統一性を短い文で表現すればよい。文学の場合は、具体的な経験を伝えることが目的であるため、「作品の統一性は常にプロットにある」と言える。そのため作品のプロットを簡潔に要約できれば良い。
- 部分が、どのように全体を構成しているかを知る。文学の場合、部分とは、プロットの展開のための細部(性格描写、事件の細部など)でそれが発端から結末までどのように展開するかを見なければならない。
教養書の場合は部分を取り出しても、独立したものとして読むことができるが、文学の場合は、「章」や「幕」「スタンザ」などを切り離すことはできない。
解釈的規則の文学への応用
教養書の場合は、解釈の規則は名辞、命題、論証などの論理的用法の規則であった。これを文学に置きかえると、論理的用法ではなく詩的用法となる。
- 名辞に相当するものは、登場人物、事件、エピソード、登場人物の思想、会話、感情、行動などである。読者は登場人物をよく知り、彼らと事件を体験できるほど親しくならなければならない。
- 作品の各要素は、相互に結びつけられ物語が展開する。「命題を見つける」という規則を文学に当てはめると、登場人物と親しくなり、事件や悩みごとに真摯につき合うということになる。
- 「論理の規則」では、証拠や論拠から結論に進む動きを追っていた。同じように文学では、登場人物の動きについていく必要がある。つまりプロットの展開を理解する必要がある。
以上の三つのステップから、作家の創造過程と、その秘密がわかればよい。これを知ることは、作品を読む楽しみをます。こうして、「何が」好きかではなく、「どうして」好きなのかもわかるようになるだろう。(抜粋)
批判的規則の文学への応用
最後は、批判的規則の文学への応用であるが、これは、「作家が読者に経験させようとしたものを十分に感得できるまでは批判してはならない」ということになる。
そして小説の場合は、反対したり賛成したりするのではなく、好きであるか嫌いであるかとなる。なぜならば「教養書」を批判する基準は「真」だが、文学の場合は「美」であるからである。
以上を、一つの心得としてまとめると、次のようになる「作品の好ききらいを言う前に、読者は、まず作品を誠実に味わうように努力すること」。(抜粋)
この批評も最初のうちは、自分の好みが中心となるが、ほんとうの批評となるには、それだけでは足りない。本当の批評になるには、自分の好みや見方を離れ、その本から自分の得た感動の原因となっているものを、客観的に述べる必要がある。
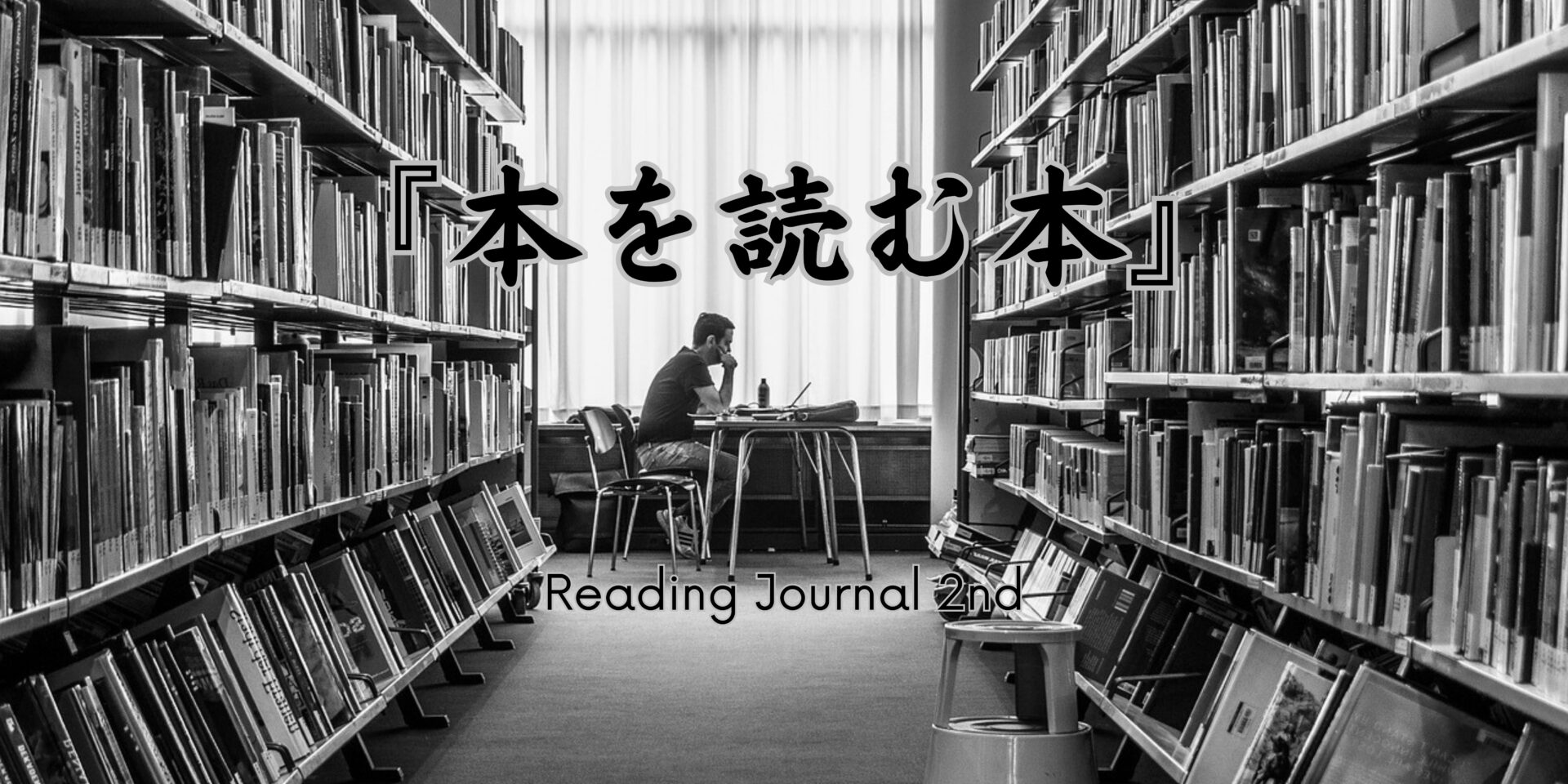


コメント