『本を読む本』 M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二部 分析読書 — 読書の第三レベル 11 著者に賛成するか、反対するか(後半)
今日のところは、「第二部 分析読書」「11 著者に賛成するか、反対するか」の”後半“である。“前回”までで、分析読書の解説が終わった。今日のところは、今までの分析読書に対する議論を俯瞰しまとめとしている。それでは読み始めよう。
分析読書の三つの段階
ここで著者は、分析読書の三つの段階の規則をまとめている。まずはこの部分を長文引用する。
1 分析読書の第一段階 --- 何についての本であるかを見分ける ---
(1)種類と主題によって本を分類する
(2)その本全体が何に関する者かを、できるだけ簡潔に述べる。
(3)主要な部分を順序よく関連づけてあげ、その概要を述べる。
(4)著者が解決しようとしている問題が何であるかを明らかにする。
II 分析読書の第二段階 --- 内容を解釈する ---
(5)キー・ワードを見つけ、著者と折り合いをつける
(6)重要な文を見つけ著者の主要な命題を把握する
(7)一連の文の中に著者の論証を見つける。または、いくつかの文を取り出して、論証を組み立てる。
(8)著者が解決した問題はどれで、解決していない問題はどれか、見きわめる。未解決の問題については、解決に失敗したことを、著者が自覚しているかどうか見定める。
III 分析読書の第三段階 --- 知識は伝達されたか ---
(A)知的エチケットの一般的心得
(9)「概略」と「解釈」を終えないうちは、批評に取りかからないこと。(「わかった」と言えるまでは、賛成、反対、判断保留の態度の表明を差し控えること)
(10)けんか腰の反論はよくない。
(11)批評的な判断を下すには、十分根拠をあげて、知識と単なる個人的な意見を、はっきり区別すること。
(B)批評に関してとくに注意する事項
(12)著者が知識不足である点を、明らかにすること。
(13)著者の知識に誤りがある点を、明らかにすること。
(14)著者が論理性に欠ける点を、明らかにすること。
(15)著者の分析や説明が不完全である点を、明らかにすること。
〈注意〉(12)(13)(14)は、反対の心得である。この三つが立証できない限り、著者の主張に、ある程度、賛成しなければならない。そのうえで、(15)の批判に照らして、全体について判断を保留する場合もある。(抜粋)
ここで、分析読書の第一段階の4つの規則は、「この本は全体として何に関するものか」という質問に答えるために役立つ。つぎの分析読書の第二段階の4つの規則は「何がどのように述べられているか」という質問に答えるために役立つ。そして第三段階の7つの規則 — 知的エチケットと批判の注意 — は、「本に書いてあることが真実であるか」と「それにどんな意義がるか」という質問に答えるために役立つ。
ここで著者は、本に書かれていることが真実であるならば、「それにはどんな意義があるか」という最終の質問があるとしている。読者は読書の過程で常にこのことを問い続けなければならない。
最後に著者は、これまで解説してきた分析読書の規則は、あくまで理想であるとしている。そして極わずかの本を除けばこの規則のとおりに読む読者はいないとしている。
そして、理想的な読書に近づくためには、このような規則を守った読書を一冊でも多くすることが大切であり、そのように熟読に値する本は数多くある。しかし、点検読書に留めておく本はさらに多くある。そのため
本当の意味ですぐれた読書家になるには、それぞれの本にふさわしい読みかたを見つけ、読書の技術を使い分けるコツを体得することである。(抜粋)
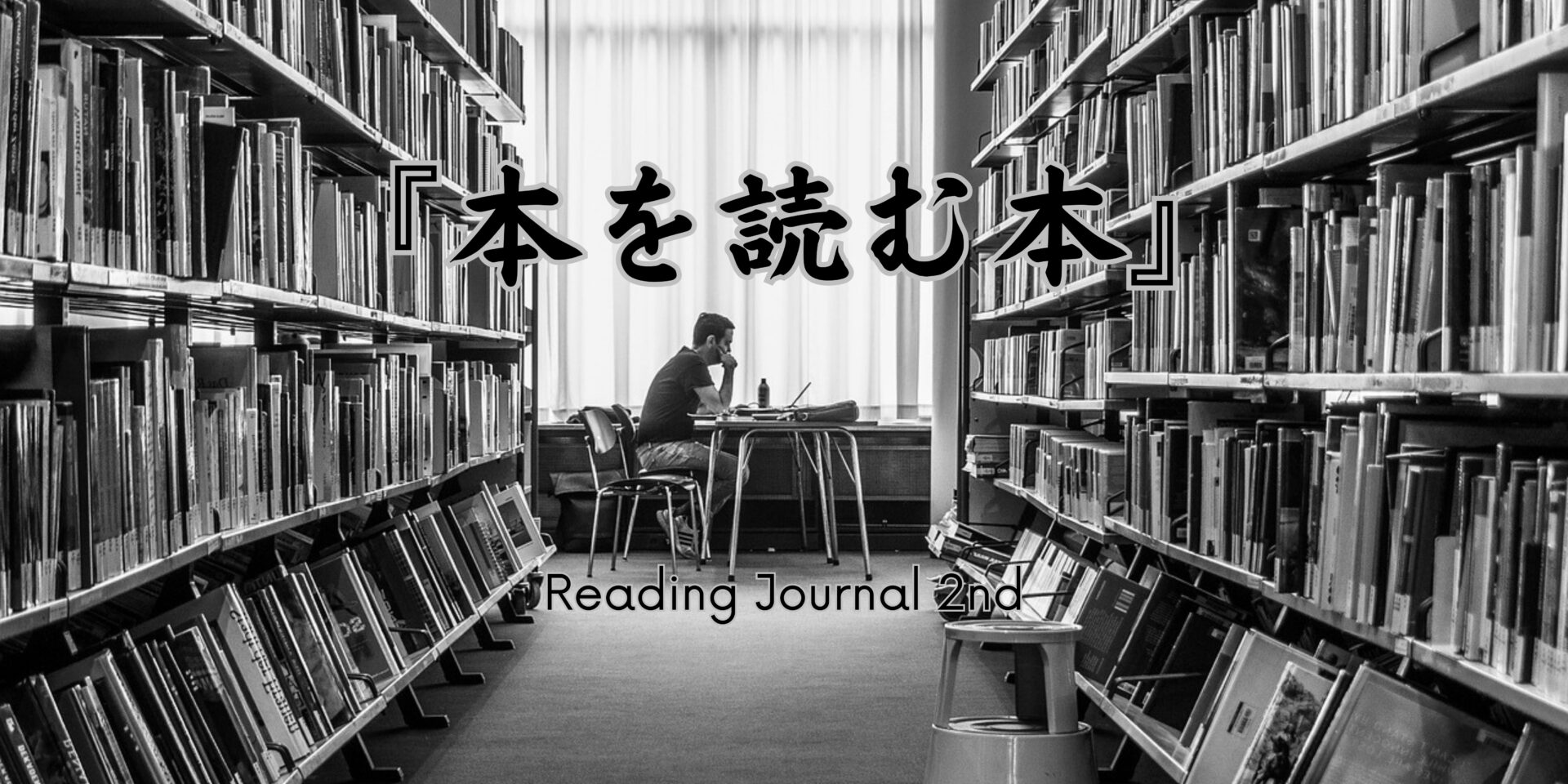


コメント