『本を読む本』 M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二部 分析読書 — 読書の第三レベル 9 著者の伝えたいことは何か
今日から、「第二部 分析読書」「9 著者の伝えたいことは何か」に入る。ここでは”前回“につづき、分析読書の第二段階を扱う。
”前回“は、分析読書の第二段階の規則の最初、規則五「単語の使い方の理解」であった。今日のところはそれに続き、規則六「本の命題を知る」、規則七「論証を見つけ、組み立てる」、そして規則八「著者の解決を検討する」についてである。それでは読み始めよう。
分析読書 第六 の規則「本の命題を知る」
知識を伝える「教養書」は、著者は本にあらわす知識や意図を序文で明らかにする。この「あることがらにおける著者の判断(肯定、否定など)の表明」を「命題」呼ぶ。読者は、著者が序文に示したことが守られているか、命題を見つけ検討する必要がある。
分析読書第六の規則は「本の命題を知る」である。読者は、著者の命題を知るだけで十分ではない。なぜならば「はっきりと根拠が示されていない限り、著者の命題は個人的な意見にすぎない」からである。そのため読者は、「その命題をたてるにいたった理由」を理解する必要がある。
分析読書 第七 の規則「論証を見つけ、組み立てる」
そのため、分析読書第七の規則は「論証」を取り扱う。
ここで「論証」とは、「ある結果を導くための根拠、理由を示す一連の文」のことである。論証は、一つのパラグラフ、少なくともいくつかの文が必要である。
ここで、著者は「解釈の規則には文法と論理の二つの側面がある(ココを参照)」ことに再び言及している。ここで文法は、言葉そのものを扱い、論理はことばの意味、言葉の背後の思想を扱う。
ここで文法の単位、「単語、文、一連の文(パラグラフ)」に対して論理は「名辞(単語の意味)、命題、論証」に対応する。
文および命題 — [第六の規則]
単語と名辞(単語の意味)のところでは、一つの単語が複数の意味(名辞)を表わすことがあることに触れた(ココ参照)。それと同じように、一つの、文(パラグラフ)が常に一つの命題をあらわすとは限らない。その理由は少なくとも二つある。
- 単語というものは、さまざまな意味(名辞)をあらわす
- 多くの文は、複雑な構造を持ち、言葉が曖昧でなくても、いくつかの文が組み合わされると、二つ以上の命題を表わす
複雑な文ではいくつかの命題を含むことがあり、決して文と命題は一体一の対応ではない。
ここで大切なことは、著者の意見に同意できるかどうかはともかく、著者の主張を理解することが先決である。なぜなら、著者の主張(命題)が理解しなければ、著者の述べることに判断を下すことはできないからである。
解釈の三つの決まりの確認
ここで著者は、解釈の三つの決まりを再度確認している。
- 「重要な単語を見つけ、著者と折り合いをつけること」:分析読書の第五の規則
- 「もっとも重要な文に注目して、そこに含まれる命題を見つけること」:分析読書の第六の規則
- 「一連の文から基本的な論証を見つけ、これを組み立てること」:分析読書の第七の規則
これらの規則は主に「教養書」のためのものであり、文学書については、第三部「文学のよみかた」に示される。
キー・センテンスを見つける — [第六の規則]
分析読書の第六の規則を行うためには、重要な文(キー・センテンス)を見つける必要がある。
重要な文、読者が注意すべき文は、一読してだけでは完全に理解できない、解釈に骨が折れる文である。このような文は、時間をかけて、注意深く読む必要がある。
文ではいろいろなことが述べられるが、「著者が伝達すべきもっとも重要なことは、あることがらについての著者自身の判断(肯定ないし否定)の表明と、その理由」である。読者はこのような文をしっかり理解しなければならない。
このような文には、文を目立たせるような印刷上の工夫がしてあったり、説明の順序や表現に配慮がしてあるものもある。しかし基本的には、そのような文を発見することは読者の仕事である。
そのような文を発見するには「理解できない箇所」をはっきりさせること、重要な単語が文に使われているかどうか、などが役立つ。
また、主要な命題は主要な論証に含まれているはずなので、はじめと終わりがあって、ひとつのまとまりをなしている一連の文は、重要な文であることが多い。
命題を見つける — [第六の規則]
重要な文がわかったら、次に行うことは、命題を見つけること、つまり文のあらわす意味をつかむことである。
単語の意味が分かれば名辞がわかるように、文を構成する単語を解釈することにより命題がわかる。また、ある特定の単語の意味(名辞)をつかむには、前後の単語の意味を手がかりにするように、解釈すべき文の命題をつかむには、関係ありそうな文を前後から拾い出し利用することである。
また、複雑な文は、二つ以上の命題をあらわしている。関連があっても異なる命題は、すべて切り離して初めて文を理解したことになる。
文中の命題が理解できたかどうかを確かめる一番良い方法は、「自分の言葉で言いかえてみる」ことである。もし、著者の言葉から離れることができない場合は、それは著者の「思想や知識」が伝わっていることにならず「著者の精神をつかんだ」ことにならない。
これはまた、同じテーマについて数冊の本を読むシントピカル読書の場合でも問題になる。著者が違えば同じことを述べるにも、違う言葉を使うため、正しく言葉の意味(名辞、命題)を捉えていない読者では、関連書を比較検討することはできないからである。
命題を理解できたか知るもう一つの方法は、「一般的真理を具体的な経験に即して、あるいは、あり得る場合を想定して、例証すること」である。
重要なことは、命題は真空の中に存在しているのではなく、われわれが現実に生きている世界について述べたものだということである。命題が何らかの関連がある現実、あるいは、あり得る事実を示すことが出来なければ、読者によって「思想や知識」にかかわることはできない。それでは、「言葉の遊び」に終わるだけである。(抜粋)
論証を見つけ、組み立てる — [第七の規則]
分析読書の第七の規則では、扱うのは文の集まりである。第七の規則「論証」は、さまざまな文の集まりであらわされる。
ここでパラグラフには、論証を扱わないものもあるため、分析読書第七の規則は、「まず重要な論証を述べているパラグラフを見つけること、そのようなパラグラフが見つからないときには、あちらこちらのパラグラフから文を取り出し、論証を構成する命題が含まれている一連の文を集めて、論証を組み立てることである」、と言える。
すぐれた「教養書」は、思想がはっきり示されている。そして、論証が展開されていくにつれて自然と要約されていく。複雑な論証の後で、それが要約されていれば読者は論証の過程を跡づけることができる。
反対に悪い本は、論証の手順をしばしば省く。それは、論証に密接に関係のあることがらを、反駁されるのを恐れて故意に伏せておくからである。そのため、読者は論証のすべての手順を注意深く抑えておく必要がある。
ここで著者は、解釈の第三規則、つまり論証を実行するため役立つことを幾つか述べるとしている。
- どの論証にもいくつかの叙述が含まれていること:その中には著者の結論をなぜ受け入れなければならないかという理由を述べたものがある。
- 論証には、帰納的(事実によって一般化する証明法)と演繹法(一連の一般的叙述によって、一般的法則を発見する方法)がある。
- 著者が「仮定」しなければならないことは何であるか、論証や証拠によって「立証できるもの」は何か、論証を必要としない自明のことはなにか、をしっかり見定めること。
著者の解決を検討する — [第八の規則]
ここで、「解釈」の三つの規則から、分析読書第八の規則、「著者の解決が何であるかを検討すること」が導き出される。それは「解釈」の規則の最終ステップであり、分析読書の第一段階「概略」と第二段階「解釈」とを結びつけるものである。
分析読書の第一段階の最終手順(第四の規則)は、著者が解決しようとしている主要な問題を見つけることだった。そして、第二段階の「解釈」を通して、名辞、命題、論証がわかった。そこで著者が解決しようとしていた問題のうち、何が解決できたかを確認するのが、この第八の規則である。
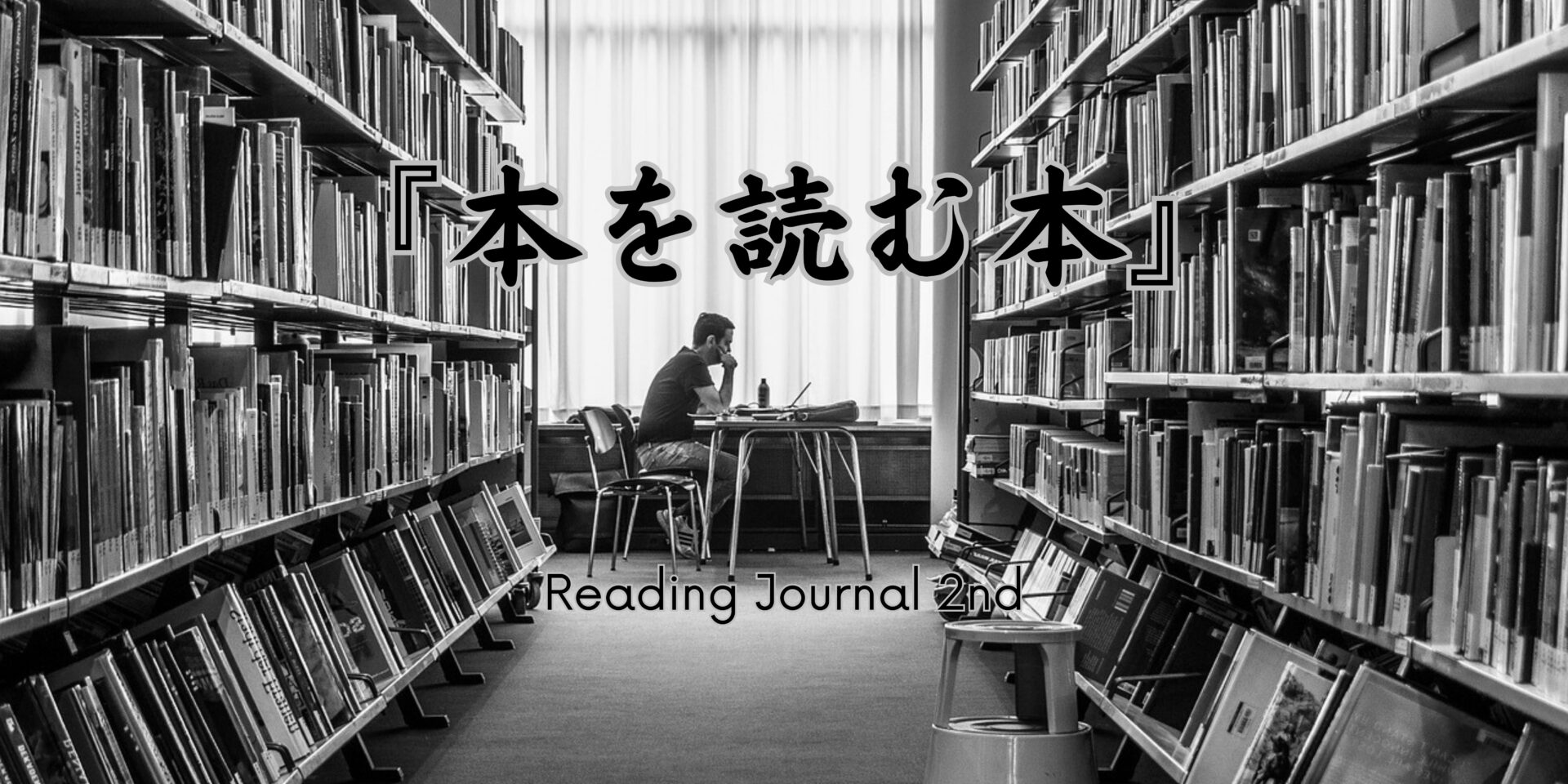


コメント