『本を読む本』 M.J.アドラー / C.V.ドレーン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二部 分析読書 — 読書の第三レベル 7 本を透視する
今日から、「第二部 分析読書」「7 本を透視する」に入る。”前回“は、分析読書 第一の規則である「本の種類を知る」ということについてであった。本章では、分析読書第二の規則「本の全体の統一の要約」、第三の規則「本の部分の構成の把握」、そして分析読書第四の規則「著者の問題を知る」について書かれている。それでは、読み始めよう。
どの本も、二枚の表紙の間には骨格が隠れている。分析的読者の仕事は、それを見つけ出すことである。(抜粋)
どんな本も、骨格の上に衣装をまとっている。本を理解するということは、その構造を把握しなければならない。
分析読書 第二の規則「本の全体と統一の要約」
読むに値する本であれば、例外なく統一があり、その部分も秩序よく組織されている。そして「その本の全体の統一を二、三行か、せいぜい数行の文にあらわしてみる」というのが分析読書の第二の規則である。ここで問題にするのは本の内容であり「どんな種類」の本であるか(第一の規則)とは違う。
その統一を見つけることによりその本の主題や目的がわかる。しかし、漫然と統一があるとわかっただけでは十分ではなく、その統一がどういうものか自分の言葉で言ってみることが必要である。
分析読書 第三の規則「本の部分の構成の把握」
分析読書の第三の規則は「その本の主な部分を述べ、それらの部分がどのように順序よく統一性を持って配列されて全体を構成しているかを示すこと」である。
どのような本でも、それは複合的な統一体である。それは部分にわかれ、それらの部分がある程度の独立性を持ち、秩序をもって配列されている。良い本は、これらの部分が機能的につながり全体として統一性を持っている。
この著者の設計図、つまり構想を見つけ出すことは、読者の仕事である。
構想とプロット — 本の統一 [第二の規則]
ここで著者は、分析読書第二の規則に戻り、実例を示し読者が規則の実行する場合の参考にするとしている。
まず著者は『オデュッセイア』を例に、さまざまなエピソードの中に筋の統一、プロットの太い線がある、ことを指摘している。アリストテレスは、そのことがすべての良い物語、戯曲のしるしであるとが『詩学』のなかで述べている。
このプロットがわかり、物語の統一が見出されるとそれぞれの部分の意味もわかる。また、このようなプロットは煎じ詰めると、世の中にそれほどの数はい。
本の統一を発見することを著者が助けてくれる場合もある。題名だけで事足りることもある。序文で著者自身が構想の統一を語っている場合もある。また、「教養書」の場合は、各パラグラフの最初に要約が書かれていることもある。
著者の力を借りられる場合は、素直にその力を借りた方がよい。しかし、統一を見つける仕事はあくまでも読者の仕事で、そのためには本全体を読み通す必要がある。
著者は、この統一を探す作業で心に留めておくことが二つあるとしている。
- ひとつ目は、読者が本の構想を述べるにあたり、表題や序文などに十分に注意すること
- そして二つ目は、要約は簡潔で性格でわかりやすいものがよいがある要約が絶対であるということはなく、まったく違った書き方の要約が両方ともよかったり、また悪かったりする場合もあることである
アウトラインをつかむ [第三の規則]
次に第三の規則「本の部分の構成の把握」に移る。この第三の規則は、第二の規則と密接に関連している。全体の統一(第二の規則)を把握すれば、主要部分(第三の規則)はおのずから明らかになる。逆に部分がわからなければ、統一はわからない。
それなら一つの規則でよさそうだが、それを二つにするのは便宜的理由である。つまり「複合的で統一性のある構造を把握するためには、一段階より二段階に分けてする方がやさしい」からである。つまり
- 第二の規則:統一に注目
- 第三の規則:複合性に注目
となる。
そして、もう一つ二つに分けた理由は、統一をつかんだとき、本の主要な部分はわかるが、部分はそれ自体が複合的で内部構造をもつ。そのため、第三の規則では、その部分のそれぞれの統一性を複合性を持った小さな全体として要約を試みる必要がある。つまりアウトラインを見つけることである。
ここで著者は、この第三の規則の手順について次のように解説している。
たとえば、(一)著者の構想は五つの主要部分に分かれている。第一部はこれこれについて、第二部はこれこれについて・・・・第五部はこれこれについて。(二)第一の主要部分は三つに区分できる。第一の区分はXについて、第二はYについて、第三はZについて。(三)第一部の第一区分で、著者の述べている要点は四つある。第一はA、第二はB、第三はC、第四はD.(抜粋)
このようなことをするのは大変だと思うかもしれないが、良い読者はこれが習慣となっている。しかし、最高水準の読者でも理想に近い規則で読む本はごく少数であり、どこまで厳密に規則を適用するかは、本の性格と読者の目的による。
本によっては、表向きの構成区分が読者のつくるアウトラインと違っている場合もあるが、重要なのはアウトラインをつくることである。
本の構造を見分けること(第三の規則)は重要で、それなしには本の統一(第二の規則)を見つけることもうまくいかない。
読む技術と書く技術
ここでの分析読書の二つの技術、つまり「本の全体の統一の要約」と「本の部分の構成の把握」は、書くときの技術でもある。
書き手は、骨組みから出発してそれに衣装をつけ、骨組みを「包みこもう」とするが、読み手は隠れている骨組みを「あばき出そう」とする。(抜粋)
良き書き手は、厚ぼったい脂肪の下に貧弱な骨組みを隠したり、骨が透けて見えるほど薄い肉付けをしない。ほどよい肉付けをして、間接の位置を接合の所在がわかるようにする。
また、ある知識体系を順序良く示すことが目的の「教養書」にも、骨組みだけでなく肉付けが必要である。なぜなら、本の肉付けも骨組みと同様に、書物の部分だからである。この肉付けが、書物に命を吹き込むのである。
この二つの規則により、できの良い本とできの悪い本を見分けることができる。つまり、まず十分に熟達した読者に統一性が認められない本は悪い本と言える。
分析読書 第四の規則「著者の問題を知る」
分析読書の第四の規則は「著者の問題としている点は何であるかを知る」である。
本は、著者の問題の答えが書いてあるものだが、その問題まで書いてないこともある。その著者が何を問題としているかを、できるだけ正確に読み取るのは読者の仕事である。また、主要な問題が複合的である場合は、その部分部分の問題も正しく把握し整理することが肝心である。
この第四の規則は、前の二つの規則と重複している部分もあり、また第四の規則を実行することにより前の二つの規則の実行にも役立つ。
この規則は、前の二つの規則よりとっつきにくく、熟達した読者でもこの規則を守っている人は少ない。しかし、難しい本に取り組もうとする場合には、ずっと役立つ。
分析読書の第一段階 [第一~第四の規則]
ここまでの規則(第一~第四の規則)は、互いに関連していて、目的が一つのグループを成す。ここまでをまとめて分析読書の第一段階である。
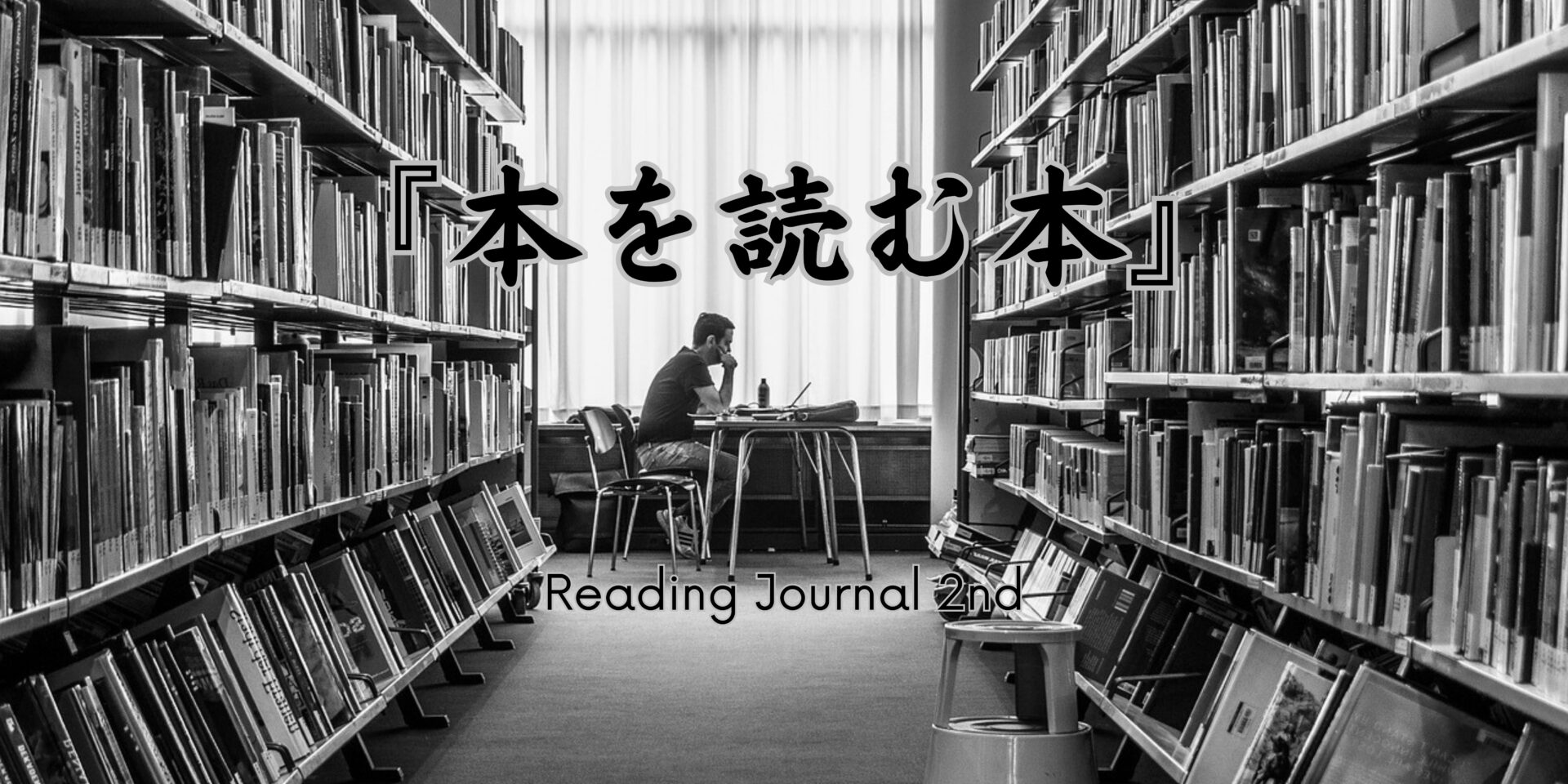


コメント