『刺青 痴人の愛 麒麟 春琴抄』 谷崎 潤一郎 著、文藝春秋(文春文庫・現代日本文学館)、2021年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
『刺青 痴人の愛 麒麟 春琴抄』
井波律子の『論語入門』を読んだのですが、その中で気になった話がありました。つまりこの条
子 南子を見る。子路 説ばず。夫子 之れに矢いて曰く、予れ否らざる所の者は、天 之れを厭てん、天 之れを厭てん。(雍也第六)(抜粋)
先生が南子と会われた。子路は不機嫌であった。すると先生は子路に誓って言われた。「もし私のしたことが道にはずれていたならば、天が私を見捨てるだろう、天が私を見捨てるだろう」。(抜粋)
である。
南子は、衛の霊公の夫人であり、いわくつきの悪女であったらしい。そして孔子が衛に身を寄せていた時、南子の求めに応じて、彼女を謁見した。そのことを快く思わなかった高弟の子路とのやり取りが上の条である。
謁見の時、南氏は薄い葛布の帳ごしに対面し、孔子の稽首の礼に答えて再拝したとき、彼女の腰につけていた佩玉がすがすがしい音をたてた、と伝わっている(『史記』孔子世家)。
井波が言うには、この条はその艶麗な雰囲気のためか、谷崎潤一郎の『麒麟』や中島敦の『弟子』の題材となっているとのことである。
なるほど、何か気になる。調べてみると中島敦の『弟子』は入手しづらそうだが、谷崎潤一郎の『麒麟』は、この本『刺青 痴人の愛 麒麟 春琴抄』に収録されている。なので、まずは本書を入手してみました。
「文藝春秋BOOKS」によると、この本は、1960年代に刊行を始めた「現代日本文学館」の谷崎作品の中から、戦前の代表作(「刺青」「痴人の愛」「春琴抄」)と初期佳作「麒麟」」を選んで収録したとのことである。そして、井上靖による評伝・作品解説が巻末に収録されていると、ある。そうそう、確かにカバーに「現代日本文学館」って書いてあるね♬
[追記]
上の部分に、「中島敦の『弟子』は入手しづらそうだ」とあるのですが、本書を読んでいる時、ふと巻末の文春文庫の宣伝を見ると、同じく「現代日本文学館」シリーズの中島敦『李陵 山月記』の中に『弟子』が収録されていること書いてあった。「なんだぁ~、こんなところにあったじゃん!」とちょっと喜んだ。
が、しかし、その他も文庫を調べてみると、岩波文庫、新潮文庫、角川文庫、ちくま学芸文庫、ちくま文庫と収録されていて、ある意味「中島敦にもれなく『弟子』がついてくる」状態だった。がぼん!
読み始める前に、各作品のページ数を数えてみた。
『刺青』・・・12ページ、『麒麟』・・・21ページ、『痴人の愛』・・・312ページ、『春琴抄』・・・68ページ、「谷崎潤一郎伝」・・・29ページ、「作品解説」・・・5ページ、である。
『痴人の愛』が全体の2/3以上を占めている。確かに新潮文庫や角川文庫、中公文庫などでは『痴人の愛』だけで1冊となっている。そういう意味で、この本、だいぶ“お得”な感じがする。(今回は、『麒麟』目当てですがね)
『刺青』
井上靖の作品解説によると、この『刺青』は、次の『麒麟』とともに、谷崎の作家としての地位を決定づけた出世作である。そして一般にはこの作品が処女作として通っている(実際にはその前に『誕生』という作品がある)。『刺青』は、発表された当時は、何の反響もなかったが、翌年に永井荷風が「谷崎潤一郎氏の作品」という評論で他の作品と共に絶賛した。これにより谷崎は文壇に花々しく登場する。
「刺青」は、清吉と云う加虐性を持った腕利きの刺青師が、「光輝ある美女の肌を得て、それに己の魂を彫り込む」という宿願を果たす物語である。
清吉は、娘に男を犠牲にし、それを肥してしまうような本性を感じ取る。そして、刺青を施した娘からは、もう臆病さのかけらもなくなってしまう。娘は最後に、
「親方、私はもう今までのような臆病な心を、さらりと捨てました。 ---- お前さんは真先に私の肥料になったんだねえ」(抜粋)
と言って、その目を輝かせる。
清吉の加虐性が、この刺青の施しにより娘に移動している。そしてその後、娘の言葉のように、立場が逆転し清吉が娘に翻弄される側になるのだろうか?しかし、物語はそこで終わっている。
『麒麟』
さて、いよいよ『麒麟』である。冒頭に書いたように、この話は、孔子が悪女と名高い南子と謁見する場面がハイライトとなる。
魯の国を離れ衛の国に入った孔子一向は、霊公に求められ「仁の道」を説いた。するとそれまで疲弊していた衛に少しずつ明るさが戻ってくる。そして、霊公の心が離れていくことに危機感を増した南子は、孔子に謁見するように要請した。断り切れない孔子は南子と謁見する。
結局、仁の道を歩み始めた霊公は、南子の誘惑に逆らうことはできず、また南子の言いなりになってしまう。そして、孔子一向は、衛の国を離れ曹の国へと去っていった。衛の国を去るときの最後の言葉が
「吾未見好徳如好色者也」(抜粋)
であった。結局、孔子の徳は、南子の色に負けてしまったという、結末である。(この論語の一節は、『論語入門』にも取り上げられているが、随分と違う見方となっている。ココを参照)
この話を読むにあたって、ボクには少しアドバンテージがあった。井波律子の『論語入門』を読んでいるとともに『故事成句でたどる楽しい中国史』も読んでいて、孔子の高弟の名前や性格、中国の歴代の皇帝などが何となくではあるが、知っていたので、面白く読めた。小説は中国的な雰囲気がたっぷりあって、なかなか臨場感である。もっとも多くの参考文献に当たっているだろうが、大部分は谷崎の創作なのであろう。
『痴人の愛』
やっと読み終わりました。井上靖の解説によると『痴人の愛』は、谷崎が関西に移住した直後の作品であるという。しかし、まだ関西の影響は全く現れていず、初期作品で追及された主題や手法が集成れている、とのことである。
小説のプロットは単純で、登場人物はほぼ、私とナオミの二人だけ、重要な脇役の浜田と熊谷も役割を終えたらソソっといなくなってしまう。登場人物が少なく、そして登場人物が次第に成長するなどの変化もないので、読みやすい。
物語的には、単純なぶるいなのですが、やはり谷崎流のエロティシズムは感じました。もっとも、大正時代の小説だからか、それともそれが谷崎流だからか、あからさまな、いわゆる濡れ場のような場面はなく、女の足や肌そして匂いなどの表現が細やかな色気を醸している。
それは、『刺青』や『麒麟』にも類似している。刺青では、まず女の足を垣間見て、これが自分の意図した女であることを悟り、その肌の細やかな表現があった。『痴人の愛』でも、ナオミの白い肌、日焼けしてその皮がむける状況、さらにはダンスの先生、アレシサンドラ・シュレムスカヤとの比較など細かな描写があった。
さらに匂いに関しては、ナオミが私を誘惑する場面で、口にはぁぁっと息を吹きかける「友達の接吻」が出てくるが、その時ナオミは唇に香水をたらしていた。この情景は『麒麟』の南子が口の中に「鶏舌香」を含んでいたことを思い出させた。
『春琴抄』
『春琴抄』が読み終わりました。ここまで『刺青』『麒麟』『痴人の愛』と同じようなテーマの話を読んできたが、一番良いと思う。井上靖の解説でも「発表当時から今日まで谷崎文学の傑作として、変わらぬ評価をかちえている作品である」と書いている。
ここでの一連の作品は、嗜虐的志向をもつ美しい女とそれに翻弄される男という話である。ここでも井上靖の解説から引用するとしよう。井上は、
谷崎文学を代表する傑作を三つ選ぶ場合、この作品を選ぶか、選ばないかは、なかなか面白い問題である。完成度という点からは当然一位か二位に置かれるべき作品であるが、この作品の主題となっている殉教者的なものの肯定、どこかに病的なものの感じられる愛の謳歌に同調できない者もあるに違いなく、そうした者は「春琴抄」をとらないだろうと思われる。筆者も亦、自分の好みから言えば、「少将滋幹の母」「瘋癲老人日記」「吉野葛」などの作品の方が好きである。(抜粋)
と言っている。
確かにこのどこかに病的な世界に同調できるかというと、そうではない。佐助は、春琴が顔に火傷をした後、自分の眼にやきついている春琴の顔をとどめるために、自ら針で目を突き、盲目となる。こういう場面は、個人的には、想像を絶することで、もはやオカルトに近い。そういう予備知識もあり、『痴人の愛』などを読んだ影響もあり、中ごろまでの話は、あまり気持ちが乗らなかった。
しかし、しばらく読み進めていくと、時おりその美しい文体もあり心奪われる場面が現れてくる。たとえば、鳥道楽の春琴が物干し台に上がり雲雀を放ちその声を聞く場面である。雲雀は真上に上昇し鳴きながら真っ逆さまに落ちてくるのであるが、その声を聞く春琴を、物好きな若い衆がその顔を拝むために屋根に上る。
雲雀の声が聞こえるとそれ女師匠が拝めるぞとばかりに急いで屋根に上っていった彼らがそんなに騒いだのは盲目というところに特別な魅力と深みを感じ、好奇心をそそられたのであろう平素佐助に手を曳かれて出稽古に赴く時は黙々としてむずかしい表情をしているのに、雲雀を揚げる時は晴れやかに微笑んだり物を云ったりする様子なので美貌が生き生きと見えたのであろうか。(抜粋)
このような場面に、ただ嗜虐的でわがままな女という平板さの裏にある、盲目ということの苦しさや悲しさが透けて見えるように思う。
さらに、春琴が恨みから顔に火傷をおい、佐助が眼に針を刺して盲目となる、そのあとは、文章にも時折、見える内面の複雑さも、さらに二人の愛にも、なかなか読ませるものがある。
考えてみれば『痴人の愛』などは、年端もいかぬ少女を囲って、わがままに育てて、振り回されるのだが、そこに「女体の美」とか「牲への渇望」とかいっても限界があり、愛とかいっても、なんだか分からない。『春琴抄』の場合は、春琴はなるほど、わがままで言うことを聞かず、吝嗇で意地悪である、そして佐助は、そんな春琴に仕えることを生きがいとする。そこに病的な感じがあり、汲みいれない部分もあるが、春琴と佐助の交わりの密度は深く、最初から一心同体と言っても良いほどである。『痴人の愛』で、ナオミの若い時分に私がナオミの体を洗う場面が描かれていたが、春琴の場合は、自分の下の世話を含め春琴は何もしない。それが二人にとって普通の日常であった。そして、春琴の美貌が崩れ、佐助が盲目となってからは、春琴と佐助の日常は変わらないが、そこには二人の心が本当にひとつになっているような情景となっていく、そのように感じた。
関連図書:
井波律子(著)『故事成句でたどる楽しい中国史』、岩波書店(岩波ジュニア新書)、2004年
井波 律子(著)『論語入門』 、岩波書店(岩波新書)、2012年
中島 敦(著)『李陵 山月記』 、(文春文庫・現代日本文学館)、2013年
中島 敦(著)『山月記・李陵』 、岩波書店(岩波文庫)、1994年
中島 敦(著)『李陵・山月記』 、新潮社(新潮文庫)、2003年
中島 敦(著)『李陵・山月記・弟子・名人伝』 、角川書店(角川文庫)、1968年
中島 敦(著)『教科書で読む名作 山月記・名人伝ほか』 、筑摩書房(ちくま文庫)、1968年
中島 敦(著)『ちくま日本文学012 中島敦』 、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、1968年
目次
刺青
麒麟
痴人の愛
春琴抄
谷崎潤一郎伝 井上靖
作品解説 井上靖
谷崎潤一郎年譜 稲垣達郎
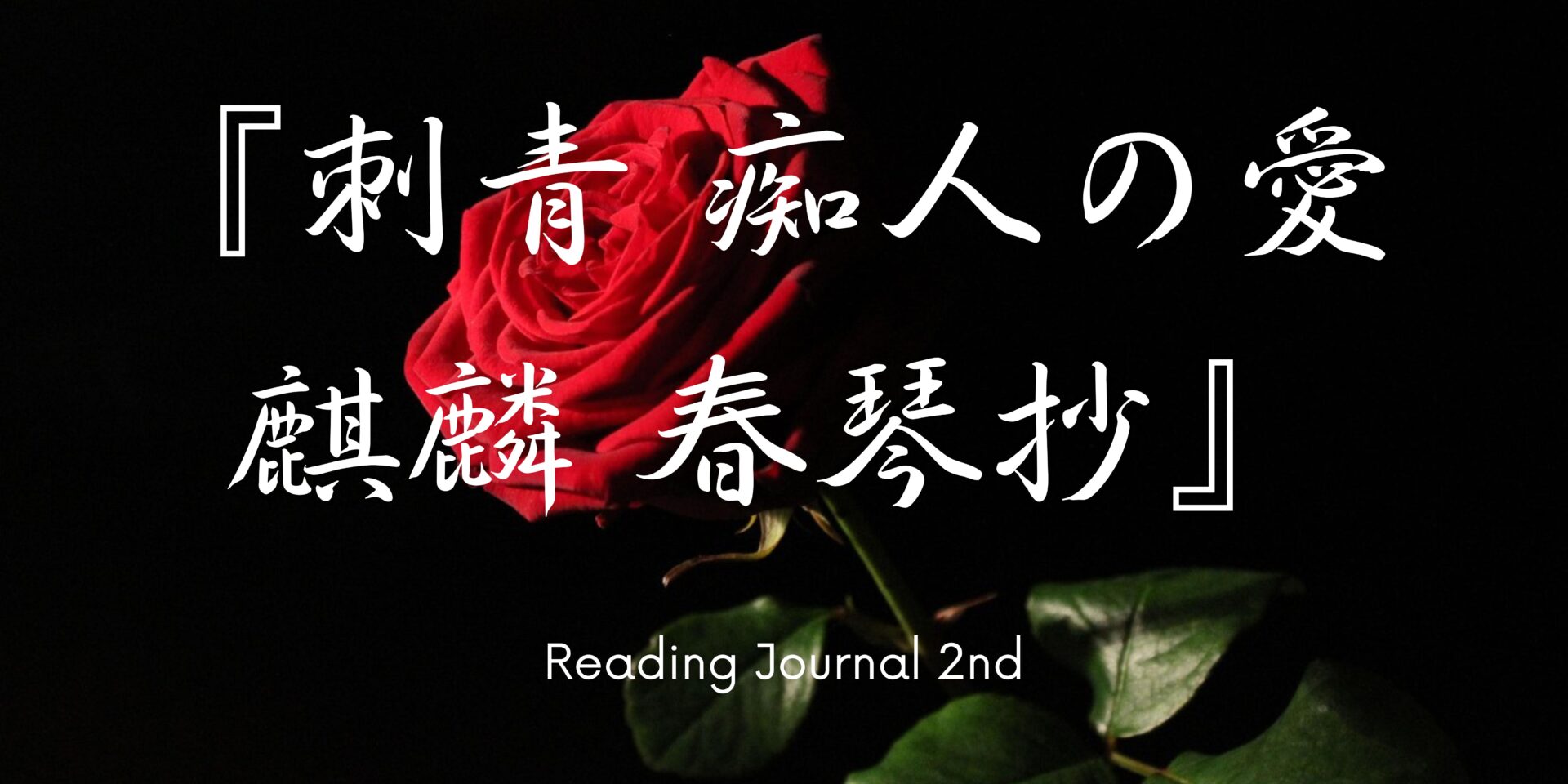


コメント