『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第四章 孔子の素顔(その6) — 6 楽しむ孔子
今日のところは、「第四章 孔子の素顔」の“その6”である。孔子はときに怒りを爆発させ、ときに悲観にくれるなど、激情をあらわに示すこともあったが、基本的には伸びやかな陽性のひとであり、生きることを楽しむ人であった。
今日のところ“その6”では、そんな孔子がゆったりと楽しんでいる話が取り上げられている「楽しむ孔子1」である。この節は、二つに分けてまとめるとする。それでは読み始めよう。
楽しむ孔子1
No.135 之れを知る者は之れを好む者に如かず。之れを好む者は之れを楽しむ者に如かず。
子曰く、之れを知る者は之れを好む者に如かず。之れを好む者は之れを楽しむ者に如かず。(雍也第六)(抜粋)
先生は言われた。「ものごとに対して知識をもち理解する者は、それを好む者にはかなわない。好む者はそれを楽しむ者にはかなわない」。(抜粋)
この条は、対象とのかかわり方は、「知る」⇒「好む」⇒「楽しむ」に深化するということを表してしている。そして、著者は、この三段階は、さらに人としての成熟のプロセスにも当てはまると言っている。
No.136 疏食を飯らい水を飲み、肱を曲げて之れを枕とす
子曰く、疏食を飯らい水を飲み、肱を曲げて之れを枕とす。楽しみ亦た其の中に在り。不義にして富み且つ貴きは、我れに於いて浮雲の如し。(述而第七)(抜粋)
先生は言われた。「粗末な食事をとって水を飲み、ひじをまげて枕にする。そんな暮らしのなかにも、楽しみはある。不正な手段で得た富や高い地位は、私にとっては空に浮かぶ雲のようなものだ。」(抜粋)
この条は、質素な暮らしにも、安らかな楽しみがるといい、逆に不正な手段で得た地位や富は、浮雲のようだとしている。
孔子は、高い地位や富を否定しないが、質素な暮らしの中で思い通りに学問に生きた楽しんだ顔回の生き方に深く共感している。(No.76を参照)
No.137
子の雅に言う所は、詩・書・執礼、皆な雅に言う也。(述而第七)(抜粋)
先生がいつも話題にされていたのが、「詩」「書」「礼」であった。この三つについていつも話題にされたのである。(抜粋)
この条は、幾つかの読みあるが、ここでは朱子の新注(ココ参照)によるとのこと。
ここで「詩」は『詩経』(孔子により選定された歌謡集)、「書」は『書経』(古代の為政者の発言を孔子が編纂したもの)、「礼」はもともと王朝の基礎を築いた周公旦が定めた儀礼や法則、である。
No.138 詩三百、一言以て之れを蔽えば、曰く、思い邪無し
子曰く、詩三百、一言以て之れを蔽えば、曰く、思い邪無し。(為政第二)(抜粋)
先生は言われた。「『詩経』三百篇の詩を、一言で総括すれば、「思い邪無し(感情の純粋さ)」ということだろう」。(抜粋)
孔子が古代の歌謡集『詩経』に収録された歌謡の特徴をひとことで言い表した名言である。この詩経は、孔子一門の教科書であった。そして、それは読むのだけではなく、歌われたと思われる。無骨な子路も瑟[しつ]を演奏している(No91参照)。
No.139 関雎は、楽しみて淫せず、哀しみて傷らず
子曰く、関雎は、楽しみて淫せず、哀しみて傷らず。(八佾第三)(抜粋)
先生は言われた。「「関雎」の詩は、いかにも楽しげでありながら、節度を保って沈溺するところがない。悲哀の感情もあるが、心を鋭く傷つけることはない」。(抜粋)
「関雎」の詩は、『詩経』「国風」の冒頭に配される「周南」の最初の詩である。ここでは、この詩のバランス感覚にあふれた表現を称賛している。
孔子の時代、「関雎」は、楽器の伴奏によって広く歌われた楽曲であった。そのためこの条も歌詞ではなく、そのメロディーについてものもという説がある。しかし、著者は、歌詞自体にも哀楽が歌いこまれていて、そうとも言い切れないと言っている。
No.140 少子何ぞ夫の詩を学ぶ莫きや
子曰く、少子何ぞ夫の詩を学ぶ莫きや。詩ま以て興す可く、以て観る可く、以て群う可く、以て怨む可し。之れを邇しては父に事え、之れを遠くしては君に事う。多く鳥獣艸木の名を識る。(陽貨第十七)抜粋
先生は言われた。「若者たちよ、どうして詩(『詩経』を学ばないのか。詩を学べば、もろもろの事がらを比喩的に表現できるし、世間を観察できるし、みんなといっしょに楽しむことができるし、政事を批評することもできる。近くには父に仕え、遠くには君主に仕え、多くの動物や植物の名称を覚えるにも役立つものだ)。(抜粋)
この条は、『詩経』を学ぶ効用を説いた有名な発言である。その効用として、
- 「興」:『詩経』独特の暗喩の一種。(ここでは、比喩的表現に習熟できるとした)
- 「観」:広く世間のありさまを観察しうること
- 「群」:大勢の人々と楽しみを共有しうること
- 「怨」:間接的に政治を批判しうること
である。そしてそのほかにも、『詩経』を学べば父や君主になど上位者への態度や姿勢を学び、さらに多様な動植物の名称が覚えられるとした。
孔子が、『詩経』を最重要視したことは、息子孔鯉に、まず『詩経』を学ぶように言ったことで明らかである(No.7)。
ここで著者は、この条はあまりに功利的で孔子本来の伸びやかさに欠けていると指摘し、おそらく孔子の言葉をそのまま記したものでなく、後の編集者によって整理されたものだろうと言っている。
No.141 始めて作すに翕如たり。之れを従ちて純如たり。皦如たり。繹如たり。
子 魯の大師に楽を語りて曰く、楽は其れ知る可き也。始めて作すに翕如たり。之れを従ちて純如たり。皦如たり。繹如たり。以て成る。(八佾第三)(抜粋)
先生は魯の楽団長に音楽のことを語って言われた。「音楽の構成を私はこう理解しています。最初は打楽器がさかんに鳴り響き、ついですべての楽器が自在に調和して合奏され、さらにそれぞれの楽器が順を追って明瞭に演奏され、連綿と展開されて、完結するのですね」。(抜粋)
この話は、孔子が優れた音楽的センスの持ち主であったことを示している。ここで
- 「翕如」:(打楽器が)いっせいに大きく鳴り響くさま
- 「純如」:ゆるやかに調和するさま
- 「皦如」:はっきりと明瞭なさま
- 「繹如」:連綿と連なり鳴り響くさま
である。
No.142 三月 肉の味を知らず
子 斉に在りて韶を聞く。三月 肉の味を知らず。曰く、図らざりき 楽を為すことの斯に至るや。(述而第七)(抜粋)
先生は斉の国で韶の音楽を聞かれ、三か月間、肉の味さえわからなくなられた。そこで言われた。「音楽のもたらす感動が、これほどまでに深いとは思いもしなかった。」。(抜粋)
韶は、伝説の聖太子舜が作ったとされる音楽である。孔子が斉の国で、この韶を聞いたとき、その感動のため、最上の食物であった肉の味さえ分からなくなったというエピソードである。
孔子は韶に対して、「(韶は)美を尽くせり、又た善を尽くす也」(八佾第三)と言っている。
No.143
子 喪有る者の側に食すれば、未だ嘗て飽かざる也。子 是の日に於いて哭すれば、則わち歌わず。(述而第七)(抜粋)
先生は服喪中の者の側で食事をされるときは、満腹まで食べられることはなかった。また、弔問に行き、死者のために哭令(声をあげて泣く礼)をされた日には(帰宅してからも)歌をうたわれなかった。(抜粋)
儒家思想では、葬礼を重んじ、服喪中の者の側では控えめに食事をとること、死者のために哭令を行った日には歌を歌わないなども喪礼の一種であった。
そして、著者は、孔子はこのような特別の日以外は、毎日門下生と『詩経』を歌い楽しんでいたとおぼしい、と言っている。
No.144
子 人と歌いて善ければ、必ず之れを反さしめて、而る後に之えれに和す。(述而第七)(抜粋)
先生は歌の会のさい、いい歌だと思われたときには、必ずもう一度うたわせたあと、自分も合唱された。(抜粋)
この条は、歌好きな孔子の姿を現している条である。
そしてここで著者は、孔子は、会いたくない人物の訪問を受けたとき、病気を口実に断った後、瑟を弾きながら歌をうたい、自分は病気ではなく、会う意思がないということを婉曲に伝えた(陽貨十七)とう、逸話を語っている。
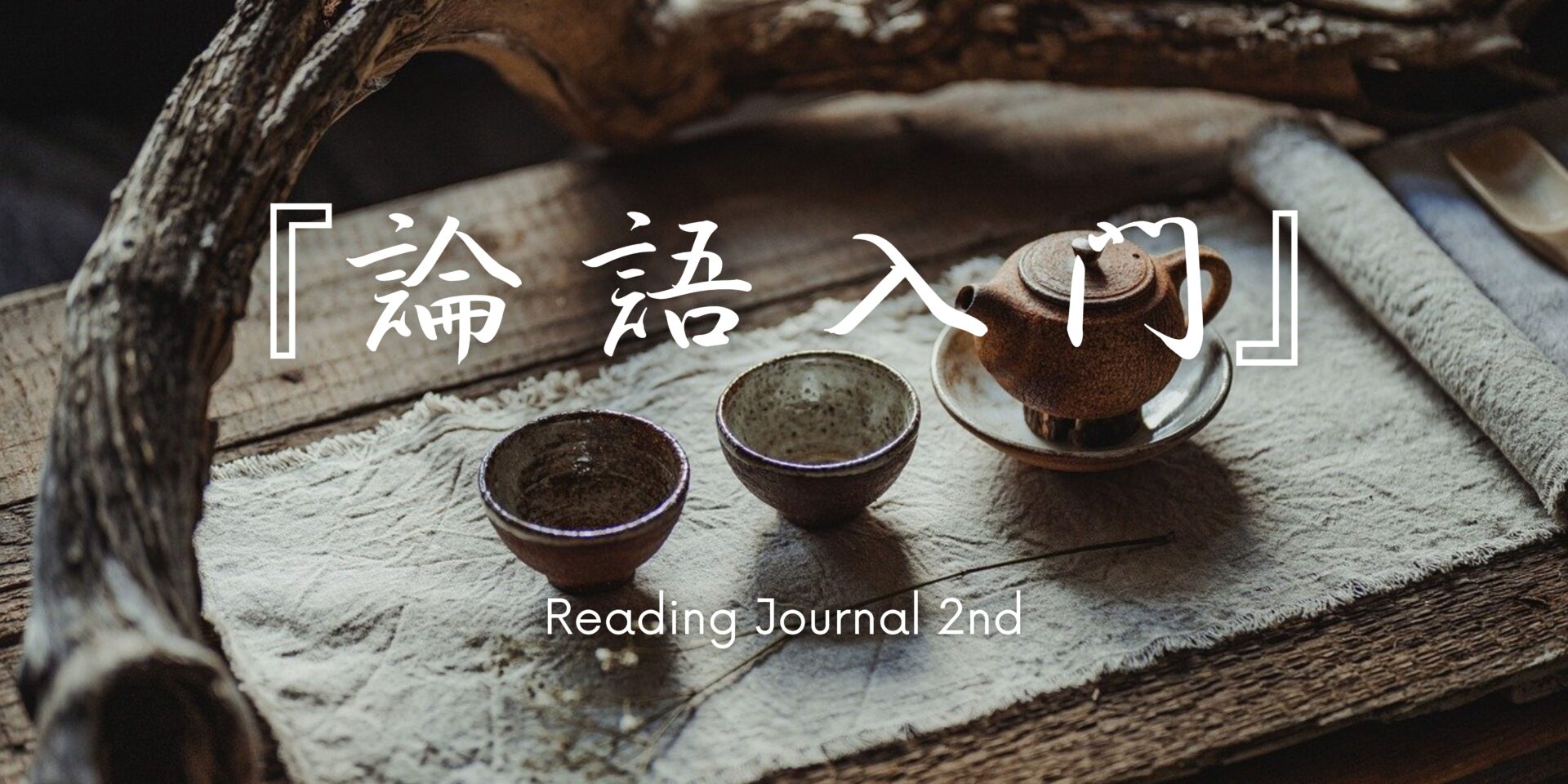


コメント