『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第四章 孔子の素顔(その5) — 5 辛辣な孔子
今日のところは、「第四章 孔子の素顔」の“その5”である。孔子は、基本的には明るくおおらかであったが、その一方、容認しがたいものには手厳しく、容赦なくその痛いところをついた。今日のところ“その5”は、そのような孔子の一面を捉えた条が集められた「辛辣な孔子」である。それでは読み始めよう。
辛辣な孔子
No.130 巧言令色
子曰く、巧言令色、鮮し仁。(学而第一)(抜粋)
先生は言われた。「巧妙な言葉づかい、とりつくろった表情の人間は真情に欠ける」。(抜粋)
言語に美的表現や細やかに神経がゆきとどいて行動形式を重視した孔子にとって「巧言令色」は論外だった。
この発言の対極にあるのが、「剛毅木訥、仁近し」(No.37)である。
No.131 吾れ未だ徳を好むこと 色を好むが如くする者を見ざる也
子曰く、吾れ未だ徳を好むこと 色を好むが如くする者を見ざる也。(子罕第九)(抜粋)
先生は言われた。「私は美女を愛するように、徳を愛する人にいまだかつてお目にかかったことがない」。(抜粋)
「色」は、美女。「徳」は、徳義(のある人)である。
この条に関して著者は、
美女と徳を対比させた大胆な発言であり、のちの頭の固い道学者には想像もつかない、すこやかなエロス性を含む大胆な発想である。(抜粋)
と評している。また、孔子自身も理想の人周公旦をあたかも恋人のように夢見続けた(No.123)と、言っている。
・・・・・・・(区切り線)・・・・・・
この部分は、谷崎潤一郎の『麒麟』の結末でもあるんだけど、著者と谷崎ではだいぶとらえ方が違うねぇ。え?どうして『麒麟』?っていうことは、『麒麟』が孔子の南子との謁見をテーマとしているからだね(No89参照)。(つくジー)
No.132
子曰く、後世畏る可し。焉んぞ来者の今に如かざるを知らんや。四十五十にして聞こゆること無くんば、斯亦た畏るるに足らざるのみ。(子罕第九)(抜粋)
先生は言われた。「後輩や若者こそ畏敬すべきだ。未来の人間である彼らがどうして現在の人間より劣るものとわかるか。しかし、(その若者とて)四十五十になっても、何も名声が得られないようなら、これまたいっこう畏敬するに値しない。(抜粋)
孔子には、多くの若い弟子がいて、彼らに多くの期待を寄せていた。そして、決して彼らを軽んじたりしなかった。しかし、その若者もいつか年を取り四十五十になってもひとかども者になれかければならないと、鋭くコメントしている。
No.133 古の学者は己の為にし、今の学者は人の為にす
子曰く、古の学者は己の為にし、今の学者は人の為にす。(憲問第十四)(抜粋)
先生は言われた。「昔の学者は自分のために勉強し、今の学者は人に名を知られるために勉強する」。(抜粋)
孔子は、社会的名声を得ることのみを目標とする当時の学問を強烈に批判している。しかし著者は、この言葉は、
二千数百年後の「今」に生きる「学者」にもそのままあてはまる。以て銘すべし。(抜粋)
と言って、自らを戒めている。
No.134 紫の朱を奪うを悪む也
子曰く、紫の朱を奪うを悪む也。鄭声の雅楽を乱るを悪む也。利口の邦家を覆す者を悪む。(陽貨第十七)(抜粋)
先生は言われた。「紫色が朱色を圧倒することを、私は憎む。(煽情的な)鄭[てい]の音楽が雅楽を混乱させることを、私は憎む。口のうまい野心家が国家を混乱させることを、私は憎む」。(抜粋)
青・黄・赤(朱)・白・黒を正色、二つ以上の正色を混ぜ合わせたものを間色という。古くは正色が尊ばれたが、しだいに紫のような間色が尊ばれるようになった。孔子はこのような純粋なものより混ぜものの価値が高くなることを憎んだ。
音楽においては、優美な雅楽が次第に衰え、煽情的な鄭の音楽が流行ることも憎んだ。
このような「まがい物」を嫌う孔子は、弁はたつが実のない野心家が巧妙たち振舞って、国家を混乱させる事態を、厳しく攻撃した。
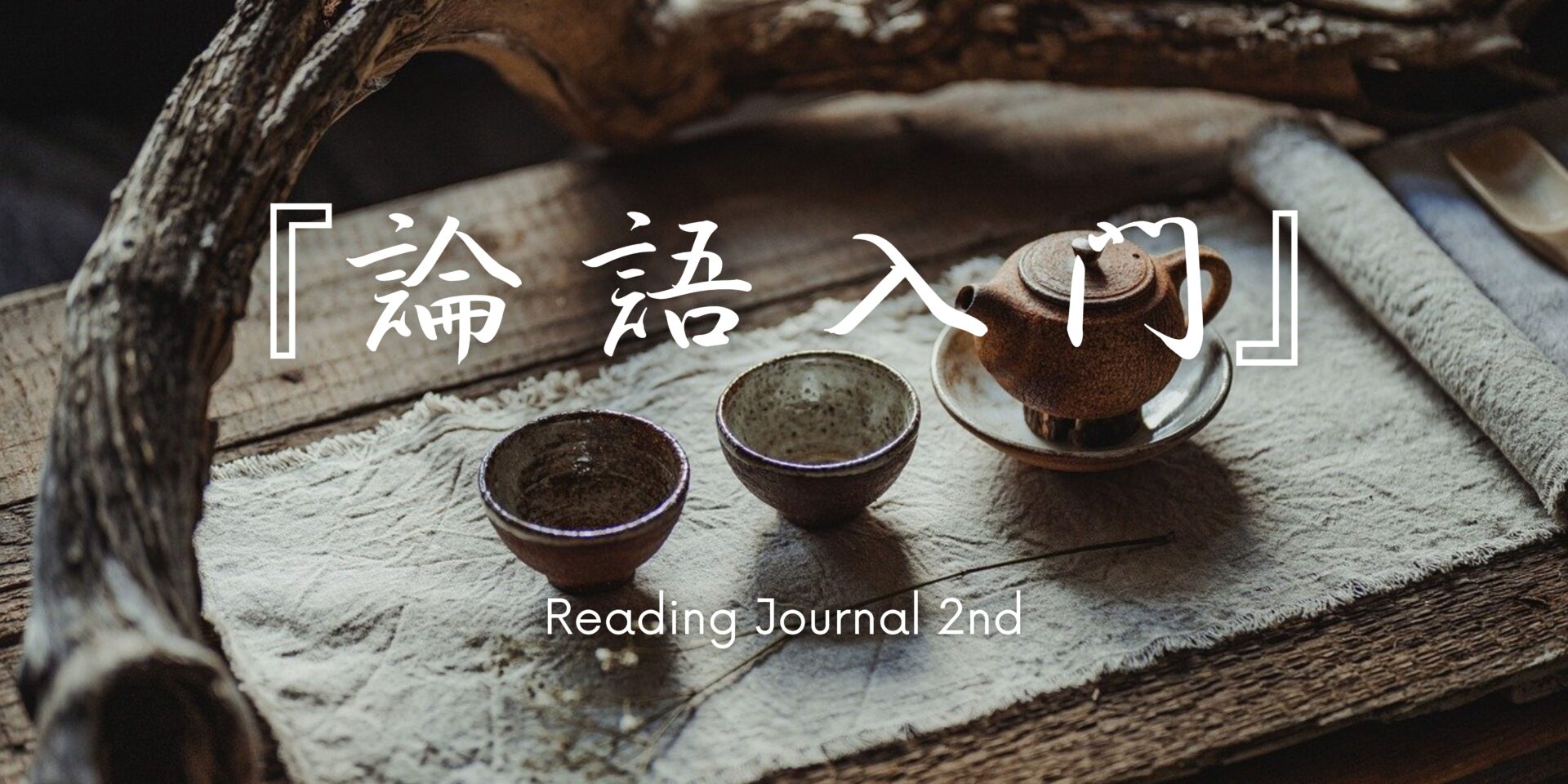


コメント