『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第四章 孔子の素顔(その3) — 3 激する孔子
今日のところは、「第四章 孔子の素顔」の“その3”である。孔子は理不尽なもの、許しがたい事がらにたいしては、色気ばみ、断固として拒否した。今日のところ“その3”では、そんな孔子の激しい一面が現れている条が紹介されている。それでは読み始めよう。
激する孔子
No.120
孔子 季氏を謂う、八佾を庭に舞わす。是れをしも忍ぶ可くんば、孰れか忍ぶ可からざらん。(八佾第三)(抜粋)
孔子が季氏を批判した。「(天使が宗廟の祭祀に奉納する)八佾の舞を自分の家の中庭で舞わすとは。これをがまんできるなら、世の中にがまんできないことはない」。(抜粋)
魯の三大貴族(三桓)の一つの、季孫氏が、天使が宗廟の祭祀を行うときに奉納される八佾の舞を自宅に中庭で実施した。それに対して孔子の怒りは爆発した。著者は、これを秩序を重んじる孔子らしい怒りの爆発であると、評している。
No.121
宰予、昼に寝ぬ。子曰く、朽ちたる木は雕る可からず也。糞土の牆は、杇る可からず也。予に於いてか何ぞ誅めん。子曰く、始め吾れ人に於けるや、其の言を聴きて、其の行を信ず。今吾れ人に於けるや、其の言を聴きて、其の行を観る。予に於いてか是れを改む。(公冶長第五)(抜粋)
宰予が昼間から奥の間に引っ込んで寝ていた。先生は言われた。「腐った木には彫刻ができない。泥土の垣には上塗りができない。宰予のような者は𠮟ってもしようがない」。また先生は言われた。「私は今まで他人に対して、その言葉を聞くと、(言葉どおりだと思って)その行動も信じてきた。これからは他人に対して、その言葉を聞き、その行動もよく見るようにする。宰予のことをきっかけに、このように態度を改めよう。(抜粋)
この条は、昼間から奥の間で寝ていた宰予(子我、宰我)(No.41参照)を孔子がしかりつけている。彼は、「言語には宰我、子貢」と言われる秀才であったが、あまりに才気走ったところがあり、孔子はしばしば𠮟りつけている。
しかし、昼寝をしているだけで、孔子がここまで腹を立てるのも異様な感があるとして、荻生徂徠は、宰予が昼間から奥の間で寝ていたのは、「蓋し言うべからざるもの有り(言うに言えないことがあったのだろう)」と言い、つまり女性と同衾していたという説を唱えている。
No.122
子の疾病なり。子路 門人をして臣と為らしむ。病間えたり。曰く、久しい哉、由の詐を行うや。臣無くして臣有りと為す。吾れ誰をか欺かん。天を欺かんか。且つ予れ其の臣の手に死せんよりは、無寧二三子の手に死せんか。且つ予れ縦い大葬に得ざるも。予れ道路に死なんや。(子罕第九)(抜粋)
先生が病気で重態になられた。子路は門弟を家臣にしたてようとした。病気が小康状態になると、先生は言われた。「よくも長い間、由(子路)よ、おまえは私をごまかしてきたものだ。家臣がないのに家臣があるように装った。私はいったい誰を欺こうというのか。天を欺こうというのか。それには私のニセの家臣に手をとられて死ぬよりは、きみたちに手をとられて死にたいのだ。それにまた、私はりっぱな葬式をしてもらえなくとも、私が路上で野たれ死にするはずもなかろう」。(抜粋)
孔子が重態になったとき、子路が門弟を家臣に仕立て上げたことを、小康状態になった孔子が叱った。このころ諸侯や重臣の臨終から葬式は、その家臣が様々な役割を分担して行っていた。しかし、そのころ孔子は無位無官であったため家臣はいなかった。そのため、子貢が弟子たちを家臣に仕立て上げようとしていた。そのことを孔子が叱っている。また、そのころ臨終にさいしては、側で見守る人たちが両手両足を持つことが風習であったが、孔子はニセの家臣に手を取られて死ぬよりは、門弟たるきみたちに手を取られて死にたいといっている。もちろんその門弟の中には子路も入っている。
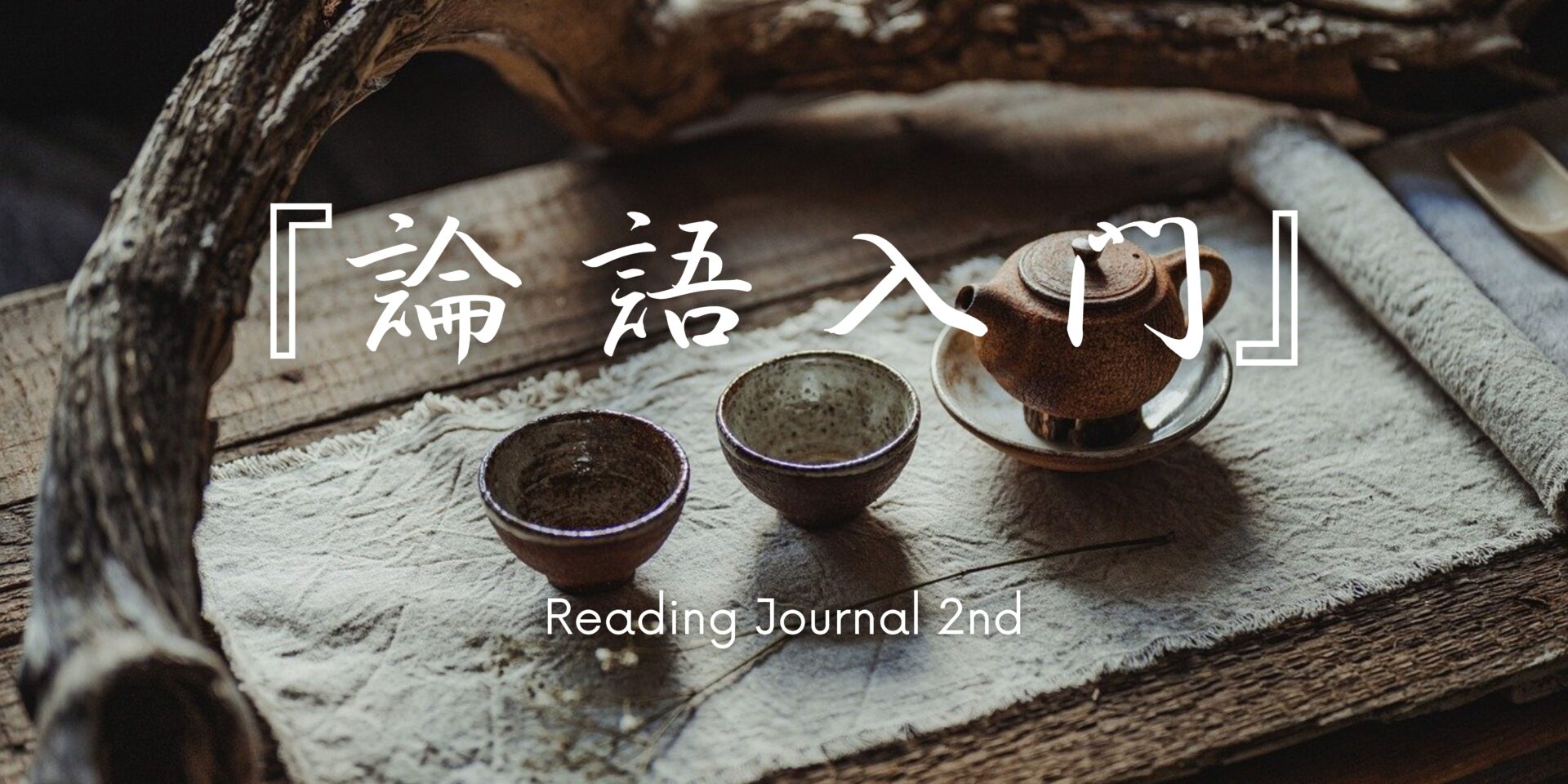


コメント