『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第四章 孔子の素顔(その2) — 2 不屈の精神
今日のところは、「第四章 孔子の素顔」の“その2”である。前回“その1”では、孔子のユーモアの感覚に関する条が紹介されたが、今日のところ“その2”では、打って変わて、孔子の「不屈の精神」についてである。それでは読み始めよう。
不屈の精神
No.112
子貢曰く、斯に美玉有り。匱に韞めて諸を蔵せんか。善き賈を求めて諸を沽らんか。子曰く、之れを沽らん哉。我れは賈を待つ者也。(子罕第九)(抜粋)
子貢が言った。「ここに美しい玉があるとします。それを箱のなかに入れてしまいこんでおいたものでしょうか。よい買い手をみつけて売ったものでしょうか」。先生は言われた。「売るとも。売るとも。私は買い手を待っているのだ」。(抜粋)
この条は、晩年に官途に就かなかった孔子に、今なおご出仕の意志があるかを子貢が確かめようとした話である。その時の孔子の答えは、このようい、積極性にあふれるものだった。
No.113
子曰く、三軍も帥を奪う可き也。匹夫も志を奪う可からざる也。(子罕第九)(抜粋)
先生は言われた。「三軍の総大将を奪い取ることはできても、一人の人間の志を奪い取ることはできない」。(抜粋)
個人の不屈の意志や精神力は、強制的に奪い取ることはできないという、積極的な発言であり、それは人を奮い立たせるものである。
ここの匹夫はもともと地位の低いものを指した言葉である。後に明の滅亡後に、征服王朝清に使えることを潔とせずに、明の遺民として生涯を終えた顧炎武は、「天下を保つ者は匹夫の賤も与って責め有るのみ(天下を保っていくことには、卑賎な一人の人間にも責任がある)」と言った。この言葉は、「国家の興亡は匹夫にもせめあり」という表現で清末の改革はスローガンとなった。
これらの言葉はこの孔子の発言をもとにしながら、そこに強烈な政治性や社会性を帯びさせたのである。(抜粋)
これに関しては、同じく井波律子の『故事成句でたどる楽しい中国史』にも記述がある(ココ参照)。(つくジー)
No.114
子曰く、歳寒くして、然る後に松柏の彫むに後るることを知る也。(子罕第九)(抜粋)
先生は言われた。「寒い季節になってはじめて、松や柏(ヒノキなどの常緑樹の総称)がしぼまないことがわかる」。(抜粋)
厳冬になってはじめて常緑樹の強靭さがわかるように、人間も危機や逆境に直面してその本質がわかる、ということである。著者は逆境をへてきた孔子の経験に裏打ちされた含蓄のある言葉であると、評している。
この言葉がもとになり、志操堅固な者を「松柏の質」と形容するようになった。
いいことばですねぇ~。つくジーも「松柏の質」と言われるようになりたいもんですよね。(つくジー)
No.115
子路 石門に宿る。晨門曰く、奚れ自りする。子路曰く、孔子自りす。曰く、是れ其の不可を知りて、而も之れを為す者か。(憲問第十四)(抜粋)
子路が石門の宿屋に泊まったとき、門番が聞いた。「どこから来られたか」。子路は言った。「孔子のところから来ました」。(門番は)言った。「ああ、あの不可能だと知りながら、やっているお方ですね」。(抜粋)
これは子路が石門にある宿に泊まった時に、そこの門番と交わした会話である。門番の言葉に対する孔子の意見はないが、きっと孔子は、門番の言葉に大喜びしてだろうと著者は言っている。
No.116
公山弗擾 費を以て畔く。召ぶ。子 往かんと欲す。子路説ばずして、曰く、之くこと末ければ已む。何ぞ必ずしも公山氏に之れ之かんや。子曰く、夫れ我れを召ぶ者は豈に徒らならんや。如し我れを用うる者有らば、吾れ其れを東周を為さんか。(陽貨第十七)(抜粋)
公山弗擾が費を拠点として魯に反乱をおこし、孔子を招聘した。先生は応じようとされるが、子路は不機嫌になって言った。「行くところがなければそれまでのことです。どうしてわざわざ公山弗擾のもとへなぞ行かれるのですか」。先生は言われた。「そもそも私を招聘する者に理由のないはずがない。もし私を用いてくれる者があれば、私はそこを東の周にしてみせよう(初期の周王朝のすぐれた政治と文化をこの東方で実践してみせよう)」。(抜粋)
孔子の時代の魯は下剋上の時代だった。その政治の実権は三大貴族(三桓)から、その家臣に移っていた。その中で力があった三桓の一人季孫の執事だった陽虎が、魯の国政を意のままにしていた。陽虎は内々に孔子を招聘したが、孔子はそれを断った。
やがて、陽虎は、三桓を排除しようとしてクーデターを起こす。そのとき、それに呼応して反旗を翻したのが公山弗擾であった。孔子は公山弗擾の要請には、即座に応じようとした。それは、公山弗擾が礼儀を持った人であり、正式な招聘だったからであると言われている。しかし、著者は孔子はもともと三桓のやり方に憤慨を抱いていて、その打破をはかる公山弗擾に共感するところがあったのではないかと、言っている。しかし、この時は弟子の反対もあり結局要請に応じなかった。
しかし、結果的には公山弗擾に加担しなかったことは孔子にとって幸運だった。このクーデターが失敗した後、孔子は定公に認められ大司寇(司法長官)に抜擢される。しかし、このように念願がかなって政治の表舞台に立った孔子だが、そのわずか二年後に、三桓の勢力削減に失敗し失脚してしまう。
No.117
子 匡に畏す。曰く、文王既に没す、文 茲に在らざらんや。天の将に斯の文を喪ぼさんとするや、後死の者 斯の文に与ることを得る也。天の未だ斯の文を喪ぼさざるや、匡人 其れ予れを如何せん。(子罕第九)(抜粋)
先生が匡の町で襲撃されたとき、言われた。「周の文王はすでに亡くなっており、(その文化は)ここ、私の身に存在しているではないか。天が(私の身にそなわっている)この文化を滅ぼそうとするならば、後の時代の者はこの文化の恩恵に浴することができなくなる。天が(私の身にそなわっている)この文化を滅ぼそうとしないのならば、匡の者どもが私をどうすることもできないぞ」。(抜粋)
この言葉は、孔子が匡の国で襲撃されたときに言った言葉である。この言葉には、自分こそが、周の文化を受け継ぐ者であり、そんな自分がこんなところで命を落とすわけがないという、強い自負がこもっている。(No79を参照)
No.118
子曰く、天 徳を予れに生せり。桓魋 其れ予れを如何せん。(述而第七)(抜粋)
先生は言われた。「天が私に徳をさずけられている。桓魋のごときが私をどうすることができようぞ」。(抜粋)
この条も、前条と同様に孔子の強い自負が現れた言葉である。匡での襲撃の五年後に宋国で弟子たちと礼の実習を行っていた時に、孔子に反感を持つ桓魋に殺されそうになった。そのとき孔子はこのように言って弟子たちの動揺を抑えたという。この桓魋については、No106を参照。
No.119
陳に在りて糧を絶つ。従者病んで、能く興つこと莫し。子路慍って見えて曰く、君子も亦た窮すること有るか。子曰く、君子個より窮す。小人窮すれば、斯に濫す。(衛霊公第十五)(抜粋)
陳の国にいたとき、食料の補給が途絶えた。つき従う弟子たちは病み衰え、立ち上がることもできなかった。子路が激怒して対面して言った。「君子もやはり困窮することがあるのですか」。先生は言われた。「君子ももちろん困窮することがある。小人は困窮すると自暴自棄になるのもだ(君子はそんなことはない)」。(抜粋)
陳の国にいたとき、食料の食糧危機となり、孔子一行も食料の供給が出来なくなった。怒って詰問する子路にたいして孔子は「君子個より窮す」と言ったのち、窮したときに自暴自棄になるのは小人だと言ってのけた。著者はこれに際して、孔子の危機に直面したときの強靭さが、なまじのものでないと、評している。
この後まもなく孔子一行は楚に迎えられて危機を脱する。
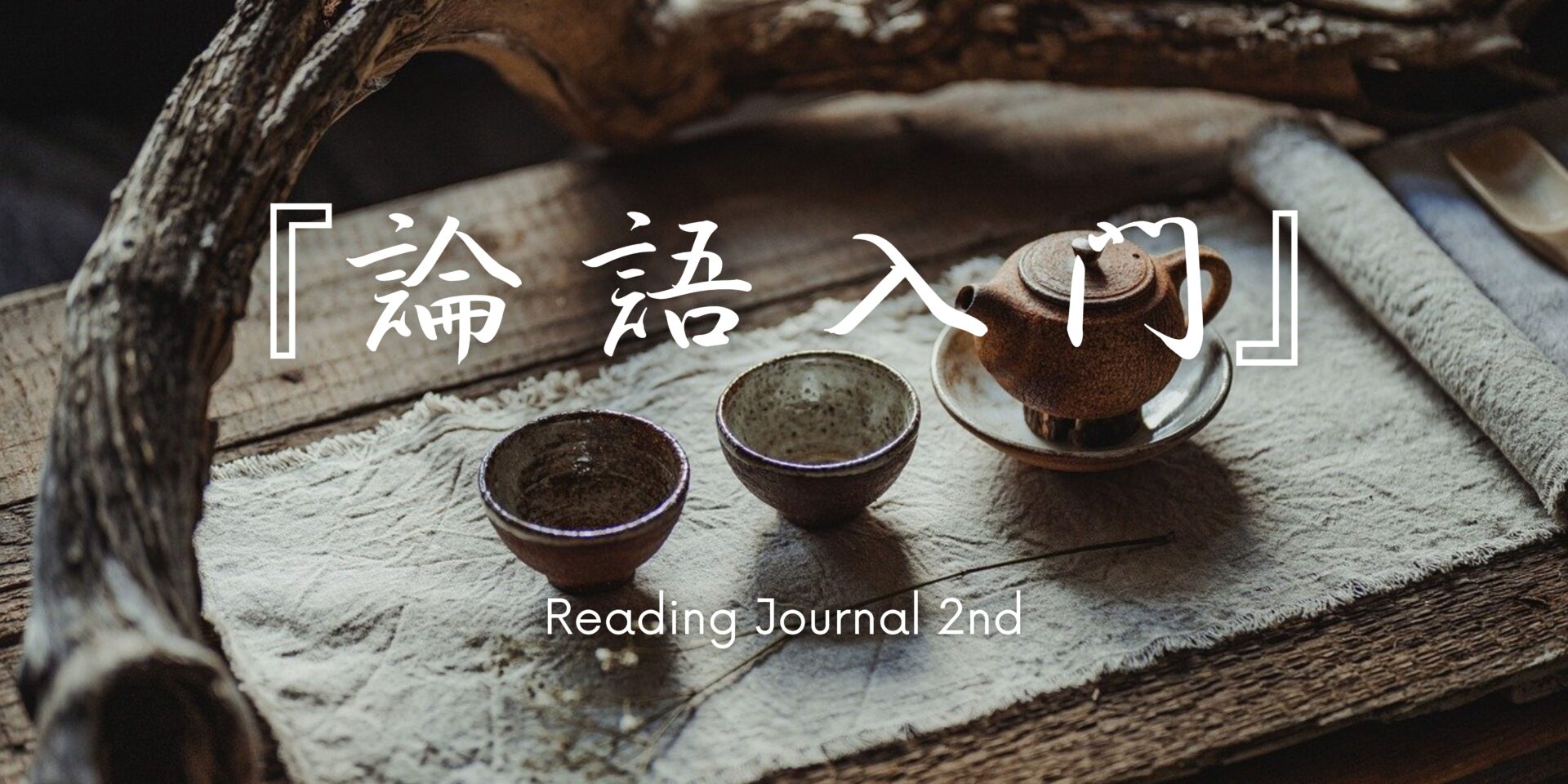


コメント