『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第三章 弟子たちとの交わり(その7) — 4 受け継がれゆく思想
今日のところは、「第三章 弟子たちのとの交わり」(その7)である。第三章は孔子と弟子との交わりに関わる条が集められていた。今日のところは第三章の最終節である。ここでは、孔子の没後にその思想を受け継いだ曾氏と子夏にスポットがあてられる。
この曾子は、孔子が率いていた原子儒家集団をおおむねまとめて行った人である。そして、その後、孔子の孫の孔汲(あざな子思)が受け継いだ。孟子は子思の弟子に学んだとされ、後世の宋代儒学はこの孔子・曾氏・子思・孟子の流れを正統とした。
子夏は、孔子の死後、西河で弟子の教育にあたり、魏の文候に招かれ、その師となった。性悪説を唱えた荀子は、子夏の系統を受け継いだとされる。
こうしてみると、性善説を唱える孟子は曾氏の系統につながり、性悪説を唱える荀子は子夏の系統につながることになる。こうして孔子の思想は弟子の手を経てさまざまなヴァリエーションを生みながら、後世へと伝搬されていったのである。(抜粋)
ここで出てきた孟子と荀子ですが、同著者の『故事成句でたどる楽しい中国史』に詳しく載っているよ。孟子はココ、荀子はココを参照してくださいませませ。(つくジー)
曾子 — 思想を広める
No.102
曾子曰く、吾れ日に三たび吾が身を省りみる。人の為に謀りて忠ならざるか。朋友と交わりて信ならざるか。習わざるを伝うるか。(学而第一)(抜粋)
曾子は言った。「私は毎日、三つの事について反省する。他者の相談に乗りながら、まごころを尽くさなかったのではないか。友人との交際で、信義を守らなかったのではないか。よく理解していないことを、後輩に伝授したのではないか、と」(抜粋)
著者は、この条を、いかにも実直で生真面目な曾子らしいと、評している。曾子は、「魯」と評される(No97)こともあったが、篤実で手堅く、孔子亡き後に一門を取りまとめるには最適任者だった。
No.103
曾子 疾有り。孟敬子 之れを問う。曾子言いて曰く、鳥の将に死なんとするや。其の鳴くこと哀し。人の将に死なんとするや、其の言や善し。君子の道に貴ぶ所の者は三。容貌を動かせば、斯に暴慢を遠ざかる。顔色を正せば、斯に信に近づく。辞気を出だせば、斯に鄙倍を遠ざく。籩豆の事は、則ち有司有存す。(泰伯第八)(抜粋)
曾子が重態になったとき、孟敬子が見舞った。曾子は彼に対していった。「絶命直前の鳥の鳴き声は哀切であり、絶命直前の人間の発言は誠実だと申します。君子が礼の道において、尊重すべきことが三つある。第一に、立ち居ふるまいに気をつければ、他人の暴力や侮りから遠ざかることができます。第二に、顔の表情を正しくおごそかにすれば、人からだまされないという状態に近づくことができます。第三に、言葉づかいに気をつければ、他人の下品で道理にあわない言葉が耳に入らなくなります。籩豆(祭祀用の器)のことなどは、担当の役人にまかせればよろしい」。(抜粋)
ここで前置となっている二句「鳥の将に死なんとするや。其の鳴くこと哀し。人の将に死なんとするや、其の言や善し。」は、当時のことわざであったようであるが、後世、名言として広く流布した。
ここで曾子は、三つのことを注意するが、ここでの訳は、他人から嫌な目にあわないための注意とする伝統的な解釈である。
No.104
曾子曰く、士は以て弘毅ならざる可からず。任重くして道遠し。仁以て己が任と為す。亦た重からずや。死して後已む。亦た遠からずや。(泰伯第八)(抜粋)
曾子は言った。「士たるものおおらかで強い意志をもたなければならない。その任務は重くて、道のりは遠いからである。仁愛の実践を自分の任務とするのだから、なんと重いではないか。死ぬまでがんばって完了するのだから、なんとはるばる遠いではないか」。(抜粋)
ここで曾子は、強い意志を持ち、仁の実践に死ぬ瞬間まで頑張る「士」にエールを送っている。著者は、この言葉を「時を超えて、今もなお人を鼓舞する言葉である」と評している。
子夏 — 学問を受け継ぐ
No.105
子夏曰く、賢を賢として色に易え、父母に事えて能く其の力を竭くし、君に事えて能く其の身を致し、朋友と交わるに、言いて信有らば、未だ学ばずと曰うと雖も、吾れ必ず之れを学たりと謂わん。(学而第一)(抜粋)
子夏は言った。「賢者を賢者として美女のように尊重し、父母につかえて力のかぎり尽くし、君主につかえて骨身をおしまず、友人との交際において、自分の言ったことに誠実であるならば、たとえその人が正式に学問をしたことがなくとも、私は必ず学のある人として認める」。(抜粋)
著者は、この発言については、様々な解釈があるとしている。解釈が分かれるのは「賢を賢として色に易え」の部分であるが、ここでは、開放的なニュアンスのある伝統的な注(古注)によったとしている(古注についてはココ参照)。
また著者は、子夏が正式な学問をしていなくても、実践や行動において優れた人物を、高く評価したことは、実践を重視した孔子の薫陶にようるものであろう、と言っている。
No.106
司馬牛憂えて曰く、人皆な兄弟有り。我れ独り亡し。子夏曰く、商之れを聞く。死生命有り。富貴天に在り。君子は敬して失う無く。人と与わるに恭しくして礼有らば、四海の内、皆な兄弟也。君子何ぞ兄弟無きを患えんや。(顔淵第十二)(抜粋)
司馬牛が嘆いて言った。「人にはみな兄弟があるのに、私だけはない」。子夏は言った。「商(子夏の本名)は、「人間の生き死にには定めがあり、富貴は天の与えた運命だ」と聞いている。君子たる者が慎む深く過失をおかさず、他人と丁重に礼儀正しく交わったならば、世界中の人がみな兄弟となる。君子は兄弟がいないことなど気に病まないものだ」。(抜粋)
この条では、自分に兄弟がいないと嘆いている司馬牛を子夏が慰めている。
しかし、司馬牛には兄があったという説が古来よりある。孔子が諸国を旅していたさい宗に立ち寄った時、宋の重鎮だった司馬牛の兄、桓魋(司馬魋)に襲撃されたという事件が起こったという。司馬牛は兄と絶縁状態であったようだが、このことを気にかけ悩んでいたという。
そんな司馬牛があえて「私には兄弟がいない」と言い切り、子夏に孤独感を吐露したところ、子夏は司馬牛が憂鬱になるわけを百も承知でありながら、すべは運命であり、きちんとした態度で他者と交わったならば「四海の内、皆な兄弟也(世界中の人がみな兄弟となる)」と、ややオーバーな表現で、司馬牛をあたたかく慰めた。司馬牛の来歴を知ったうえで読むと、なかなか含蓄に富む問答である。(抜粋)
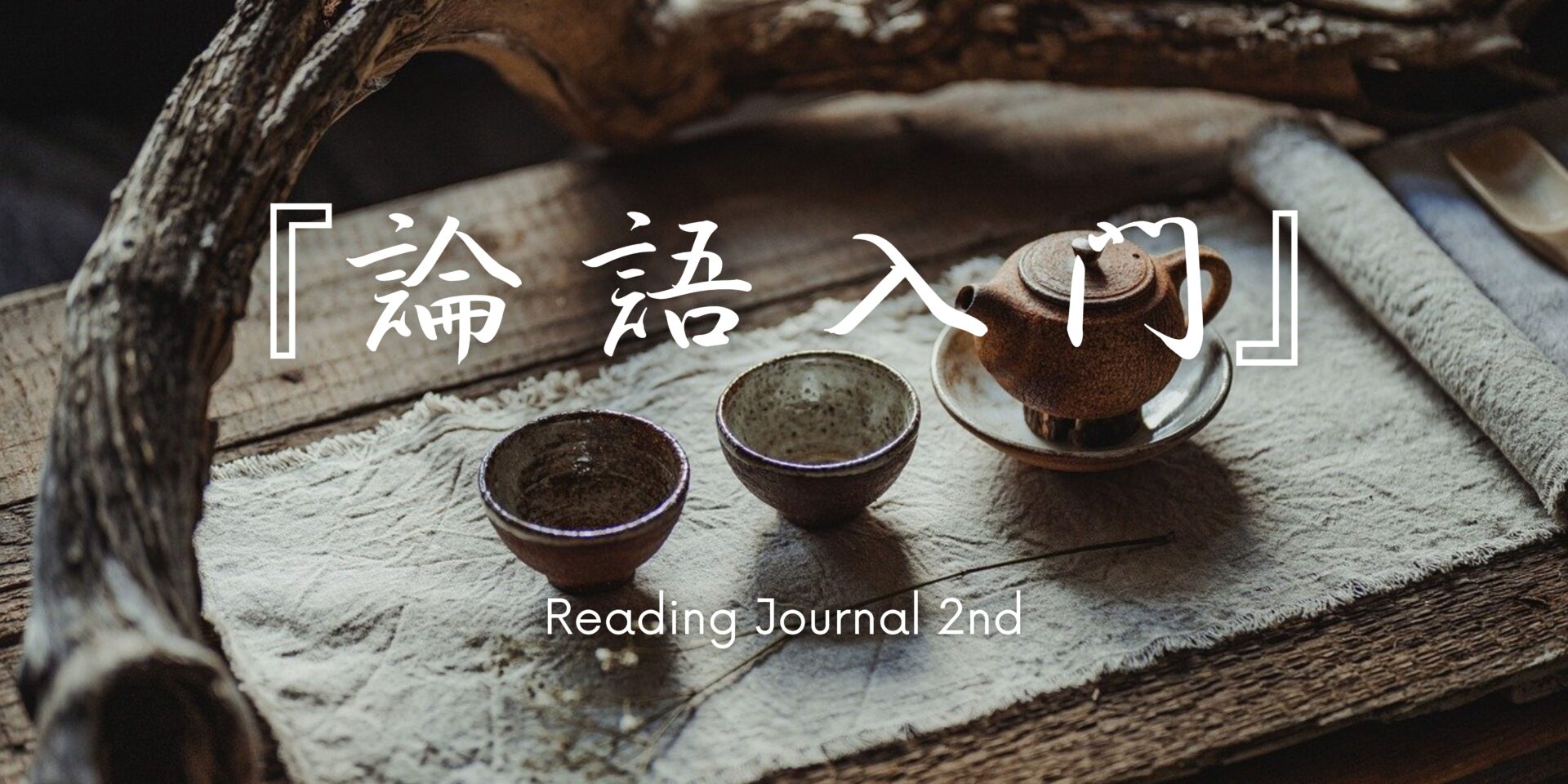


コメント