『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二章 考え方の原点(その6) — 2 政治理念と理想の人間像
今日のところは、「第二章 考え方の原点」の“その6”である。前回までは、孔子の言葉をキーワードごとに紹介されていたが、ここでは、孔子の政治理念と理想の人間像がわかる言葉が紹介されている。
政治理念と理想の人間像
No.64
子曰く、政を為すに徳を以てせば、譬えば北辰の、其の所に居て、衆星の之れに共うが如し。(為政第二)(抜粋)
先生は言われた。「政治をおこなうのに徳によったならば、北極星がじっとその場にいて、他の多くの星がこれに向かっておじぎをするように、調和がもらされるだろう。(抜粋)
穏やかな徳性を発揮して頂点に立つものを北極星にたとえた言葉。徳にもとづく政治が調和をもたらすさまを美しく描いている。
この「衆星の之れに共うが如し」について、吉川幸次郎著『論語』では、
「共は拱の音通であるとし、星たちが北極星の方向に向かっておじきをし、挨拶をしていると、説く間の鄭玄の説を、わたしはとりたい。砂子をまきちらしたように、大空いっぱいにひろがる星が、北極星に向かって、おじぎ、おじぎといっても、それはからだを折りまげたことごとしいおじぎではなく、今の中国人がよくするように、軽く両手を前に組合わせてのおじぎをしている、というのは、道徳による政治の効果の比喩として、美しいイメージである」。(抜粋)
と言っている。
No.65
哀公問いて曰く、何を為さば則ち民服せん。孔子対えて曰く。直きを挙げて諸を枉れるに錯けば、則ち民服す。枉れるを挙げて諸を直きに錯けば、則ち民服せず。(為政第二)(抜粋)
哀公がたずねた。「どうすれば民衆は従うでしょうか」。孔子は答えて言った。「正しい者を抜擢して不正な者の上におけば、民衆は従います。不正な者を抜擢して正しい者の上におけば、民衆は従いません」。(抜粋)
この条は、農民反乱が頻発した当時、哀公(魯の君主)の問いに答えたものである。孔子は、最大の問題は、民衆と関わる役人の質であると答えている。これは理想の政治を述べた前条(No.64)とは違い、現実的な視点からなされている言葉である。
No.66
或ひと孔子に謂いて曰く、子奚んぞ政を為さざる。子曰く、書に云う、孝なるかな惟れは孝、兄弟に友なり、有政に施すと。是れ亦た政を為すなり。奚んぞ其れ政を為すことと為さん。(為政第二)(抜粋)
ある人が孔子丹生たずねて言った。「あなたはどうして政治に関わらないのですか」。先生は言われた。「『書経』に、「ひたすら親孝行であり、兄弟仲睦まじければ、政治に貢献したことになる」とあります。これもまた政治にたずさわることです。何もわざわざ国の政治に関わる必要はありません。(抜粋)
孔子は、家庭内の秩序をきちんと保つことも政治であり、大きな視点で見れば国の政治に結びつくと言っている。著者は、このようい家庭、国家、天下へと秩序性を拡大してゆくのが儒家思想・儒教の根本であるとしている。
No.67
子貢 政を問う。子曰く、食を足らしめ、兵を足らしめ、民之れを信ず。子貢曰く、必ず已むを得ずして去らば、斯の三者に於いて何をか先にせん。曰く、兵を去らん。子貢曰く、必ず已むを得ずして去らば、斯の二者に於いて何をか先にせん。曰く、食を去らん。古自り皆な死有り。民 信無くんば立たず。(顔淵第十二)(抜粋)
子貢が政治についてたずねた。先生は言われた。「食料を充分にし、軍備を充分にし、民衆が信頼感をもつことだ」。子貢は言った。「どうしてもやむえず、どれかを捨てなければならないときは、この三つのうち、どれを先にしたらいいでしょうか」。先生は言われた。「軍備を捨てることだ」。子貢は言った。「どうしてもやむえず、どちらかを捨てなければならないとき、残る二つのうち、どれを先にしたらいいでしょうか」。先生は言われた。「食料を捨てることだ。昔から誰でもみな死ぬ運命にある。民衆は信頼感がなえれば、立ちゆかないものだ」。(抜粋)
ここで孔子は、政治で最も大事なことは、民衆の信頼を得ることだと言っている。著者は、このような孔子を「不可知な世界には踏み込まない現実主義者」であるとともに「現実をいささかでも理想社会に近づけたいと、夢を追い続けるロマンティスト」でもあると言っている。
No.68
子曰く、述べて作らず。信じて古を好む。竊かに我が老彭に比す。(述而第七)(抜粋)
先生は言われた。「祖述して創作はしない。古の文化のすばらしさを確信して心から愛する。こうして自分をひそかに老彭になぞられている」。(抜粋)
この条は「叡智の結晶である過去の文化や学問を受け継ぎ、そのエッセンスを吸収するけれども、独創による創作はしない」という姿勢を示している。
孔子は、『詩経』や『書経』などの古典を整理・編纂したとされるが、自らの著書は残していない。この『論語』も弟子たちのまとめた孔子の言行録である。
No.69
子曰く、道に志し、徳に拠り、仁に拠り、芸に游ぶ。(述而第七)(抜粋)
先生は言われた。「大いなる道に志し、徳を根本とし、仁によすがとし、六芸の世界に遊ぶ」。
この条は、孔子の理想とする境地を述べたものである。孔子は、道、徳、仁など精神性と同時に、礼儀作法、音楽、スポーツなど身体性に関わる項目を含む六芸の世界に遊ぶことを理想とした。
No.70
子曰く、詩に興り、礼に立ち、楽に成る。(泰伯第八)(抜粋)
先生は言われた。「『詩経』を学ぶことによって精神や感情を高揚させ、礼法を学ぶことによって自立し、音楽によって教養を完成させる」。(抜粋)
『詩経』は、もともと三千篇以上あった歌謡を孔子が三百五篇にまとめたものである。孔子は、この『詩経』を学んで精神を高揚させ、礼法を学んで社会的に自立し、音楽を楽しむことにより教養が完成するとした。
ここで著者は、No.7で孔子は、息子の孔鯉に、「詩を学ばずば、以て言う無し」と告げて『詩経』を学ぶことを勧め、次に「礼を学ばずば、以て立つ無し」と告げていると指摘している。そして、この第一に『詩経』、第二に「礼」の順番は既定の順序だったと言っている。
No.71
子曰く、篤く信じて学を好み、死を守って道を善くす。危邦には入らず。乱邦には居らず。天下に道有れば則ち見れ、道無ければ則ち隠る。邦に道有るに、貧しくして且つ賤しきは、恥也。邦に道無きに、富む且つ貴きは、恥也。(泰伯第八)
先生は言われた。「確信をもって学問を愛し、命あるかぎり正しい道の実現のために尽くす。危機に瀕した国には足を踏み入れず、混乱した国にはとどまらない。天下に道義が行われている場合は、世に出て活躍するが、天下に道義が失われている場合には、隠棲する。国に道義が行われているときに、(世に出て活躍せず)貧しくて低い地位にいるのは恥辱である。国に道義が行われないとき、裕福で高い地位にいるのは恥辱である。(抜粋)
この第二句には、「死を守って道を善くす」には、「守って善き道に死す(守り続けて善き道において死ぬ)」という読み方もあるが、孔子は「命がけ」という発想をしない人であるので、著者は、この「死を守って」を「死ぬまで」と読んでおく、としている。
この最後の部分を見ると孔子がけっして偏狭な清貧至上主義の人ではないことがわかる。
関連図書:吉川幸次郎(著)『論語(上)(下)』 、朝日新聞出版(中国古典選)、1996年
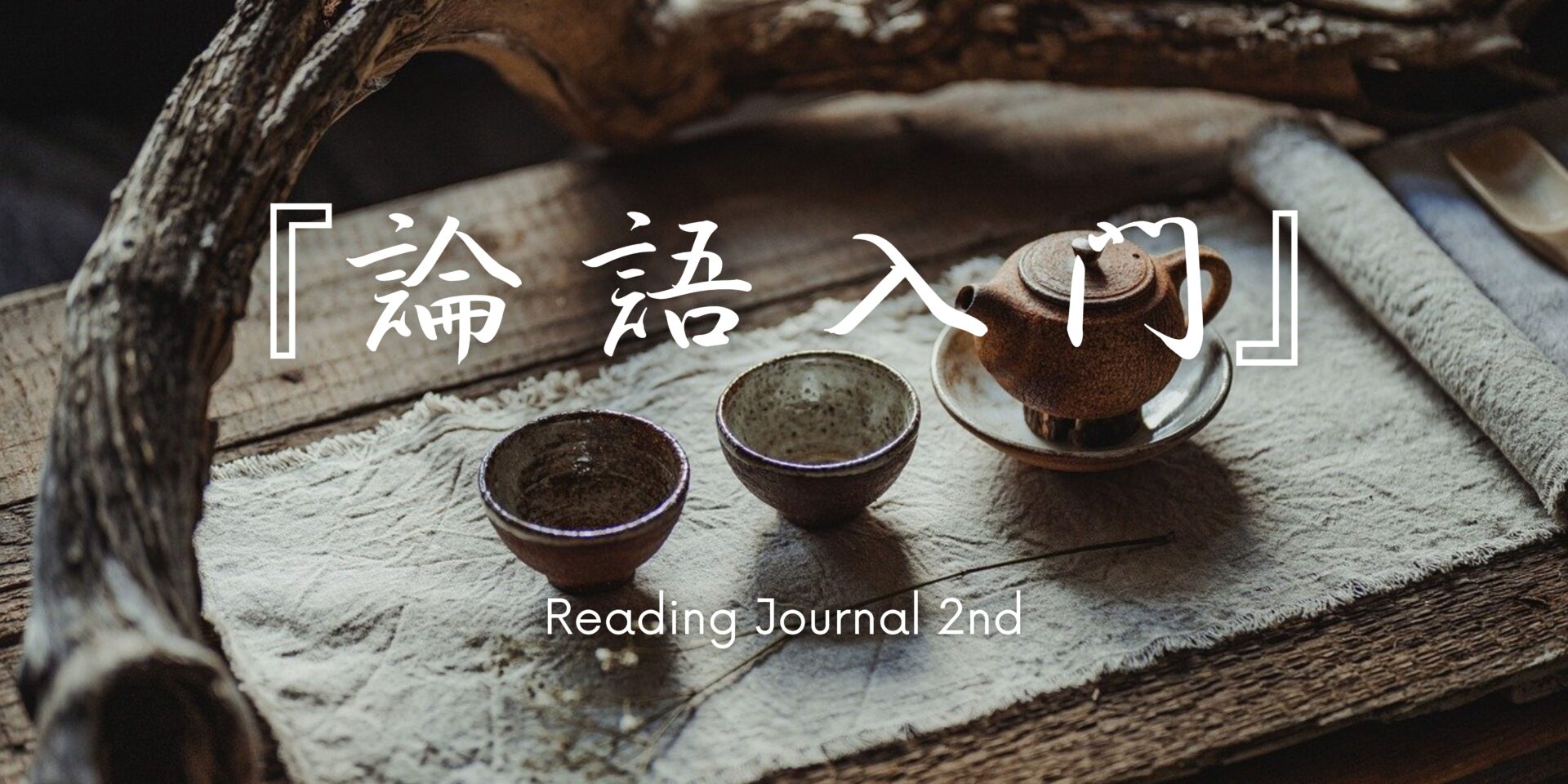


コメント