『日本軍兵士』 吉田 裕 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第3章 無残な死、その歴史的背景 (その3)
今日のところは、「第3章 無残な死、その歴史的背景」の“その3”である。これまで、“その1”で、陸海軍の軍事的思想の問題が取り上げられ、“その2”は、明治憲法に由来する問題、さらに陸海軍の軍紀の弛緩と廃退などの問題であった。
そして、今日のところ“その3”では、日本の資本主義の後進性に焦点があてられる。それでは読み始めよう。
3 後発の近代国家 — 資本主義の後進性
兵力と労働力の競合
欧米列強の軍隊と比較してみると、日本資本主義の後進性が軍備の増強や近代化にとって大きなマイナス要因となっていることがわかる。(抜粋)
その一つが、兵力と労働力の競合である。列強に比べ労働生産性の低い日本では、多数の熟練工を労働現場に確保する必要があった。同じように、零細農家が支配的な日本では、農村でも労働力が必要であった。結果として兵力動員と労働力動員の間に競合関係が生まれ、列強に比較して総人口に占める動員兵力の割合が低い水準にとどまった。
この隘路を打破するためには、二つの道しかないと著者は言っている。
- 植民地からの兵力動員
- 女性の動員
である。
①に関しては、政府はこれに消極的であった。「植民地支配に不満を持つ被支配者を軍隊に組み入れることの恐怖」と「兵役義務を課した場合に「反対給付」として参政権の付与を余儀なくされる」ことを危惧したからである。
ここの、「兵役義務を課した場合に、参政権の付与を余儀なくされる」というのは、意外な感じがあるが、『憲法とは何か』の中に、ヨーロッパで参政権が広がった理由として、第一次世界大戦後の行われた徴兵制度であるということが、説明されている。大量の国民を兵力として動員するために、民主化や福祉の向上などの政策が取られたということである(ココ参照)。(つくジー)
②に関しては、深刻な労働力不足のなか労働力として女性の動員が始まり、多くの女性が軍需工場などで働いたが、日本では「家」制度を重視したため、基本的に動員されたのは未婚の女性だけであった。欧米では、補助部隊に女性が従軍し、ソ連では女性の戦闘部隊が作られたが、日本では結局、極少数の女性通信隊が作られただけだった。ここに、「家」制度と絡んで、戦争未亡人の再婚問題について触れられている。
いずれにせよ、兵力と労働力の競合を突破する二つの道は、どちらも重点政策にはならなかった。
少年兵への依存
植民地出身者や女性の軍事動員には消極的であったのに対して、少年兵を重視した。海軍では、一九三〇年に飛行予科練習制度(予科練)(一五歳から一七歳)が創設され、陸軍でも一九三四年に少年飛行兵制度が創設され、さらに少年通信兵、少年戦車兵などが次々と誕生した。
純真で心身ともに柔軟な少年期から徹底した専門教育を実施し、特殊技能を持つ下士官を育成することが目的だった。(抜粋)
アジア・太平洋戦争期には、
- 海軍特別少兵(海軍練習兵)制度
- 少年船員制度
が重要である。
① は、もともとは一四歳以上一六歳未満の少年に特殊技能教育を行い、海軍中堅幹部を養成するものであった。しかし、戦況の悪化から、短期間の教育の後に第一線に配置する方針に変わり、実戦に参加した少年たちの多くが戦死した。
② は、船舶の新造と、船舶の喪失による船員の死亡による、船員の不足を補う制度である。入所者は一四歳以上の男子で三ヵ月という短い教育期間の四万人が配属された。アジア・太平洋戦争での戦没船員数は六万六〇九人とされるが、そのなかには、一五歳前後の少年船員が含まれていた。
遅れた機械化
第一次世界大戦は自動車の大量使用という面でも大きな画期となった。(抜粋)
それ以降、欧米では馬に変わって軍用自動車が人員や物資の輸送にあたった。しかし、日本では、自動車産業そのものが未発達だったため、満州事変、日中戦争、アジア・太平洋戦争でも多くの軍馬が徴用され、輸送を担った。そして多くの軍馬もまた戦争の犠牲となった。
この機械化の遅れについて、元陸軍中佐の加登川幸太郎は、『日本陸軍の実力 第二集』の中で、日露戦争から一歩も進んでいないとし「日本陸軍は『馬の軍隊』であり、『人力の軍隊』であった」と酷評している。
また、わずかながら使用された自動車についても、国産の自動車の性能の悪さが軍隊の足を引っ張っていた。
この輸送における馬への依存、そして軍馬の犠牲については『餓死した英霊たち』にも書かれるよ(ココ参照)。(つくジー)
体重の五割を超える装備
このような状況において、乗馬が認められた将校を別とすれば、歩兵の移動は徒歩による行軍が中心となった。
兵士たちは、鉄帽(ヘルメット)、背嚢、雑嚢、小円匙(シャベル)、天幕、小銃、銃剣、弾薬盒(弾薬入れ)などの武器や装備を身につけて行軍する。長期の戦闘、特に後方からの補給が期待できない戦闘に参加するときは、予備の弾薬や食料がさらに加わる。問題は、どれだけの重量の負担に兵士が耐えられるかである。(抜粋)
ここで著者は、日中戦争が長期化する中で兵士の携帯する武器装備の重量は体重の五〇%になったという、調査結果を紹介している。
中国戦線では、拉致してきた住民に武器や装具を担わせる部隊と行動を共にさせることが普通に行われたが、住民が完全に避難している地域では、それもできなった。著者は大陸打通作戦時の
「一番ひどい兵は、ほとんど自分の体重に近い負担量を持って行動」していることがわかった。(抜粋)
という調査結果を引用している。このような悲惨な状況であったが、司令部では何の対策も立てられない状況であり、軍中央も負担量の増大を容認していた。
著者はこのような歩兵の負担ついて幾つかの事例を挙げて論じている。山岳部を通過して進んだインパール作戦時には、兵士の個人装備は、四〇キロ~五〇キロもあった。この負担量は、一人では立ち上がれない重さであり、
「出発準備の号令がかかった時など、亀の子みたいに手足をバタつかせても起き上がれず、かわるがわる手を引いてもらって立」ち上がったという(『歩兵第二一五連隊戦記』)。(抜粋)
飛行場設営能力の格差
機械化の立ち遅れによって不利な戦闘を強いられた典型的な事例としては、飛行場の設営能力があげられる。(抜粋)
ソロモン諸島やニューギニアでの航空戦では、米軍がブルドーザーやパワーショベルなどの土木機械を駆使し、一週間内に飛行場を建設したのに対して、日本軍は人力主体の設定方式に依存し、完成までに一ヵ月から数ヵ月を要した。そして飛行場の性能も米軍の方が圧倒的に優れていた。
海軍は徴用工具を主体とした設営体が飛行場を建設したが、「その内容は人夫を集めて、『つるはし、もっこ、ローラー』を装備した時代遅れのもので」、設営能力不足のため必要な地点に飛行場が建設できず、やむをえず建設可能な地点に飛行場を建設するしかなかった(『戦史叢書 海軍航空概史』)。(抜粋)
この設営能力の低さにより不利な航空戦を強いられていることが明らかになると、設営体の機械化がなされたが、国産の土木機械は、アメリカ産の模倣でしかなく性能が悪く、運転員や修理工、建設資材の不足などにより、十分な能力を発揮できなかった。
この設営能力の低さにより不利な航空戦を強いられていることが明らかになると、設営体の機械化がなされたが、国産の土木機械は、アメリカ産の模倣でしかなく性能が悪く、運転員や修理工、建設資材の不足などにより、十分な能力を発揮できなかっ
一〇年近く遅れた通信機器
日本軍の通信機器にも大きな技術上の欠陥があり、作戦として無視できない障害となっていた。(抜粋)
陸海軍の戦闘機に搭載されていた無線電話は性能が悪く、効果的な編隊戦闘が出来なかった。
そもそも陸軍では、通信の必要性に関する認識が極めて低く、通信隊ができるのも日中戦争以後のことである。この通信には、有線と無線があるが、陸軍は有線通信にこだわり重視した。その結果、米軍の爆撃が始まると通信線は、随所で断線し通信不能となった。そのため司令部は各部隊の状況を把握できず、各部隊も司令部の統一した指揮を受けることができなかった。ペリリュー島の防衛戦では、早期に通信が寸断され、各部隊は健在にも関わらず、統一した指揮がないまま、孤立した各部隊がばらばらに米軍と戦闘している状態となった。
通信機器でのもう一つの問題は、米軍がと違い、片手でも奉じ可能は携帯用小型無線機(ハンディ―トーキー)を持っていないことである。日本軍の歩兵用無線機は、駄馬に背負わせて運ぶような大型のものであった。この携帯用小型無線機がないため、指揮官と前線、前線の各部隊との連絡は伝令に頼るほかなく、連携の緊密さを欠いた。
著者は無線部隊の「装備」は、無線機一台と伝書鳩五羽という事例を引き、まだ未だに伝書鳩が使われたことを指摘している。さらに、長い縦隊の先頭と後尾との連絡などで、連絡事項を口頭で順次申し送る逓伝という原始的な方法もよくつかわれた。
これに対して米軍は小型無線機などを使用し統合した作戦を行った。さらに、日本軍のこのような問題点を把握していていた。
軍需工業製品としての軍靴
ここで著者は、「軍靴の製造について、工業の面から簡単な分析」を行っている。
陸軍の軍靴の粗悪さについて、
「帰路、自分の軍靴は泥道ばかり歩いていたため縫い糸が腐り、段々程度が悪くなり泥道に突っ込んだ時に、踵の意図が切れてポッカリ口が開いてしまい、仕方なく縄で絡げて歩き続け」た(抜粋)
などのいくつかの事例を紹介している。このように、軍靴の劣化については、皮革の問題(第二章のココ参照)以外に糸の問題があった。
まずミシンであるが、戦前の日本では外国製のミシンが中心であった。しかし、輸入が事実上不可能となったため、国産ミシンの製造に力をいれる。しかし、軍需用品に必要なミシンは精密な工業用ミシンであるため、資材・技術者・熟練工の不足、さらに開発面の遅れにより軍の要望を満たすまでに量産することは難しかった。
そして、糸であるが、まず、頑丈な軍靴の縫い糸は、亜麻糸でなければならなかった。しかし、この亜麻糸は冷涼な北海道でしか栽培できず、軍の需要に生産が追いつかなくなった。結局、品質の劣る亜麻の繊維まで使用せざるを得なくなり、軍靴の縫い糸が切れやすくなる原因となった。
以上のように、こうした基礎的な産業面でも、日本はかなり早い段階から総力戦上の要請に応えられなくなっていたのである。(抜粋)
関連図書:
長谷部 恭男 (著)『憲法とは何か』、岩波書店(岩波新書)、2006年
藤原 彰(著)『餓死した英霊たち』、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2018年
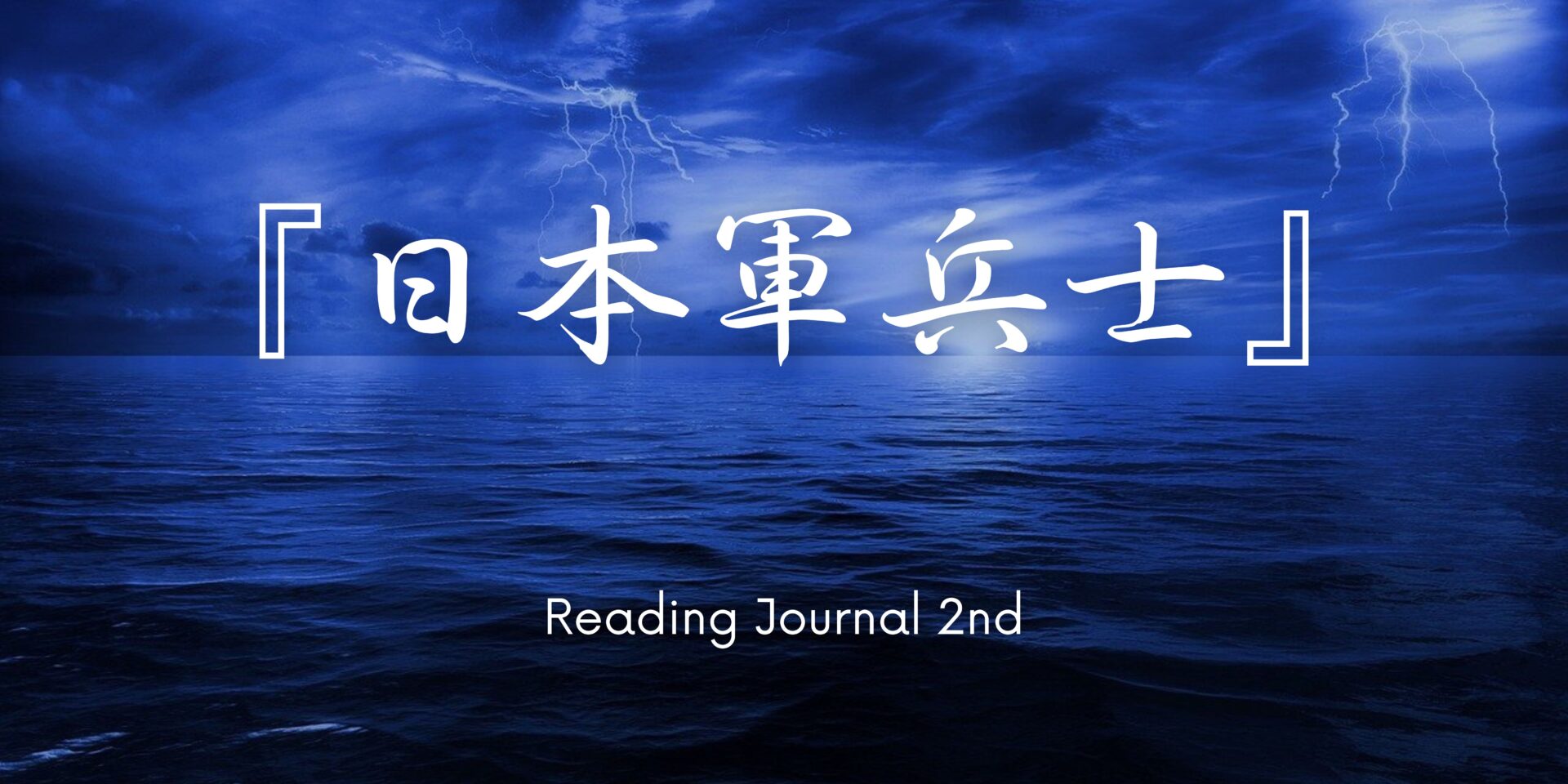


コメント