『「モディ化」するインド』湊 一樹 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第4章 ワンマンショーとしてのモディ政治(その3)
今日のところは“第4章 ワンマンショーとしてのモディ政治”の“その3”である。この章では、モディ首相の政治手法を「ワンマンショー」として捉え(その1)、そしてその手法がどのようなカラクリであるか(その2)を詳説された。今日のところ“その3”は、BBCのドキュメンタリーとそれに対するモディ政権の反応についてである。
BBCドキュメンタリーの波紋
BBCのドキュメンタリー
二〇二三年にイギリスの公共放送BBCは、『インド‐‐モディ政権を問う(India: The Modi Question)』と題する二回シリーズのドキュメンタリーを放送した。
その内容は、インド最大のマイノリティー集団であるイスラーム教徒を取り巻く状況に焦点を当て、現政権を率いるモディ首相の政治姿勢を厳しく問うものであった。そのため、インド政府の過剰ともいえる反応と相まって、BBCのドキュメンタリーは大きな波紋を広げることになった。(抜粋)
第一回目の放送は、二〇〇二年のグジャラート暴動をとりあげ、イギリス政府の調査報告書、イギリス政府関係者や被害者の証言、当時の映像を織り混ぜながら紹介された。第二回目の放送は、二〇一九年の総選挙後に起こった、イスラム教徒を狙い撃ちにした差別的政策や直接暴力などの迫害を映像と共に放送した。
インド政府の反応と攻撃
このドキュメンタリーが放送されるとインド政府はすぐに反応しBBCに厳しい非難の言葉を浴びせた。インド政府やその周辺の人々は、このドキュメンタリーは、モディへの誹謗中傷であり、なかには政治的意図のある陰謀であると主張した。
このインド政府の攻撃は単なる言葉だけのものではなかった。インド政府は番組の動画を削除するようにユーチューブとツイッターに命じ、両社はすぐにその指示に従った。この事態を受けて野党、国内貝のメディア、言論・表現の自由を推進する団体などからインターネットの検閲であると非難の声が上がった。
このインド政府による削除命令が出ると、それに対抗するように『『インド‐‐モディ政権を問う』の映画の上映会が各地で催された。しかしモディ政権は、それをあらゆる手段を使って防止した。
さらに、インド財務当局がBBCの現地支局に家宅捜索に入った。この家宅捜索は、BBCへの報復とメディア全体への見せしめを意図していると著者は指摘している。
このBBCのドキュメンタリーへのインド政府の反応は、過剰反応気味であった。それまでも、海外メディアや外国人記者については、現地支局への家宅捜索のような目立たない形をとって行われてきた。それに加えインド政府は「インドに否定的な報道」をしているジャーナリストに対して、ビザの発給を脅しと嫌がらせの道具にした。
しかしこのような過剰反応気味の反応は、ただちに深刻な政権批判に結びつかないというモディ政権の予想があったからだと、著者は言っている。
BBCがインドの税務当局による家宅捜索を受けた後、イギリス政府は「状況を注視する」と述べるのみで公式な声明をだしていない。これはイギリス政府がインド政府との自由貿易協定の締結に向けて批判を差し控えたとの観測がある。アメリカとフランスも表立った批判を行っていない。それと関係があるかわからないが、インド政府はちょうど家宅捜索が始まった日に、インド最大の航空会社エア・インディアが欧州のエアバスと米ボーイングの旅客機を計四七〇機発注すると発表した。クワッドの一員の一員でもあるオーストラリアも、普遍的価値よりもインドとの利害関係を重視するという姿勢を取った。そして、日本政府もいっさいコメントをしていない。こういう状態であるため、
日本において、インドについての一般的な認識と現実のあいだに大きなズレがあるのは、当然というべきなのかもしれない。(抜粋)
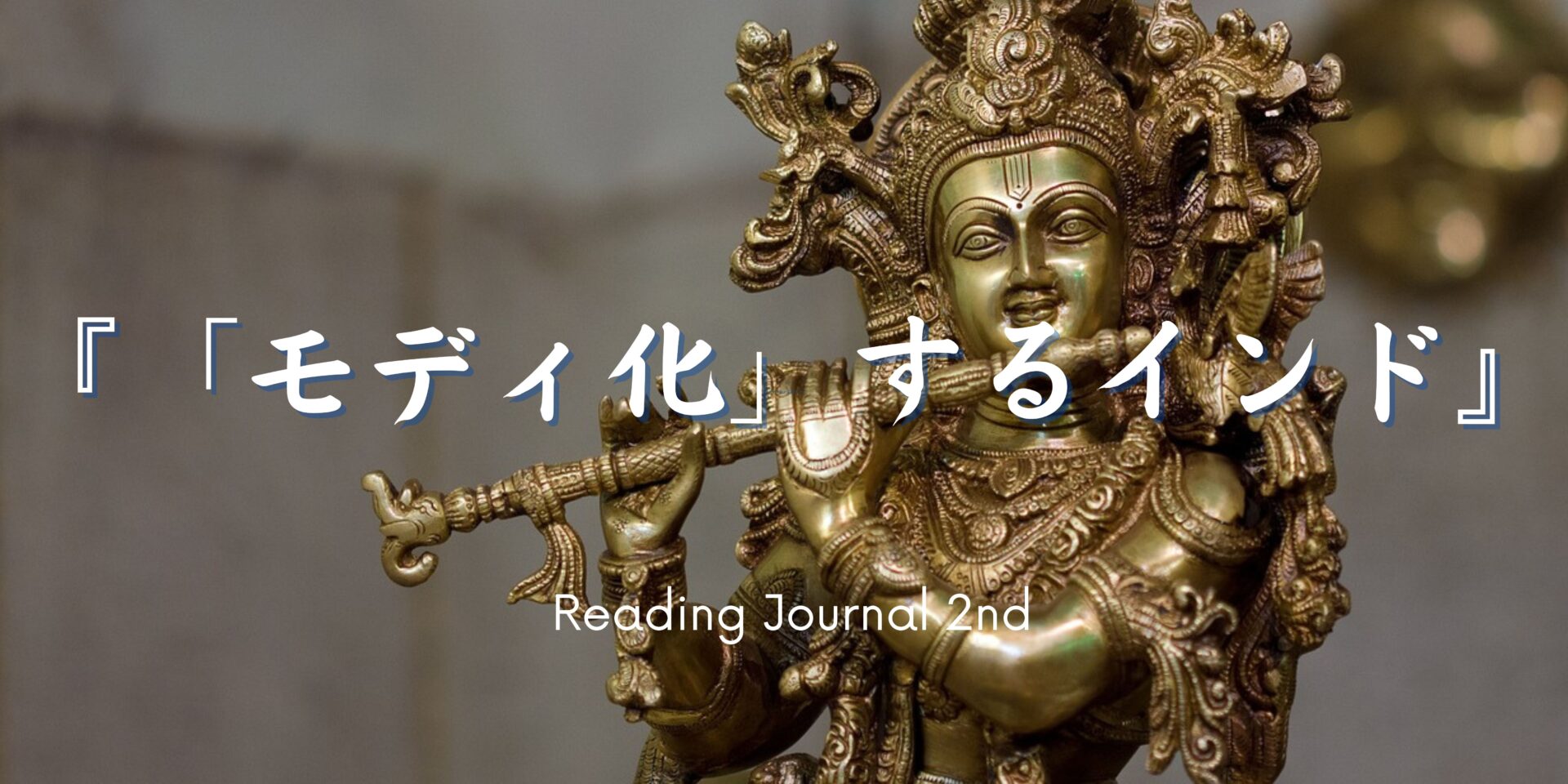


コメント