『人生の一冊の絵本』 柳田邦男 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
少年が本に魅せられるとき
子どもが物語の世界に惹きこまれて、夢中になって本を読むようになるきっかけは、何だろうか。おそらく子どもの生活の文脈のなかで、たまたま何かの出会いがあって、本好きになるのだろが、その出会いには一人ひとり造ったドラマがあるに違いない。(抜粋)
冒頭でそのように語った柳田は、自身が読書へと導かれた経験を語っている。この章では、アメリカの図書館員の働きかけによって、本の世界に導かれた少年の物語として二冊。さらに図書館についての絵本を二冊の計四冊を紹介している。
『ぼくのブック・ウーマン』
かつてアメリカでは、アパラチア山脈地方で図書館員が馬の背に本を積み、地域の家庭に本を届けるというプロジェクトがあった。馬で配達をした図書館員(公式には「荷馬図書館員(Pack Horse Librarian)」は、女性が多かったため彼女たちは「ブック・ウーマン」と呼ばれていた。『ぼくのブック・ウーマン』はそのような図書館員の活躍をある一家の物語として絵本化したものである。
絵本に書かれている一家は牧畜と農業を営んでいて、父を助けて働く長男のカルは、本などに興味はない。しかし、妹のラークは、ブック・ウーマンが二週間ごとに届けてくれる本を心待ちにしていて、一日中本を読んでいた。
ある冬の日、カルは、吹雪のなかを馬にまたがってやってきたブック・ウーマンの姿を窓越しに見る。そして、その勇気に心を打たれた。
そして、ラークに本に何が書いてあるのかを聞くのだ。それはカルが本を読む少年に変容する扉を開いた瞬間と言えるだろう。(抜粋)
『トマスと図書館のおねえさん』
『トマスと図書館のおねえさん』は、カルフォルニア大学リバーサイド校の学長を務めたトマス・リベラさんが自らの少年時代を描いた絵本である。
トマスは、スペイン語を第一言語とするメキシコ系アメリカ人であった。トマスは、おじいさんが話してくれるスペイン語の話を聞くのが大好きだった。そしてある日、おじいさんは、話が尽きたので、図書館で本を読んできてその話を聞かせておくれと言った。
トマスは、図書館が初めてだったが、図書館員のおねえさんにやさしく向かい入れられ、図書館はトマスの良い居場所となった。そして、図書館で本を読んだ後、家に帰えると家族やおじいさんに読んだ本の内容を聞かせて大いに喜ばれた。
『図書館ラクダがやってくる — 子どもたちに本をとどける世界の活動』
『図書館ラクダがやってくる— 子どもたちに本をとどける世界の活動』は、世界一三か国で行われている「移動図書館」の活動を紹介している写真絵本である。
途上国の子どもたちが、いかに本のサービスを受けることを渇望しているかが、この絵本の写真記録から伝わってくる。(抜粋)
『としょかんのよる』
最後の一冊『としょかんのよる』は、ねずみを追ってキツネが図書館に迷い込んでしまう。ねずみはキツネにつかまりそうなところで、
待ったをかけ、ネズミは本の面白さを教える。キツネは食わないから本を読めるように言葉をおしえろと、ネズミやくわえてきたニワトリに要求するのだ----。(抜粋)
関連図書:
ヘザー・ヘルソン(文)、デイビッド・スモール(絵)、藤原宏之(訳)『ぼくのブック・ウーマン』、さ・え・ら書房、2010年
パット・モーラ(文)、ラウル・コローン(絵)、藤原宏之(訳)『トマスと図書館のおねえさん』、さ・え・ら書房、2010年
マーグリート・ルアーズ(著)、斎藤規(訳)『図書館ラクダがやってくる — 子どもたちに本をとどける世界の活動』、さ・え・ら書房、2010年
ローレンツ・パウリ(文)、カトリーン・シェーラー(絵)、若松宣子(訳)『としょかんのよる』、はるぷ出版、2013年
生きるに値すると思える時
この世の中は、戦争や民族紛争など不条理な死が多く、人間に対して絶望的な気持ちになる。
しかし、目をこらして世界の細部を見つめると、人間はそんな悪人ばかりじゃない。私たちをほっとさせてくれたり、感動や勇気を与えてくれたりする人々もすくなくない。(抜粋)
この章では、そんな人物やエピソードを紹介する絵本を二冊紹介されている。
『サンパギータのくびかざり』
この本の著者は、フィリピンの現地NGO法人「ミンダナオ子ども図書館」を運営している元福武書店(現・ベネッセ)児童図書編集長だった松井友さんである。
主人公の少女リンにはお父さんがいない。そしてお母さんも病気で寝たきりである。リンは家計を助けるためにサンギータの花に糸を通して首飾りをつくり、村の教会前で売っている。
ある日、リンが売れ残った首飾りをもってしょんぼりしていると、黒い服を着た不思議な女の人が現れ首飾りを全部買ってくれた。リンはそのお金でご飯をかって家に走って帰る。
だが、お母さんには死の影が訪れ始めていた。
<かあちゃん、しなないで! ごはん かってきたよ、たべて!>
お母さんはリンを見ると、かすかにほほえんだ。だが、間もなく目を閉じて、もう二度と目を開かなかった。(抜粋)
その後、何日もリンはぼーっと海を見つめていた。そして、ある日サンギータの花飾りをいっぱい作ると、夜教会の前に行った。すると、あの黒い服をきた女の人がまた現れ、首飾りを全部買うとリンの首にかけてくれ、
<なんのおねがいが したいの?>と聞いた。<かあちゃんの ところに いきたい>。リンがそう言うと、女の人が白く輝き出し、お母さんの姿になり、リンをしっかりと抱きしめてくれたのだ。そして、お母さんはこう言った。
<いつも そばにいるから、あんしんして 生きていきなさい>
リンはお母さんのひざの上で眠りについた。(抜粋)
『パパ・ヴァイト ―― ナチスに立ち向かった盲目の人』
二冊目は『パパ・ヴァイト ―― ナチスに立ち向かった盲目の人』である。
この本は、盲目のオットー・ヴァイトという人が第二次世界大戦中にナチス・ドイツの支配下で、同じ障害のある人たちの命を救った出来事を描き出している。
ヴァイトは、ホウキやブラシを作る作業所を営んでいた。作業員のほとんどはユダヤ人の障害者であった。ホウキやブラシは日常生活で欠かせないためナチスもヴァイトの事業を特別に認めていた。そして、ヴァイトは、従業員が連行された時に、秘密警察にわいろを送って解放してもらったり、強制収容所からの脱走を支援したり、ベルリンの隠れ家にかくまったりして多くの従業員の命を救った。
関連図書:
松居友(文)、ボン・ペレス(絵)『サンパギータのくびかざり』、今人舎、2015年
インゲ・ドイチュクローン(作)、ルーカス・リューゲンベルク(絵)、藤村美織(訳)『パパ・ヴァイト ―― ナチスに立ち向かった盲目の人』、汐文社、2015年
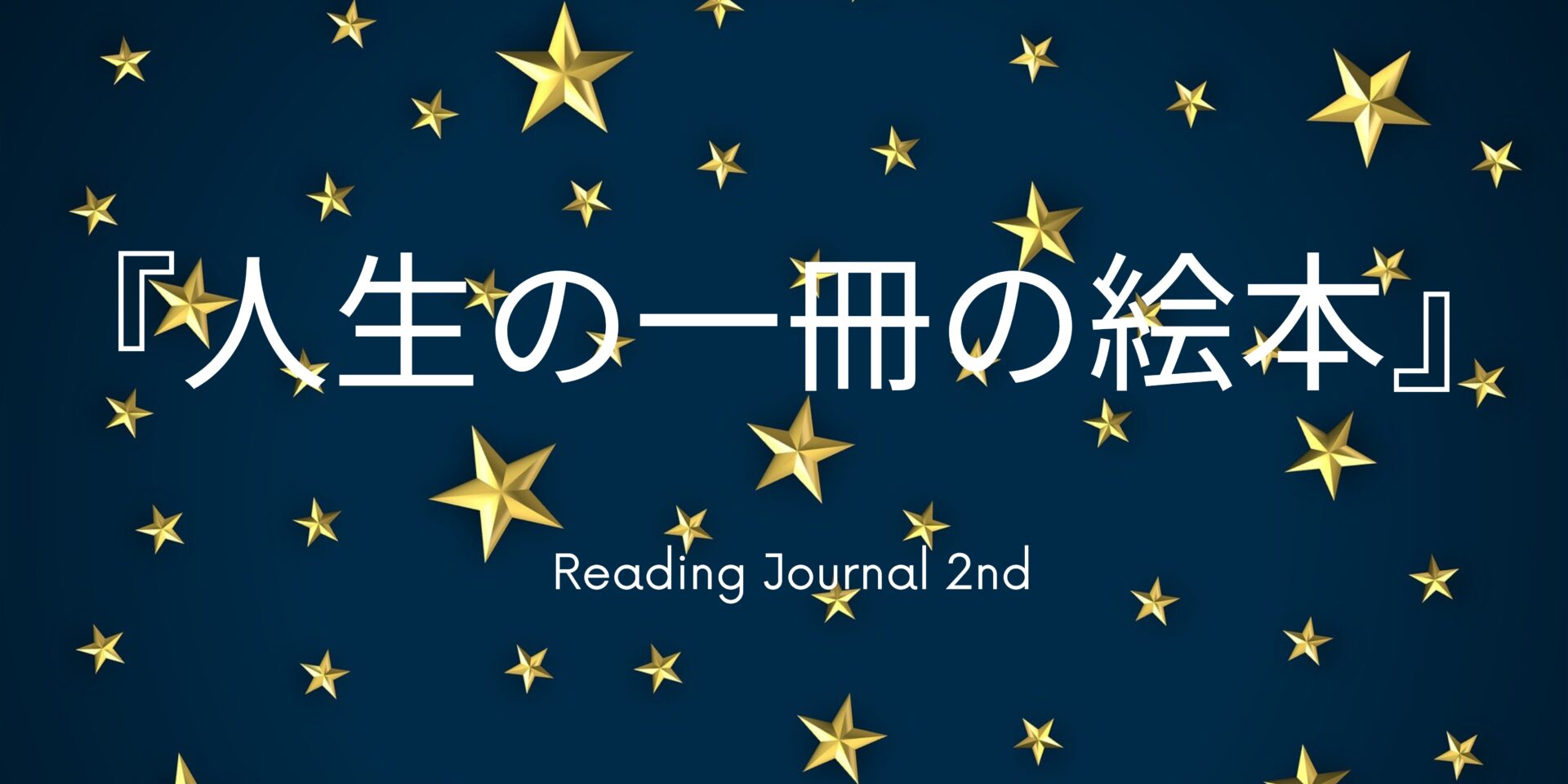


コメント