『人生の一冊の絵本』 柳田邦男 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
戦争や災害をどう伝えるか
戦争や事故などの命を奪う出来事の恐ろしさや犠牲者の家族の悲しみを、経験したことのない人が理解したり共感したりすることは難しい。それでも、そのような体験をしていない人がその悲しみやつらさを一〇分の一でも理解しようとすることは大切である。そして当事者のために何ができることはないかと寄り添う気持ちを持つことが必要である。
また、子ども時代に、戦争や災害、事故の悲惨さを知ること、世の中には大変な境遇に陥ってつらく悲しい思いをしている人がいることを理解することは、その子の人生にとって重要な意味を持つ。子ども時代にそのような感情を持ったことがないと、戦争悲惨さや災害、事故の遺族の悲しいなどに、ほとんど心を動かすことのない人間になってしまう。
私は戦争は絶対悪だという拒否感を根強く持っているが、九歳のときの空襲での恐怖体験は自分の人格(パーソナリティ)形成の大事な経験だったととらえている。(抜粋)
最近の絵本の世界では、死別や悲しみをどう受けとめ、その後のこころの持ち方をどのようにしていきるかという問題や、戦争や災害、事故を経験した人々がこころにかかえこんでいるトラウマの問題をテーマにした絵本が数多く創作されている。ここではそのような絵本を三冊紹介されている。
『タケノコごはん』
一冊目は『タケノコごはん』である。この絵本は映画監督の大島渚が小学生の時に経験した戦争の苛酷さを記した文に、伊藤秀男が絵を描いて絵本化したものである。大島は、戦争中の子供たちと先生のことを一貫して描いている。
このころ軍国主義の教育が小学校にも浸透し、子どもたちは早く大人になって兵隊になることが国のためになることだと教えられた。そして、強いことが良いことだと思いこまされていた。強いとは喧嘩が強いこと。同じ学年いちばん強いのは、さかいくんだった。でもさかいくんは、弱いものいじめはしなかった。
しかし、兵隊として中国に送られていたさかいくんのお父さんが戦死したという報せが届くと、さかいくんが、変わってしまい弱いものいじめをするようになる。
やがてたくましいタイプの担任が戦場に送られる。次の担任はやさしい先生で、みんなに人気があった。そして、前の担任の戦死の報せが届き、こんどはやさしい担任が兵隊に征くことになる。
子どもたちが担任の家にお別れに行くと、食糧難なのにタケノコごはんをご馳走してくれる。最後まで黙々と食べ続けていたさかいくんが気がつくと涙を流している。はじめて見せる涙だった。突然さかいくんがしゃくりあげながら、担任に言ったのだ。
<先生、戦争なんかにいくなよっ>(抜粋)
『とどけ、みんなの思い – 放射能とふるさと』
二冊目は『とどけ、みんなの思い – 放射能とふるさと』である。この絵本は、大地震に続く東京電力福島第一原発事故の後、家族とともに避難できた二匹のネコと仲良しの犬のふくちゃんを主人公とし、ふるさとを放射能汚染で奪われるという不条理を、やわらかく描いている。
『ふくしまからきた子』
三冊目は『ふくしまからきた子』である。この絵本は、原発事故で避難してきた少女まやと、避難先の広島の男の子だいじゅの出会いと変化を描いた作品である。
公園でサッカーをしていただいじゅが、転がってきたボールを蹴り返してくれたまやの足さばきがうまいので話しかける。まやは、福島でサッカー部員だったという、でも、福島では放射線量が高いので子どもたちは外で遊べない。まやは<もう わたし サッカーやらない>と心に決めたという。
その話を聞いただいじゅは、家に帰ると<ほうしゃせんというのは なんじゃ?>と聞いた。原爆の恐怖を知るひいおばあちゃんが、放射能の恐ろしさについて話してくれた。
<どうやったら その こわいの なくせるんじゃ?>と聞くと、ひいばあちゃんは、<わたしゃあ そうりだいじんじゃないけぇ よう わからん>と言う。翌日、だいじゅは、まやに言う。
<おれ しょうらい そうりだいじんになる! そうして ほしゃのう なくすんじゃ!>(抜粋)
関連図書:
大島渚(文)、伊藤秀男(絵)『タケノコごはん』、ポプラ社、2015年
夢ら丘実果(文)、渡辺あきお(絵)『とどけ、みんなの思い – 放射能とふるさと』、新日本出版社、2014年
松本猛、松本春野(絵)『ふくしまからきた子』、岩崎書店、2012年
あとがき
柳田邦男は、今は絵本のルネッサンス期であると言っている。
それは絵本という表現ジャンルの中に実に多様な人生の課題の解答例といえる作品が生まれているからである。人生には様々な哲学や宗教、そして精神分析など課題があるが、そういうものを扱っている絵本が増えている。
絵本は、子どもが読んで理解できるだけでなく、大人が自らの人生経験やこころにかかえている問題を重ねつつ、じっくりと読むと、小説などとは違う独特の深い味わいがあることがわかってくるものだ。(抜粋)
ここでこの本の成り立ちが書かれている。この本はもともと看護専門誌『看護管理』に現在(2020年)も連載されている小文をまとめたものである(2024年4月号~2019年9月号より)。
「大人こそ絵本を」「絵本は人生に三度(幼少期、子育て期、中高年期)」「大人の気づき、子どものこころの発達」という呼びかけを始めて、二〇年になる。合理主義、効率主義、利己主義、ネット依存が支配的になっている索漠とした時代状況のなかで、この本が人々のこころと人生の歩みに少しでも温もりをもたらすことができればと願っている。(抜粋)
[完了] 全27回
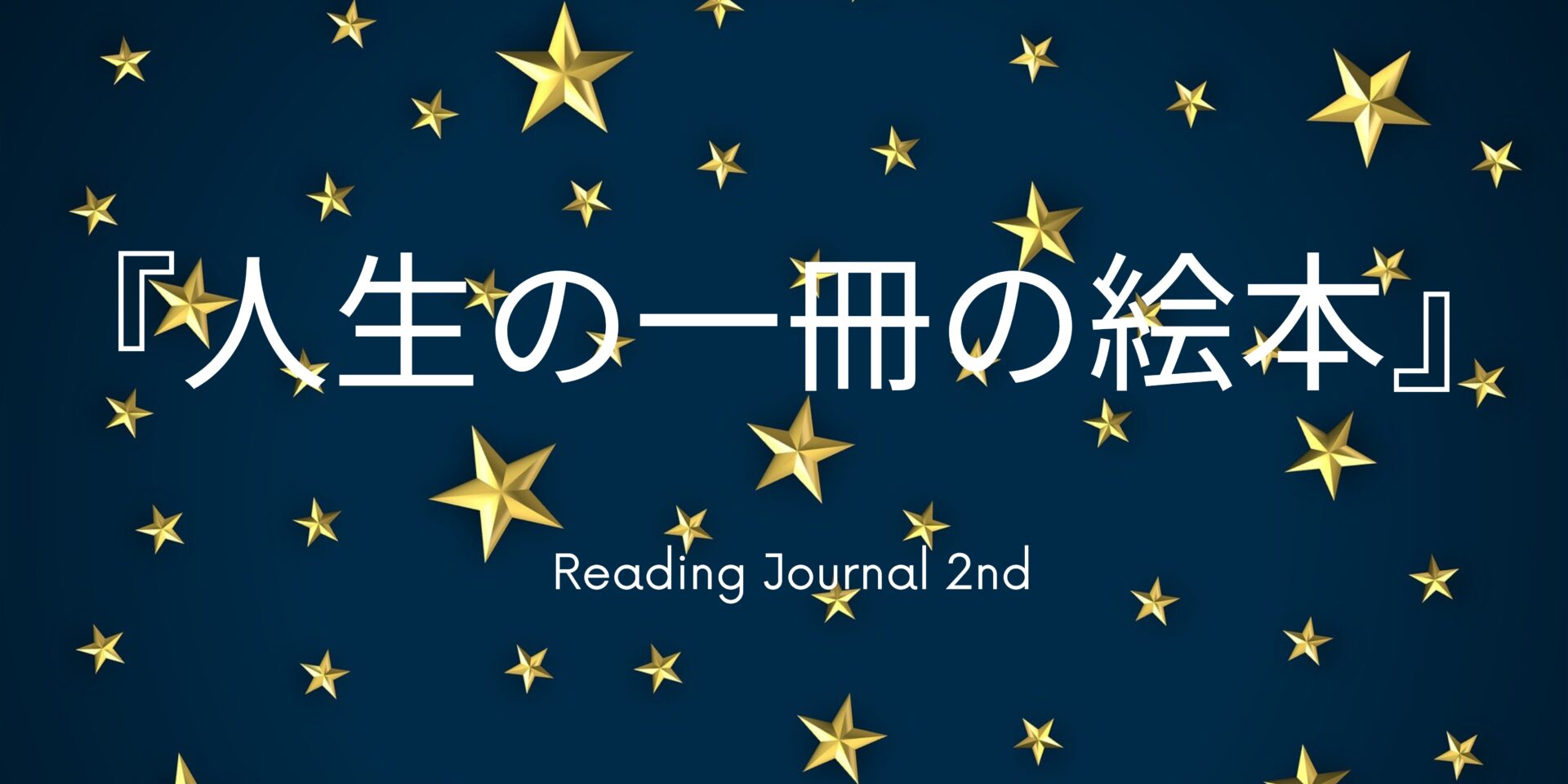


コメント