『論語入門』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第三章 弟子たちとの交わり(その3) — 2 大いなる弟子たち — 子貢 「一を聞いて二を知る」秀才
今日のところは、「第三章 弟子たちのとの交わり」(その3)である。前回“その2”では、顔回が取り上げられた。今日のところは、孔子の三人の高弟の二人目、「子貢」である。それでは読み始めよう。
子貢 — 「一を聞いて二を知る」秀才
No.81
子曰く、回や其れ庶きか。屢しば空し。賜は命を受けずして、貨殖す。億んばかれば則ち屢し中る。(先進第十一)(抜粋)
先生は言われた。「顔回は理想的存在に近いだろう。だが、しょっちゅう無一文になる。賜(端木賜すなわち子貢)は君命を受けないで、自由に商売し金儲けをする。予測すればしばしば的中する」。(抜粋)
これは、顔回と子貢を比較した言葉である。顔回は孔子の理想とする存在に近かったが貧乏だった(No76参照)。それに対して子貢は、魯の外交使節として斉・呉・越などに赴いたり、自由な商売で金儲けをするなど裕福だった。
子貢が大商人として『史記』の「貨殖列伝」にも次のような記載がある。
「(子貢は)曹・魯の地方で、物資を売りに出したり買占めしたりして貨殖した。孔子の高弟のうち、子貢がもっとも金持ちだった云々」(抜粋)
ここで著者は、貧乏は顔回と、金儲けの上手は子貢について孔子は優越をつけていないと注意し、孔子は優秀な二人の弟子のそれぞれ個性的な生き方を、温かく無見守っていると言っている。
No.82
子貢曰く、貧しくて諂うこと無く、富んで驕ること無きは、如何。子曰く、未だ貧しくて楽しみ。富んで礼を好む者に若かざる也。子貢曰く、詩に、切するが如く磋するが如く、琢するが如く磨するが如しと云うは、其れ斯を之れ謂うか。子曰く、賜や、始めて与に詩を言う可きのみ。諸に往を告げて来を知る者なり。(学而第一)(抜粋)
子貢は言った。「貧しくとも卑屈にならず、金持ちでも高ぶらないというのは、どうでしょうか」。先生は言われた。「それもよいが、貧しくとも楽しく暮らし、金持ちであって礼を好む者には及ばないだろう」。子貢は言った。「『詩経』の「切するが如く磋するが如く、琢するが如く磨するが如し」というのは、このことをいうのですね」。先生は言われた。「賜(子貢の本名)よ。おまえとこそはじめていっしょに詩の話ができるというものだ。おまえは何かを告げると、その先のことがわかる人間だ」。(抜粋)
この条は子貢の質問に対する孔子の答えに、子貢が『詩経』の言葉を引用して返答し、それを孔子が絶賛したという話である。
著者は、このような孔子と子貢の会話はいきいきとしてテンポがはやく、快感を覚えると評している。
No.83
子貢問いて曰く、賜や如何。子曰く、女は器也。曰く、何の器ぞや。曰く、瑚璉也。(公冶長第五)(抜粋)
子貢がたずねて言った。「賜(子貢の本名)はどうですか」。先生は言われた。「おまえは器だ」。(子貢は)言った。「何の器ですか」。先生は言われた。「瑚璉だ」。(抜粋)
「瑚璉」は、宗廟でお供え物を盛るための最上級の器である。
孔子は、「君子は器ならず(君子は用途のきまった器物であってはならない(No3参照)」。と言っていてこれが、持論だった。しかし、子貢の問いに、うっかり「器」であると孔子が言ってしまう。そして気色ばった子貢の「何の器ですか」という問いに、孔子が「瑚璉」と答えて事なきを得たという話である。著者は、この条にもさまざまな解釈があるが、このように読みたい、としている。
No.84
子 子貢に謂いて曰く、女と回と孰れか愈れる。対えて曰く、賜や何ぞ敢えて回を望まん。回や一を聞いて以て十を知る。賜や一を聞て以て二を知る。子曰く、如かざる也。吾れと女と如かざる也。(公冶長第五)(抜粋)
先生は子貢に向かって言われた。「おまえと顔回はどちらがすぐれているかね」。(子貢は)答えて言った。「賜(子貢の本名)は顔回におよびもつきません。顔回は一を聞いて十を悟りますが、私は一を聞いて二を悟るだけです」。先生は言われた。「(顔回に)おまえは、およばないな、私もおまえもおよばないのだ」。(抜粋)
孔子が子貢に、顔回と自分との評価を尋ねた時の話である。両者は互いにライバルであるが、ここで子貢はあさりと顔回に兜を脱ぐ。孔子の答えは、そのような子貢に対する称賛と励ましであったと、著者は評している。
No.85
子貢問う。師と商と孰れか賢れる。子曰く、師や過ぎたり、商や及ばず。曰く、然らば則ち師愈れるか。子曰く、過ぎたるは猶お及ばざるがごとし。(先進第十一)(抜粋)
子貢がたずねた。「師(顓孫師あざな子張)と商(卜商あざな子夏)とどっちがすぐれているでしょうか」。先生は言われた「師はやりすぎであり。商は引っ込み思案だ」。(子貢は)言った。「ならば師のほうがすぐれていますか」。先生は言われた。「やるすぎと引っ込み思案は似たようなものだ」。(抜粋)
この条も孔子の人物評価である。子貢が「師」と「商」のどちらが優れているかと公私に問う。すると「師」はやりすぎで「商」は引っ込み思案であるといい、どちらも似たようなものあると評した。
これが、後世に広く流布する「過ぎたるは猶お及ばざるがごとし」の出典となった。
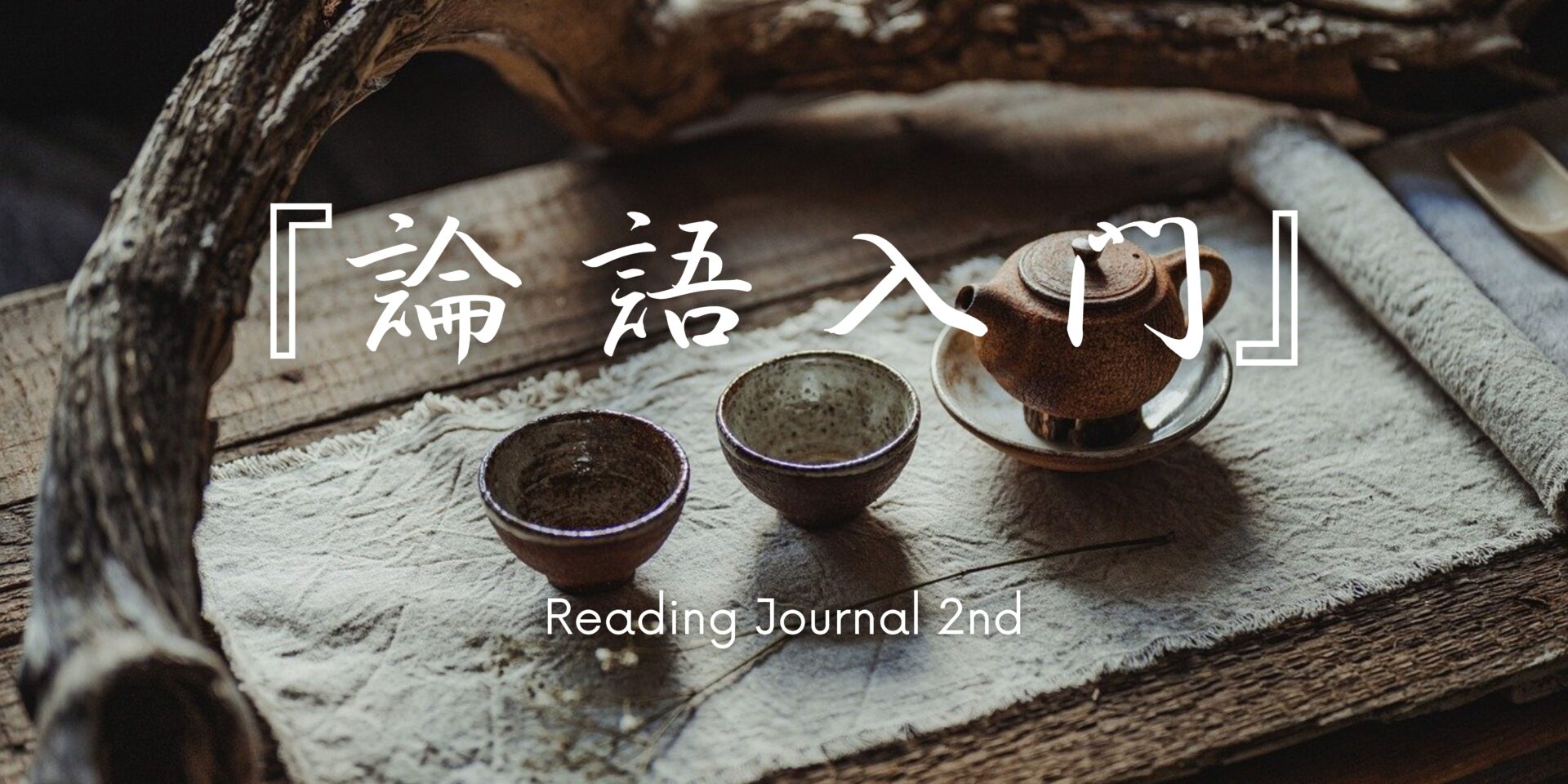


コメント