『外国語学習の科学』 白井恭弘 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第2章 なぜ子どもはことばが習得できるのか -- 「臨界期仮説」を考える (後半)
今日のところは、“第2章 なぜ子どもはことばが習得できるのか”の“後半”である。”前半“では、「年齢が外国語の習得に非常に大きな影響を与える」ことが示された。そして、そのことを説明するために「臨界期仮説」が解説された。しかし、この「臨界期仮説」については、賛成派と反対派で意見が分かれている。今日のところ”後半“では、”前半の最後“に示された、年齢が外国語習得に影響することの説明・③「心理的態度の違いによる説明」と④「母語フィルター」の二つについて、具体的な実験結果より検討している。
心理的態度の違いの影響(ジセラ・ジアの研究)
中国語母語話者の研究
まず、学習開始年齢が外国語習得に影響することを「心理的態度の違い」から説明する研究について検討する。
ジセラ・ジアらの二〇〇三年の研究では、中国・台湾からアメリカに渡った一〇人の中国語母語話者の英語習得を三年間に渡って追跡調査した。彼らが英語と中国語のどちらの言語を好むかという質問に対して、
- 到着三カ月後・・・・すべの子どもが中国語と答えた
- 一ニカ月後・・・到着時「五歳-八歳」の子どもーーすべて英語と答えた
到着時「九歳」の子どもーー両方とも同じと答えた
到着時「一ニ歳-一六歳」ーー中国語と答えた
これをみると、年齢がすべて決めているように見えるが、実際には年齢によって行動パターンが違う。年少でアメリカに来た子どもは、英語を話す友達が多く、同年代のアメリカの子ども同じようなテレビを見ていた。しかし、一ニ歳以降にアメリカに来た子供は、中国人話者の友達が多く、中国のニュース、映画などを見ていた。したがって、どれだけアメリカ社会に適応して、英語を話す友達を作るかということと、どちらの言語を話すことを好むかが連動している。つまりこの研究では
- A)・・・・学習開始年齢 → 学習到達度
- B)・・・・学習開始年齢 → 学習環境 → 学習到達度
のどちらが、正しいのかはっきりとわからない。
人種による違い
ジセラ・ジアは、ニ〇〇二年の研究で、人種によって、臨界期の現れ方が異なるというデータを提示している。ここでは、ヨーロッパ系(主にロシア母語話者)とアジア系(北京語・広東語・韓国語母語話者)についてアメリカ到達後の年齢と英語能力の関係を比較した。すると「ヨーロッパ系学習者には統計的に優位な年齢的影響がなく、アジア系学習者にだけ有意な年齢の影響があった」のである。
中国系・韓国系人がアメリカに行くと、いろいろな意味でアメリカに適応せず、遊ぶ仲間もアメリカ人というよりはアジア系同士の場合が多い。そしてその傾向は、移住した年齢が高くなるほど強くなる。
しかし、ロシア人の場合は、アメリカ社会で主流の白人系アメリカ人と、見かけでは区別できずある程度の年齢がいってもお互いに親近感を感じてつき合いやすい。
つまり、年齢だけでなく人種によっても心理的態度が変わりそれが学習環境に影響を及ぼしている。
ジアらの研究の結果は、言語習得と年齢の関係に関して、いわゆる環境的要因のほうが重要で、脳による生得的な制約のような要素はさほど重要でない可能性があることを示していることになります。(抜粋)
外国語環境での年齢の影響(リン・フィリーの研究)
その言語が話されている環境での調査では、学習開始年齢が到達度を決めるのか、学習環境が決めるのかが複雑に絡み合いはっきりしない。ここで著者は、その言語が話されていない「外国語環境」で学習開始年齢の影響を調べた研究として、リン・フィリーの研究を紹介している。
リン・フィリーは、心理学専攻の大学生に英語の音の聞き取りテストを行い、その平均点と学習開始年齢を比較した。すると、中学以前に英語学習を始めた学生の方が有意な差をつけて、それ以降に始めた学生よりも優れていた。
しかし、このような習得の研究でも、その他の要素を「完全に」排除しているとは言い切れないと著者は注意している。そして今後、このような外国語環境での研究を積み重ねていく必要があるとコメントしている。
母語フィルターの影響
母語フィルターの研究
次に、大人になると外国語習得が難しくなることを「母語フィルター」から説明する研究について検討する。
乳幼児は、世界の言語に存在するすべての音を区別することが出来る。たとえば日本の赤ちゃんは、生後数ヶ月は、 l と r の音が区別できる。しかし、これは生後六ヵ月から一歳くらいの間に急速に低下する。これは母語である日本語において区別されていない音の区別を無視することを学習するからである。パトリシア・クールは「ヘッドーン実験」の手法でこのようなことを研究した。
クールの研究グループは、生後七カ月の時点の母語にある音の認識能力が、母語にない音の識別能力と負の相関がある、つまり反比例することをしめし、母語の学習することによって、外国語の区別ができなくなることを明らかにしました。(抜粋)
クールは二〇〇三年に、生後九カ月のアメリカ人の赤ちゃんに、一回二五分、四週間(計五時間)にわたって、中国語で絵本を読んだり、おもちゃで遊んだりする実験を行った。すると、中国語を聞いたグループは、この五時間のトレーニングで、台湾の赤ちゃんと同じレベルの識別能力を示した。第二言語の音声習得の臨界期には、いろいろな説があるが、この実験により少なくとも生後九ヶ月くらいならば逆転可能であることが明らかに示された。
母語の習得により、母語の処理能力があがるにつれて外国語の処理ができなくなるというデータは、第二言語習得の臨界期が、実は母語を習得することによっておこるのだ、という可能性を示唆しています。(抜粋)
英語子育て
赤ちゃんのころから子どもに英語を聞かせる「英語子育て」で、心配になるのが母語の習得に悪影響がないかである。
パトレシア・クールのヘッドターン実験で、 l と r の音の聞き分けの実験で中国語を聞いたグループと英語を聞いたグループで母語の習得に影響はなかった。つまりほとんど英語だけを聞いて育っている赤ちゃんが五時間ほど中国語を聞いたところで英語に影響があるとは考えにくい。
要するに、十分に母語を聞いて育つ環境にあれば、幼児外国語教育などで外国語を聞かせるぐらいで、悪影響が出るという心配はほとんど必要ないということです。(抜粋)
しかし、問題なのはインターナショナルスクールなどに子どもを送る場合である。うまくいけば二つの言語を使いこなせるようになるが、英語で教科を学ぶためついて行けずに落ちこぼれてしまうと、母語でも第二外国語でも複雑な言語使用が出来なくなってしまう危険性がある。
帰国子女とバイリンガル
幼児の外国語習得能力の高さは、多くの研究や、事例で明らかになっている。身近な例では、子ども時代を外国で育った「帰国子女」がある。彼らは英語と日本語を非常に流暢に話し、彼らの英語は非常に自然でネイティブの英語に近い。
しかし、重要なのは小さいうちに外国に行けば、すべての子どもがバイリンガルになれるわけでは無いということである。その外国語を十分に使う環境にいることが前提条件となる。そして、逆に母語を保持することもそう簡単ではなく、母語で読み書きができなかったり、話せなくなって聞いてわかるだけの「受容バイリンガル」になってしまうケースも多くある。
また、研究によるとバイリンガルには認知的なメリットもある。ひとつの言語しか話さないモノリンガルの子どもに比べて、複数の刺激に対して選択的に注意を向けることをコントロールする能力に優れていることがわかっている。これは二つの言語をコントロールすることを身につける過程で認知的負荷がかかるために、情報処理能力が高まると考えられている。
エレン・ビアリストックの実験では、この認知的優位性は、バイリンガルの子どもだけでなく老人でも優位性がみられることが示された。そして、認知症の発症も平均で四年遅れることも判明している。
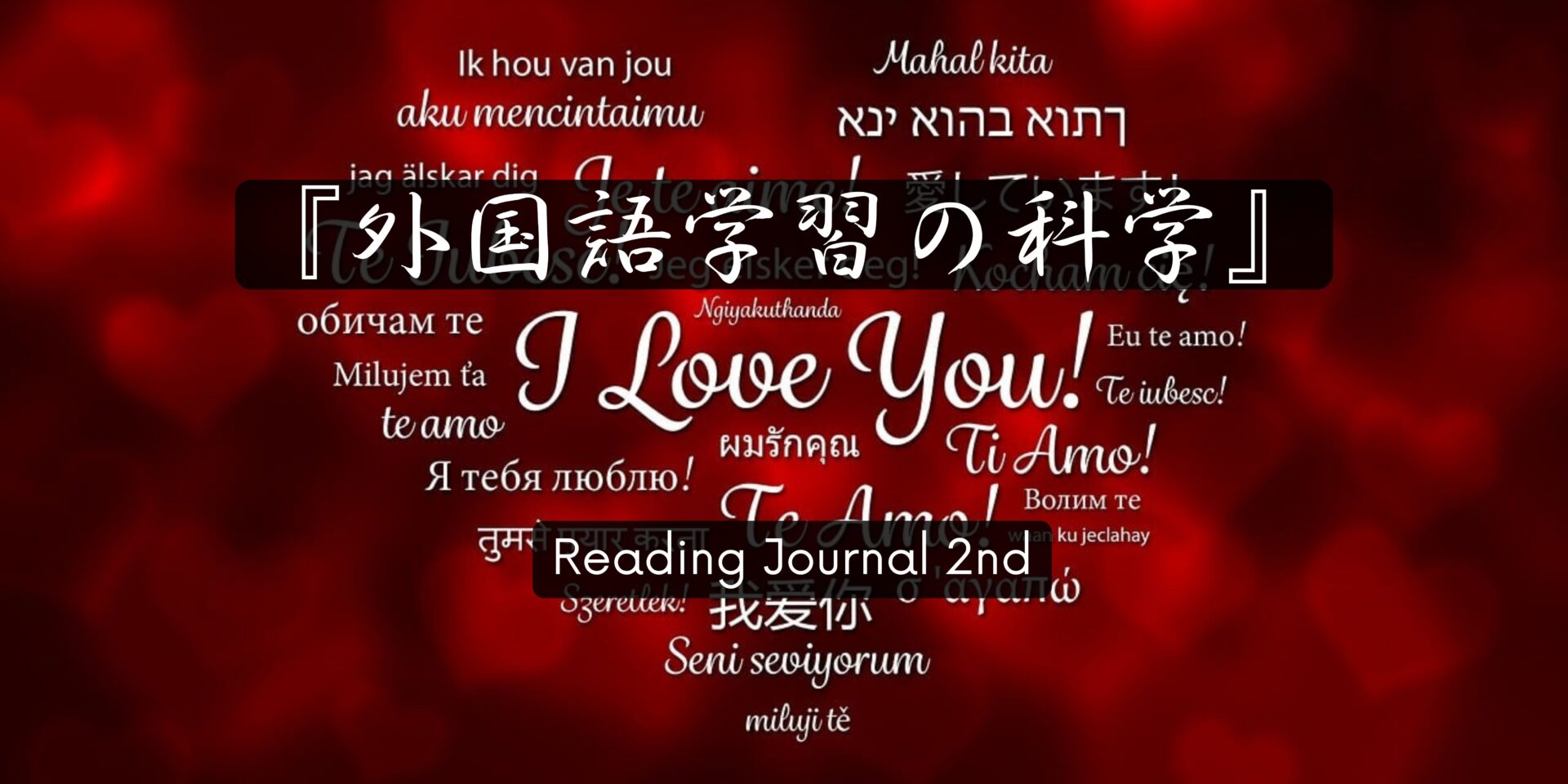


コメント