『プロカウンセラーの聞く技術』 東山紘久 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
31 沈黙と間の効用
沈黙と間の多用
プロカウンセラーの会話と一般の人の会話で違う点は、「沈黙と間の多用」である。普通の会話では、間が入ると落ち着かなくなり、沈黙はさらに重苦しくなってしまう。しかし、プロのカウンセラーのところに来る相談者は、みな深刻な悩みを抱えている。そのため、双方の会話には沈黙が重要になる。沈黙は来談者が自分の考えを、自分がわかり、自己に沈潜するために必要な時間である。
著者はここで来談者との会話の例を示している。この2ページの会話に実に20分の時間がかかっている。会話の中に長い沈黙や間が入っているが、この間も会話はと切れているのではなく、心の中で会話が続いている。
聞き手が、会話に間や沈黙を必要に応じて入れられるようになりますと、話し手の会話は、つづきます。沈黙のあとにこちらの意見をはさみますと、会話の主導権がこちらに移り、そのときに今度は話し手が間や沈黙を入れますと、こちらのほうがしゃべらなければならなくなります。主客が逆転するのです。 主客が逆転すると、場の雰囲気が変わります。この変化には、話し手と聞き手の沈黙に対する迫力の差が関係します。真剣な話し合いは、真剣勝負に似た迫力がありますが、ここには聞き手と話し手がもっている人格が関わって来るようです。(抜粋)
この沈黙と間の迫力を生むものは聞き手の度量である。話し手の内容が深刻であればあるほど、必要とされるものである。
あとがき
日常生活において、話すことより聞くことの方が大切であると言われているが、話す技術の本や教室は多数あるにもかかわらず、聞く技術の本も教室もほとんどない。それは、話すことは自己表現であるので自分中心で表現の仕方を組み立てられるが、聞くことは、相手中心であるのでそれが出来ないからである。また、話す方は、話し方などの技術的なことが役立ち、また練習もできる。
しかし、聞く方はスピーチのような練習ができません。いつでもぶっつけ本番です。相手の状況や表現方法、場面や雰囲気などによって同じことはありません。(抜粋)
そして、聞く技術に関しては、それは重要であるが、日常・非日常を問わず、普通に単に聞くだけでよければ、どのように聞いてもあまり相手に影響をあたえない。
だから、このような日常的な聞き方に慣れていますと、聞くことが相手のとの関係を破壊してしまうような場合でも聞く技術の獲得が行われていないので、相手とのコミュニケーションに失敗してしまいます。しかし、聞く技術を習得していれば、多くの人との人間関係の危機が救えます。大切な人との人間関係が構築でき、信頼感を得ることができます。このようなことから、聞く技術をできるだけ簡単に習得できるような本を書きました。(抜粋)
最後の引用部を読むと、これは東畑開人の『聞く技術 聞いてもらう技術』とつながるところがあると思った。東畑も、単に「聞く」というのは普通にできている、がそれが非常時になると聞けなくなってしまうと言っていた。大切な人との人間関係を壊さないように、相手の本意でじっくり聞くことが大切なのだと思った。(つくジー)
関連図書:『聞く技術 聞いてもらう技術』東畑開人 著、筑摩書房(ちくま新書)、2022年
[完了] 全17回
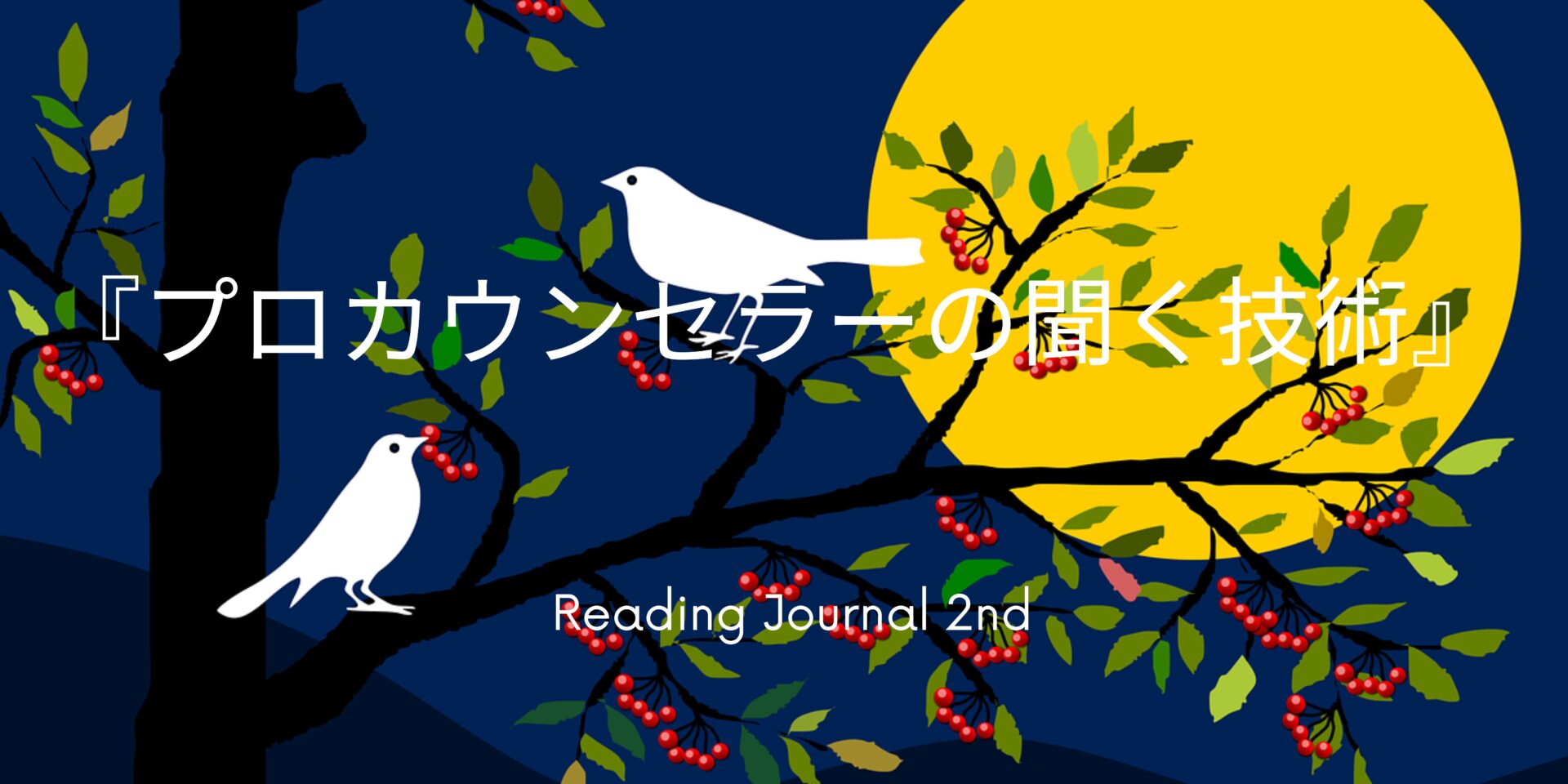


コメント