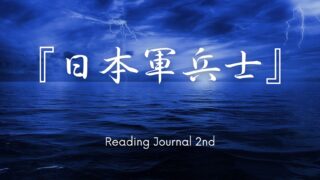 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd [読書日誌]『日本軍兵士』
吉田 裕 著
『日本軍兵士』は、アジア・太平洋戦争で膨大な犠牲を出した日本軍兵士について、戦後歴史学を問い直す、「兵士の目線」「兵士の立ち位置」から戦場をとらえ直す、「帝国陸海軍」の軍事的特徴との関連性を明らかにするという3つの問題意識から書かれている。:『日本軍兵士』より
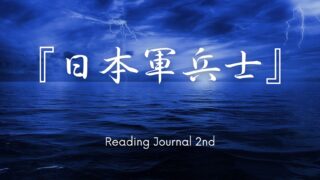 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 1st
Reading Journal 1st 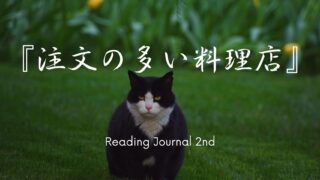 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 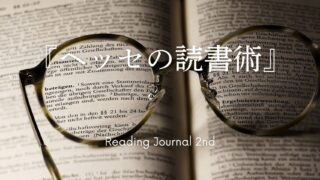 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 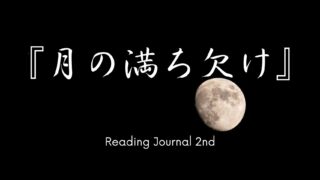 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd -320x180.jpg) Reading Journal 1st
Reading Journal 1st 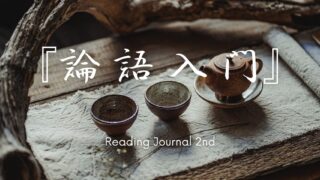 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 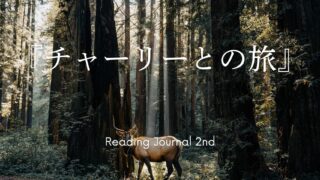 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 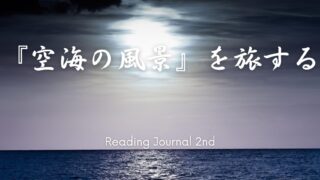 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd