 Reading Journal 1st
Reading Journal 1st [再掲載] 『星の王子とわたし』
内藤 濯 著
(初出:2007-02-02)の再掲載:『星の王子とわたし』内藤 濯 著
 Reading Journal 1st
Reading Journal 1st 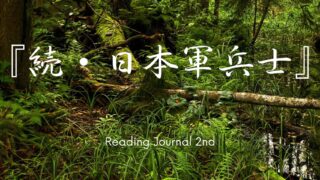 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 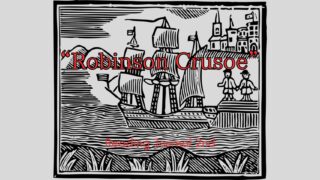 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 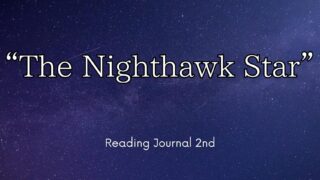 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 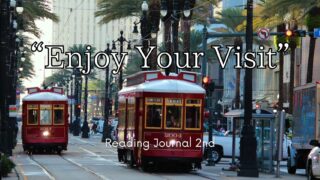 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 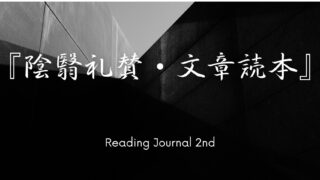 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 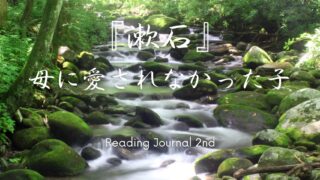 Reading Journal 1st
Reading Journal 1st 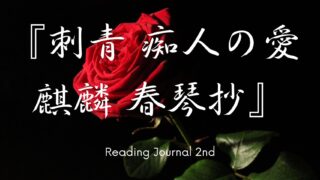 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 1st
Reading Journal 1st 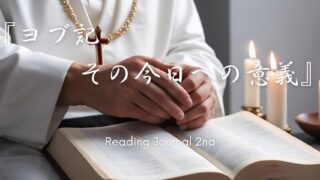 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd