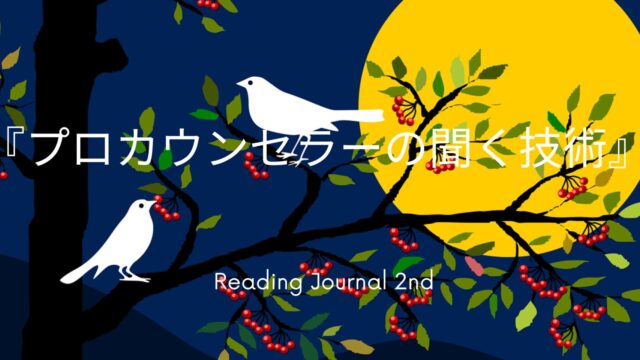 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 聞き上手は話さない / 真剣に聞けるのは、一時間以内
東山紘久 『プロカウンセラーの聞く技術』 より
聞き上手になるために重要なことは、「話さない」ことである。話を聞くことは相手の気持ちを理解しなければならず負担がかかる。そのため聞き上手になるには、訓練が必要である。聞くことは負担が大きいため1時間くらいが限度である。:『プロカウンセラーの聞く技術』より
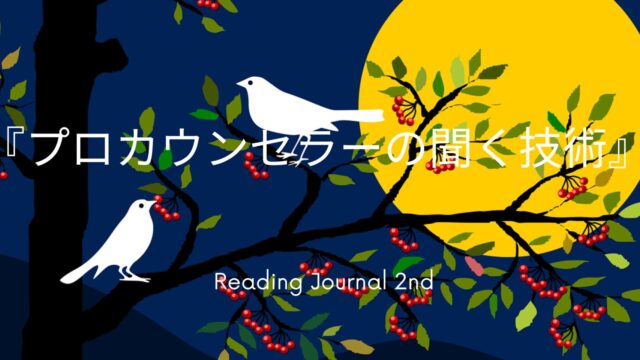 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 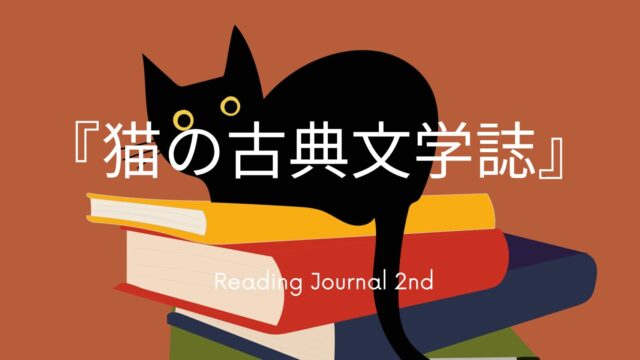 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 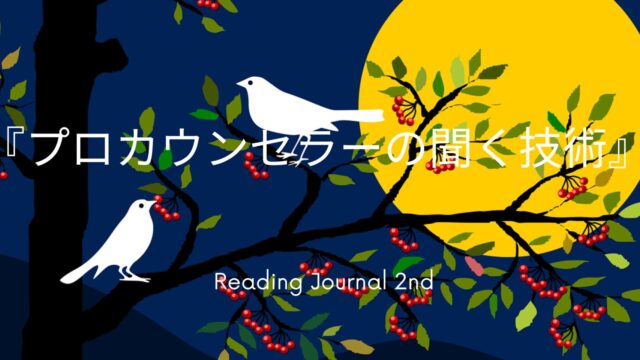 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 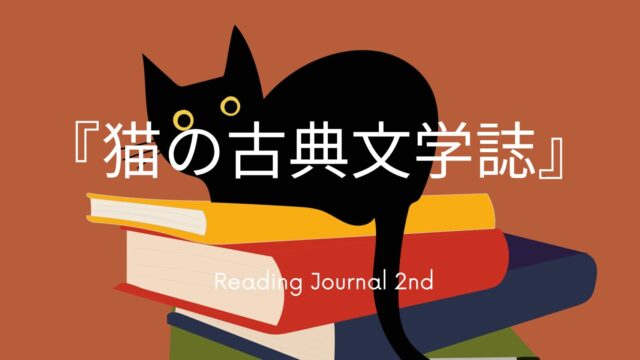 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 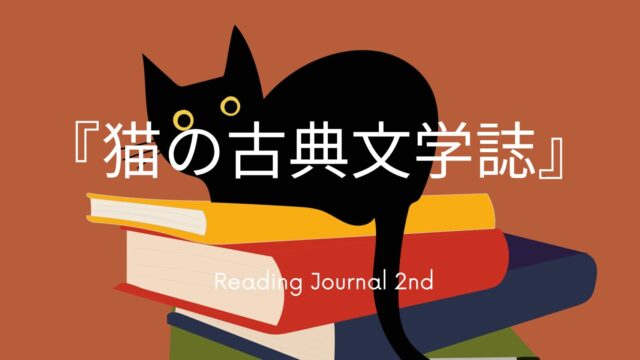 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd