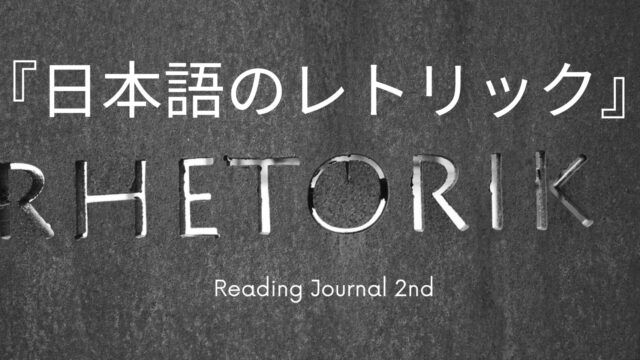 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd くびき法 / 換喩
瀨戸 賢一 『日本語のレトリック』 より
「くびき法」は、「服装の乱れは、心の乱れ」のように「同じ表現でその意味が異なる」というレトリックである。そして換喩(メトニミー)は、意味を横滑りさせ、空間的な結びつきや時間的な結びつきで表現するレトリックである。:『日本語のレトリック』より
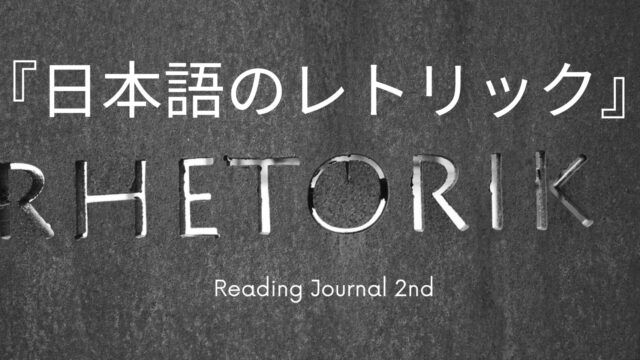 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 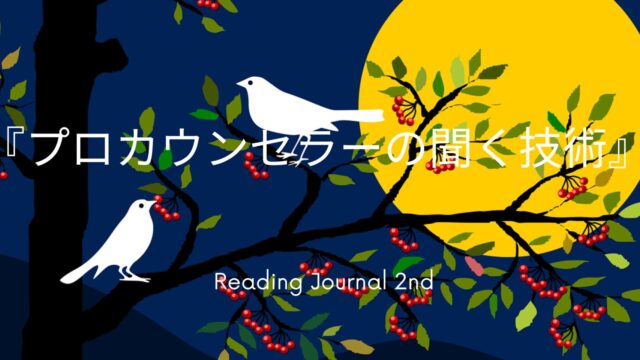 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 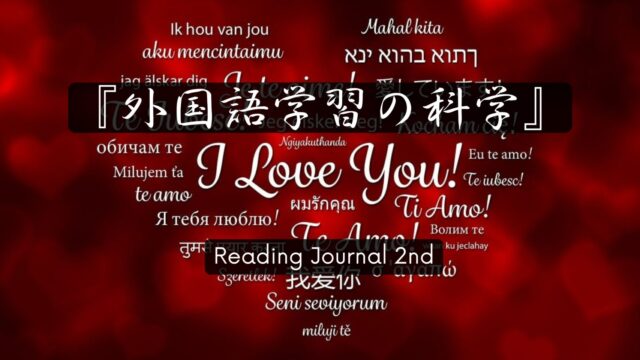 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 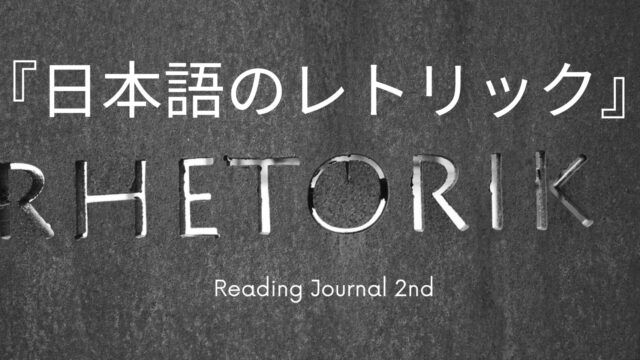 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 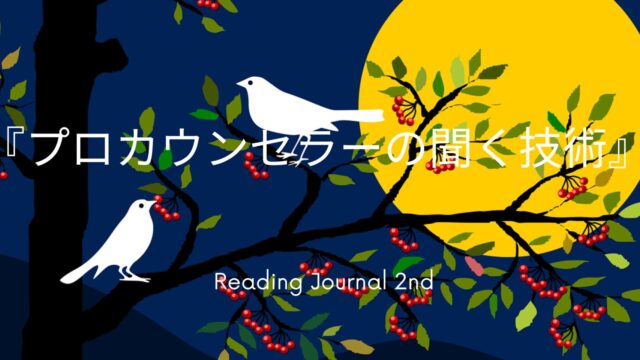 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 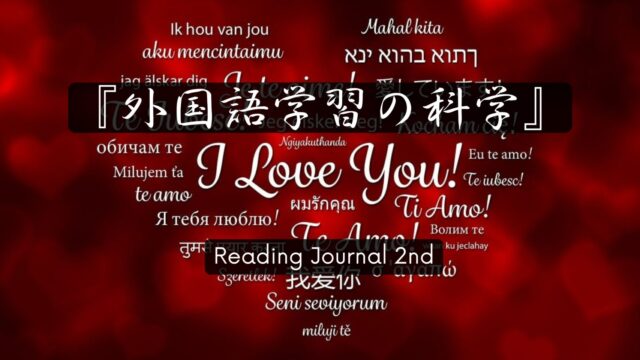 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 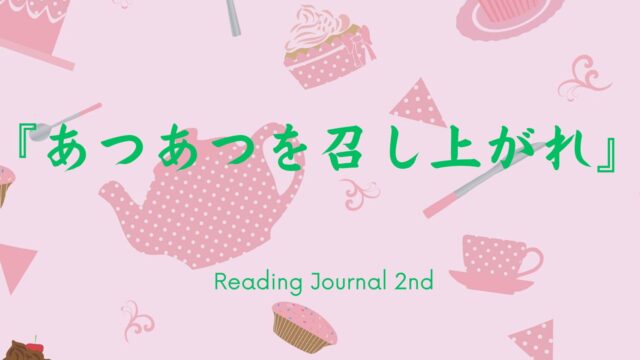 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 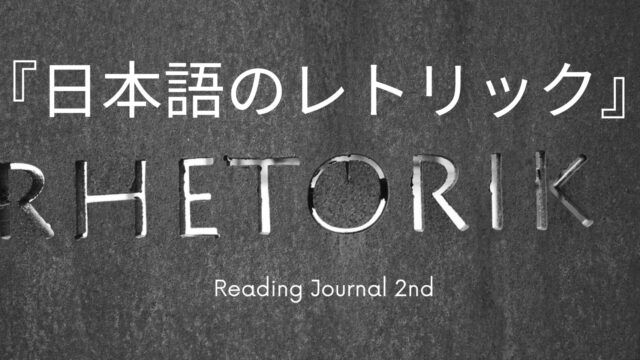 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 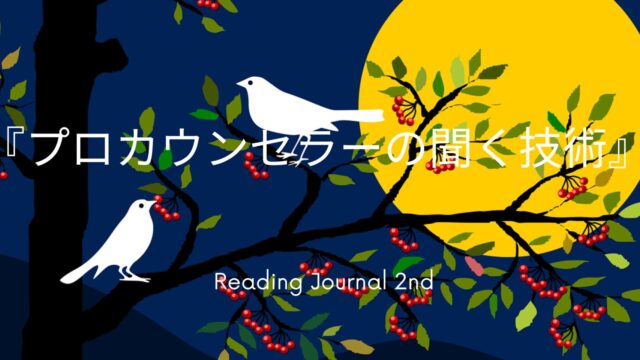 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 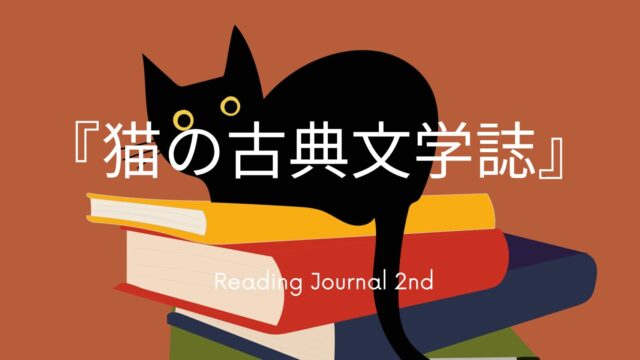 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd