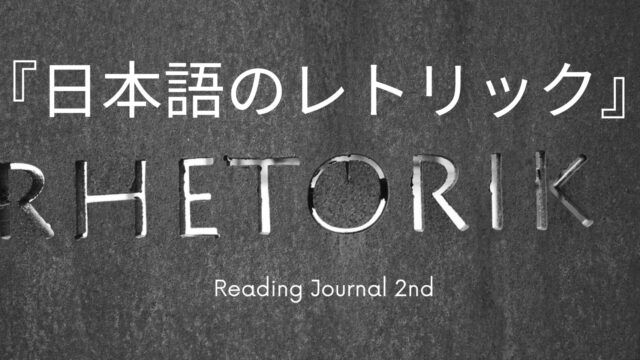 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 逆説法 / 諷喩
瀨戸 賢一 『日本語のレトリック』 より
逆説法・パラドクスは、一般に明らかに矛盾したり非常識と思われるなかに一条の光が差し込むときに生ずる。また、風喩(アレゴリー)は、意味の一貫した隠喩の連続である。ストーリーに展開した諷喩は、寓喩と呼ばれることがある。:『日本語のレトリック』より
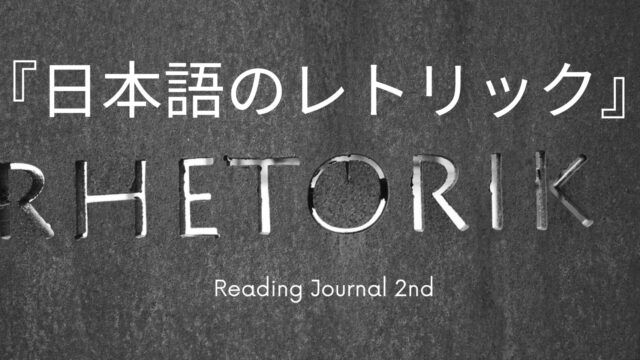 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 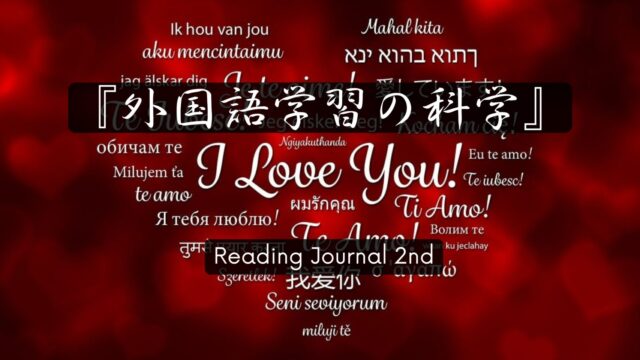 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 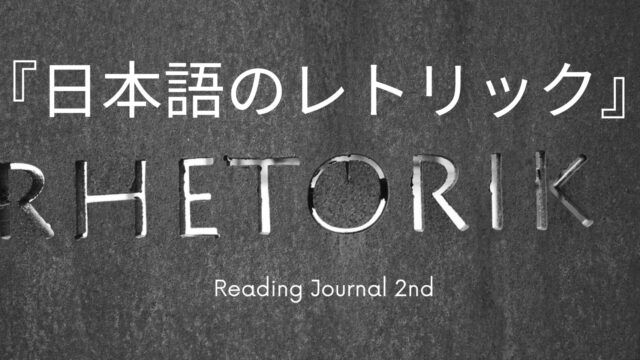 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 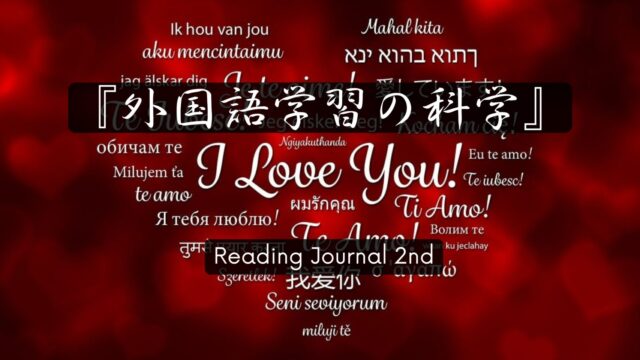 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 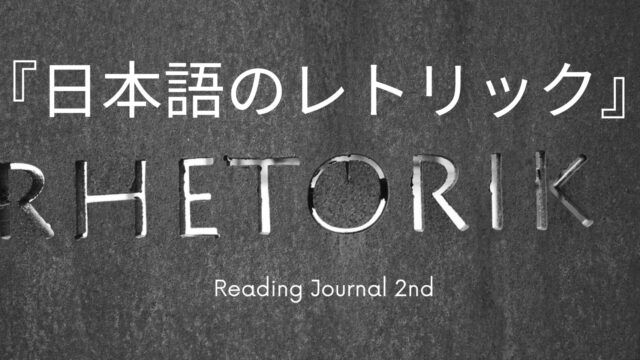 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 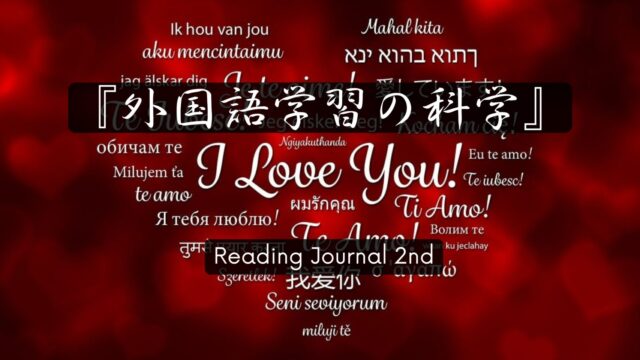 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 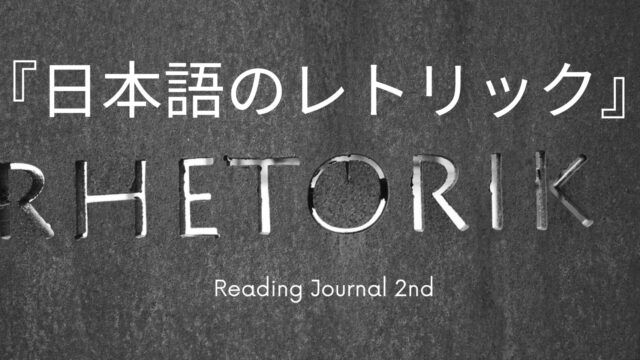 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd