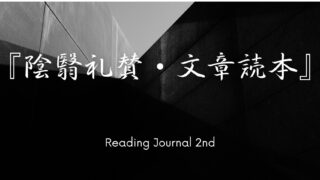 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 体裁について(その1)
谷崎 潤一郎 『陰翳礼讃・文章読本』より
芥川竜之介が「読者に一番親切なやり方は、全部に振り仮名を附けることだ」と言ったが、それは作者にとっても迷惑がない。漢字の読み方が一様でなく、さらに送り仮名はもっと混乱するからである。しかし総ルビは、活字面の美しさが犠牲となる。:『陰翳礼讃・文章読本』より
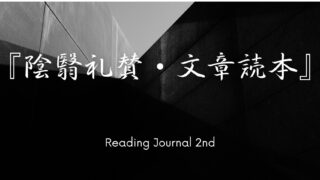 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 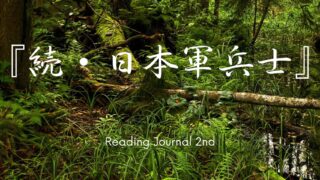 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 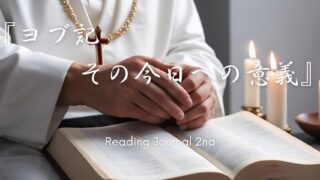 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 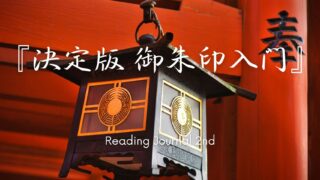 Reading Journal 1st
Reading Journal 1st  Reading Journal 1st
Reading Journal 1st 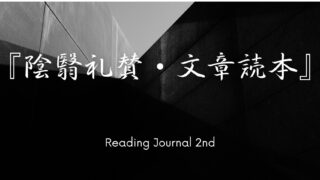 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 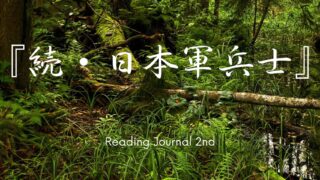 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 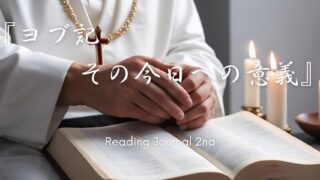 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 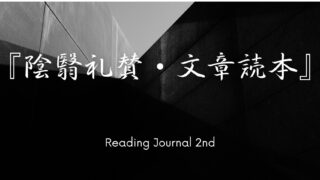 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 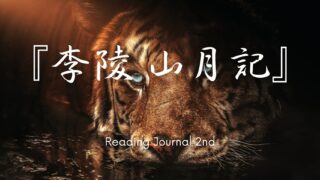 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd