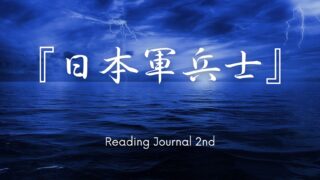 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 日本軍の根本的欠陥 — 無残な死、その歴史的背景(その2)
吉田 裕 『日本軍兵士』より
明治憲法には「統帥権の独立」や「国家諸機関の分立制」などの根本的な欠陥があった。そのため統一した国家戦略を決定できず、戦線拡大の歯止めや戦争終結のなど決断が遅れた。さらに軍政改革も挫折し、軍紀の弛緩と退廃を招いた。:『日本軍兵士』より
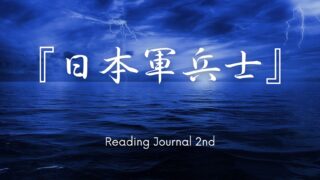 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 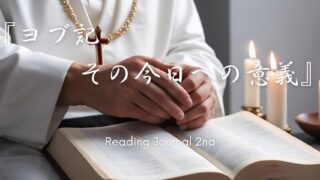 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 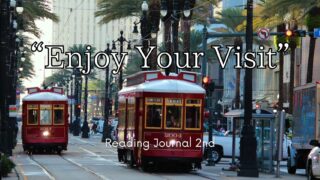 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 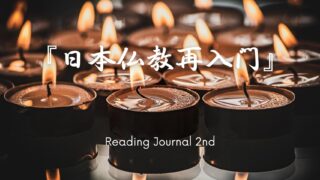 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 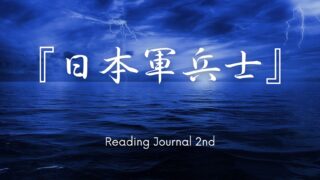 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 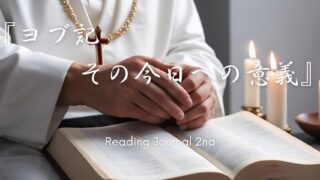 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 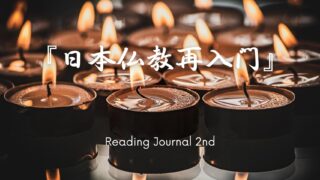 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 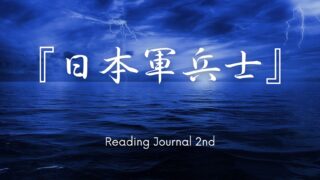 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd  Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 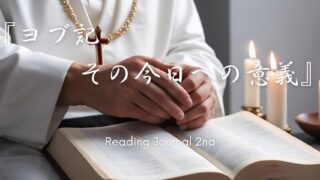 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd