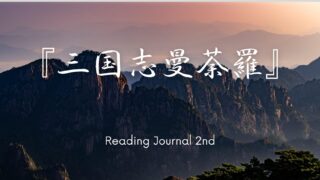 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 曹操の出自 — 曹操と清流派(その1)
井波 律子 『三国志曼荼羅』より
数々の「姦雄伝説」に包まれた曹操は、およそ姦雄とはかけ離れたパーソナリティーを持った人物であった。しかしその出自は、父が宦官の養子という決して自慢できないものであった。曹操はこのハンディキャップを乗り越え、英雄へと成長していく。:『三国志曼荼羅』より
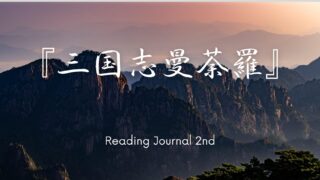 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 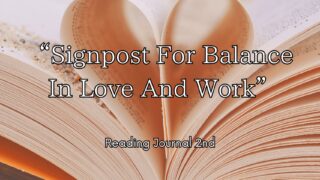 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 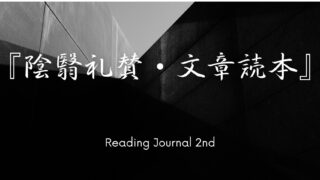 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 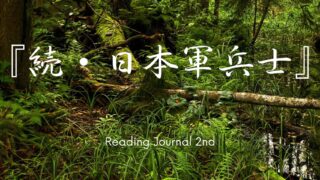 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 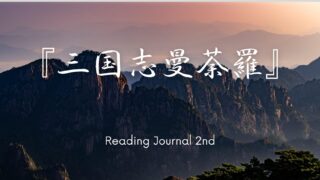 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 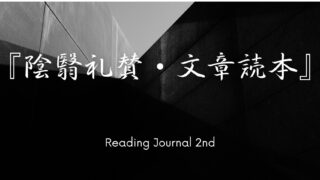 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 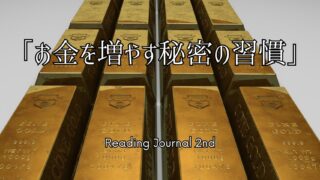 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 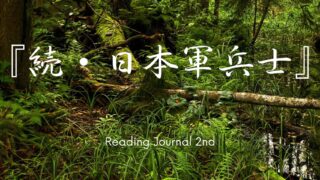 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 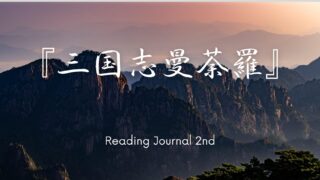 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd 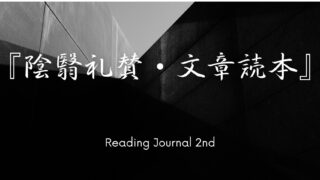 Reading Journal 2nd
Reading Journal 2nd