『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第二章 「呉越同舟」 — 乱世の生きざま 4 西方の大国・秦(後半)
今日のところは「第二章 呉越同舟」「4 西方の大国・秦」の”後半”である。ここで、やっと第二章、春秋戦国時代の混乱が終わり、秦による国家統一がなされる。今日のところでは、戦国四君の話に始まり、しだいに秦が他国を追い詰める過程、そして最後に始皇帝が誕生する。それでは読み始めよう。
「鶏鳴狗盗」戦国四君
戦国の乱世で従横家に次いで、戦国四君が登場した。この戦国四君は、斉の孟嘗君、趙の平原君、魏の信陵君、楚の春申君である。彼らのうち孟嘗君は君主の甥だが、その他の三人は公子である。そして彼らは故国あるいは他国の宰相となり君主以上の力を振るった。そして、彼らは単なる宰相ではなく、数千人の食客を抱えた任侠の大ボスでもあった。
ここで著者は、戦国四君のうち孟嘗君にスポットを当ててその逸話を紹介している。
秦の昭襄王が宰相にと孟嘗君を招いたとき、孟嘗君が斉の利益を優先するだろうと反対にあい、彼は投獄されてしまった。そこで、昭襄王の愛妾のもとに使者をやり、釈放に尽力してほしいと訴えた。すると高価な「狐白裘(狐の白い腋毛を集めて作った毛皮)」をくれたら尽力するとの返事があった。孟嘗君はこの狐白裘をすでに昭襄王に献上してしまったため、彼の食客の中にいた「狗盗(こそ泥)」に蔵から盗み出させ、これを愛妾に献上しその口添えで釈放された。そして、解放後、孟嘗君は秦からの脱出を図ったが、函谷関に差し掛かると、鶏が鳴かないと関所の門が開かないという難問に出くわす。追手が迫っている孟嘗君は、同行していた物まねのうまい食客に「鶏鳴」の真似を差した。すると他の鶏もつられて鳴きだしたため、首尾よく関所を通ることができた。
これが、有名な「鶏鳴狗盗」の故事である。
「怒髪上りて冠を衝く」藺相如と和氏の璧
昭襄王は、秦の版図を大々的に拡大していった。そしてその圧力をはねのけたのが趙の藺相如である。
昭襄王は、趙の恵文王が手に入れた「和氏の璧」という美玉が欲しくなり、恵文王に、璧と秦の十五の城を交換しようと持ち掛けた。これを受けて趙では会議が開かれたが、壁を渡したところで城は得られないだろうが、渡さないと秦の軍勢が攻めてくる恐れがあり、意見がまとまらなかった。そして、当時無名だった藺相如が知恵と度胸を買われて使者となり秦に向かうことになった。
藺相如は、無償で璧を巻き上げようとする昭襄王と、「怒髪上りて冠を衝く(激怒して髪の毛が逆立ち、冠を衝きあげる)」ほどの気迫をこめて渡りあい、みごとに璧を趙に持ち帰りました。(抜粋)
「完璧(璧を完うす)」の語は、この故事による。
この功績により藺相如は、趙の上卿となった。すると趙きっての名将廉頗は、自分より位が高いくなった藺相如に対して憤慨する。しかし、藺相如は「秦が今、趙に攻めてこないのは廉将軍と私がいるため」とへりくだった。それを知った廉頗は謝罪し、以後二人は「刎頸の交」を結び無二の親友となった。
「奇貨、居くべし」呂不韋の策略と秦王政(始皇帝)の誕生
秦の昭襄王は、趙に圧力を加えていたが、一方、孫の子楚を人質として趙に送り込んでいた。その子楚に目を付けたのが大商人の呂不韋である。呂不韋は、「奇貨、居くべし(この値打ち物はおさえておかねばならない)」とし子楚に接近し財力に物をいわせて巧みな政治工作をした。
子楚は実母が正夫人でなかったため、人質として趙に送り込まれていたが、昭襄王の太子・安国君の正夫人・華陽夫人には息子が無かった。呂不韋はこれに目をつけ、華陽夫人に高価な贈り物をして子楚を彼女の養子にすることに成功した。つまり、子楚は安国君の正式な皇太子となる。
そして昭襄王が死去すると、太子の安国君(孝文王)が即位するが、ほどなく死去して、趙から脱出し帰国していた子楚が即位し、荘襄王となった。
子楚は即位後わずか三年で死去し、紀元前二四七年に息子・政が十三歳で即位した。
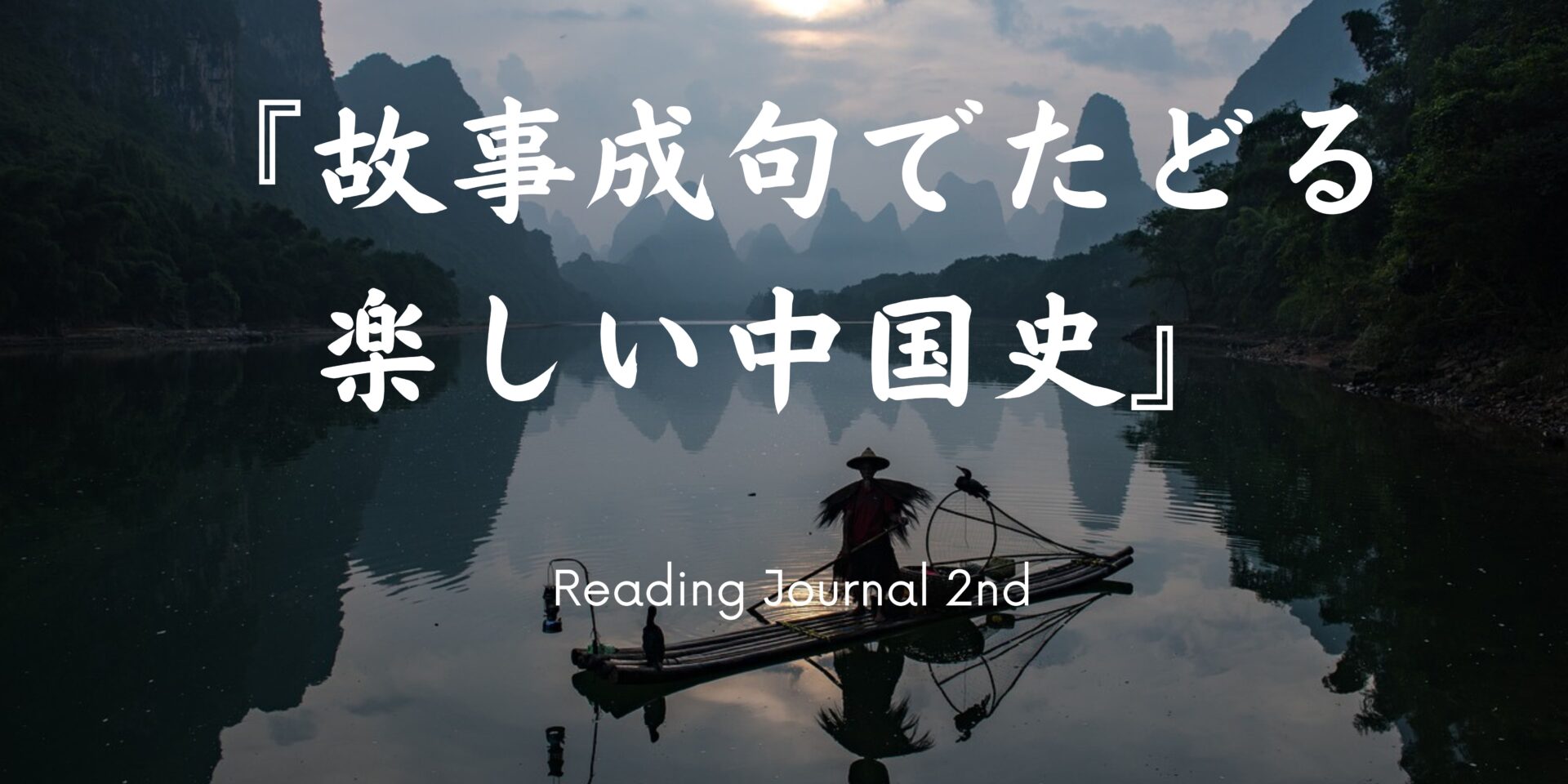

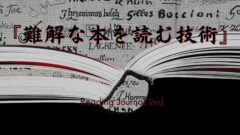
コメント