『難解な本を読む技術』 高田 明典 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第3章 本読みの方法(1) 一度目:通読(前半)
今日のところは「第3章 本読みの方法(1):通読」である。ここまで「第1章 基本的な考え方」(“前半”、“後半”)において、本の型の分類、読み方の態度の違いなどを学び、「第2章 準備」で選書の重要性とその方法についての解説があった。やっと今日のところから具体的な読書の方法である。ここではまず、頭の中に「その本の大まかな地図」を作ることを目的とした「通読」について解説される。
第3章は、”前半“と”後半“に分け、まず”前半“で、1回目の通読の意義と方法、読書ノートの作り方、”後半“で読書ノートを取りながらの通読の方法、その他の通読時の注意点などをまとめる。それでは読み始めよう。
1回目の通読「本のおおまかな地図を作る」
本を読む行為は1回で終わるものではない。特に難読書と呼ばれる本は、何度も何度も繰り返し読まなければ理解することができない。
しかし1回目と2回目以降で、同じ読み方をするのは効率的ではありません。(抜粋)
基本的な方法は、1回目は通読し、頭の中に「その本の大まかな地図」を作り、2回目以降に読みをしっかりしたものにする方法である。そして、この地図を作る具体的な方法として「読書ノート」に見出しを作っていくことが勧められる。
本を読む順番
読み始める前の前段階として、まずは目次を眺め、さらに翻訳書の場合には訳者の解説があるので、そこから読み進めることを勧めている。この解説は非常に良いガイドになっていることが多く、解説を読んで原著者の主張をあらかじめなぞっておくと、すんなりと本編に入って行ける。
通読の方法
通読には、大きく三つのパターンがある。
- 全体を通読:途中で少々わからないところがあっても、最後まで一気に読むという方法。比較的分量が少ない本の場合は、最後まで読むのが良い。
- 章ごとに通読:分量が多い本や「積上げ方式」の本の場合は、適当な理解のままで読み進めるのはかなり苦痛となる。その場合は、章ごとに通読し、折り返し同じ章を二度目読みする方法が良い。
- 数ページごとに通読する:これは数ページごとに「自分の理解の度合い」を判定し、理解不足の場合は、その部分の最初に戻って読み返す方法。
この三つのパターンは、通読する範囲をどのくらいに設定するかという問題である。通読は大まかな見取り図を描くことが目的なので、その範囲をどのくらいに設定するかという問題になる。それをどの範囲に設定するのがよいかは本のタイプにもよるが、
最初のうちは、できるだけ短い範囲(章ごとなど)で見取り図・地図を作る作業を行った方が得策です。(抜粋)
しかし、ここで重要なことは、全体の見取り図/地図は必ず必要であるということである。
ノートの外形を作る
本書では、読書ノートを取りながら読むことを勧めている。著者はここからこの読書ノートの作成方法を示すとしている。この作業は、知識のおおまかな枠組みを作る作業である。
- 読書ノートの作成
まず、1冊の本に対応する読書ノートを「1冊」作る。(ノートは、80ページのものが多いのでそれをもとに説明。分量の多い本などはページ数の多いノートを使うとよい) - 区分を考える
目次を見て、「どういう区分で区切るか」を考える。それぞれの章に何ページ割り当てるか考え、そのページごとに「第~章」と記入していく。章の構成を持たない本、章の分量の違いなどは適時調整。「タグシール」を使うと後で役立つ。 - 区分の量を意識
各章を区切ったノート分量でまとめることを意識する。 - 小見出しを記入
章の下部に小見出しがある場合はそれを読書ノートに記入。大体均等になるように注意。
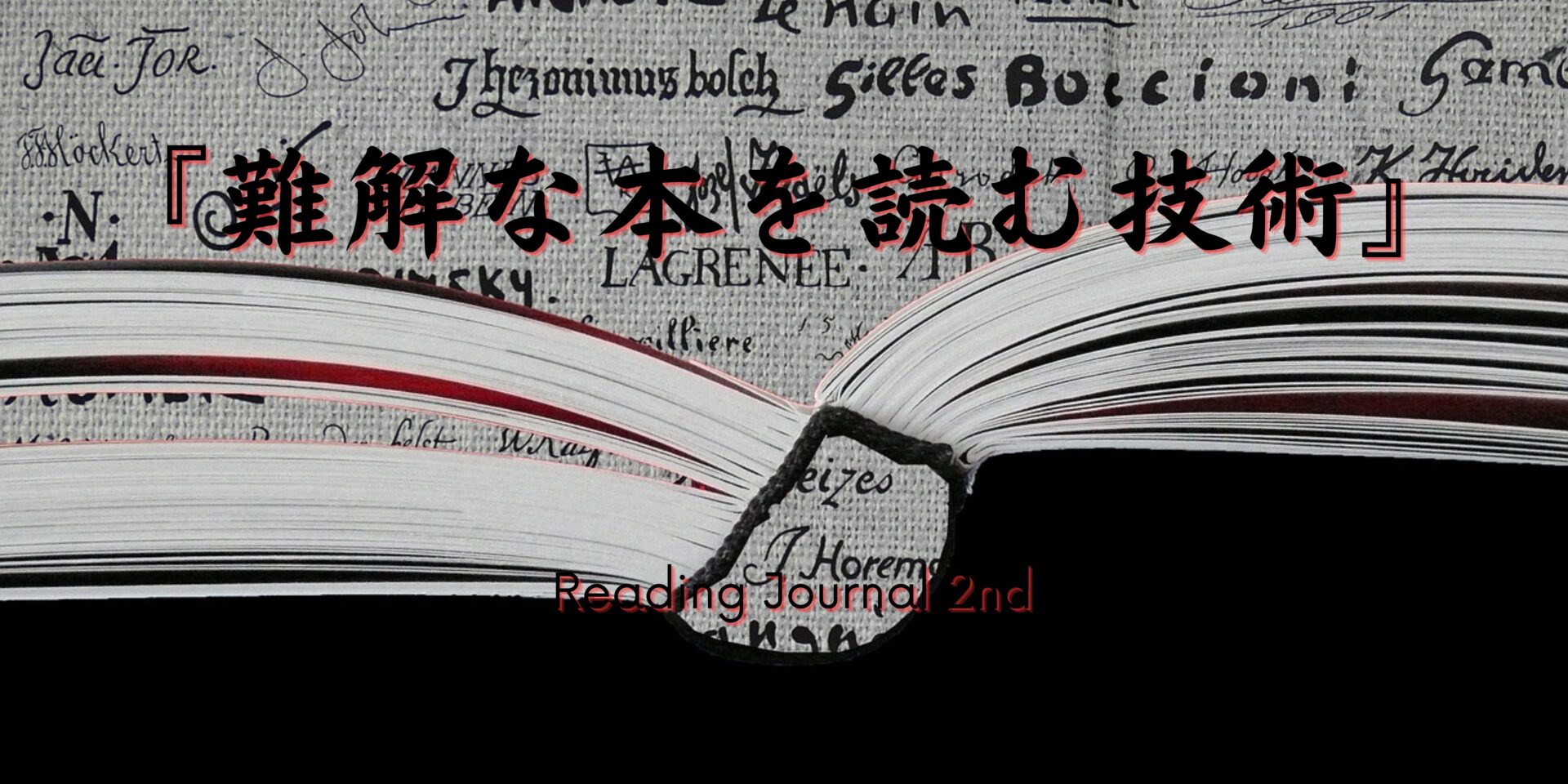


コメント