『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
⑥ 問いかけを活用する(後半)
今日のところは「⑥ 「問いかけ」を活用する」の“後半”である。ここでは、“前半”に続き、具体的な支援の事例を紹介している。ここでは、同僚への支援、退院時の退院コーディネーターの支援、さらに妻の介護という支援の事例を扱っている。それでは、読み始めよう。
事例4 コンサルティングが失敗した理由 — 別の人が行う支援へのアドバイス
事例4は、著者の同僚への支援の過程が詳細に記述されている。
著者の同僚から、コンサルティングが四つとも失敗した理由を探る手助けをしてほしいとの依頼があった。コンサルティングの内容は、企業の情報管理を経営者に助言する内容であった。
ここで著者は、純粋な問いかけから始めて、同僚が「医師と患者というモデルを用いてクライアントを操作している」との感触を得た。
私はこの時点で、質問のプロセスを省略して、自分の反応を伝えたいという誘惑に強く駆られた。ジムのアプローチのせいで、クライアントは防衛的な態度を示すかもしれないという私の仮説を示したくてたまらなかったのだ。(抜粋)
しかし、著者はその衝動を抑えて代わりに「どうしてこんなことになったと思いますか」と診断的な質問をする。ここで同僚は、あり得そうな答えを見つけ出そうとした。
ここで著者は、この「なぜ」という質問は強力な介入であることを指摘している。これによりクライアントはごく当然と思っていたことに注意が向けられ、それを新たな視点から調べる必要が出てくるからである。
著者は、この「なぜ」という質問や行動指向的な質問をして、同僚自身にクライアントの反応を診断的に考えさせることにした。
そして、同僚が最も苦痛を覚えたのが、重役会において同僚が指摘した問題について、CEOからまともに反撃をされたことであることがわかった。
ここで著者は、「なぜ、最初に自分の分析をCEOに伝えなかったのですか」と対決的な質問を行った。すると、同僚は実は事前に分析をCEOに伝えていたと事実を打ち明けた。
この時点で、私は自分の質問の形が単なる言葉上のものだったことを悟った。私はジムがCEOのところへ行くべきだったと本気で言ったが、彼が行かなかっただろうと推測していた。これは間違いだった。というのも、それをやったかどうかを尋ねるだけでよかったのに、私はジムが何もしなかったと決めつけてしまったからだ。(抜粋)
これは、無知について考えないという失敗であるとしている。しかし、この失敗により新たないくつかの課題が表面化し、次に取り組む課題が提起された。
このような過程をへて、二人は次第に対等な関係となり、お互いに客観的な分析が増えていく。
事例5 退院コーディネーターの思い込み — 役に立たない支援
事例5と事例6は、著者の妻が病院からの退院時の退院コーディネーターの支援とその後の著者による介護が取り上げられている。
著者の妻は簡単な外科手術の後の感染症が元で入院していた。家に帰るまで体力が回復した後もまだ抗生物質の静脈内投与が必要であった。
この時、病院の退院コーディネーターは「病院の予約不要な外来で毎日静脈注射を行う」ことを勧めた。著者には妻が病院の外来に行って他の患者からの感染を気にしながら待合室で待つことが難しいと感じられた。そして、著者は「訪問看護のシステム」について尋ねた。すると、コーディネーターの返事は、それはあるがとても高額であるという返事であり、彼女は費用の面とらわれ、それを選択肢にもしていなかった。
こうしてわれわれは見捨てられたような気になっただけでなく、大いに苛立ちを覚えた。この問題が妻の健康と安心感ではなく、費用という不適切な尺度で決められようとしていたからだ。
コーディネーターは見落としていたのは、さらに感染症を患って安心感を失うことのほうが、この時点では金銭より重大な問題だったということだった。(抜粋)
彼女の支援の失敗は、自分の思いこみで意思決定のプロセスが費用によって決めてしまい、訪問看護の選択肢などは知らせる必要がないと考えたことである。
事例6 妻の介護 — 継続的な関係に起こりがちな失敗
妻の退院後、著者による介護が始まった。この経験は支援関係というものを考える良い機会になった。
妻は、しばらくはベッドで一日中すごしていた。著者は二階の寝室にいる妻の求めで定期的に物を取ってくる必要があった。
この役割で最も困難だった点は、何かを階下からとってきてもらう必要が生じるたびに、自分が一番低い位置にいると妻に感じさせないためにはどうするか、だった。(抜粋)
このため著者は、妻が頼むのを待つのではなく、こちらから頻繁に何か取ってくることはないかと尋ねる事にした。
一般的にこう言っていいだろう。一段低い位置にクライアントが慢性的にいるのなら、支援者はイニシアティブをとって支援を申し出るべきであり、絶えず頼みごとを必要とするせいで、クライアントがあまり自尊心を失うことがないようにしなければならない、と。(抜粋)
しばらくして妻が自分でできることが増えると安堵の表情を浮かべるようになった。
望まれない支援
ここで、著者は妻の介護での失敗について語っている。それは、医師や訪問看護師と妻の話の間に口を挟んでしまったことである。妻が話さない病状について、それを代わりに伝えてしまった。そしてその行為を妻が起こっていることがわかった。
そのため著者は、医師のもとで情報を付け加えたりしないように、あらかじめ妻に「医師にどんなことを話すのかい」と尋ねる事にした。
私には重要だと思われる何かを妻が省こうとしたら、二人きりのときにその点を持ち出し、この情報を医師に伝えるべきかどうか、伝えるならばどのようにするかを話し合えばいい。(抜粋)
ここで著者は、このように過剰な支援の被害に遭った場合に、サインを送るのはクライアントであると指摘し注意をしている。支援者はもう支援が必要でないということを、示してもらう必要がある。このような時にクライアントが何も言わなかったり、怒って立ち去るだけでは、そうしたことは達成できない。
コントロールを諦めること
次に著者はクライアントが立ち直ってきた時に適切な専門家や医師の役割を諦めること難しさについて説明している。
妻がしだいに回復すると次第に家事に加わり始める。そのため著者が行ってきたやり方を変える必要が出てくる。やり方が変更されることに著者は戸惑ったが、妻にあまり頼りたくないという欲求があることに気づきそれに適応することにした。
著者は妻と意見が対立した時に支援をすることの難しさを感じた。そのような時は、控えめな質問をすることにより妻からもっと情報を引き出すように心掛けた。そして妻の行動の理由がわかれば、リラックスした状態でプロセス・コンサルテーションのモードに戻ることができる。
まとめ
最後にこの章のまとめとして次のようにいって章を閉じている。
この章では、どの支援関係においても、社会経済学や適切な役割を管理するための質問をするという役割を理解することがどれほど重要かについて、具体例をあげて示した。慢性的な支援が必要な例では、自問すること(破壊的な罠に落ちるのを避けるため)と、必要に応じて役割を変えることを学ぶのが特に重要である。(抜粋)
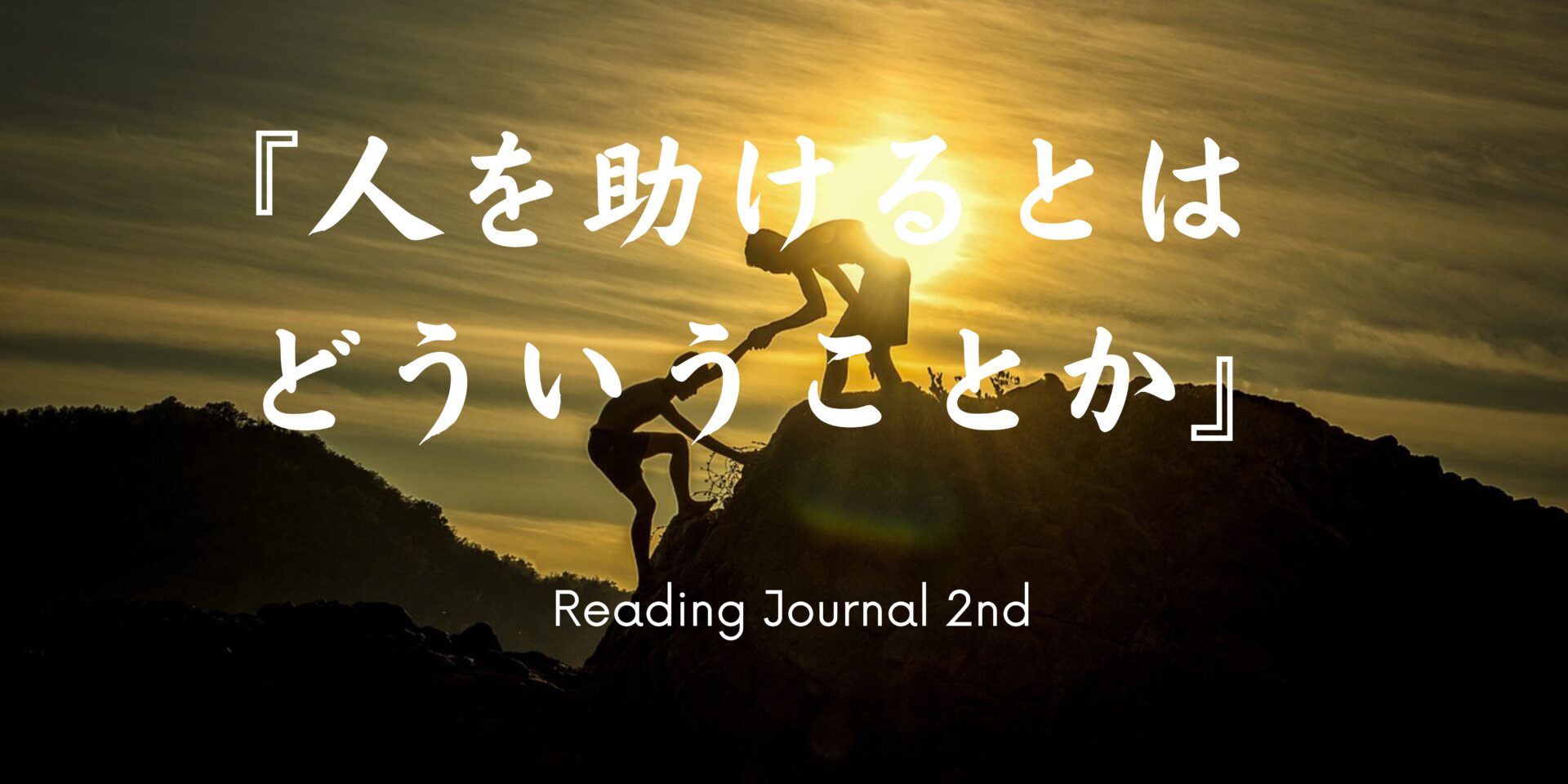
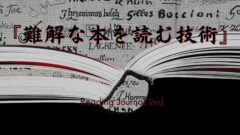

コメント