『引き揚げを語る』読売新聞生活部 編、岩波書店(岩波ブックレット)、2024年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
『引き揚げを語る』
本屋さんにて、岩波ブックレットの一冊『引き揚げを語る』を買ってみた。なぜ引き揚げかというと、加藤陽子の『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』の最終章に書いてあったことが気になっていたからである(ココ参照)。日本はアジアに対して多大な被害をもたらした加害者の立場であるはずなのに、その語られ方はむしろ受け身、被害者のように語られることが多い。その理由の一つとして、加藤は過酷だった満州からの引き揚げにあるとしている。
亡くなった方を除き、また、帰国のすべがなかった残留孤児や残留婦人などを除き、多くの国民は満州から引き揚げます。先の人口から換算すると、敗戦時の人口の8.7%の国民が引き上げ体験をしていることになる。
・・・中略・・・・
確かに満州からの引き上げ体験は過酷なものであったはずです。被害や労苦の側面から語られがちであるのは仕方ありません。(抜粋)
太平洋戦争については、その戦いの激しさや、沖縄戦、大空襲や原爆被害などテレビでも多く放送されるが、さて、引き揚げというとあまり見た印象もない。シベリア抑留よりも少ないのでないかと思う。ボクとしては、ほぼ全く知らないこともあり、ではまずは、この小冊子から読んでみようかと思った。
『引き揚げを語る』を読み終わった。資料も含めて70ページあまりのブックレットなので、それほど時間もかからなかった。
この本は、読売新聞のくらし面に掲載された「引き揚げを語る 戦後七八年」の記事をまとめてブックレットの形にしたものである。内容の中心は新聞記事に載った引き揚げ体験者へのインタビューであるが、さらにブックレット化あたり、日本近代史を専攻している加藤聖文さんと自身が引き揚げを経験した漫画家のちばてつやさんのインタビューが加えられている。
この加藤氏のインタビューに書かれていたこと、実際の戦争というものは実は引き揚げのような状況の中にある、ということには非常に感銘した。
加藤氏のインタビューから
まずは、引き揚げ者とその犠牲者であるが、民間の引き揚げ者の人数は約三一九万人、そして犠牲者の数はざっくりとした数値であるとしながら約三〇万人であるとしている。そして朝鮮半島南部、台湾、中国本土で亡くなった人は少なく、圧倒的に多いのは大戦末期にソ連軍が侵略した満州と朝鮮半島北部と樺太である。満州での犠牲者は二四万五〇〇〇人くらいで、この数字は広島の原爆犠牲者、約一四万人、沖縄戦の民間人犠牲者、約九万四〇〇〇人、東京大空襲の犠牲者、約一〇万人に対しても圧倒的に多い。しかしこの事実はあまり知られていない。
満州での犠牲者が多くなった原因は、ソ連の侵攻である。戦争に民間人が巻き込まれると、難民化し、食べる手段などを失い自力で生き延びる必要が生じる。そして生き残れない人が出てきて犠牲者がうなぎ上りに増える。
ここで加藤氏は、日本人の戦争観はむしろ特殊であること言っている。
一方、日本人の戦争観は特異で、一九四五年八月一五日に流れた昭和天皇の玉音放送で戦争がおわりましたといえば、空襲が止んだ --- 。それが戦争なんだという感覚を抱いています。しかし、それは本当にレアケースなのです。日本の本土では、平穏ななかで進駐軍がやってきて、占領が始まったのですが、これは非常に特殊な状況です。この感覚で戦争をイメージしてしまうと、満州での犠牲が異常に見えてしまいます。ですが、世界史的にみると満州で起こったことが戦争の現実なのです。(抜粋)
通常の戦争では、空から爆弾が降って来るだけでなく、地上では生身の人間が攻撃してくる。そして戦争が終わっても勝った側と負けた側の立場は大きく異なってしまう。そして、戦争により法による社会秩序や人間の倫理観が破壊されてしまいそれまでの常識が通じなくなる。そしてその過程で、殺人や暴行、略奪などのあらゆることが起こってしまう。このような状況では、弱いか強いかだけの世界になり、弱い者は誰にも助けられず、バタバタと死んでしまう。そして一番ダメージを受けるのは子どもや高齢者である。
引き揚げの体験談にソ連兵の暴行、略奪の話が多く出てくるが、それはソ連兵だからというわけではない。戦争というのは兵士の人間性を破壊するものであり、同様なことは日中戦争でもベトナム戦争でも起こっている。
戦争の目的がはっきりしている場合は、軍隊の士気も高く、モラルも維持されるが、戦争が長引き目的が曖昧になると、たががゆるんで凶暴性があらわれる。満州の引き上げ時のソ連軍は、独ソ戦で残酷な殺し合いしてモラルが破壊していた。そのような軍隊が極東に転戦してきたためより悲惨な状況になってしまった。
そして、加藤氏はこのような満州の状況と今、ウクライナで起きている出来事と同じであると強調している。
引き揚げ者のインタビューから
このブックレットでは、読売新聞に掲載された引き揚げ体験者へのインタビューが10話、漫画家のちばてつやさんのインタビューが載っている。
そのなかで印象的だった、田口充子さんのインタビューから、幼くして亡くなった妹と母の話を長文引用しておく。
初秋にさしかかり、朝鮮半島北部の郭山で冬を越すことに。四六年三月、末妹の澄子さんが栄養失調とはしかで息を引き取った。高熱で二、三日苦しんだが、医者もおらず薬もなかった。「『涙も出なかった。そればかりか、これでもう苦しませずにすむと安心した』と母は言っていた」
丘の中腹に凍土を何とか掘って埋葬した。ベビー服を何枚も着せ、真綿で足をくるんで土をかけた。翌日、母が見たのは、裸で横たわる遺体だった。何者かに掘りおこされ、身ぐるみをはがされていた。母は、「あのときは悔しくて涙がこぼれた」と生前、打ち明けた。四〇、五〇人いた集団も、郭山で半分に減っていた。
春も終わり、一行は南下を再開し、何とか三八度線を越えた。四六年七月仁川港から船に乗り、博多港に着いた。
生前、母は引き揚げについて周囲に語ろうとしなかった。特に、厳格だった父に気を使い、澄子さんの話は家族のなかで「ご法度」だった。母が持ち帰った澄子さんの爪と遺髪は、小さな木箱に入れられ、台所の食器棚の隅に置かれた。田口さんが「もっと暖かいところに移してあげようか」とたずねても、「ここがいいの」とかたくなだった。「誰もいないときに手を合わせて、語りかけていたのでしょう」。八〇年に父が死去した後、同じ墓にようやく澄子さんの名前を刻むことができた。(抜粋)
引き揚げ関連資料館:
平和祈念展示資料館:東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル33階
舞鶴引揚記念館:京都府舞鶴市字平1584番地 引揚記念公園内
浦頭引揚記念資料館:佐世保市針尾北町824番地(浦頭引揚記念平和公園内)
目次
まえがき……………小坂佳子
Ⅰ 引き揚げとは……………加藤聖文(駒沢大学教授、日本近現代史)
Ⅱ 引き揚げを語る
1 父の言葉を背に、兄と三八度線を越えた
2 収容施設で母と妹を亡くす
3 決死の逃避行、脳裏に悲痛な母
4 南樺太から帰郷、貧しかった戦後
5 集団自決、ソ連兵
6 妹と二人だけ、不安の帰国
7 「私世代で最後」
8 荒れ狂う大海原を密航船で
9 「父親に子どもを渡さずには死ねない」
10 母との約束「死んだら書き置いて」
引き揚げ体験を振り返る……………ちばてつや(漫画家)
Ⅲ 引き揚げを知る・学ぶ
施設紹介
ブックガイド
あとがき……………小野 仁
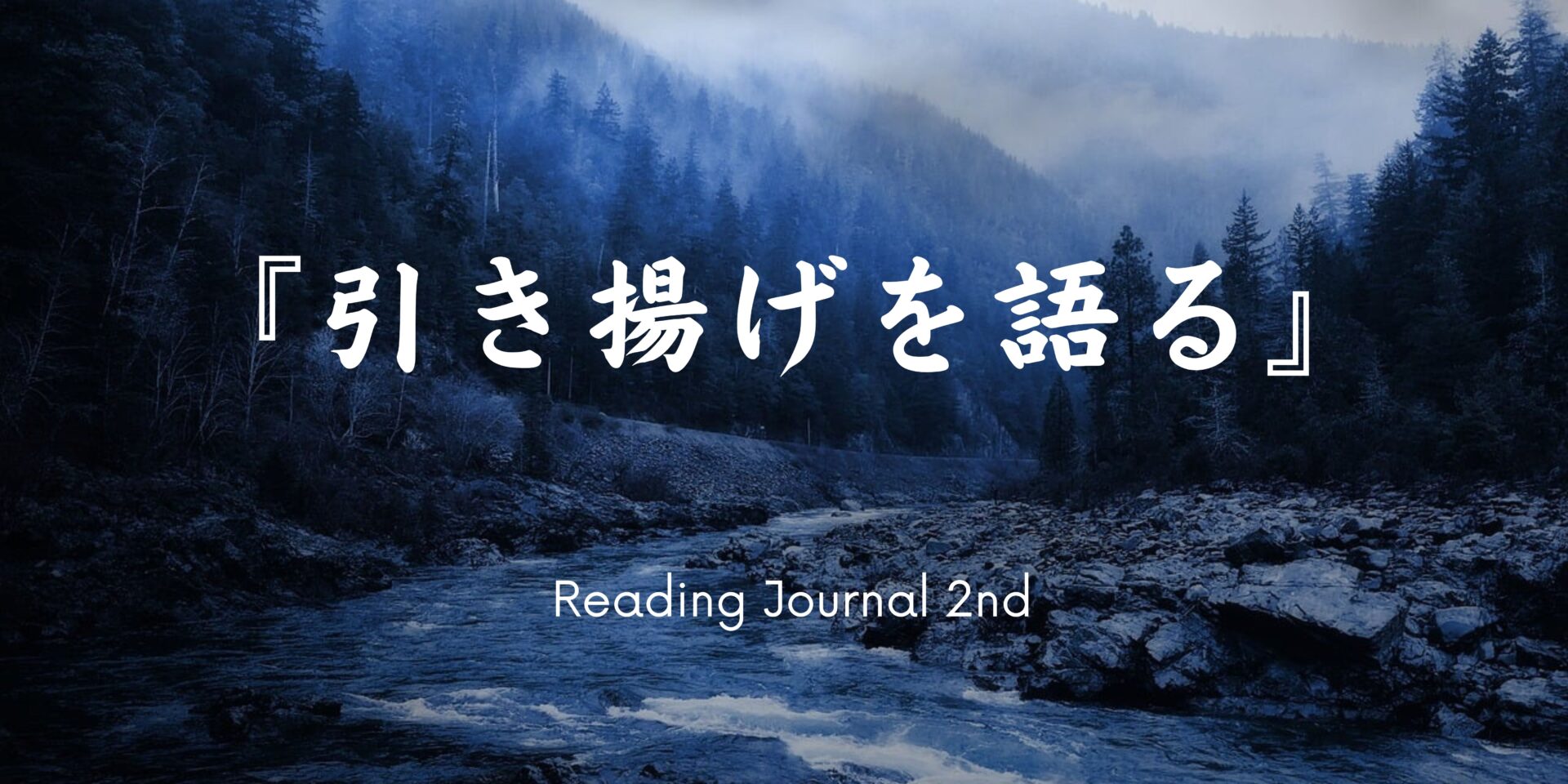


コメント