『故事成句でたどる楽しい中国史』 井波 律子 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第一章「覆水盆に返らず」 — 名君と暴君の時代 2 亡国の君主たち(前半)
今日のところは、「第1章 覆水盆に返らず」の“2 亡国の君主たち”である。前回の“1 五帝時代”では、五帝時代と夏王朝の始祖である禹まであった。今日のところは夏の滅亡と殷王朝さらに周王朝についてである。“2 亡国の君主たち”は、”前半”と”後半”の2回に分けてまとめることにする。それでは読み始めよう。
夏の滅亡と殷王朝
伝説の五帝時代と夏王朝は、現在のところ、その実在を立証する根拠が発見されていない。夏は『十八史略』によれば十七代、四百三十二年つづいた。
夏の最後の天子・桀は典型的な亡国の君主で末喜という美女に夢中になり贅沢三昧をしたため夏は衰え、殷王朝の初代君主湯王(成湯)により滅ぼされた。
この桀は、同じく殷の最後の天子紂とともに桀紂と呼ばれ暴君の代名詞となった。
夏を滅ぼした殷(商ともいう)は、その実在が確認されている最古の王朝である。五帝時代及び禹の時代は、天子の位は直系の血統によらず、次々と優秀な者に譲り渡す、禅譲が行われたが、この夏から殷への王朝交代は、殷が夏を武力で討伐する、放伐であった。
殷王朝は、亀の甲羅や獣骨を焼いて、そのヒビの割れ方から吉凶を占うような呪術的な祭政一致国家であった。
殷王朝の初代天子の湯王は、慈愛深い名君であった。その後、殷は約五百年にわたって命脈を保つが、第三十代の紂の登場により弱体化し滅亡する。
殷の滅亡と「麦秀の嘆」
殷の最後の天子紂は、愚かな者ではなく聡明で力も強かった。しかし、かれはその恵まれた素質を自らの欲望を満たすためにのみ使った。
そして紂のもとに、類い稀な美女、妲己が献上される。紂は妲己の言いなりになって贅沢三昧の暮らしをした。沙丘で池に酒をみたし、樹木に肉をひっかけ「酒池肉林」とし、宴会を催すなど享楽にふけり、莫大な散財をする。
このような経費は、厳しい租税の取り立てで補ったため、民衆に不満がつのり、諸侯が叛旗をひるがえす。そこれに対し紂は残酷な厳罰主義でのぞむ。叛旗をひるがえした諸侯には、「炮烙の刑」(油を塗った柱を横にして上からつるし、下から火をたいて熱くなったところを、受刑者に渡らせた。受刑者は、みな下に落ち焼け死んでしまう)に処した。
このように紂の歯止めが効かなくなると、心ある重臣は愛想をつかして次々と国外に脱出する。紂はただ一人とどまった叔父の比干も残酷な方法で殺してしまった。そしてその際限のない享楽と残酷の果てに、紂は周の武王に敗れてしまった。
紂の親類だった箕子も叔父の比干と同じく、紂を諫めたが聞き入れられず、それでも狂人のふりをして殷にとどまった。彼は殷の滅亡を確認してから、周の武王に降伏し、武王から朝鮮の領地を賜った。
箕子は、領地の朝鮮から周に参朝するさいに、殷の都の廃墟を通りかかった。宮殿はすでにあとかたもなく、ただ麦や禾や黍が伸び放題というありさまだった。箕子は、「麦秀の歌」を作り慨嘆した。
「麦の穂はぐんぐんのび、禾や黍も盛んに生い茂っている。あのずる賢い小僧(紂を指す)が私の諫めをきかなかったばかりに、こんなことになってしまった」(抜粋)
以後、亡国の悲哀を「麦秀の嘆」という。
もう一つ殷の亡国に関する記事成句として「殷鑒遠からず、夏后の世に在り(殷が手本とすべきは、すぐ前の王朝夏の滅亡だ)」がある。この故事より、「殷鑒遠からず」という言葉は、自分の戒めとすべき手本はすぐ近くにあるという意味で用いられる。
太公望と「覆水盆に返らず」
ここで時代を少しさかのぼる、やがて殷王朝にとってかわる周の始祖、后稷の話になる。后稷は、堯・舜・禹の三代に仕えて、大いに功績をあげる。そして現在の陝西省の西部に領地をあたえられた。そこが周の発祥の地となる。
周はそれ以降勢力を強めるが古公亶父の代に、北方異民族の脅威を避けて西南に大移動し岐山のふもとに定住する。このは、古公亶父には、太伯、虞仲、季歴がいたが、三男の季歴の息子、昌が生れた時に瑞祥(聖人が誕生するさいのめでたい現象)があった。このことを、古公亶父は大変喜んだ。そして、兄の太伯、虞仲は、古公亶父が季歴、昌を後継者にするのだと察して、周の地をさった。二人は行きついた南の地の風習にしたがい「文身断髪(入れ墨をして髪を切ること)」をて、周との縁を切る姿勢を明らかにした。
この昌が西伯(西方諸侯のリーダー)、後の周の文王となる。
この西伯には、またとない補佐役の呂尚がいた。この呂尚は、渭水のほとりで釣りをしていたとき、西伯とであい重用されるにいたる。西伯は、呂尚と出会った時「わが大公は(祖父または父を指す)はあなたのような人をずっと待ち望んでおられた」と言ったため、以後呂尚は太公望(大公が望んだ人)と呼ばれた。そして、釣り好きの人を大公望と呼ぶのは、この故事による。
この太公望呂尚は、西伯に取り立てられるまでは、働きもせず読書に耽っていたため大変貧乏だった。そして愛想をつかした妻の馬氏の申し出で離婚する。しかし、太公望が出世したため、復縁を求めてきた。その時、太公望は盆に水を入れ、これを地面にぶちまけると、馬氏にすくい取るように言った。そして「いったん離別した夫婦は、覆水収めがたし(ぶちまけられた水はもうもとにもどせない)、もういっしょになれないのだよ」と言った。この故事がもとになり「覆水盆に返らず」という表現が生れた。
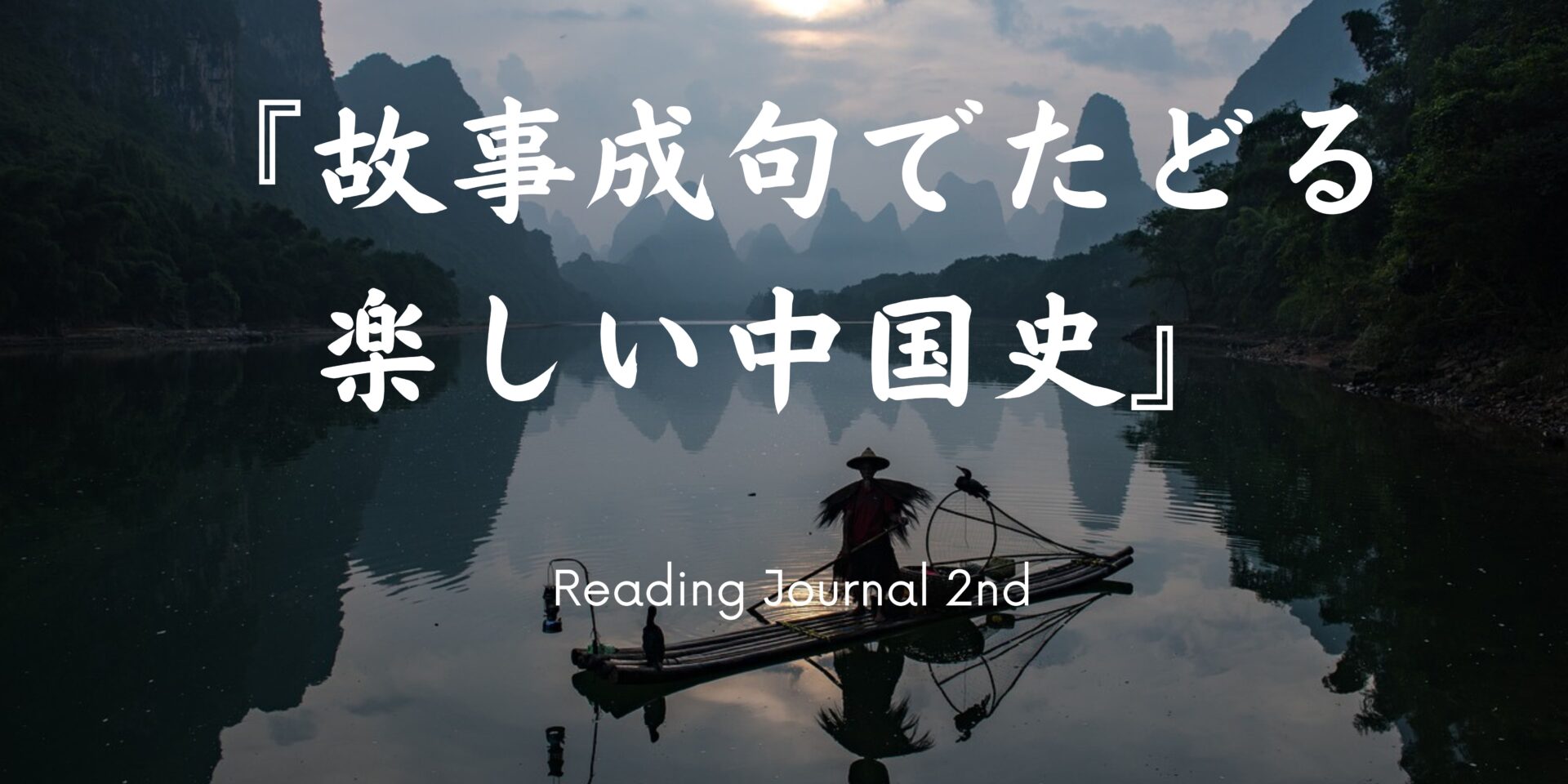

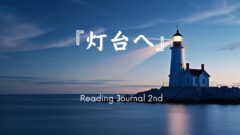
コメント