『人を助けるとはどういうことか』 エドガー・H・シャイン 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
③ 成功する支援関係とは?(その1)
今日から「③ 成功する支援とは?」に入る。「② 経済と演劇」(”前半”、”後半”)では、人間関係を「社会経済的ルール」と、人々が自らの役割を演ずる「演劇」として捉えた。本章「③ 成功する支援とは?」では、支援の状況における基本的なダイナミズムと支援関係を築く上での落とし穴に焦点を当てる。②は、三回にわけ、まず”その1“で、支援状況の基本的ダイナミズムを”その2“支援関係を築く上での「クライアントが陥りやすい五つの罠」を、そして”その3“で、今度は「支援者が陥りやすい六つの罠」についてまとめることにする。それでは読み始めよう。
支援の状況のダイナミズム
信頼関係がある人間関係や日々の非公式な支援など、スムーズに行われている支援は、ほとんど気づかれないこともなく提供される。しかし、関係に問題が発生したり、予想外の出来事が発生したりした場合などは、支援者とクライアントの役割が顕著になり社会経済学が作用しはじめる。
うまく支援が行かない場合、その根底にあるダイナミックスに気づかないことが多い。このようなダイナミズムは、人生が混乱した状況において最も多くみられる。人生が混乱した場合に、公式、準公式の支援を受ける必要がある場面に直面するかもしれない。
以下ではまず、公式・準公式の状況における経済性や役割について考え、その後、日常の非公式な支援にそれがどのように応用できるかを見てみよう(抜粋)
支援を求める立場 = ワンダウン
支援する状況とは本質てきに不釣り合いで、役割が曖昧である。(抜粋)
まず支援を求める人は「一段低い位置」に身をおくことになる。この支援を必要とすること、つまり依存することを人は、認めたくないと思い、屈辱と感じてしまう。
成長することが自立を意味する文化においては、自分に主導権があると感じたい気持ちがつよく、自立した人とは支援が必要のない人を意味する。そのため、支援を求めた場だけでなく全ての状況において、ワン・ダウンの存在と思われることを避ける。
この感情は精神科医の診察でも現れる。支援を求めるクライアントは一段低い状況になり支援者に対しての立場は不安定になる。心理療法では治療に関する二人が対等でないことが明らかであるため、セラピストはこの不平等を乗り越えるか、患者が対等であるかのように振る舞って隠すしかない。
支援を求められる立場 = ワン・アップ
支援者の役割を演じると、たちまち地位と権力を得る(抜粋)
面目保持という観点から分析すると、支援を求める人は、支援者になりそうな人に権力や価値を与えている。そして権力を与えるため、人間関係で不公平が生じる。権力を与えた後、クライアントは受動的で依存型の観客の役割になり、支援者となりそうな人に役者の役割を与えてしまう。
こうした微妙な真理の綾を理解しておくことは重要だ。というのも、これによって支援者になりそうな人には、状況を有利にできる可能性が生じるからである(抜粋)
事情を複雑にする別の要因として、支援を求められた場合は、必ず反応しなければならないということがある。支援を求める人にドアを開けられたからには、ただ立ち去るわけにはいかない。
クライアントは、支援を求めると弱い存在になるため、バランスを取り戻す必要ができる。そのため支援者の候補は、その要求に真剣な注意を向け、価値があることを示さなければならない。そのような注意を向けることでクライアントの面目も保つことができる。しかし、頼みを無視したり、関わることを拒否したりすると、クライアントは一段低い位置にいるという思いを強め、怒らずにはいられない。
要するに、そもそもどんな支援関係も対等な状態ではない。クライアントは一段低い位置にいるため、力が弱く、支援者は一段高い位置にいるため、強力である。支援のプロセスで物事がうまくいかなくなる原因の大半は、当初から存在するこの不均衡を認めず、対処しないせいだ。(抜粋)
支援者もクライアントも、最初は何を期待していいのか、何を与えるべきなのかわからない。クライアントと支援者の力の不均衡と相手の期待していることの曖昧さのため、両者に不安感と緊張感が生まれる。これには対処しなければならない。
このような不安があることを認識されないと、当事者のどちらも、機能不全や受け身の行動になり、緊張があると支援は難しくなる。そして感情的な反応は、支援者もクライアントも陥りがちな罠となる。
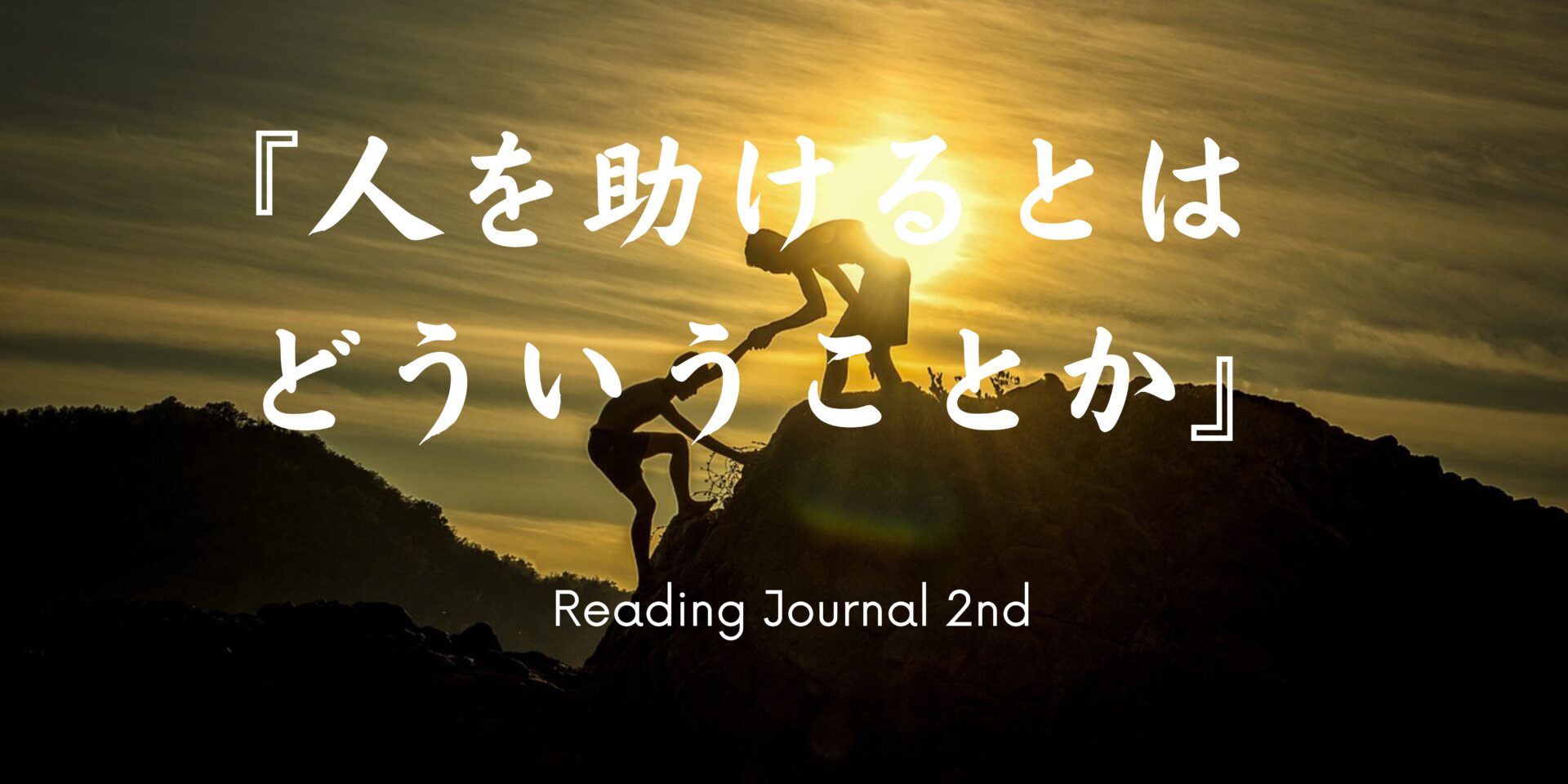


コメント