『あなたを変える行動経済学』 大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第7章 仕事や勉強の中の行動経済学
いよいよ、最終章「第7章 仕事や勉強の中の行動経済学」に入る。”はじめに“にあったように、本書はもともと、著者が大手受験予備校の早稲田塾で行ったオンライン連続講義が元となっている。つまり聴衆は、受験生!いよいよ聴衆が一番聞きたいと思っている「勉強」をどのように行動経済学的に改善するかという話題に入るわけである。
ここでは、勉強や仕事を効率的にこなすことに参考になるピア効果と「シーシュポスの岩」の実験の実験や、行動計画を立てることの重要性について説明されている。それでは読み始めよう。
ピア効果
私たちは、物事を評価するときに絶対的基準で評価するのではなく、何かの「参照点」を基準としている。その例として「損失回避」がある。
私たちは、この「参照点」を友人や同僚などの周囲の人に置くことも多く、多くの人の意見に従ってしまう「同調行動」などがある。
「ピア効果」とは、グループ内のメンバーの行動や性格(「参照点」)が、他の人の行動に影響が与えることを言う。このピア効果には「正のピア効果」と「負のピア効果」がある。
- 「正のピア効果」:周りの人が優秀なとき、自分も努力する。周りの人がサボっていると自分もサボる。(正のピア効果も良いことばかりではない)
- 「負のピア効果」:周りの人が優秀なとき、自分は諦めて努力しなくなる。
また、「順位効果」(「井の中の蛙効果」)と言って、同じ実力でもグループの中で上位となると意欲が高まる、というものもある。
この後、ピア効果の実験例として「スーパーのレジ打ちの実験」と「水泳選手による実験」が紹介されている。(この実験は、前に読んだ『行動経済学の使い方』のピア効果の項に詳しく書いてあるので、そちらを参照ください。ココ。)
「シーシュポスの岩」の実験
次に仕事や学習の意欲に関する行動経済学的な実験の話である。ここも『行動経済学の使い方』に詳しく書かれているので、詳細はそちらを見てもらうとして、著者は、この実験のポイントは、
- 仕事そのものに意味があると実感できるようにすることが大切
- 仕事をした成果が目に見えるようにすること
と説明している。
行動計画を立てることの重要性
最後に、職探しに関する実験の結果が示される。
ざっくり言うと、職を探している人を、具体的計画をたてたグループと立てなかったグループに分けて実験すると、具体的な計画をたてたグループの方が、効率的に職探しをしたということである。
ここでこの実験結果を行動経済学的に分析している。行動計画の効果として、「行動計画がコミットメントになって現在バイアスを防ぐ効果があった」という仮説が考えられるが、研究の結果、その効果はなかった。つまり現在バイアスによる先延ばしが原因ではなかったことがわかった。そして、計画をたてたけれど忘れてしまう可能性があるのでリマインダ・メールを送るグループを作ったが、それも関係なかった。
では、何が関係していたのでしょうか。それは、行動計画の作成です。就職活動をこれだけしますという計画だけでなく、複雑な課題を特定の行動に分解することで、焦点を当てるべき目標とそれを達成するために必要なステップを現実的に理解することができるようになったことです。逆に言えば、就職活動が達成できなかったボトルネックは、具体的にどのように行動すべきかということが曖昧だったからです。(抜粋)
[完了] 全10回
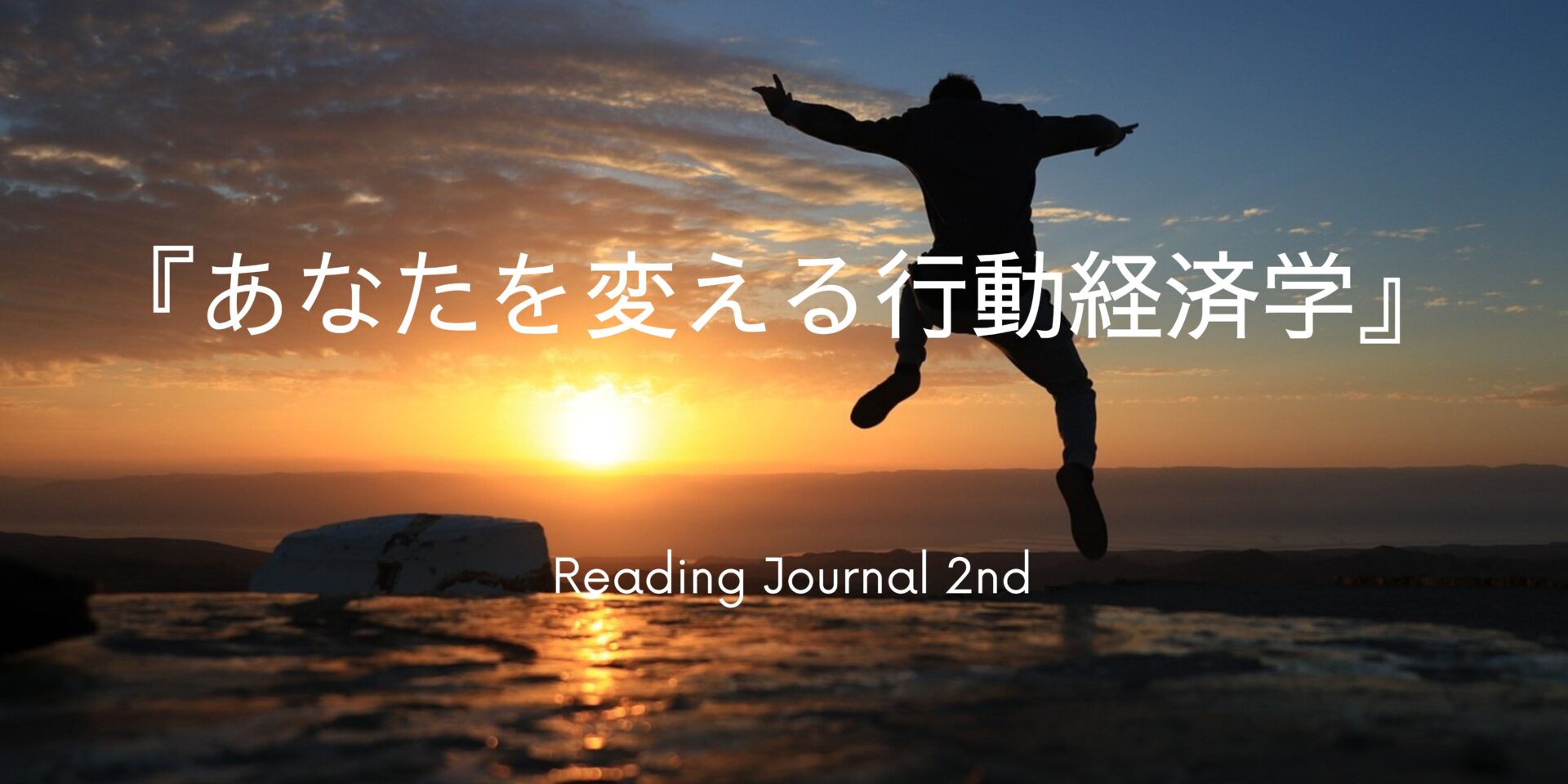


コメント