『作家の仕事部屋』 ジャン=ルイ・ド・ランビュール 編
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
クロード・レヴィ=ストロース – 私のなかには画家と細工師がおり、たがいに仕事を引き継ぐ
クロード・レヴィ=ストロース (Claude Lévi-Strauss) は、文化人類学者。ブラジルとアメリカで長く教鞭をとった。人類学に新しい方法論を導入し《構造主義》の思想家の一人となる。
仕事の方法
私の唯一の規則は、ただの一日たりとも何行か書かずには過ごさないということです。(抜粋)
そのため午前中、あるいは午後に研究所と自宅に仕事を振り分ける。書物を予め明確なアイデアを盛って書きはじめることはない。あるのはある予感だけで、仕事はその問題を掘り下げることからなっている。
すべては無数の書物との差し向かいの対話から始まる。そして読書カードの段階をへて、講義ノートの段階がくる。その内容を講義で話すと、自分で自分の錯誤に気がつく、そして最後に執筆の段階にいたる。
自分がなぜ何年もまえからある問題を研究し、教えているか、その理由を発見する瞬間が訪れるというわけです。(抜粋)
フィールドワークとの関係
フィールドワークについては、自分自身も長い時間を使っている。しかし、現場で過ごした時間は、仕事自体というよりもいかに仕事すべきかを習得することに費やされてしまう。
他の科学の場合と同様、民俗学においても、実験者のための場と理論家のための場があるのは当然のことです。過去五十年間に蓄積された観察記録の量はまったく膨大なものなので、誰かがそれを整理し、解釈することに専念しなければならないのです。(抜粋)
執筆の方法
執筆にあたっては、自分の中の画家と細工師が順番に活躍する。最初に段階では、デッサンする画家のように書物全体をざっくりと書くことから始まる。ここで大事な唯一の規則は決して中断しないこと、そのため繰り返しや中途半端な文章、何も意味のない文章があってもかまわない。とにかくひとつの文章を最初から最後まで書くことが重要である。
そして、執筆が始まる。その作業は、一種の細工に近い作業である。その作業は、不出来な文章をきちんと書きなおすことではなく、最初から自分が言っているはずのことを見つけることである。
私はまず手はじめに初稿のあちこちを抹殺し、あるいはさまざまなサイン・ペンや色鉛筆を使って行間に加筆します(そのために初稿は行間を広くあけてタイプで打つことにしています)。(抜粋)
その後、原稿が解読不要となると不要な部分を白く塗って加筆訂正したり、白い紙を原稿に貼りつけて訂正したりする。
ようするに仕事が仕上がった時には、紙切れが三枚も四枚も重ね貼りされていて、ほとんどある種の画家たちのコラージュに似たものになっているのです。(抜粋)
神話と構造主義
まず、第一に神話を暗唱できるようでなければならない。神話が裏返され、内部構造や他の神話との関係が明らかになるには、何度となくそれらを読み返し、休ませ、濾過しなければならない。
その過程は次のようである。まずトランプのように自分のカードを、恣意的にもっとも簡便なレッテルに従って幾つかの箱に分類する。そしてもう書き出せる、書き出すべきだと思ったときに、そのカードをすべて取り出しテーブルの上に広げていくつかの山に分ける。そしてカードをあらためて分類し直す。そしてその寄せ集めがいくつかできたときに、はじめて書物の全体構造が描き出され、あるひとつのプランに達する。
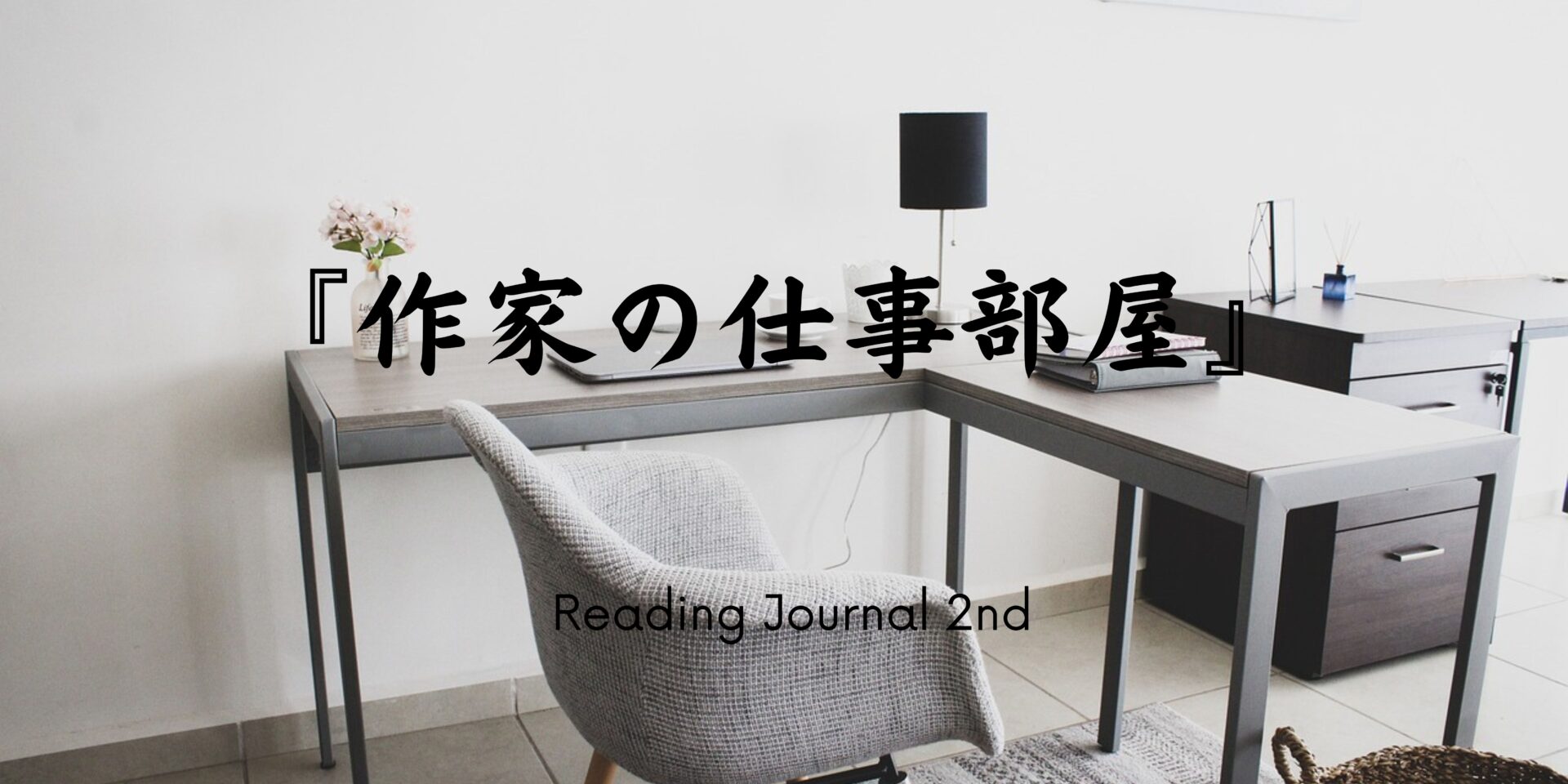
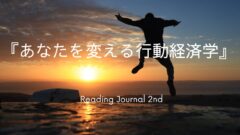

コメント