『行動経済学の使い方』大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第8章 公共政策への応用(後半)
今日で本書も最後、最終章・第8章「公共政策への応用」“後半”に入る。第8章では「医療・健康活動」の応用が取り扱われたが、”後半“は、保険制度の問題と献血の問題である。最後に著者による「おわりに」がある。それではラストスパート。
保険制度の問題
ここでは、公的年金や公的健康保険への加入が、なぜ義務となっているか、について考える。
伝統的経済学での答え
現在は、年金や健康保険の加入は任意加入でなく義務となっている。この問いについての伝統的経済学の答えは、「年金や医療保険は、民間市場では情報の非対称性によって逆淘汰が発生するために、十分に保険商品が供給されない」というものである。
これは、まず保険会社は個々人が長寿になりそうか短命になりそうかが正確にはわからないが、個人は自分の健康度がある程度わかる(情報の非対称性)。これにより、長寿になりそうな人しか保険に入らないので保険料を引き上げないと保険会社は赤字になる。するとさらに長寿になりそうな人だけしか保険に入らなくなる(逆淘汰)。これが繰り返されて、年金保険が高くなりすぎ私的年金が民間では供給されなくなる。このような説明となる。
行動経済学での考え方
しかし行動経済学の視点で考えると、消費者に限定合理性が存在することも社会保険制度の存在理由となる。
つまり、行動バイアスや意志力の不足で老後貯蓄を過小にしてしまうこと、将来の所得予想と老後に必要な貯蓄額を計算する能力がない人も多いこと、なども年金を強制加入にする理由である。
健康保険も伝統的経済学では、情報の非対称性によって不健康な人しか医療保険を買わないことが理由であると考えられてきたが、行動経済学では、健康リスクの考え方のバイアス、計算能力の限界などにより不健康な人が過小にしか民間医療保険に加入しない可能性を考える。
モラルハザードと過小医療の問題
伝統経済学では、医療保険や失業保険でのモラルハザードが問題にされる。ここで「モラルハザード」とは「保険に加入することによって、加入者の行動が変わり、リスクの発生率が変わってしまう」ことである。具体的には、病院での治療が不要な場合でも病院に行ったり、安易に仕事や辞めたり、職探しをしなくなることである。
一方で、医療においては、過小医療の問題、つまり必要な医療を受けない、という問題もある。
ここで医療保険の窓口負担料が上がった際に、医療需要が大きく下がったことについて考える。その解釈として
- 窓口負担が少なかった時に過剰診療というモラルハザードがあった
- 窓口負担が上がった結果、過小医療が発生した
の2つが考えられる。
ここで、どちらの理由で問題が発生しているかを調べないと、正しい政策的対応が全く逆になってしまう。
法案での表現と損失回避
私たちの判断は、表示の違いで大きく変わってしまうことがある。ここでは、法案の提案の仕方で採択されるかどうかが変わってくるという実験が紹介されている。
研究者たちは、利得と損失をもたらすことを前提に政策をパッケージすることを提案している。提案において損失を見えにくくすることで、賛成票を得やすくなる。
減税政策でも、その名称が「還付」「戻し税」とするか「ボーナス」とするかによってお金の使われ方が異なるという実験結果がある。
ボーナスという利得を強調する表現だと消費を増やし、還付や払い戻しであれば既に発生した利得の後払いとして考えられるため、所得が増えたと認識されにくい、と研究者たちは指摘している。(抜粋)
社会規範を使ったナッジ
公共政策に効果があるナッジとして知られるものに、多数派の行動を社会規範として示し、それから乖離している人を少数派と意識させるナッジがある。
ここでは、このような社会規範を使ったナッジの例が示されている。
血液型と献血の問題
最後に血液型と献血の問題について著者らが行った実験の結果が示される。
血液型占いというものを信じる人が多いが、これは学術的な研究では否定されている。
しかし、著者らが行った献血行動と血液型の関係を調べた研究結果では、過去一年間に献血をした人の割合は、О型の人の割合が一番多く、それは統計的に有意な違いがあった。
献血というのは利他的な行動であるため、О型の人に利他的な行動が多い可能性もあるが、他の利他的行動での調査では血液型と有意な違いはなかった。
そこで、著者らは血液型の特性に着目した。
血液型によって輸血ができる範囲が異なるという事実である。О型の血液型は、О型以外の血液型に輸血できるから、О型の人は利他性が同じであってもより多く社会貢献がしたいと考えるのではないだろうか(抜粋)
この仮説を検証するために、О型の人で他の血液型に輸血できることを「知っている人」と「知らない人」に分けて献血する比率を比べた。すると、他の血液型に輸血できると「知っている人」は、献血する割合が大きく統計的に差が出たが、「知らない人」たちの分析では、有意な差がみられなかった。
この実験結果により、分かったことは
私たちが社会に貢献したいという気持ちを持っている場合、自分の社会貢献の効果がより大きければ、より多くの社会貢献をするという可能性があるということだ。(抜粋)
おわりに
本書の最後にある「おわりに」に本書の狙いが書いてある。
本書は、コンパクトな新書という形態で、行動経済学の考え方とナッジについて解説し、その応用例を仕事、健康、公共政策の分野に分けて消化したものだ。行動を改善したいと思った時に、どのように考えてナッジを設計すればよいか、という疑問に答えようと考えた。(抜粋)
そして本書の前に出した平井啓との共著『医療現場の行動経済学』での経験も本書を書く動機となっている。
また、本書の内容は著者の大阪大学経済学部での講義がもとになっているということである。
関連図書:大竹文雄/平井啓(編著)『医療現場の行動経済学』、東洋経済新報社、2018年
[完了] 全15回
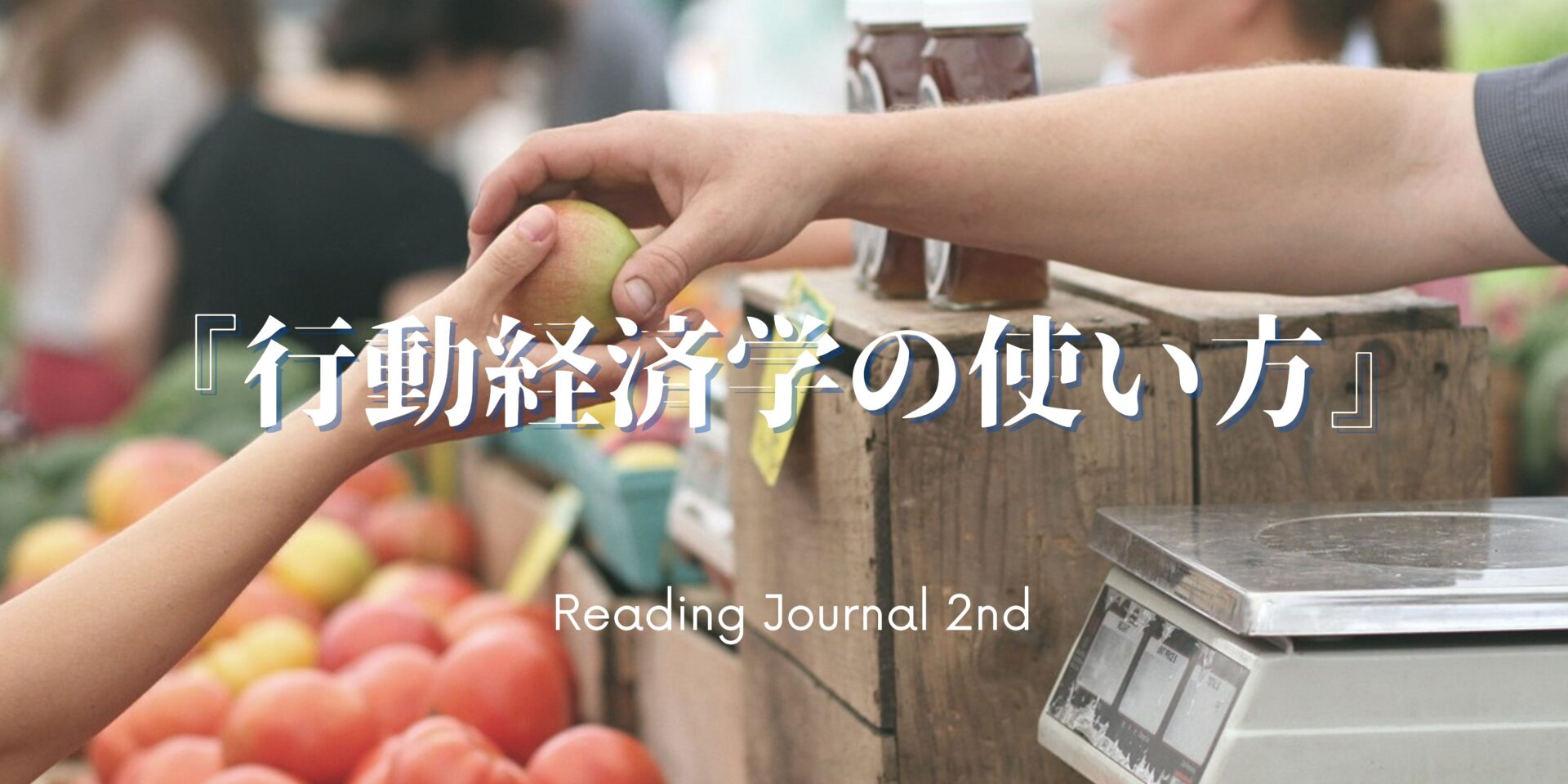


コメント