『行動経済学の使い方』大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第5章 社会的選好を利用する
今日のところは第5章「社会的選好を利用する」である。ここでは、贈与交換による生産性の向上、競争選好の男女差の研究、そして、多数派の行動を強調するナッジなど、社会的選好に関わる行動経済学の具体例が紹介されている。それでは、読み始めよう。
贈与交換
私たちは、正の互恵性を持っていて、恩恵が自分の参照点よりも高い場合は、その分の恩恵に報いる傾向がある。たとえば自分の賃金が参照点より高ければ、その分労働意欲が高くなる。これを、贈与交換という。
この贈与交換により生産性がどのくらい上がるのかについての研究によると、「労働者は、雇い主の善意に報いようとするけれども、その効果は長続きしない」というものであった。
また、賃金カットのような負の贈与もあり、実際に研究によると、賃金カットによる負の互恵性により、生産性が落ちることがわかった。これは賃金カットが労働者のモラルダウンを招くという経営者が抱く心配と整合的である。
また、贈与交換の研究では、「同じだけ賃金を支払うにしても、それが贈与として認識されやすくする工夫があると効果的である」という教訓が得られた。
この研究では、時給12ユーロで募集した仕事に、7ユーロ相当のボーナスを与えるというものであるが、そのボーナスの与え方を、
- 時給12ユーロで仕事をする(ボーナスなし)
- 現金7ユーロのボーナスを渡す
- 7ユーロ相当の水筒を渡す
- 7ユーロという値札が付いた水筒を渡す
- 現金7ユーロか7ユーロ相当の水筒が選べるようにして渡す
- 現金7ユーロを折り紙の人形にして渡す
という条件で、どの形でもらう時に一番努力するかを観察した。
この実験を伝統的経済学で考えると、固定給なのでどの場合も生産性は変わらないはずである。実験結果は、②のグループは、①のグループと同じ生産性で伝統的経済学の想定と同じであった。しかし③~⑤のグループ、つまり水筒をもらったグループは①のグループよりも生産性が上がった。そして、注目すべきは、⑥のグループ、つまり折り紙人形の形で現金をもらったグループの生産性が最も上がった。この結果により贈与というイメージが強く意識させるかどうかで、行動が変わることがわかる。
現金だけの場合は、私たちは、金銭だけを判断に用いる市場規範だけで行動する。しかし、水筒であったり、現金を人形にしたりして、プレゼントであるという意味合いを持たせると、私たちは社会規範で動機付けられ、その贈与に対して報いるために、努力して生産性を高める。日本人であれば、お礼を込めてお金を支払う際には、祝儀袋に新札のお金を入れて渡す。これは、単に市場規範でお金を支払うという意味でなく、お礼という社会規範の意味づけをもたらす効果を持っているからだろう。(抜粋)
競争選好の男女差
次に、労働市場における男女格差があるのは、危険回避度や競争選好の男女差が原因であるという行動経済学的な仮説に話題が移る。
現在は、まだまだ労働市場において男女差が存在する。その原因として従来は、
- 伝統的な価値観により、女性が家庭での家事労働を多く負担するために、長時間労働を重視する日本企業では、十分に活躍できない
- 従業員の訓練は企業負担のため、長時間労働を期待できる男性社員に訓練を集中させる
などの説明があった。
しかし、これに対して「危険回避」や「競争選好」の男女差に求める行動経済学的仮説がある。つまり、「男性は女性よりも競争に参加すること自体が好きである」ということである。これが存在するならば昇進競争の勝者の数に男女差につながる。そして存在する場合には、それが「生まれつきなのか、教育や文化によって形成されるものなのか」が問題となる。
この問題に対して、競争的報酬の生産性上昇効果や競争環境についての好みなどを実験した研究がある。それらの研究の結果「男性の方が女性よりも競争が好きであり、自信過剰である」ことがわかった。
次に、この競争的選好の結果が遺伝的なものか、文化的なものかを調べるために、マサイ族(父系社会)とカン族(母系社会)について調査した研究がある。母系社会のカン族の場合、マサイ族とは逆に、女性の方が競争的であった。そのため、「競争選好の男女差は、遺伝的というよりも文化や教育によって形成される」と研究者たちは推測している。また、女子校と共学校の研究などでも性別役割分担の意識の存在が大きい影響をあたえていることがわかっている。
多数派の行動を強調するナッジ
働き方改革の取り組みで、会社は残業を減らそうとしている。そのため、残業目標を守っていない職場に対して「このルールを守っていない人が何%もいます」と注意や警告を出すことが多い。
しかし、この方法は行動経済学的に考えると逆効果である。この方法では、「多くの人が守っていないことが社会規範である」と伝えてしまうからである。そのため、行動経済学的に正しいナッジは「残業の上限を守っている職場が多数派になっている指標を公表する」ことである。
これは、イギリス政府が行った女性取締役を高める際のナッジ(女性取締役がいる企業が多数であるという指標を公表)などの例がある。
また、病院の無断キャンセルを減らす研究も「多数派の行動を強調したナッジ」を利用している。この研究では、
- 患者が電話予約してきた際に、予約日時と予約番号を自分で書きとめさせ、患者側の積極的コミットメントさせるようにした
- そして「先月予約したのに受診しなかった患者数は※※人でした」と掲示する代わりに「先月予約どうりに受診した人は※※人です」と掲示し、予約通りに受診した人が多数派で社会規範となることを示した
その結果、無断でキャンセル人の数は30%余り減少した。
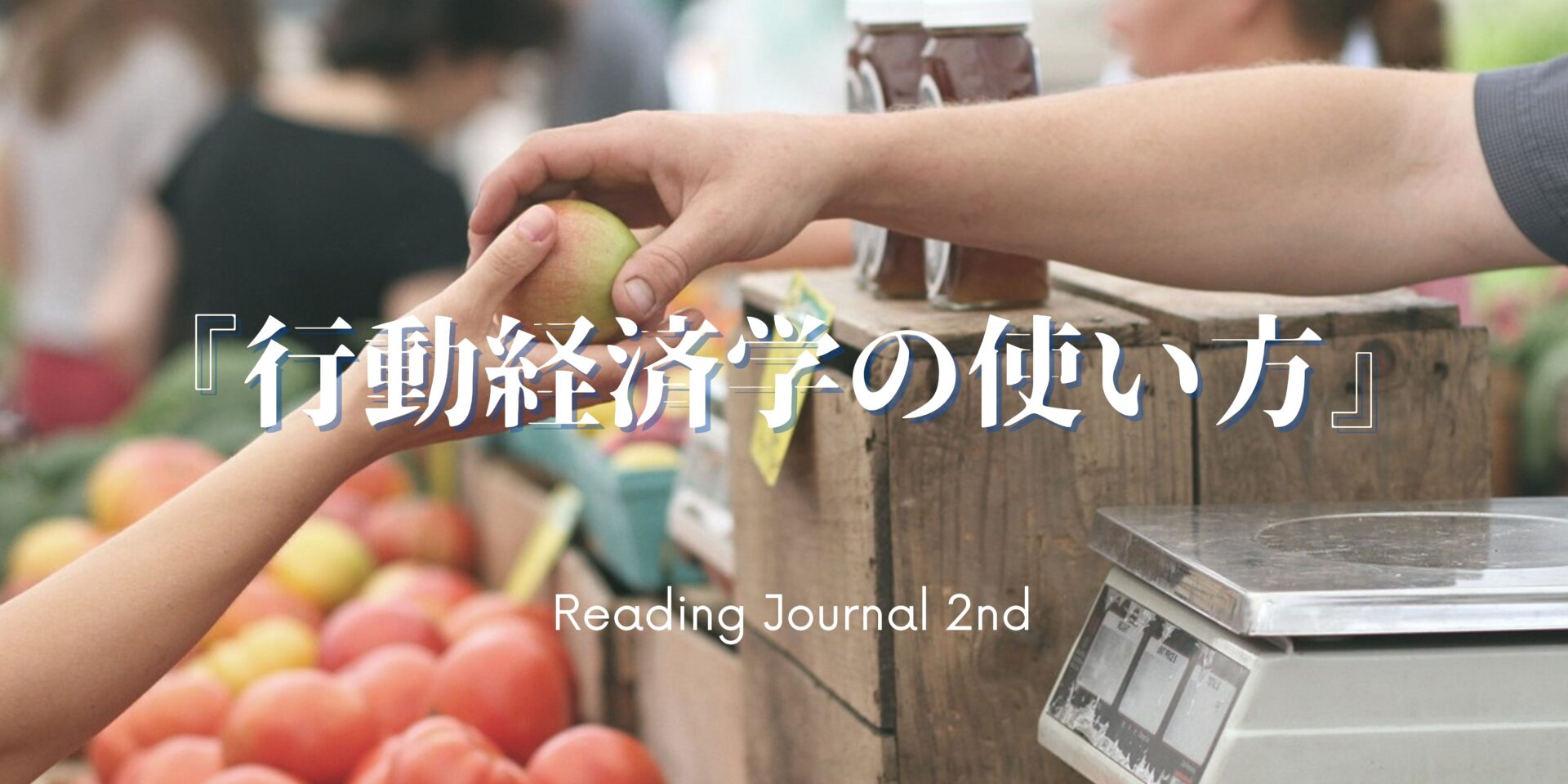


コメント