『作家の仕事部屋』 ジャン=ルイ・ド・ランビュール 編
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
エルヴェ・バザン – なにひとつ偶然にまかせない
エルヴェ・バザン(Hervé Bazin)は、裕福な地主階級に生まれた。しかし、両親の不仲などにより幼少期は不幸だった。私立学校の退学処分、療養院での生活をへて点々と職を変えながら小説を書き、リアリズム作家として大成した。
超写実主義
批評家などは、自分を「新写実主義者」と呼んでいるが、自分としてはエミール・アンリオが名づけた《超写実主義》に近いと感じている。
《超写実主義》というのは、現実に依存するとはいっても、どんな素朴な芸術観かしらないけれども、とにかくそれを満足させるために現実を再現しようなどという野心はまったくもたず、むしろ現実を、場合によっては必要に応じて特徴を強調しながら、告発と風刺の基本要素として利用しようとするジャンルです。(抜粋)
そのため、想像の世界に飛び込むために、大地に足を着けていることが必要である。エクリチュール(=書く行為)は、一種の冒険だがその他のことについては、偶然を排除するのが好きである。
書斎の構成
私の書斎を見て下さい。そこではすべてが分類され、整頓され、機能的です。仕事机から手を伸ばせば届くところに、いわば技術的な書物を乗せた《回転書棚》があります。語源、歴史、引用等々の辞書類です。右側の壁には古典の書棚。左の壁には、専門別に分類された批評ないし《参考書》の書棚。隣室の四方の壁面は現代のエッセーや小説でびっしり埋まっています。それに、四十年来、アルファベット順に整理した手紙類が戸棚に詰まっている。文房具用の整理箪笥にはタイプライターが三台。キーの配列がちがう携帯用が二台 -- 一台は私の秘書を勤めてくれる妻のため〈彼女は一作分の原稿を三日でタイプしてくれます〉、もう一台は私のため。三台目は書物の構想を練るために、キャリッジ[紙を固定し、打鍵に連れて移動させる装置]の大きいタイプ。いくつかの条りを《テスト》したり、会話の部分がものになるかどうかを確かめたりするためのテープレコーダー。そして最後に《至聖所》と呼ぶべきものがあります。鉄製の金庫で(それは絶対に不燃性のものでなければなりません)、中には画然と二つの部分にわかれています。ひとつは、原稿、新聞記事、私のいくつかの作品に関する博士論文、レコード、写真など、ようするに既刊の作品に関するもの。もうひとつはいずれも書くはずの作品に関する一件書類、計画、下書きなど(なかには、結局ものにならなかった作品もいくつか含まれています)。そのほか、忘れてはならない機材としてはウォーキー・トーキー、写真機、パイヤール社の十六ミリ・カメラなど。いずれも、場合によっては小説の背景を写真にとったり映画に撮影したりするためのものです。(抜粋)
創作の手順
想像を正確な現実に投錨させ真実らしくすることが重要である。私は家族問題、社会問題などについて一般的な考え方を持っている。それを例証するために話の筋やさまざまな場面を想像する。そしてそういった場面を読者が納得できるようにするために、現場に赴いて《偽のルポルタージュ》を行い《一件書類》を作る。いっさいのフィクションは読者が信じられるものでなければならないと思っている。
この《一件書類》が完全に揃って書き始めるまでには二、三年かかることがある(常に二十件くらいの審議中の書類を抱えている)。そして、人物や場所が完全に身近に感じられるようになったとき、やっと書き始める。
書き始めたら、世間との絆をいっさい断ち切る。入口の戸は閉め、電話の応答も妻に任せ、五ヶ月、十ヶ月の間、ひたすら書きまくる。そのときは自分の手綱を解き放つ。そうすると語り手が何でも拘束なしに語り始める。そして何もかも取り憑かれたような状態で書き続ける。書き終わると、もとの身になるのに二週間くらいかかる。
草稿を書き終わると、準備した一件書類をもう一度開いてみて、忘れていることはないかを確かめる。そして細部にテクストを差し込んだりする。また物語を豊かにするような特徴や挿話の手帳を調べ調整する。
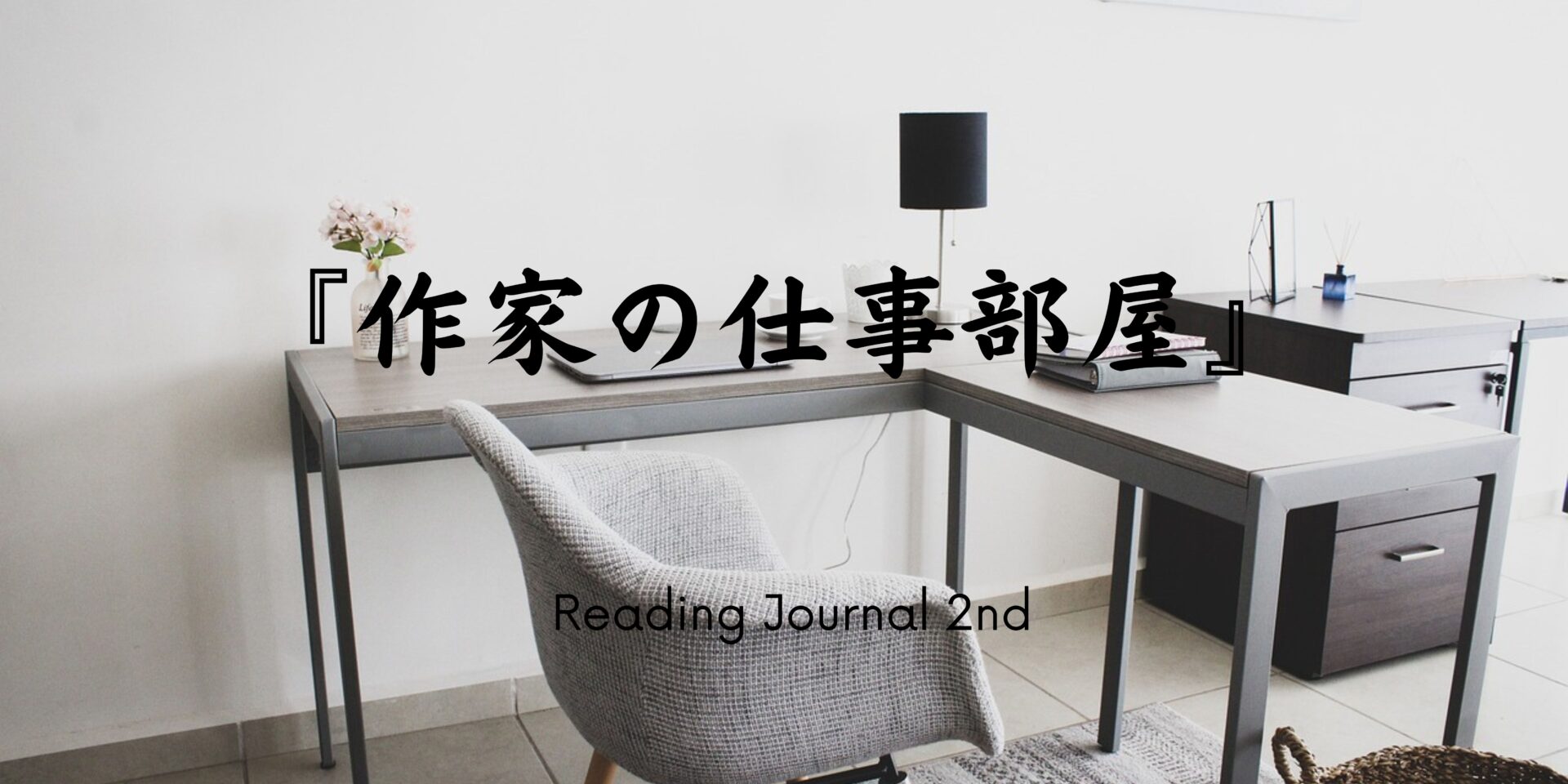


コメント