『作家の仕事部屋』 ジャン=ルイ・ド・ランビュール 編
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
ロラン・バルト – 筆記用具との、ほとんどマニヤックな関係
ロラン・バルト (Roland Barthes)は、批評家、記号学者、社会学者。
仕事の方法(小見出し)
方法論的見解というのであれば、それを持っていない。しかし、仕事の方法があることは明らかである。作家や知識人が自分の書くものについて、《時間割》について、仕事机について、話すのは下らないと思われるが、ある作家が実際にどのように仕事をするかについてたずねることは基本的に重要なことである。
書くという行為は現代においてひどく欲化されているが、人類学的文脈に置き換えてみると、それは長い間、一連の儀式に取り囲まれていたことに気づく。実際、中国や日本の古代社会では、書くためにそれなりの準備を整えるのが常であった。
私個人としては、作品をあらかじめ決定するこれらの《戒律》(僧院的な意味での)全体を --- というのも、仕事に時間、仕事の空間、書くという動作そのものなど、いくつかの座標を区別すること》と呼んでいます。その語源は明らかで、この言葉は始まるまえに貼りつける最初の紙を意味します。(抜粋)
比喩の多い華麗な文章なので読むのが大変だったのですが、要するに、文章を書くうえで、大上段からの”方法論“は持ち合わせてないけども、時間割とか机とか書き方のルールとかは、ありますよ!ってことだね。
昔は、書くことは一連の儀式に取り囲まれていた、ってくだりで、中国や日本では書く前に、一生懸命、墨をする必要があったことに触れているのが、面白かった。ヨーロッパの人から見ると、すごく精神性を感じるんですね。もっとも、弟子がすってたってこともあるんじゃないかな?(つくジー)
文房具、一日のルーティーン、仕事部屋
筆記用具については、ほとんどマニヤックである。楽しみのために、それを変え、新しい筆記用具も試してみる。しかし、結局いつも、柔らかい書体を得られる万年筆に戻る。
著作を書くときは、まずペンで書き、そしてそれをタイプするという二段階をへる。最初にテクスト全体をペンで書き、次にそれをタイプで打ちながらすっかり書き直す。これは、自分にとって神聖なものである。
パリでは、寝室に仕事場を置いている。そして毎日、朝の九時半から午後一時まで、官吏のようにものを書いている。そして音楽の場もあり、毎日ほぼ決まった時間–午後二時半ごろ—にピアノを弾く。さらに、絵画の場もあり、一週間に一度日曜画家の真似事をしているため、絵を描く場所も必要である。書くためにはこのような空間を構造的に再現できる必要がある。そのため田舎の別荘にもこれらの三つの場所を正確に再現している。
仕事のための空間については、まず机が必要である。その横にもう一つのテーブルが必要である。そして、タイプを置く場所、雑多な《思いつき》を書きとめたり三日分の《ミクロブラン》や三カ月分の《マクロブラン》を載せておく台机も必要である。さらに形や大きさを統一したカード類がある。
文献調査
自分の好きな仕事は、該博な知識を駆使したものではなく、図書館も好きではない。また、あらかじめ参考文献一覧を作ることもない。
問題のテクストを、かなり物神崇拝的やり方で読むだけです。そして私を興奮させる力をもついくつかの箇所、いくつかの契機を書きとめます。それは単語であることさえあります。読み進めるにつれて私は引用や思いつきをカードに書きつける。奇妙なことにそれがすでに文章のリズムを備えているので、その時点ですでに一種のエクスチュールとして存在しはじめるのです。(抜粋)
その後にもう一度、読み直す必要があるわけではない。ただ、別の参考文献に改めて当たることはある。その頃には、偏執狂的な状態になっていて、読むものすべてが、自分の仕事に結びついていく。
ここの部分、ようするに参考となる本を丹念に読みながら、“なるほどぉ~”って思ったところをカードに記入するって、ことだよね。それを、部屋のカード入れに入れるんだね!やっぱり読みっぱなしじゃ、ダメなんだよね(つくジー)
唯一の問題は、楽しみのために読む本が書くために読む本に干渉するのを避ける事である。そのため、楽しみのために読む本は、夜ベッドで読み、その他ものは、朝机に向かって読んでいる。
執筆のプラン
記号学をはじめたころは、プランの作成をしたが、その後、プランというものが圧迫的なものであることがわかった。そのため、一種の冒険を含む切り抜きを選んだ。しかし、論理を偶然により置きかえる時、その偶然が機械的なものにならないように気を配る必要がある。
私個人としては、《禅》のある種の定義に従って《制御された偶発時》と呼びたいと思っている方法によって事をすすめています。(抜粋)
ここもなんだか難しい。まぁ、最初からプランをがっちり固めてから書くのではなく、書いているうちに思いついた偶然を大切にする・・・・ってことじゃないかな?でも、その偶然もちゃんと制御してますよ・・・ってね。(つくジー)
小説の執筆について
最後に、「これまで小説を書こうと思われたことは一度もありませんか?」という質問がある(ロラン・バルトは、批評家・記号学者・社会学者で小説家ではない)。それに対して、
小説を定義するのはその対象ではなく、謹厳な精神の放棄です。・・・(後略)・・・(抜粋)
と答えている。
この部分、言わんとすることは何となくわかるんだけど、うまくまとめられないのでした。なんというか答えづらい質問を、うまくかわしたって感じでして・・・・・(つくジー)
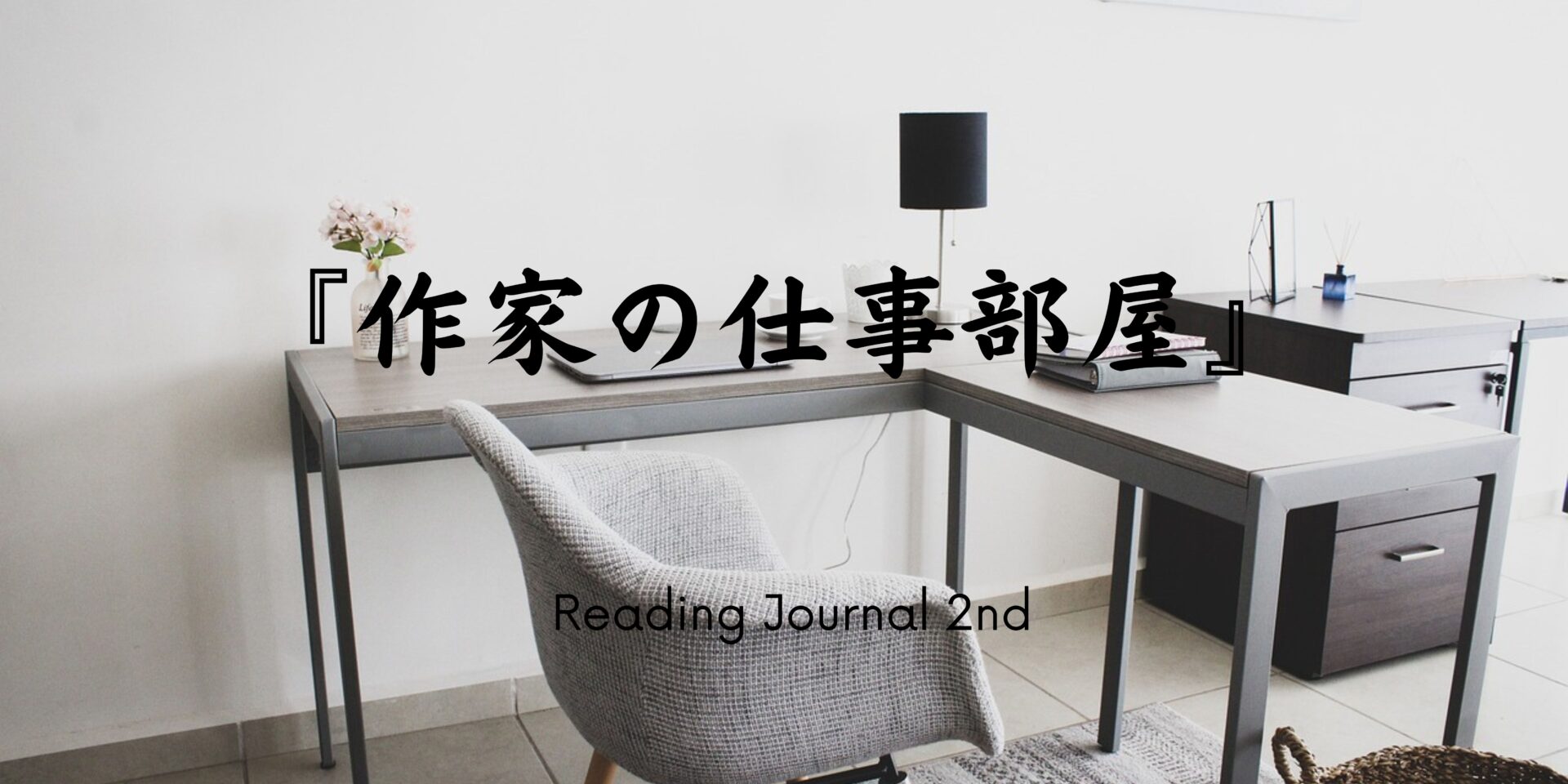


コメント