『行動経済学の使い方』大竹 文雄 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1章 行動経済学の基礎知識(その2)
今日のところは、第1章「行動経済学の基礎知識」の“その2”である。前回“その1”では、行動経済学の基礎知識として、「プロスペクト理論」つまり「確実性効果」と「損失回避」を学んだ。今日のところ“その2”では、「現在バイアス」「互恵性と利他性」そして“その3”は「ヒューリスティックス」についてまとめる。
現在バイアス
先延ばし行動と現在バイアス
伝統的な経済学では、人間の意思決定は合理的に行われていると考えられている。そのため将来を見通して合理的な計画を立て、それを合理的に実行することを基本としている。しかし、実際には計画はできているがそれを実行する際に現在の楽しみを優先して計画を先延ばしする傾向がある。
このような人間の特性は、行動経済学では現在バイアスという概念で理解することが一般的である。(抜粋)
このような、現在バイアスから生じる先延ばし行動は、いろいろなところに生じ、他の環境の変化がないにかかわらず、選択が変化してしまうことを「時間非整合な意思決定」と呼ぶ。
コミットメント手段
この現在バイアスによる先延ばし行動を防ぐために、コミットメント手段の利用が有効である。コミットメント手段とは、自分の将来の行動にあらかじめ制約をかけることであり、老後の資金をためるために、給料天引き型にする、短期間で引き出せない口座に貯蓄する、などである。
締め切りを細かく設定することも有効なコミットメントである。また締め切りを厳しくして、守れなかったときの罰則を作るなどもコミットメントである。しかし、コミットメント手段を使えば必ずうまくいくというわけでもない。たとえば締め切り厳しくするコミットメントを使うと、初めから達成できない場合を心配して、達成そのものを諦めてしまうこともある。また、罰をあたえるようなコミットメントは、罰をあたえる側がそれを躊躇し撤回してしまう場合がある。その場合は、その罰はコミットメントにならない。したがってコミットメントは目標が達成されれば自動的に実行されるようなものが望ましい。
賢明な人と単純な人
行動経済学では、「現在バイアスを自覚し、コミットメント手段を利用し、それを防いでいる人」を「賢明な人」と呼ぶ。反対に「現在バイアスが無いと思っているような人」を「単純な人」と呼ぶ。
単純な人の場合、先延ばし行動をとってしまい、忍耐強い計画を立てることはできても、計画を実行する時点になるとその計画を反古にしたり、先延ばししたりして、結果的には近視眼的な行動をとる。(抜粋)
互恵性と利他性
社会的選好
伝統的は経済学では、自分自身の物的・金銭的利得だけを選好する利己的な個人が想定されたが、行動経済学では、他者の物的・金銭的利得への関心を示す選好を人々が持つと想定されている。そのような選好を「社会的選好」と呼ぶ。
この社会的選好には、
- 利他性:他人の利益から自分の効用(満足度など)を得る
- 互恵性:親切な行動に対しては親切な行動で返す
- 不平等回避:不平等な分配を嫌う
がある。これらの社会的選好は、実験結果を理解するために生まれた概念である。
利他性
利他性には
- 純粋な利他性:他人の幸福度が高まることが、自分の幸福度を高める
- ウォーム・グロー(暖かな光):他人のためになる行動(寄付など)そのものから幸福度を感じる
という二種類がある。
互恵性
互恵性にも、
- 直接互恵性:恩恵を与えてくれた人に直接恩を返す
- 間接互恵性:恩恵を与えてくれた人と、別の人に恩を返すことで間接的に恩を返す
がある。贈与を使って人々の意欲を引き出すなどはこの互恵性を使っている。
逆に負の互恵性もある。自分が他人から損失を受けた場合に、自分の得にならなくても仕返しや罰をあたえるという行為である。
不平等回避
不平等回避には、
- 優位の不平等回避:自分だけが他の人よりも恵まれている状況や、他人が自分よりも恵まれていない状況にある場合に、悲しい気持ちになり、恵まれない人に対して再分配して所得差を小さくしたいと感じる
- 劣位の不平等回避:逆に自分よりも所得が高い人がいると不満に思うというもの
の二種類がある。
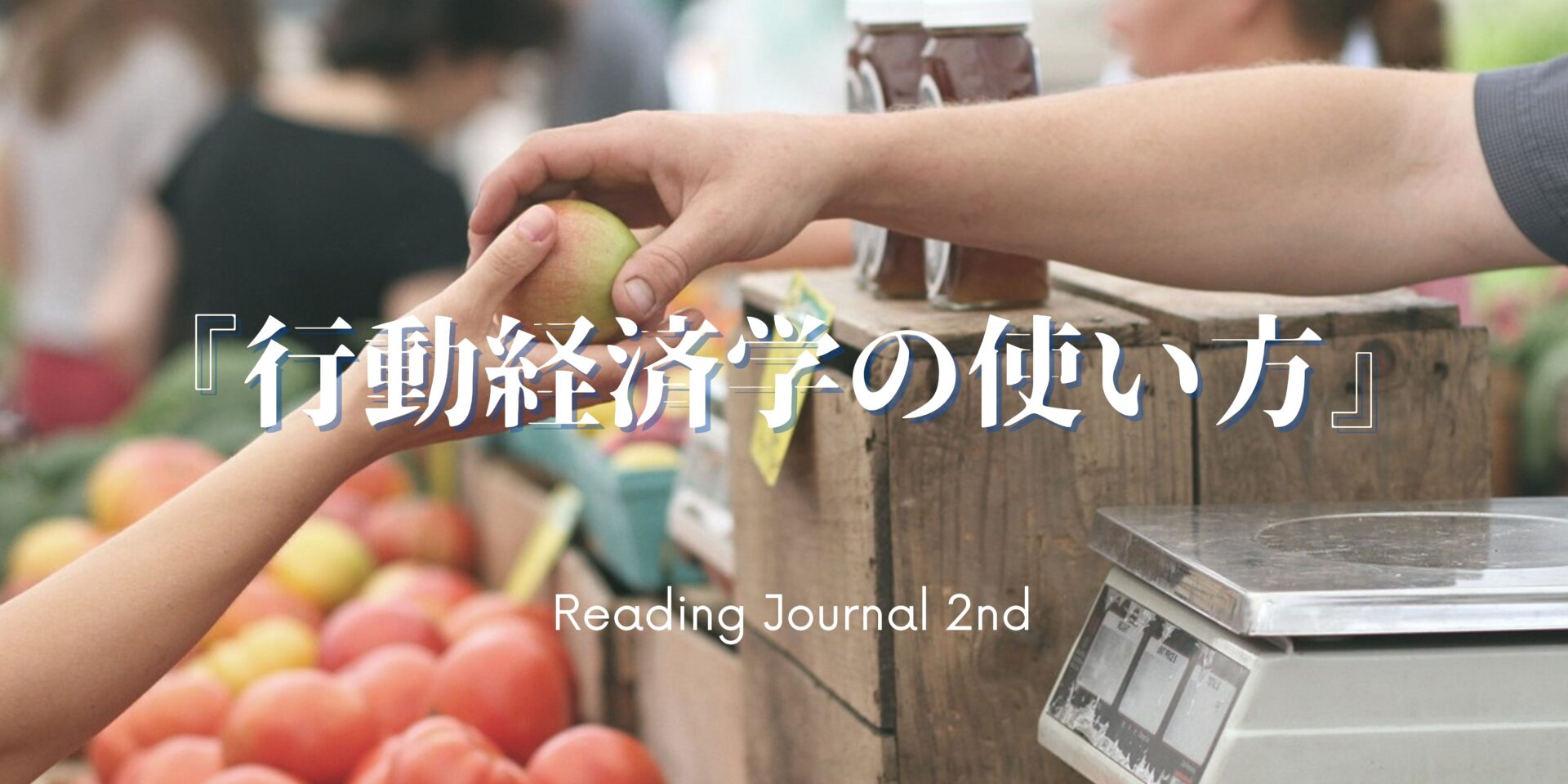


コメント