『「モディ化」するインド』湊 一樹 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第3章 「グジャラート・モデル」と「モディノミクス」(その1)
ここから“第3章 「グジャラート・モデル」と「モディノミクス」”である。グジャラート州首相であったモディは、グジャラート州での「モディノミクス」の成功を引っ提げて、二〇一四年総選挙で「モディ旋風」を起こしインド人民党(BJP)は圧勝、モディ政権が誕生した。第3章では、二〇一四年の圧勝を受けてのモディ政権の誕生と、その原動力になった「グジャラート・モデル」の実態、さらに「モディノミクス」の失敗についてである。第3章は、4つに分け“その1”で二〇一四年の総選挙での圧勝について、“その2”で「グジャラート・モデル」実態について、そして“その3”で「モディノミクス」の失敗、さらに“その4”で「経済の停滞」についてまとめることにする。それでは、読み始めよう。
二〇一四年総選挙と「モディ旋風」
モディ首相の誕生
二〇一四年の総選挙で最大野党だったインド人民党(BJP)が単独過半数の議席を得て大勝した。そして、BJP中心とした国民民主連合(NDA)が発足し、ナレンドラ・モディ首相が率いた新政権が生まれた。反対に、二期十年にわたって、統一進歩連合(UPS)を率いた国民会議派は、大敗北を喫し政権を追われた。
「モディ旋風」の中身
この選挙結果は「モディ旋風」と呼ばれたが、著者はそれには、いくつかの留保が必要であるとしている。
ひとつは、インド中部と西部については、八割以上の得票率を得ていて文字通りに「モディ旋風」といえるが、それ以外の地域でのBJPの支持は限定的であったこと。もう一つは、BJPは過半数の議席を占めたが、一方インド全体での得票率は三割程度にとどまったこと。さらには、インドで大きな影響力があった地域政党の存在感が低下したこと。である。
BPJと会議派の明暗
この選挙では、BPJが過半数の議席を得たのに対して会議派は、一割に満たない惨敗であった。その原因として著者は
- 会議派を中心としたUPA政権失政
- 地域政党との連携
- 選挙戦での大規模な動員と宣伝
- 首相候補中心の選挙戦略
をあげている。
UPA政権の第二期の失政
会議派を中心としたUPA政権は、第二期(二〇〇九~二〇一四年)の後半にさまざまな失政を重ね急速に国民の支持を失っていった。そのころのインドの経済は急激な物価上昇と経済の減速に直面し、そのような経済状況の悪化に対して政府が対処できない状況であった。さらに政府高官の汚職事件が立て続けに起こる。
二〇一四年総選挙の直前におこなわれた複数の世論調査では、物価上昇、経済の減速、政治腐敗の蔓延、という三つの争点を有権者がもっとも重視していたという結果が出ている。野党側にとっては、政治・与党を攻撃するための材料に事欠かないような状況だったのである。(抜粋)
地域政党との連携
BJPは各州の地域政党と協力関係を結んだり、他党の有力者を自らの陣営に引き入れたりするなど、BJPは議席数の獲得に積極的な動きをした。他方会議派は、そのような点で後れを取った。BJPは、地域政党との連携のおかげで、比較的低い得票率で多くの議席を獲得することが出来た。
選挙戦での大規模な動員と宣伝
BJPは選挙戦で大規模な動員と宣伝を行った。そしてそれを可能とした資金力において、会議派を圧倒していた。BJPは、支持母体である民族奉仕団(RSS)からも手厚い支援を受け、さらにモディ個人を応援するために多数の者がボランティアとして選挙活動に参加したり、献金をしたりした。
BJPは、新聞、テレビ、ラジオなどの既存メディアでの広告や屋外広告に加えて、ユーチューブ、フェイスブック、ツイッター、ワッツアップ(WhatsApp)などの媒体も駆使した。「絨毯爆弾」とも呼ばれる大規模キャンペーンを展開し、「空中戦」でも他党を圧倒することができたのは、このような資金的な裏づけがあったからである。(抜粋)
首相候補中心の選挙戦略
BJPは、総選挙の半年前から、ナレンドラ・モディを首相候補に指名し、個人を前面に押し出した選挙戦を行った。それに対して会議派は首相候補を立てないまま中途半端な形で総選挙に臨んだ。
当時のインドでは、不安定な連合政治が続き、「強いリーダー」を求める意識が高まっていた。それを背景にして、モディの人気が高まっていった。BJPは、モディの「強いリーダーシップ」を強調し、モディには、前政権を苦しめた「政策的麻痺」を克服する能力があるというイメージを打ち出した。
そして、このモディ人気のもう一つの要因は「モディ州首相による良い統治によって、グジャラート州に経済発展がもたらされた」という言説であった。この「グジャラート・モデル」の全国化によって、インド全体が発展すると主張した
しかし、この「グジャラート・モデル」が実際に何を意味し、どのような政策であるかという肝心な点に関しては、何も語られなかった。
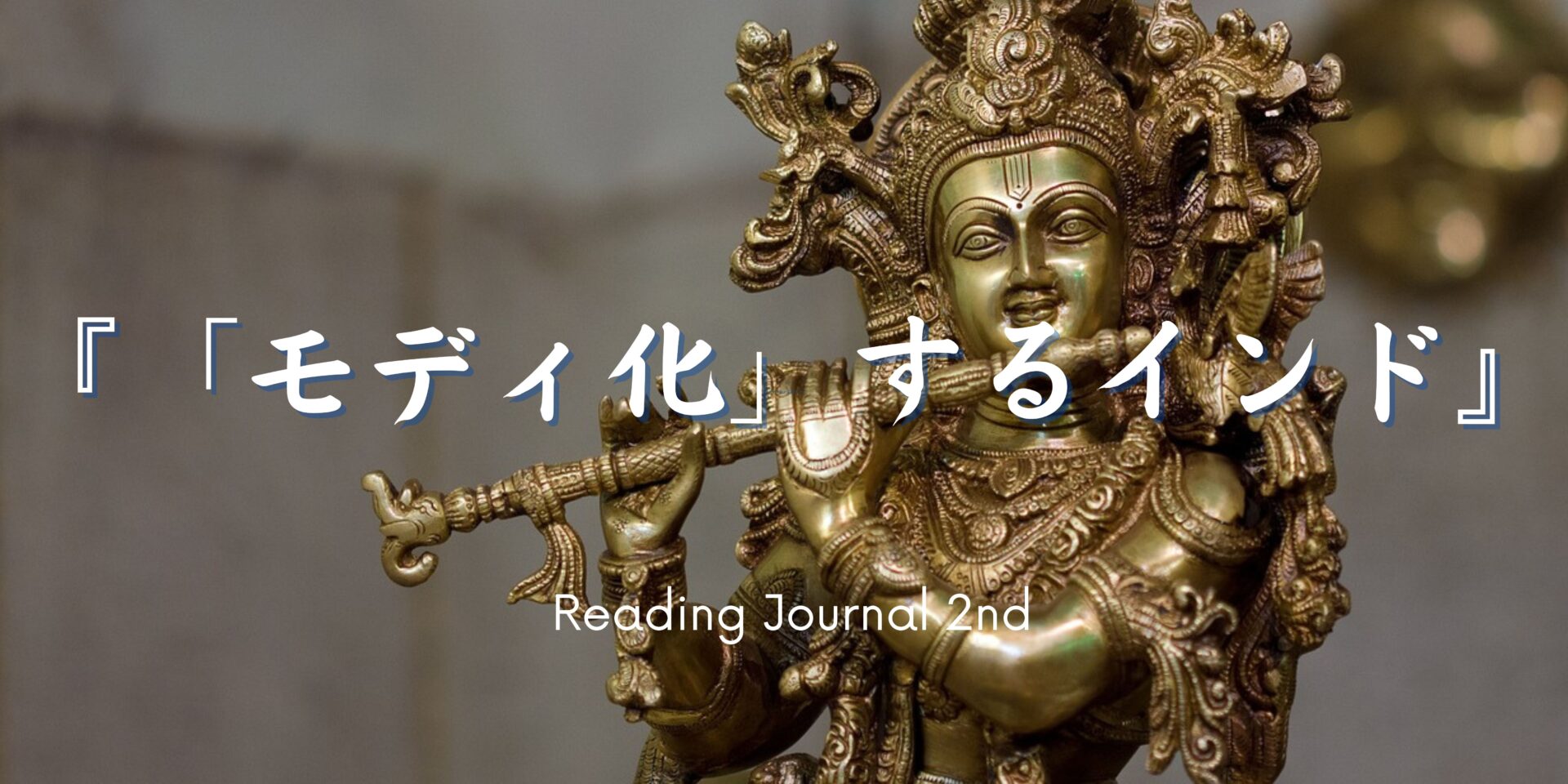


コメント