『「モディ化」するインド』湊 一樹 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1章 新しいインド?(その3)
今日のところは、第1章“新しいインド?”の“その3”である。“その1”では、世界の民主主義の後退と権威主義化の足取りが概観され、モディ首相によりインドが権威主義化していることについて説明された。そして“その2”では、「経済、外交・安全保障における問題」についてであった。そして、き“その3”では、「モディ首相が唱える「新しいインド」「大きな物語」」についてである。それでは読み始めよう。
「新しいインド」という古い物語
これまで見てきたようにインドでは、民主主義が浸食される一方、経済が危機的状態になり、また外交、安全保障では、「普遍的価値」を共有しているはずの民主主義国家と軋轢を抱えている。このように現在インドは大きな行き詰まりに直面している。
しかし、国政選挙や州議会選挙の勝利を通じてモディ首相は、自らの権力と影響力を維持・強化することに成功している。これは、モディ首相個人の人気の高さが現政権の支持の原動力となっているからである。
このような状況でも高い人気を誇るこの理解には、政府・与党が国民に向けて語る一連の政治的言説を「大きな物語」として捉え、モディ個人がその中でどのような位置づけとされているかを検討することが必要である。
モディ政権が語る「大きな物語」
「大きな物語」を貫いているのは、モディ首相という希代の指導者が、国のあり方そのものを転換するような変革をもたらし、インドが新たな高みへと導かれていくという輝かしいストーリーである。(抜粋)
著者は、この物語は、単なるイメージ戦略にとどまらず、深刻な問題を孕んでいるとしている。ひとつは、「大きな物語」があたかも現実であるかのような大がかりな演出である。政府・与党はメディア・コントロールやSNSなどを通じて「大きな物語」に都合がいいところは増幅し、そうでないところは排除している。そして、ふたつめは、「大きな物語」はヒンドゥー至上主義を色濃く反映した歴史修正主義に立脚しているという問題である。
この「大きな物語」は、二つの前提にもとづいている。
- 数千年前にさかのぼる「ヒンドゥー文明」の遺産を引き継ぐ偉大なる国という前提
- 「外国勢力」よる支配と独立後のインド国民会議派による失政と腐敗のため千年以上も停滞に陥ったという前提
である。ここで重要なのが、②の「外国勢力」は植民地支配をしたイギリスだけでなく、それに先立つイスラム王朝も含まれるという点である。
この前提は、ヒンドゥー教至上主義の歴史認識と合致している。そしてこのような歴史認識は、歴史修正主義以外のなにものでもない。
しかし、モディ政権が権力の座についてからは、この歪んだ歴史認識を主流化が組織的に行われ、学校教育にすら影響が及んでいる。
「大きな物語」の中のモディ
そして、この「大きな物語」では、モディ首相の存在感が突出していることも、この物語の危うさが表れている。
「大きな物語」でのモディ首相の位置づけは、単に優れた指導者というだけにとどまらない。ナレンドラ・モディの首相就任というのは、「外国勢力」による支配と歴代の会議派政権による失政という悪夢の歴史からの解放であり、「ヒンドゥー文明」をついに取り戻したインドが、世界から尊敬される大国への道を歩み出す転換点とされているのである。(抜粋)
つまり、ナレンドラ・モディを神格化し、権力の座に上りつめたことを神の摂理かのように印象づける組織的な意図が働いている。
さらに、政府・与党はモディの「親しみやすさ」「身近さ」の演出もしている。「神格化されたリーダー」というイメージと「親しみやすさ」「身近さ」という要素を加えることで、モディ首相の強力なリーダーシップのもとで進む大国化を国民が自ら感じ取れるようにコントロールしている。
政府・与党は、この「大きな物語」を国民に浸透させ政権基盤を強固なものとしているが、実際にはさまざまな面で政策に行き詰まり、それを必死に隠そうとしている。
「大きな物語」への幅広い共感は、大国幻想すぎないのである。(抜粋)
この「大きな物語」から考えると、確かに、アヨーディヤーの「ヒンドゥー教寺院(ラーマ寺院)建立」事件(ココ参照)が起こるのも理解できる。つまりは、イスラム王朝は「外国勢力」なので、否定されて当然ってことなんだよね。(つくジー)
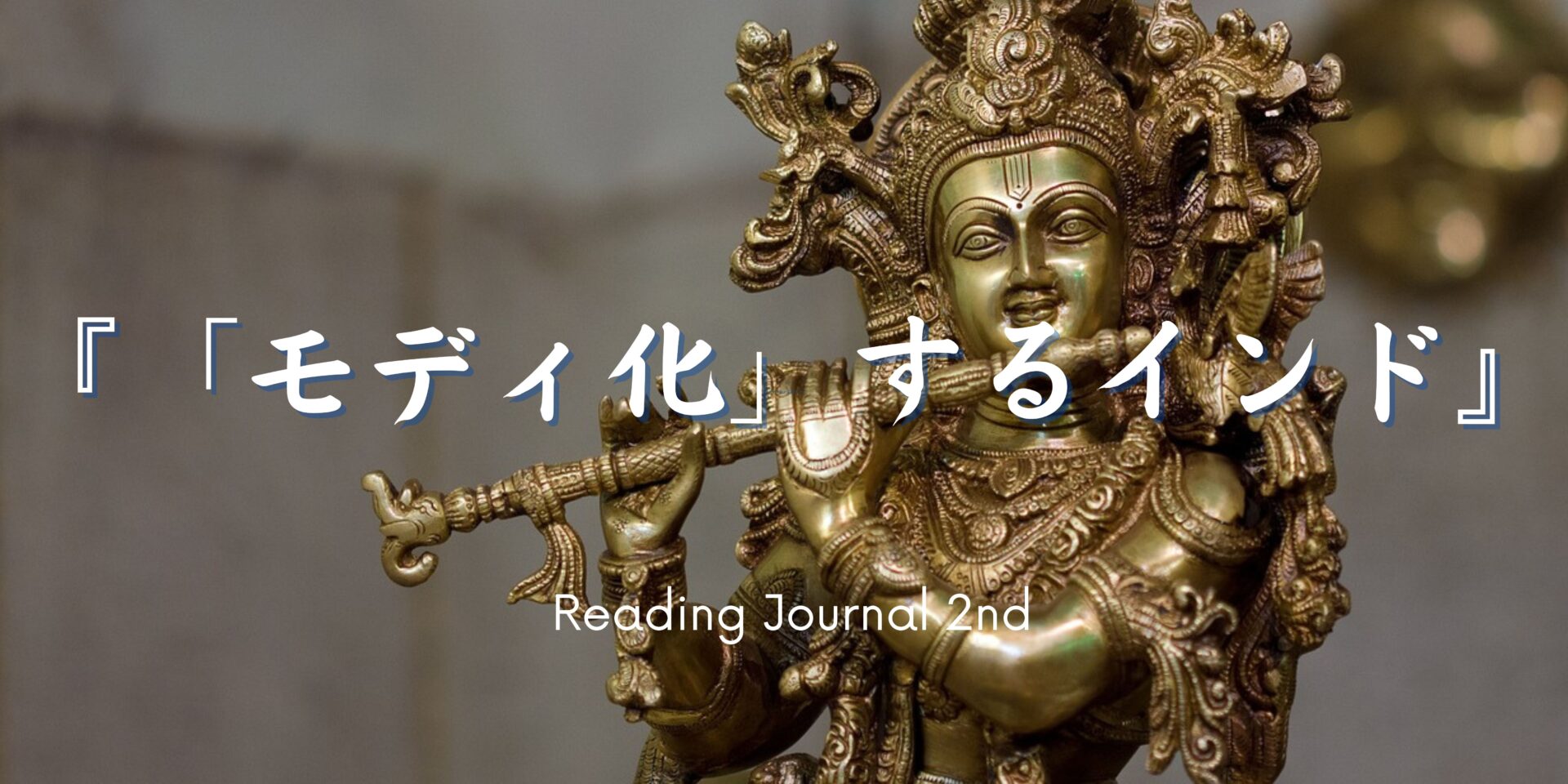


コメント