『「モディ化」するインド — 大国幻想が生み出した権威主義』湊 一樹 著、中央公論新社(中公選書)、2024年
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
プロローグ — 大国幻想のなかのインド
インドというと、古くはブッタ、新しくはマハトマ・ガンジーやネルーなどの名前が思い浮かぶが、最近になってモディという名前を頻繁に聞くようになった。いつごろかと思いだすと、日米豪印首脳会合(QUAD)というのが開かれたころからだろうと思う。その時は、「なぜインド?」と思ったのだが。
そして知らぬうちにインドの人口が中国を抜いたり、経済でももうすぐ日本を抜くような成長をしていたり、と大国化していた。モディ首相は、民族衣装に身に包み颯爽としているし、ロシアのウクライナ侵攻のさなかに、プーチン大統領に「戦争はいけない」と直接伝えるなど、好印象だった。
しかし、しだいに「ヒンドゥー至上主義」を主張して他教徒を弾圧しているなど、モディ首相の負の面も伝えられるようになった。これはどういうことだろう?
そこで、この本を手に取ってみた。帯の前面のリード部に「ヒンドゥー至上主義、個人崇拝の浸透」と書かれているので、モディ首相に批判的な論調の本であるようだ。それでは、読み始めよう
普遍的価値の共有の変化
まずプロローグの最初は日本とインドの関係の強化の歴史、そして、その共通理念だった「普遍的価値の共有」というものが徐々に後退していったことが書かれている。
日本とインドの関係は、「日印グローバル・パートナーシップ」(2000.8)、「日印戦略的グローバル・パートナーシップ」(2006.1月)、「日印特別戦略劇グローバル・パートナーシップ」(2014.9)、と段階的に関係を深め2007年からは両国の首相が相互に訪問し合って年に一回の首脳会談を定期開催するようになった。
しかし、2019年12月にインドで行われる予定だった日印首脳会談は、インドの「市民権改正法」に反発する市民のデモが全土に広がり安全上の理由で見送られた。そして、その後新型コロナ感染症の流行もあり長らく途絶え、2022の岸田総理のインド公式訪問まで途絶えてしまった。
この日印首脳会談では、両国が普遍的価値を共有していることが、強固な日印関係の基盤となっていると繰り返し強調されてきた。(抜粋)
この普遍的価値とは「自由、人道主義、民主主義、寛容性、非暴力、人権、法の支配」などである。
しかし、日印間で首脳の往来がとまっている間に、この「普遍的価値をめぐる状況に重大な変化が起きている」。
二〇一四年五月にモディ首相率いる新政権が成立して以降、インドという国のあり方とそれを支えてきた基本的理念を根底から覆そうとする動きが徐々に顕在化し、二〇一九年の総選挙での再選を追い風に、その勢いが一気に増していったからである。「普遍的価値の共有」という概念を実体の伴わない外交辞令にしてしまうほど、モディ政権の一〇年はインドを大きく変えたのである。(抜粋)
インドの民主主義の後退
インドの国際社会での存在感は増しているが、インドについてのイメージは大きく歪んでいる。その要因は、インドの広大な国土と世界有数の人口、様々な側面で変化をし続ける「流動性」と雑多な要素を内包している「多様性」などである。
著者は、その「歪んでいる認識の例」として、ひとつはインドの教育、もう一つは、新型コロナ対策を挙げている。
一般に、インドの教育について語られることは、ごく一部のエリート層の教育、すなわち優秀なIT技術者を送り出す高度な教育のみに焦点が当てられた話ばかりであり、その他大多数が格差と教育システムの欠陥により、十分な教育の機会を失っている事実については、あまり目を向けられていない。
そしてもう一つの例として取り上げられているのは、新型コロナウィルス感染症による被害と政治と政治体制の仮説についてである。この仮説は、
- 権威主義体制・・・国民の自由と権利を厳しく制限する措置がとられ、感染拡大を抑え込んだ。
- 民主主義体制・・・強硬な措置を行えず、感染拡大を防ぐことが出来なかった。
というものである。そして、権威主義体制の成功例に「中国」を民主主義体制の失敗例を「インド」が良く持ち出されている。しかし、著者は、この仮説にには、いくつもの問題があるとしている。
ひとつには、インドの対応が後手に回ったわけでもなく、強制力を欠いたわけでない点(第五章で詳説)、ふたつめは、中国を中心とした権威主義体制の国々は新型コロナウィルス感染症の被害を意図的に過小申告している可能性がある点などである。
しかし、それよりも大きな問題として著者は次のように指摘している。
新型コロナ対策のあり方と政治体制を結びつけた中印比較の最大の問題は、全く別のところにある。それは、何の疑問もなしに、インドを「民主主義国」として扱っていることだ。(抜粋)
現在のインドは、モディ政権により民主主義が大きく後退し、普遍的価値が大きく損なわれている。
インドの大国幻想
「世界最大の民主主義国」と呼ばれてきたインドは、急速に権威主義化している。そして、モディ政権の一〇年で政治のみならず経済・外交・安全保障などの分野でも一般的な認識と現実のズレが広がっている。
経済では、一九九〇年代後半からの高い経済成長は、勢いを失い、さらに新型コロナ感染症対策の失敗により深刻な停滞に陥っている。
外交・安全保障分野では、「普遍的価値を共有する戦略的パートナーシップ」のイメージから離れ、かといって中国、ロシアとの連携も困難であり、場当たり的な行動が増えている。
モディ首相の強力なリーダーシップのおかげで、「世界最大の民主主義国家」であるインドが「超大国」への道をひた走っているといった見方は、あまりにも現実離れしているといわざるをえない。(抜粋)
しかし、日本ではそのような見方はされず、実態以上にインドは評価されている。それは、日本側の事情もあるが、モディ政権が権力を維持・拡大するために、多大な労力を費やして「大国幻想」を振りまいていることによる。
著者は、プロローグの終わりに本書の狙いを次のように示している。
本書では、ナレンドラ・モディが権力を握るまでの経緯とその背景に加えて、民主主義の後退、政治の「個人化」、偽情報やヘイトの拡散とテクノロジー、中国の膨張、グローバルサウスの台頭といった国際的な潮流も視野に入れつつ、これらの疑問について検討していく。それを通して、モディ政権がインドに何をもたらしたかを明らかにする。(抜粋)
目次
プロローグ 大国幻想のなかのインド [第1回]
第1章 新しいインド? [第2回][第3回][第4回]
1権威主義化する世界とインド
2モディが変えたインド
3イメージと現実のあいだ--経済と外交・安全保障
4「新しいインド」という古い物語
第2章 「カリスマ」の登場 [第5回][第6回][第7回]
1ナレンドラ・モディの「生い立ち」
2権力の階段
3グジャラート暴動
4「暴力の配当」としての権力
第3章 「グジャラート・モデル」と「モディノミクス」[第8回][第9回][第10回][第11回]
1二〇一四年総選挙と「モディ旋風」
2「グジャラート・モデル」の実態
3「モディノミクス」の失敗
4顕在化する経済の停滞
第4章 ワンマンショーとしてのモディ政治 [第12回][第13回][第14回]
1再度の与党圧勝とモディ人気
2ワンマンショーのなかの「モディ首相」
3ワンマンショーの舞台裏
4BBCドキュメンタリーの波紋
第5章 新型コロナ対策はなぜ失敗したのか [第15回][第16回][第17回]
1突然の「世界最大のロックダウン」
2全土封鎖による深刻な打撃
3人災としての第二波
4浮き彫りになる歪んだ統治
第6章 グローバル化するモディ政治 [第18回][第19回][第20回]
1トランプ大統領の訪印とその裏側
2高まるヒンドゥー至上主義の脅威
3「グローバルサウスの盟主」の虚像と実像
エピローグ 「モディ化」と大国幻想 [第21回前半]
あとがき [第21回後半]
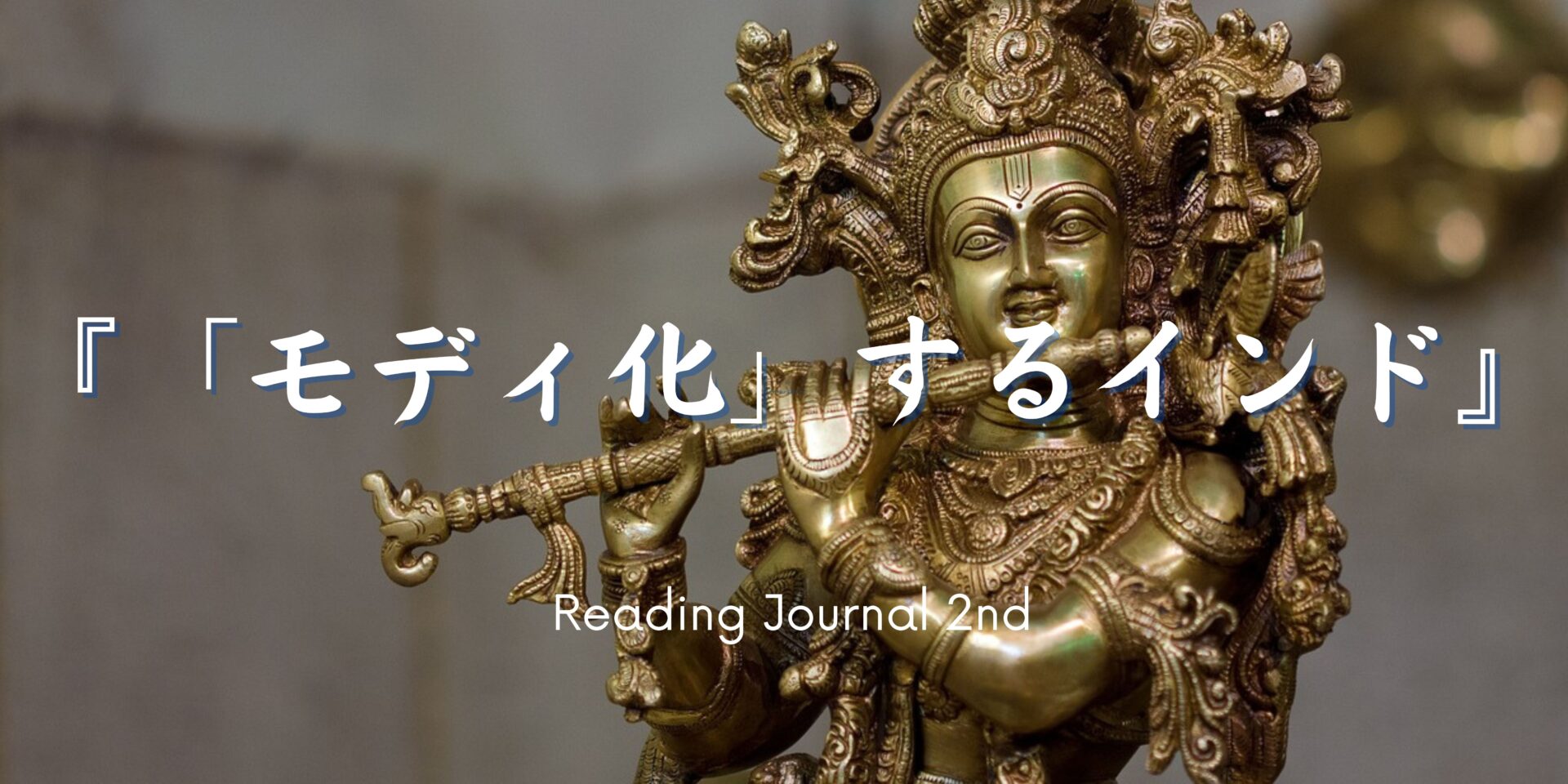


コメント