『プロカウンセラーの聞く技術』 東山紘久 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
25 説明しない
聞き上手は説明しない
「説明しない」といわれると「説明しないとわからないことだってあるのに」と思うかもしれないが、そう思う時点で頭が聞き手モードから話し手モードになっている。
相手に説明しなければならないというのは、自分の話が分かってもらえない時であるが、案外相手の話が分かってないというケースも多い。
「相手がなぜわからないか」がわかっているときは、こちらが説明しなくても、相手に納得させる手段があります。しかし、「これだけ説明してもわかっていただけませんか?」というような場合は、相手の心がわかっていないのです。だから、この場合は、聞き手として失敗であるばかりでなく、話し手としても失格なのです。(抜粋)
論理と感情の会話
話には内容とそれに関する感情がある。話し合いには利害が関係するので五分と五分、対等に進めるのが最善である。しかし利害のほうに感情がともなうのでどうしても客観的に判断できないことがある。
この感情は快・不快にもとづく判断機能であり、思考は論理の整合性にもとづく判断機能のため、お互いに拮抗する。ここで著者は、論理で説明する男性と感情で答える女性の会話例を出して説明している。
一般に親子や夫婦、友人関係などでは、論理と論理の論争は不毛なだけでなく、関係を壊してしまう。そのため論理に感情を持ち込んでなんとか気持ちの納得だけでもしたくなる。
ではどうすれば、論理と感情の会話が実りあるものになるでしょう。それは相手が感情を出したときは、こちらは説明をやめ、相手の感情を受け止めていくのです。(抜粋)
ここで、著者は前の会話例をもとにどのように感情を受け止めるかについて示している。
多少の損失があった場合でも、二人の関係性が壊れる損失よりは小さいものである。実際に相手の感情を受け入れることによって、二人とも成長することはよくある。
「揺るがず、逃げず、小さいことにこだわらず」は、リーダーや受け入れ側には大切な要素です。(抜粋)
26 話には小道具がいる
話をする部屋と遊び椅子
大切な話をするときに、椅子が二つだけ置かれている部屋では話がしづらい。しかし、それぞれの椅子の横にもう一つずつ椅子を置くだけで、雰囲気は随分と変わる。この余分な二つの椅子を「遊び椅子」という。
狭い部屋、広い部屋、暗い部屋、明るい部屋など部屋の違いは、話の内容にも影響する。カーテンや観葉植物、壁にかける絵、壁紙の色などによっても雰囲気が変わる。
話をする部屋は、自然に音が入るくらいな部屋がよく、光も柔らかな日の光が入るくらいがよい。飲み物や食べ物も話をスムーズにする雰囲気をあたえ、音楽も大切な要素になる。
話をしやすくする小道具
話をしやすくする小道具としては、火があると最高である。また土と水も大切な小道具となり、植物の鉢植えの土や、金魚鉢や水槽の水などがあると心が休まる。そして、ペットも大切な小道具となり、著名な心理療法家の中には面接室で自分の犬を侍らせている人もいる。また、大切な小道具の一つに自分の愛用品があり、気に入っている文具や本立て、パイプや灰皿などを置いておくのも良い。
ここで「火があると最高」って書いてあるけど、そういえば東畑開人の『聞く技術 聞いてもらう技術』の中の「聞いてもらう技術 小手先編 /日常編」で焚き火が最高と書いてあった(ココ参照)。やっぱ火なんですね♬(つくジー)
関連図書:東畑開人 (著)『聞く技術 聞いてもらう技術』、筑摩書房(ちくま新書)、2022年
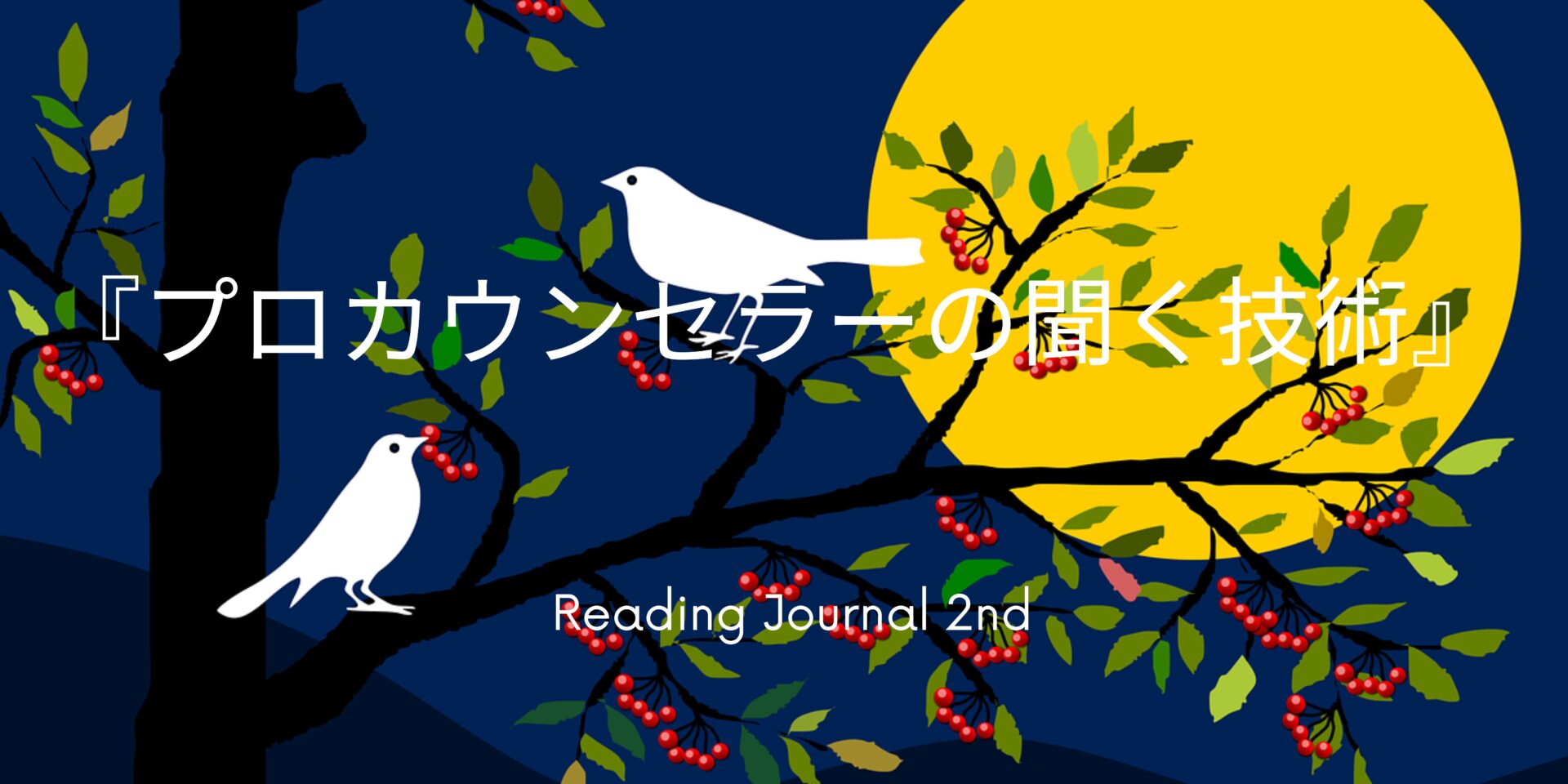


コメント