『外国語学習の科学』 白井恭弘 著
[Reading Journal 2nd:読書日誌]
第1章 母語を基礎に外国語は学習される(前半)
今日から本編に入る。まずは、「第1章 母語を基礎に外国語は学習される」である。ここでは、第二外国語を学習する際に問題になる母語の影響について解説される。第1章は前半と後半の二つ分けてまとめるとする。まず前半は、母語と学習言語との言語間距離により、学習の困難さが異なること。その原因として母語の転移がある。さて、読み始めよう
言語間距離
ある言語の習得の難しさを決めているものの一つに「言語間距離」がある。「言語間距離」は、言語と言語がどの程度似ているか、という概念である。母国語と対象の言語が「言語間距離」が近ければ近いほど学習しやすく習得が容易になる。
これは、方言話者が標準語を習得することが、それほど難しくないことに対応する。「言語」と「方言」の区別は、政治的要素で決まることも多く、「言語」と「方言」を区別することは科学的には不可能である。実際に違う言語ととらえられている言語でもかなり似ている場合がある。
言語の習得の正確な難易度の確定は難しいが、ある母語話者にとってどの程度言語が難しいかやさしいかは言語間距離によりある程度予想できる。
英語と日本語は、系統的に異なった言語であり、実際英語と同じインド=ヨーロッパ語族に属する言語の話者と比べて、日本人はかなりのハンディキャップを負っている。逆に、韓国(朝鮮)語は、日本語と文法が非常に似ているため、日本人にとって学びやすい言語である。
転移と言語転移
このような、第二言語習得(SLA)における母語の影響は「言語転移」と呼ばれています。(抜粋)
学習者の母語の知識が第二言語に転移すること「言語転移」と呼ぶ。この転移は、発音、単語、文法、文化など、様々な形で見られる。また、この転移という現象は、言語習得に限らず、学習された他のスキル、たとえば運動、などについても観察される。
習慣化した行動がそれと似た行動をするときに転移する、というのは日常生活にあらゆる場面で見られます。そして、それは何度も何度も繰り返して行ったため自動的になったものほど強いようです。(抜粋)
正の転移と負の転移
言語転移は、母語の影響で間違った言語形式になってしまう場合は、「負の転移」あるいは「干渉」という。反対に母語と第二言語で同じような形式を使うため、何も考えなくても正しい言語形式になる場合は、「正の転移」と呼ぶ。
「正の転移」になるか「負の転移」になるかは、母語と第二言語がどういう対応になっているかによっている。そして、言語間距離が近い言語の場合は、「正の転移」が起こりやすいため学習が容易になる。ただし、二つの言語が似ていることから、転移があまり強くなると、逆に違っているところの間違いはなかなかなくならないという問題が起こる。
第二言語学習における母語の影響は、母語と第二言語の距離が近いほど
- 転移がおこりやすく
- 転移は正の転移になり、全体として学習が容易になるが、
- 母語と第二言語が違っている部分については間違いがなくなりにくい。
普遍的習得順序
一九五〇-六〇年代では、学習者の犯す誤りは、すべて第一言語からの干渉(負の転移)であると言われていた。しかし、七〇年代になると母語の影響は思ったほど強くないことが明らかになる。
するとその反動から、「文法形式の習得順序は普遍的で、すべての学習者が母語と関係なく同じルートで学習する」という「普遍的習得順序」があるという主張があらわれた。この習得順序は、「自然な順序」と呼ばれる。
しかし、日本語学習者の習得順序を調べると、この「自然な順序」と一致することはほとんどない。欧米で出されている第二言語習得の教科書には、いまでも文法項目の普遍的順序を強調しているがあるが、母語の転移によってかなり左右されることを知っておくべきである。
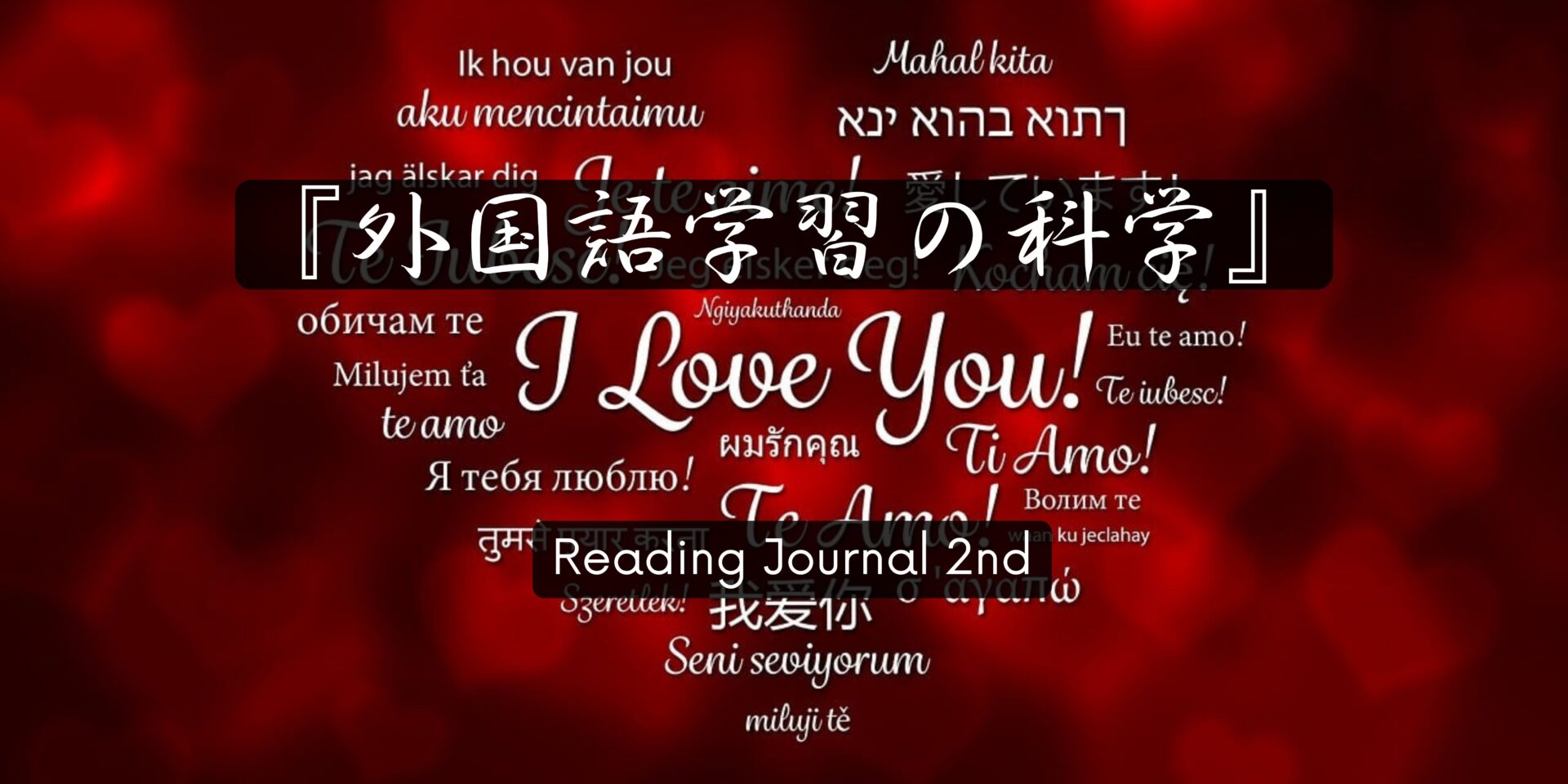


コメント